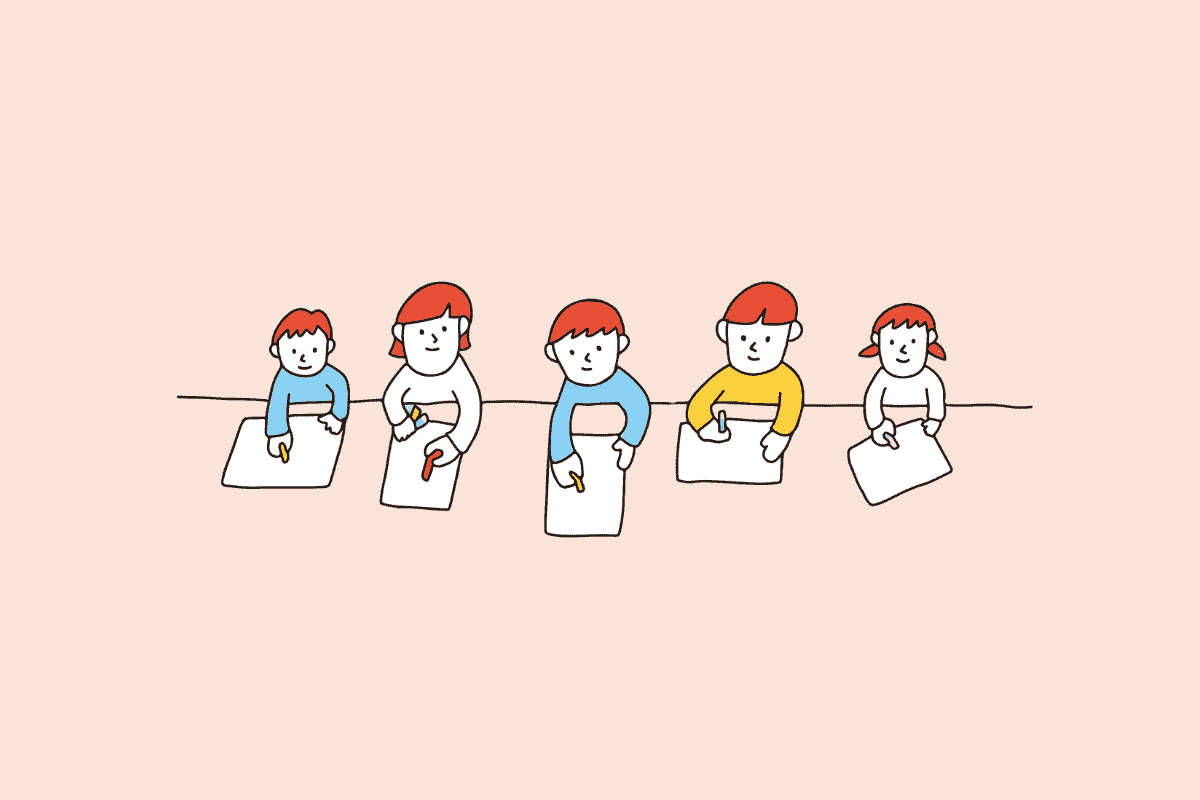
5分でわかる指導技術 対話で育てる「推敲力」
|
執筆者: 遊免大輝
|
今月の「5分でわかるシリーズ」は、遊免大輝先生(大阪府・大阪市立友渕小学校)に、書いた文章を友だちと読み合い、気付きを教え合う活動を通して、他者意識をもって文章を推敲できるようになる工夫をご提案いただきました。
作文の指導をしていると、「先生できた!」と、作文を書き終えた子どもたちがニコニコと笑顔でノートや原稿用紙を持ってくる。しかし、子どもたちが持ってきた作文を見ると、文章の構成や表現、句読点の抜けや誤字脱字など、内容や表記の誤りが多く見られる。 その作文をすぐさま教師が朱書きをする。気付いたときにはいつの間にか、子どもの行列ができている……。
これは、低学年の子どもたちのみならず、高学年の子どもたちにもみられる光景である。このような経験をされた先生方も多いのではないだろうか。実は、過去の私もその1人である。子どもたちは、文章が書けた達成感から、書いた文章を読み返すことを疎かにしている。言い換えれば、この姿は、子どもの推敲する力を教師が伸ばし切れていないことの表れであろう。
このような経験から、稿者は、推敲(以下、校正を含む)する方法を子どもたちに具体的に指導し、子ども自身が推敲する力を身に付けることで、よりよい文章に仕上がり、書く力を伸ばすことにつながると考える。
今回は、書くことの学習における「推敲」にフォーカスし、その具体的な手立てについて紹介する。
推敲には、2種類ある。それは、内容の推敲と表記の推敲である。
内容の推敲は、文章の構成や表現をより豊かでよいものへと練り直す作業であり、表記の推敲では、用語や誤字脱字、文法などの誤りや記述上の不備をチェックし、修正する作業である。したがって、下書きの後に行う順序としては、内容の推敲 → 表記の推敲の順で行うとよいだろう。
内容の推敲では、質問タイムを行う。質問タイムとは、下書きをした原稿用紙を子ども同士で読み合い、対話的に推敲する活動である。質問タイムで行う内容は以下のとおりである。
質問タイムを行うことで、「付け足してみたい!」「言葉を変えたい!」「書き直したい!」など、「文をよりよくしたい」という意欲につながる。また、質問タイムを行うときは、子ども同士が自由に交流する場をつくる。こうすることで、「〇〇さんと読んでみたいな!」と、子ども同士の対話が自然と生まれる。推敲する時間は、15分~20分を目安とする。そして質問タイムを終えた後は、2回目の下書きを行う。
2回目の下書きを終えた後は、表記の推敲をする。表記の推敲では、赤ペン先生タイムを行う。 赤ペン先生タイムとは、まず自分の書いた文章を赤鉛筆でチェックする。次に、友だちが書いた文章を子ども同士で読み合って友だちの文章を赤鉛筆でチェックし合う。それをくり返し行う。つまり、赤ペン先生タイムは、個だけで推敲する活動ではなく、他者と対話的に推敲する活動である。
赤ペン先生になるためのポイントは、以下のとおりである。
この5つのチェック項目を板書で整理し、いつでも確認ができるようにしておくとよい。
次に、表記の推敲をする際には、以下の3つのことを指導する。
原稿用紙を声に出して読むことで、視覚と聴覚の両方が刺激され、間違いに気付きやすくなる。その際、大きな声で読むのではなく、小さな声(声のものさしで言えば、1の声)で読むことを指導する。さらに、間違いを見つけたら、すぐに赤鉛筆で付け足す。 赤鉛筆で付け足す際は、 間違えている箇所に印を付けて、正しい文字や単語、語句や言葉を書くように指示する。また、間違いに気付いても下書きで書いた黒鉛筆の字を消しゴムで消さないことを指導する。
このように、書いたプロセスを赤鉛筆で書き残すことで、本番書きをする際に一目でわかるようにしておくことが大切である。
そして、表記の推敲の流れは、以下のとおりである。
個人で推敲をした後に相互推敲をすることで、自然と対話が生まれると同時に、友だちの書いた作文を批正的な目で見ることができ、「あっ! ここ間違えているよ!」などの気付きが生まれる。内容の推敲と同様、相互推敲も自由な交流にする。これをくり返すことで、書いた作文がブラッシュアップされ、よりよい文章を書くことにつながる。
推敲をする際には、赤ペン先生になるポイントや推敲する流れを板書で示すと子どもたちにとって助けとなるだろう。
相互推敲の後、数日間(2日程度)文章を寝かせておくとよい。そうすることで自分が書いた作文をより客観的に見ることができるからである。本番書きをする前に再度、個人推敲を行うことでよりよい文章を書くことができる。
「書いて終わり!」の作文ではなく、書いた文章をよりよくしていく楽しさを子どもたちが味わえるようにしていきたいと考えている。推敲を子ども同士の対話を通して行うことで、「推敲力」が磨かれていくのではないだろうか。
本実践は、低学年のものであるが、他学年でも転用できる。つまり、どの学年でも対話で推敲力を育てることが大切である。また、推敲をすることは、低学年では難しいと思うかもしれないが、低学年から継続的に指導していくことが大切だ。推敲は、手間のかかる作業である。しかし、「継続は力なり」という言葉のとおり、時間はかかっても、継続的に鍛えていけば、必ず力が伸びていく。
遊免大輝(ゆうめん・だいき)
大阪府・大阪市立友渕小学校
東京・国語教育探究の会(会員)/「立体型板書」研究会(事務局長)
