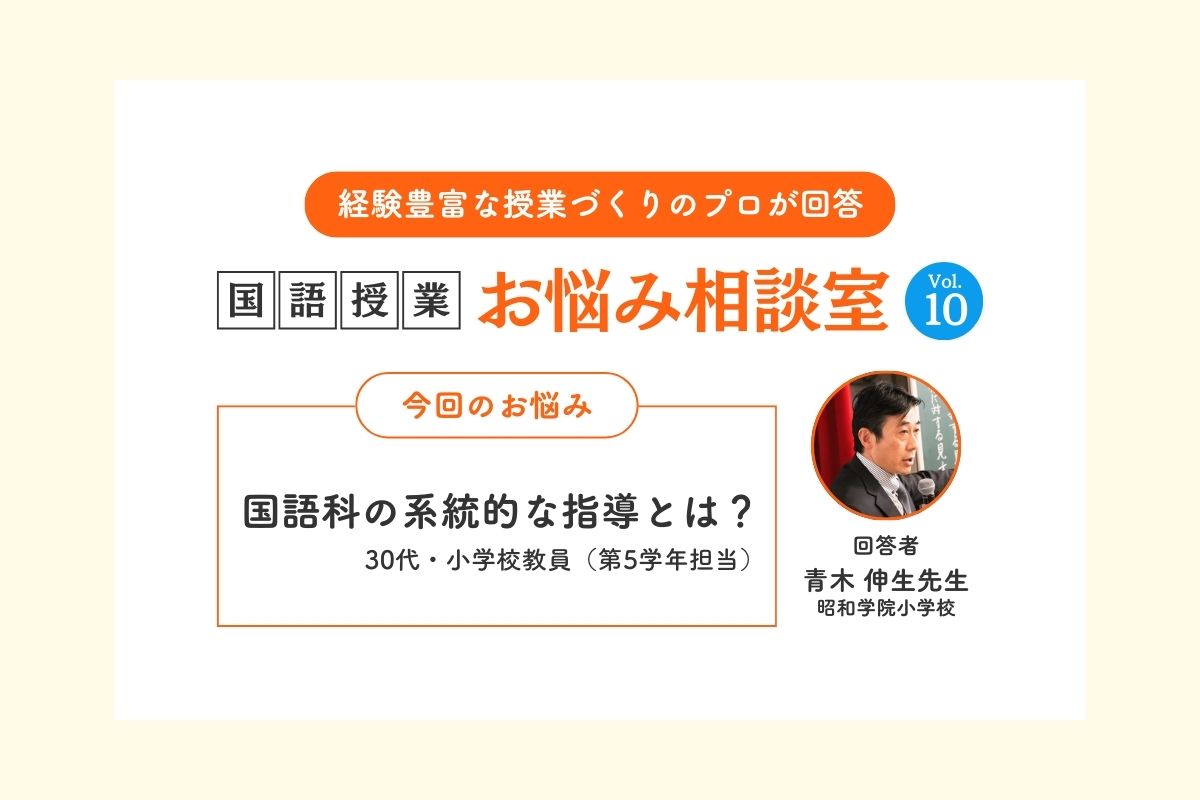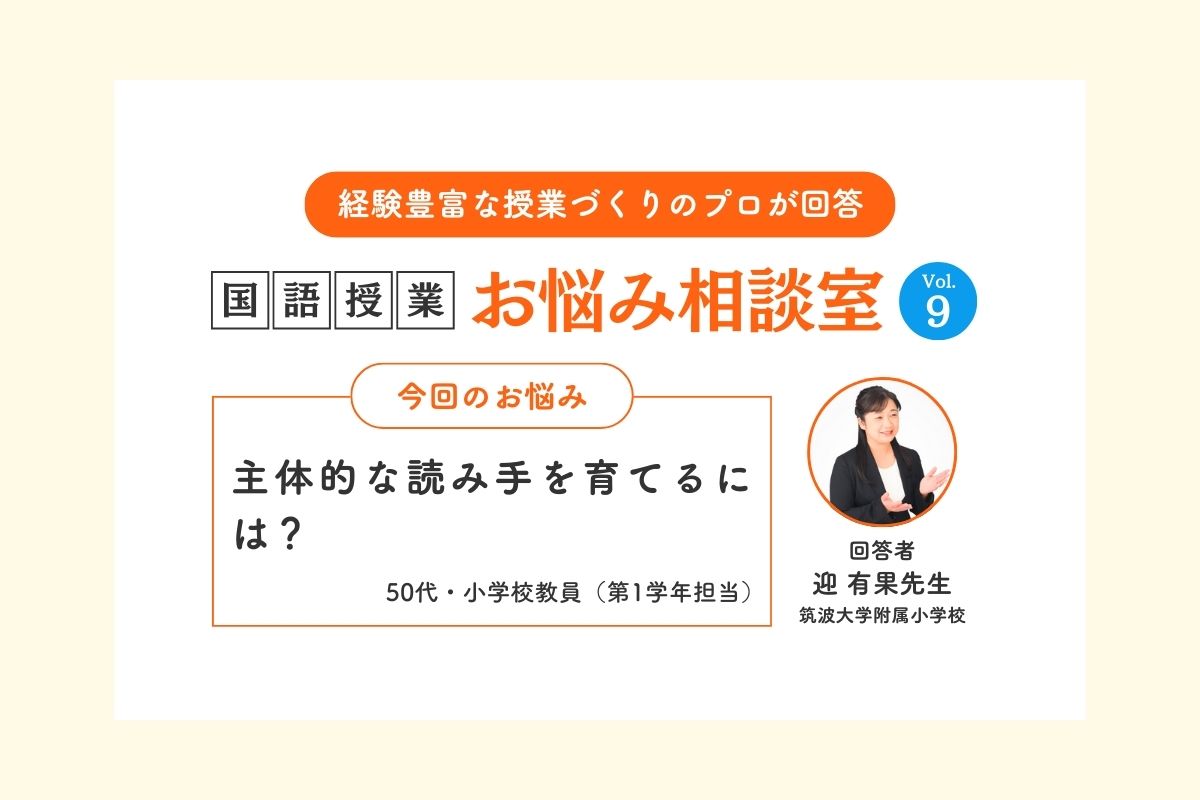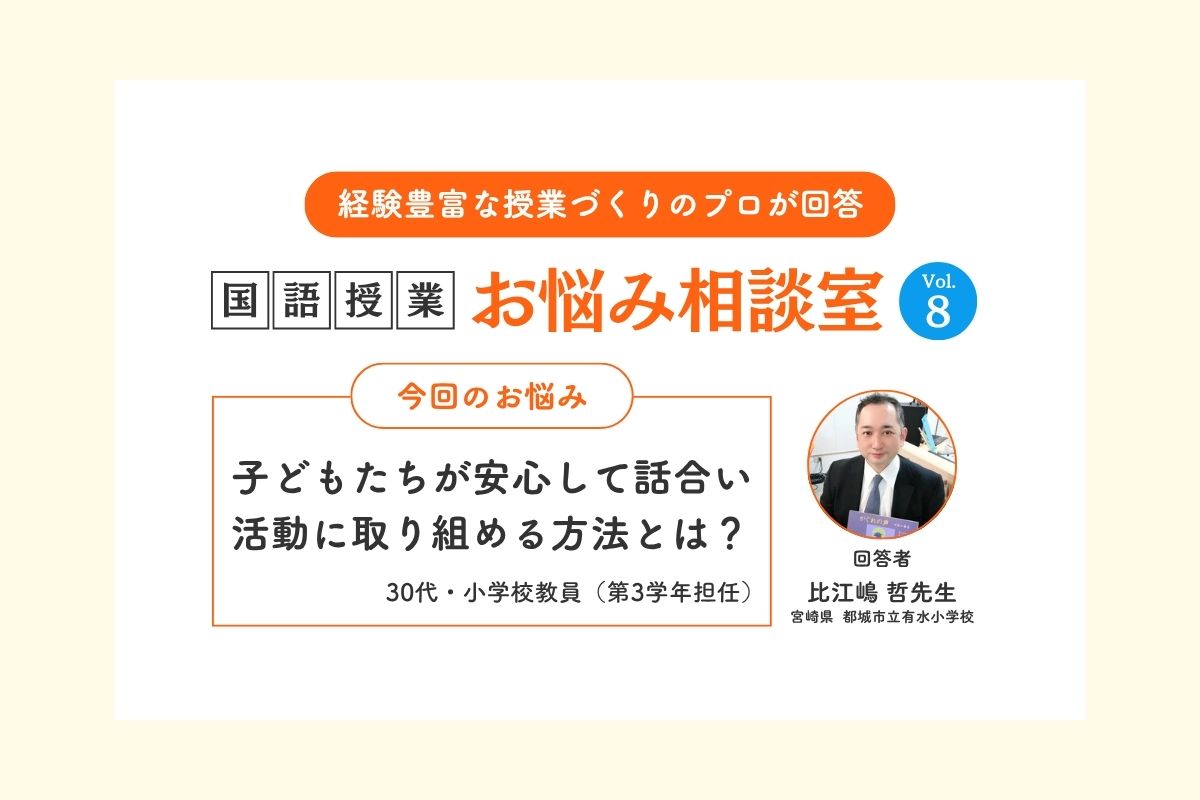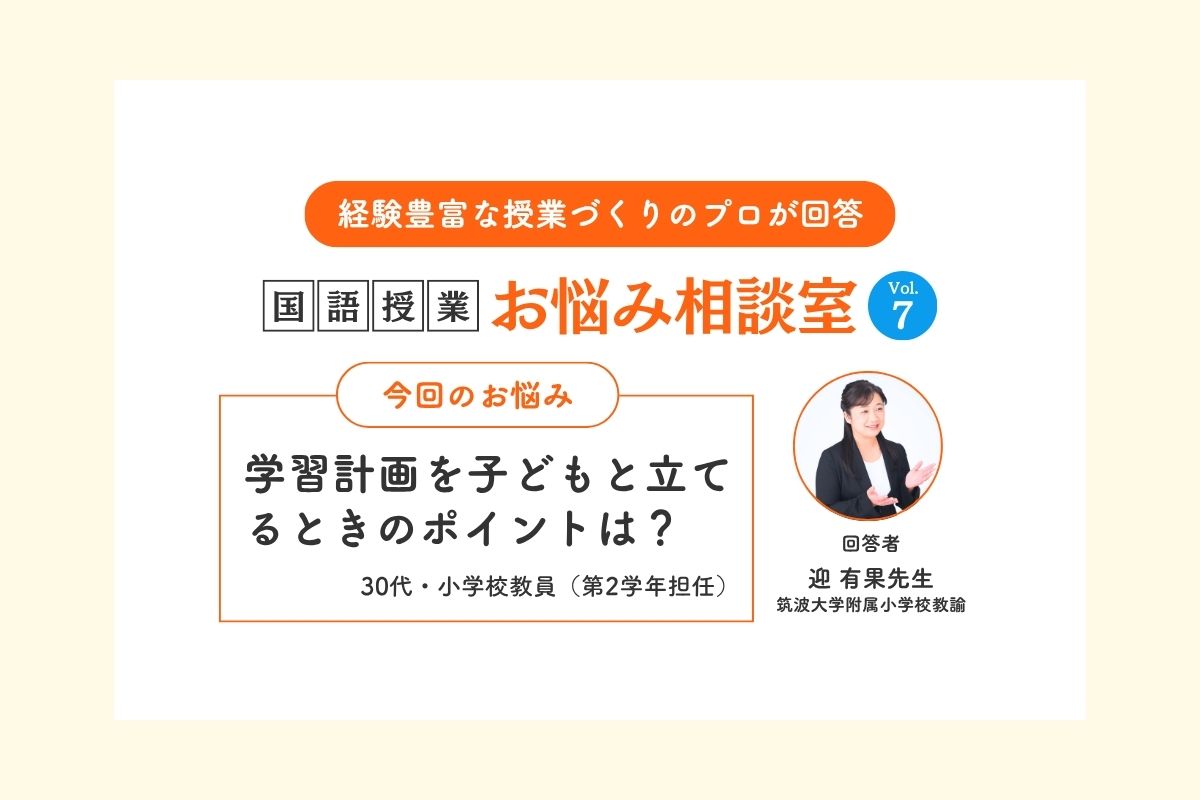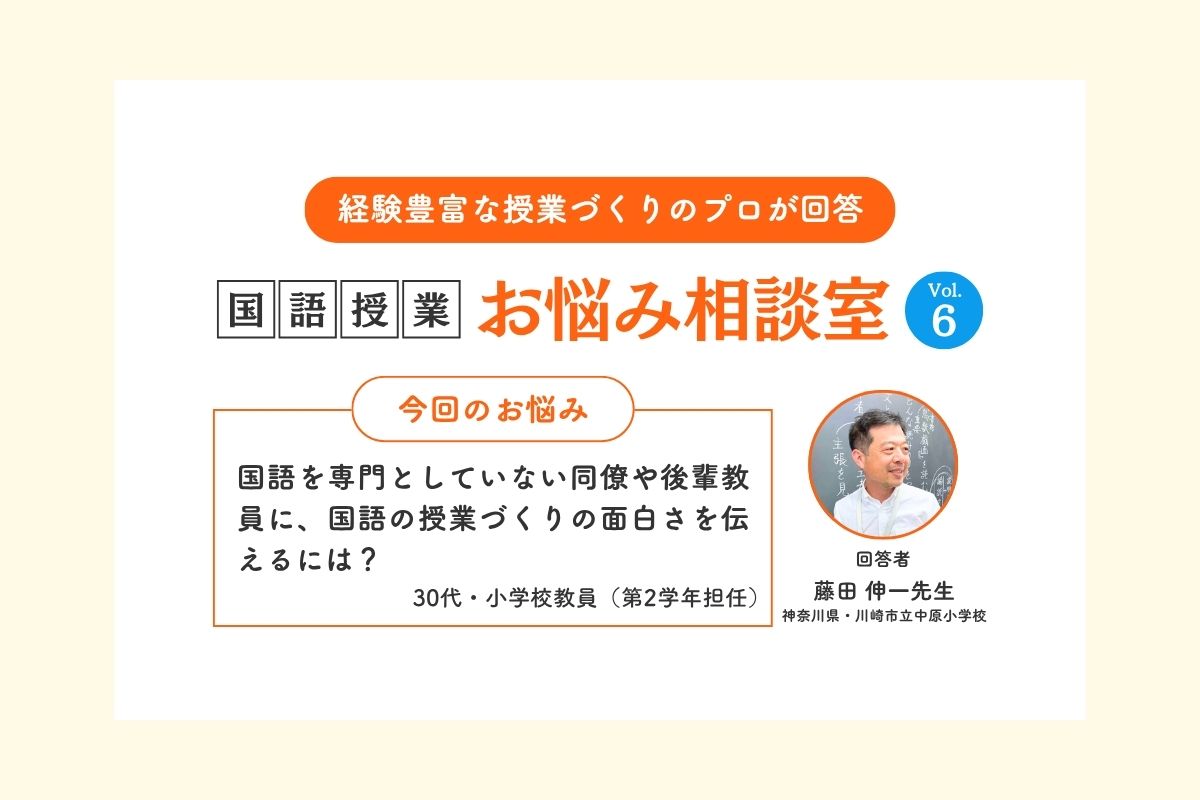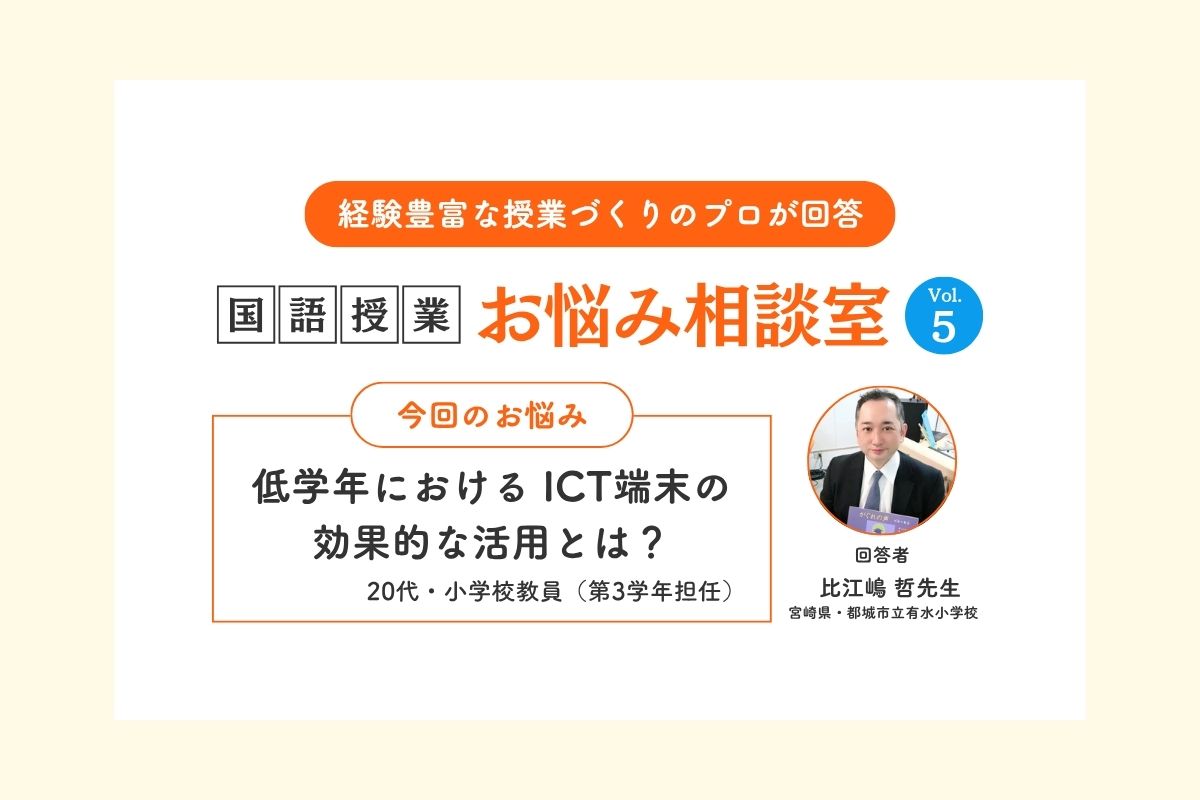子どもと創る「国語の授業」
![]() 有料記事
有料記事
Q国語科の系統的な指導とは
「ごんぎつね」で何を学ぶのか。そしてその学びを次の物語教材にどう生かすのか。国語授業の難しさは、そこが曖昧でわかりにくいところにあると言われています。今回は、青木伸生先生(昭和学院小学校)に、系統的に国語の学びを積み上げるための手立てとして「学習用語辞典」の取組を紹介いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
Q主体的な読み手を育てるには?
子ども自身が夢中になって読み、叙述をもとに語ったり、新たな読書生活に拓いていく姿。そんな「自ら読む子ども」に育つために、教師はどのような手立てを考えればよいのでしょうか。今回は、迎有果先生(筑波大学附属小学校)に、主体的な読み手を育てる活動を紹介いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
Q子どもたちが安心して話合い活動に取り組める方法とは?
ペア対話やグループ対話を授業の活動として盛り込んでも、そこに安心して話せる学級の土壌がなければ、真の話し合い活動にはつながりません。今回は、比江嶋哲先生(宮崎県都城市立有水小学校)に、話し手と聞き手を育てる活動を通して共感的に聞く力が身に付く活動を紹介いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
Q学習計画を子どもと立てるときのポイントは?
子どもたちを主体的な学び手としていくためには、自分事の学習になっていることが大切です。そのための有効な手立ての一つとして、学習計画を子どもたち自身が立てる、という活動があります。 今回は、迎有果先生(筑波大学附属小学校)に、初読後の感想をもとに学習計画を立てる際のポイントや、その方法を回答いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
Q同僚と共に授業づくりを楽しむために
国語の授業づくりを勉強し、実践を続けると、子どもたちに言葉の力が付いてきたことを実感し、嬉しくなったことがあるのではないでしょうか。でも、そのとき育った言葉の力は、学年が変わっても、担任が替わっても、同じように伸ばしてあげる必要があります。学校の先生を巻き込んで、国語授業づくりを楽しんでいきましょう。
![]() 有料記事
有料記事
Q低学年における ICT端末の効果的な活用とは?
1人1台に整備されたICT端末。授業のなかで効果的に使えているでしょうか。今回は、比江嶋哲先生(宮崎県都城市立有水小学校)に、ICT端末を使うことそのものを目的とするのではなく、学びを深めたり、広げたりするために効果的に取り入れる方法を回答いただきました。