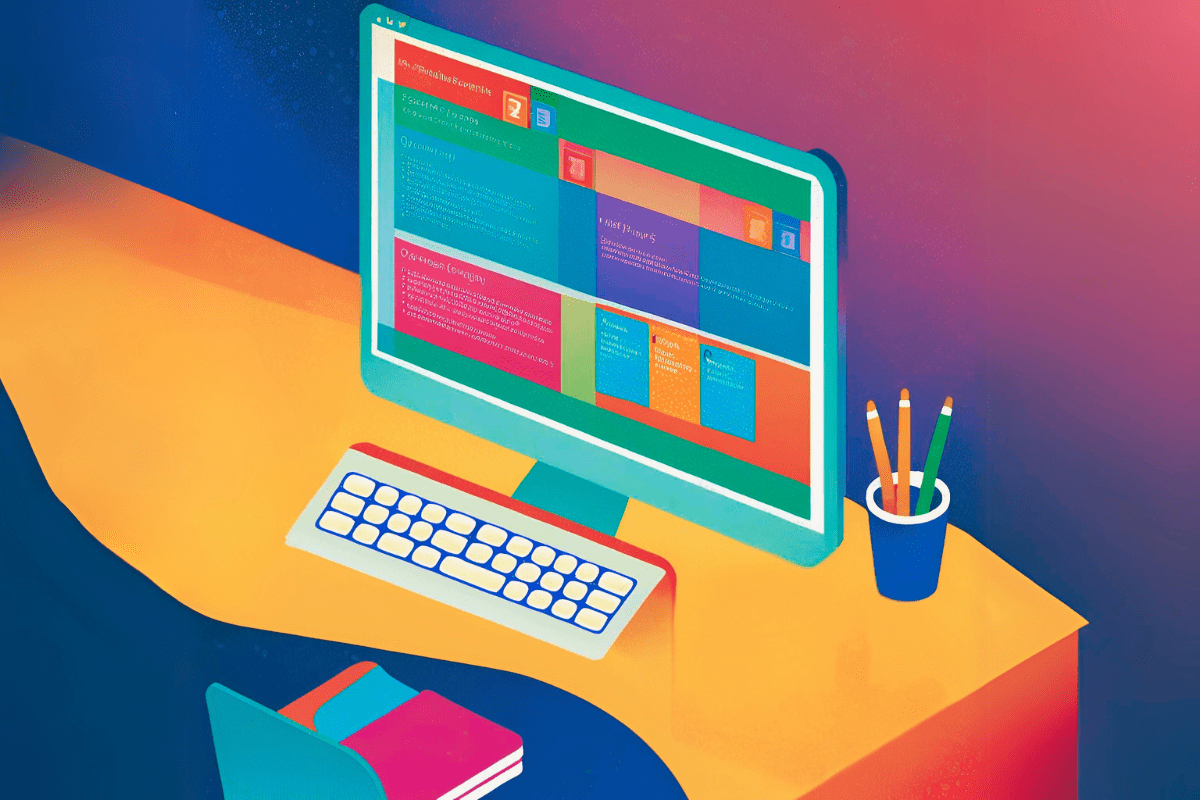
5分でわかる まちがいから学ぶ! 言語感覚を育てる語句・語彙の学習アイデア
|
執筆者: 古沢 由紀
|
4月号の「5分でわかるシリーズ」は、古沢由紀先生(大阪府・大阪市立柏里小学校)に、語と語のつながりやニュアンスの差異に気づける言語感覚を育む、クイズ形式で楽しく行える語句・語彙学習のアイデアをご提案いただきました。
単元の冒頭で行う新出語句の学習では、語の意味を調べることに重点が置かれがちである。そのため、学習者は辞書の内容をただ書き写すだけで終わってしまい、語の多様な用法や語と語との関係にまで意識が向かないことも少なくない。
学習者が新しい語句に出合い、その意味を自ら調べる中で、言葉のおもしろさや奥深さに気づくことが大切である。そうした体験を通して、ことばに関心をもち、言語感覚を育んでいくことが求められる。
語句・語彙指導には、以下のようなねらいがある。
これらを踏まえると、語の知識をただ蓄積するだけでなく、「語への感度を高めること」や「語と語のネットワークをつくること」といった言語感覚を育てる視点が、より重要となる。
中村和弘(2024)は、「言葉を意識することで、子どもたちの中に発見が生まれる。その発見や気づきが外側にあった言葉を内側に浸透させる」と述べたうえで、「子ども自身が『言葉のアンテナ』を高くする」ことが語彙学習の基盤であると主張する。
身の回りの語に対して、「この言葉には他にどのような使い方があるのだろうか?」「この使い方は適切だろうか?」と問いをもつことは、語の使い方や文脈への感度を高め、言葉のつながりに気づくきっかけとなる。こうした発見や気づきの経験を積み重ねていく中で、語を自らの表現として活用できる力が徐々に身についていく。
新たに出合った語句を単なる知識として習得するだけでなく、人と人とのコミュニケーションの中で、より適切なことばを選び、思考し、表現していく力を育むことが、これからの語句・語彙指導においてより重視されるべき視点である。
この実践では、あえて間違った語の使い方(=誤用)を考える活動を通して、語のもつ意味や正しい用法、語感への気づきを深めることをねらいとしている。語を正しく使うだけでなく、「どんな使い方が不自然か」「なぜその語では違和感があるのか」といった視点をもたせることで、語句の意味や使い方を吟味し思考することができる。このような気づきを日常的にもつことで、語句や語彙への関心や感性を高め、学習の言語能力を支える土台になる。
授業では単に語句の意味を調べるだけでなく、学習者自身が「誤用クイズ(まちがいことばクイズ)」を作成する。クイズづくりをする中で、誤用の文例をもとに、さまざまな言い回しや表現の仕方に目を向けることができる。
例えば、「感謝」という語を「先生に感謝をあげた」という文にすると不自然さを感じる。「感謝」は気持ちを表す語なので「あげる」のは誤った用法であると気づく。このように、語のつながりにおける“ひっかかり”に気づくことで、語に対する感性が養われるだろう。
まずは、教材文中に出てくる語句の中から、特に難しさや違和感のある語をいくつか選び、一人ずつ出し合う。その後、辞書や文脈を手がかりに語句や語彙の意味を調べる。
語句や語彙の意味がわかったら、その語句の使い方に関するクイズを作成する。まずは、正しい使い方を理解し、そのうえで「どんな使い方が不自然か」「違和感がある言い回しか」といった誤用の文例を思考する。“ひっかかり”のある文を作成する中で、語の意味や語がもつ微妙なニュアンスのちがいを学ぶことができる。
今回は、「Kahoot!」というクイズ作成アプリを活用し、学習者全員がクイズの作成に参加した。選択肢は4つ程度にし、そのうち1つが正しい使い方で、残りの3つは誤用になるように考える。本文中の語句を使って、4択クイズを作る。
例:「『気が重い』の正しい使い方はどれ?」
→ 正答だけでなく、なぜ他は違うのかを話し合うことで、語感が育つ。
作成したクイズはKahoot!に入力し、クラス全体でプレイする。学習者が自作のクイズを出し合うことで、楽しみながら他の子の視点や語句のとらえ方にもふれることができるだろう。
クイズの回答後には、「なぜその選択肢が誤用だったのか」「どんな違和感があったのか」を解説し合う時間も設けると、他者と協働的に取り組み、語句や語彙に対する感度を一層深めることが期待できる。意味を理解するだけでなく、人間関係を豊かにするための語句や語彙指導であり、互いにアドバイスを掛け合いながら学習する姿勢が大切である。また、作成した問題は、
このような活動を通して、語句や語彙の正しい使い方だけでなく、間違った使い方を学ぶことで、語と語のつながりや語感を鍛えることができる。活動そのものが、学びを内包した遊びの要素があるため、語彙学習がより能動的で創造的な活動に変わり、全員が楽しく取り組めるだろう。
語句や語彙指導は、理解だけではなく、学んだ語句がどのように機能するのか、語と語の関係や言葉がもつニュアンスに反応する言語感覚を育むことが大切である。また、このような語を中心とした学習の中で、人と人との間に存在する「ことば」をより尊重し、豊かな人間性を育むことができるような学びを目指していきたい。
〔引用・参考文献〕
古沢由紀(ふるさわ・ゆき)
大阪府・大阪市立柏里小学校
全国大学国語教育学会/日本国語教育学会/
