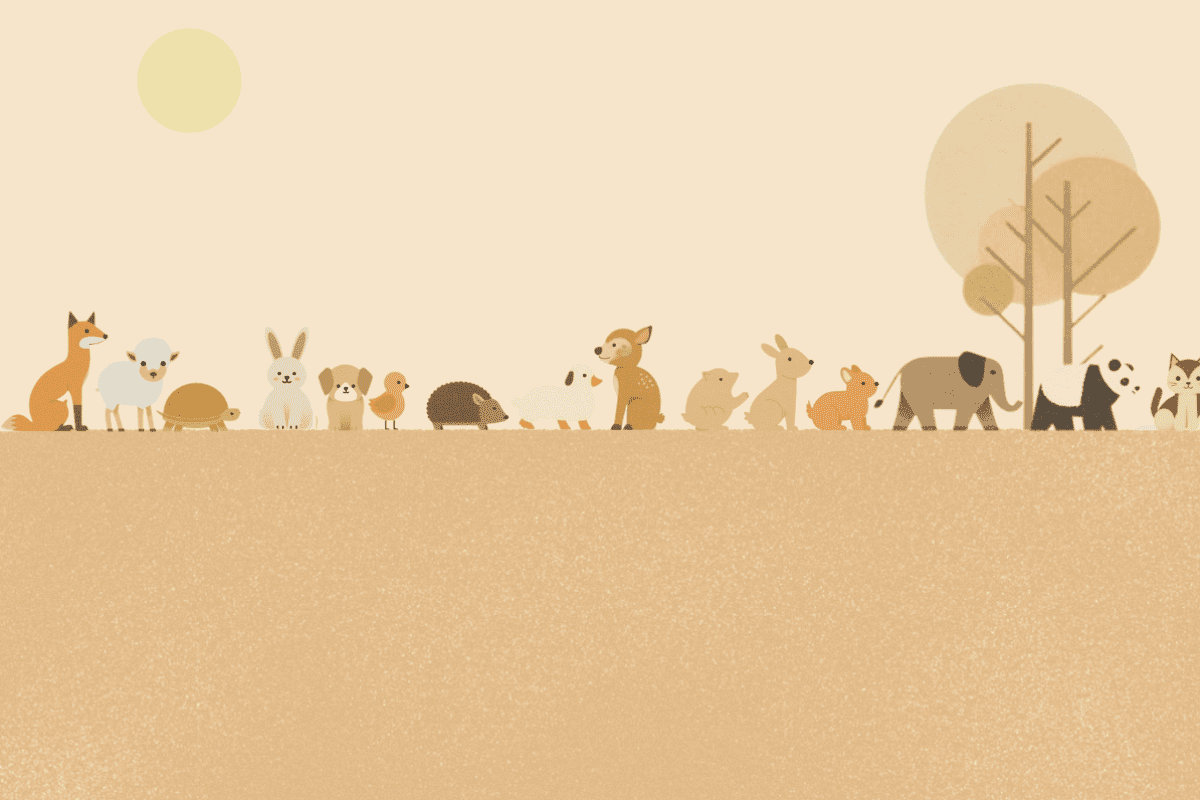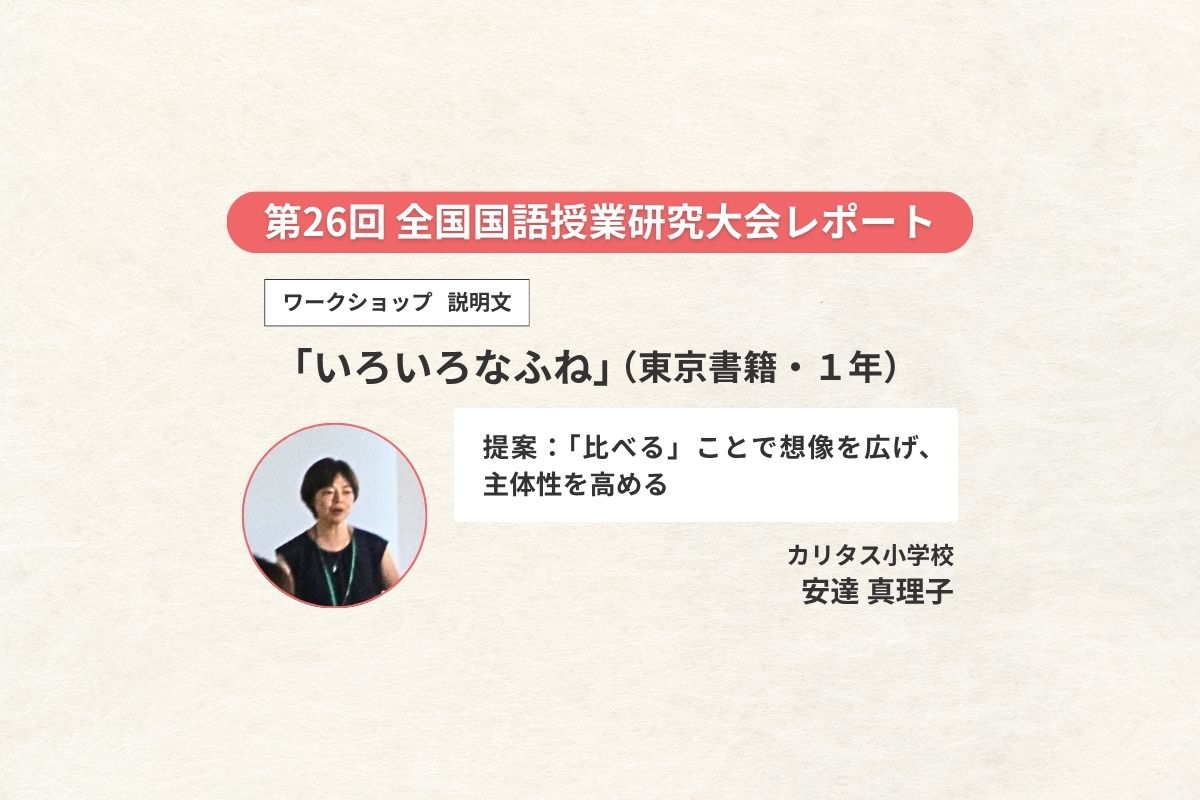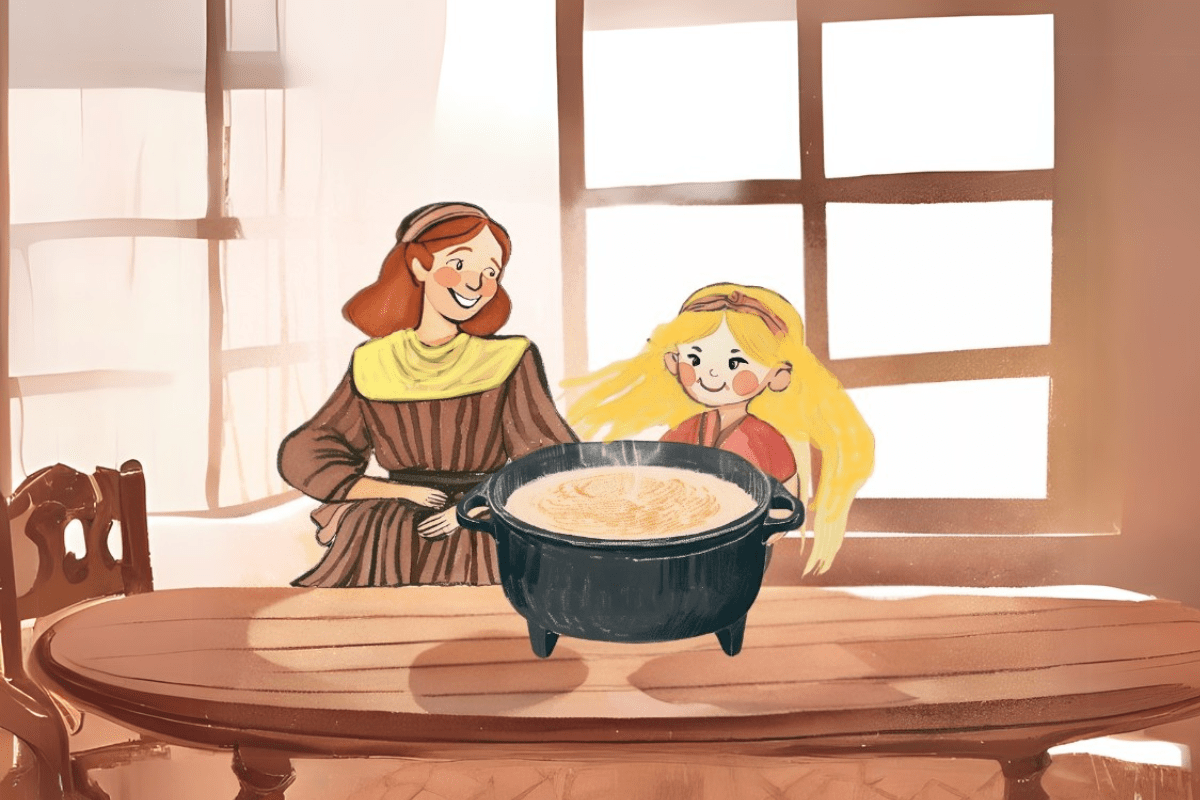子どもと創る「国語の授業」
![]() 有料記事
有料記事
「どうぶつの赤ちゃん」
―言葉を意識した授業づくり-
今回は後藤竜也先生(東京都・調布市立八雲台小学校)に、動物の赤ちゃんを比べながら読む活動を通して、文章構造や言葉の働きに気づかせ、主体的な読みを育てることをねらいとした授業づくりについてご提案いただきました。 子どもの感想から、「たった」「もう」などの本文中の言葉に注目することで、動物の赤ちゃんの特徴や違いをより深く理解できるようにし、話し合いを通して、その違いを理由を明確にして伝えようとする姿が育まれます。
![]() 有料記事
有料記事
登場人物との対話を通して物語世界を広げ、深める「くじらぐも」の授業デザイン
今回は三笠啓司先生(大阪教育大学附属池田小学校)に、本文を読み、動作化したりフキダシを用いて会話文を想像したりして、登場人物と同化してゆく学習活動についてご提案いただきました。物語のファンタジー性とごっこ遊びが好きな子どもの発達段階を結びつけ、日常と非日常を行き来する想像力が養われることでしょう。
![]() 有料記事
有料記事
「つぼみ」
—表現する言葉に着目しながら読む説明文の授業-
新教材「つぼみ」は、左のページに「問い」が示され、ページをめくると「答え」がわかるというような構成になっており、クイズを楽しむように説明文の基本である「問い」と「答え」を学べる教材です。 今回は小島美和先生(東京都・杉並区立桃井第五小学校)に、初めての説明文学習であることを踏まえ、指示語が何を指し、主語は何なのか丁寧に押さえられるよう問いかけを行い、説明文の読み方が身に付く授業づくりの工夫を提案いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
「やくそく」
-同化体験を通して、物語世界を豊かに想像する文学の授業-
本教材「やくそく」について、三笠啓司先生(大阪教育大学附属池田小学校)に、登場人物に同化する体験を通して、一人ひとりが想像力を働かせ、豊かに物語世界を楽しむことができる、「同化体験」を取り入れた授業づくりのご提案をいただきました。
![]() 有料記事
有料記事
「おかゆのおなべ」
-低学年物語文でも根拠が大切であると実感できる授業-
本教材では、「おかゆのおなべ」の呪文を、誰が知っていて、どのように言ったのかということが、この物語の起承転結をつくる鍵となっています。本教材の学習を通して、物語文を読む上で重要な、会話文を押さえることに意識が向くようになるでしょう。 今回は柘植遼平先生(昭和学院小学校)に、かぎ(「」)の役割や知識を深めつつ、かぎ(「」)が誰のセリフなのか本文を根拠にしながら読み進めることで、文学のおもしろさにふれられるような授業づくりの工夫を紹介いただきました。