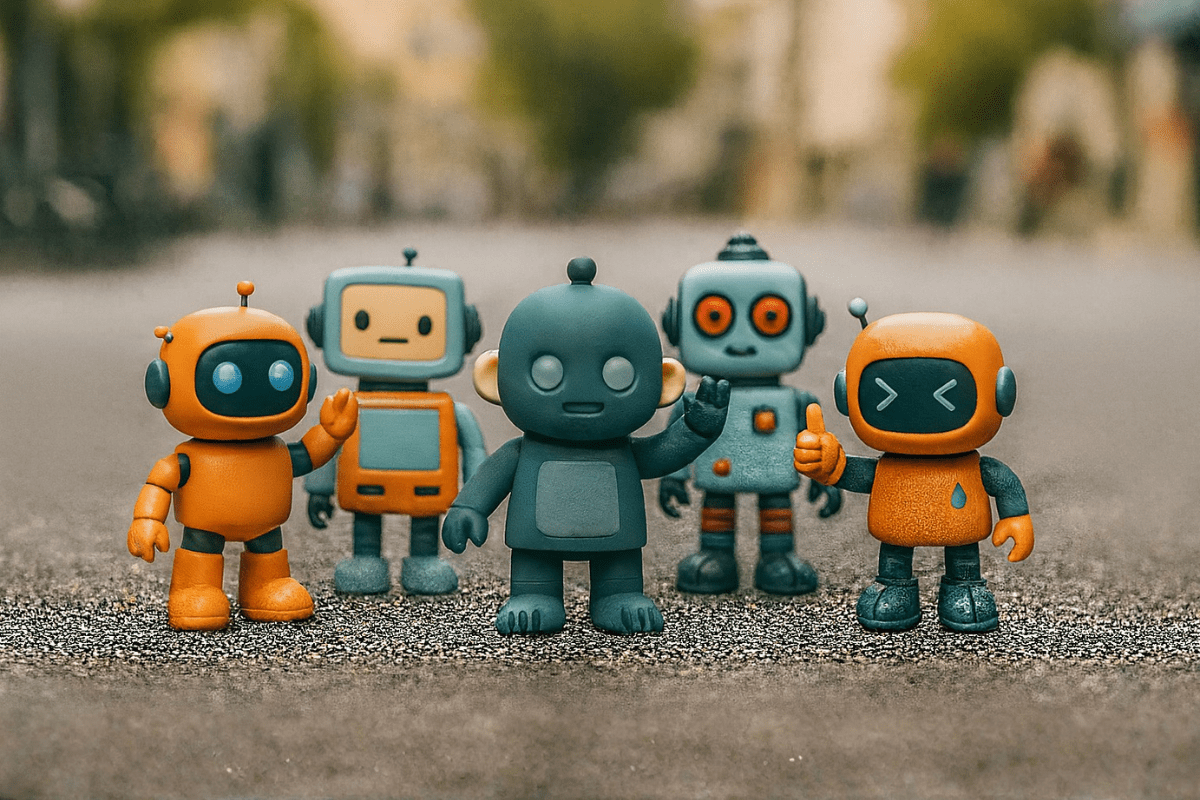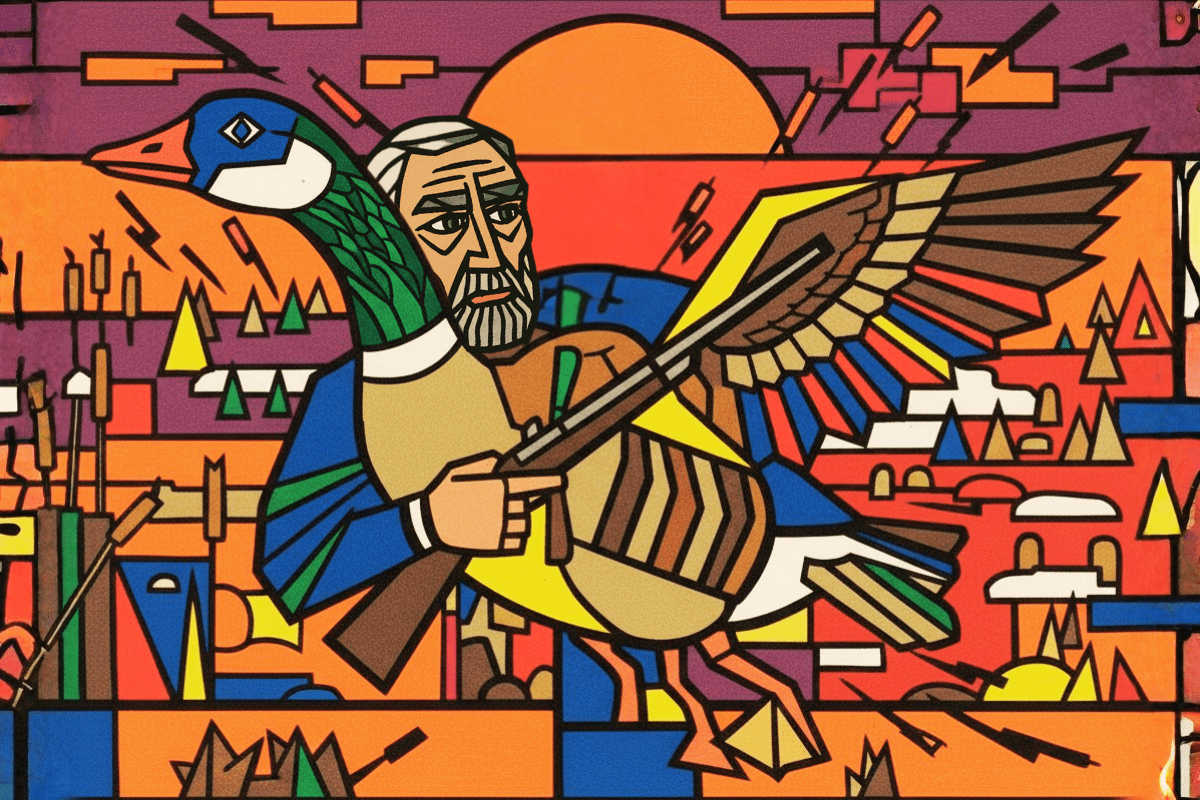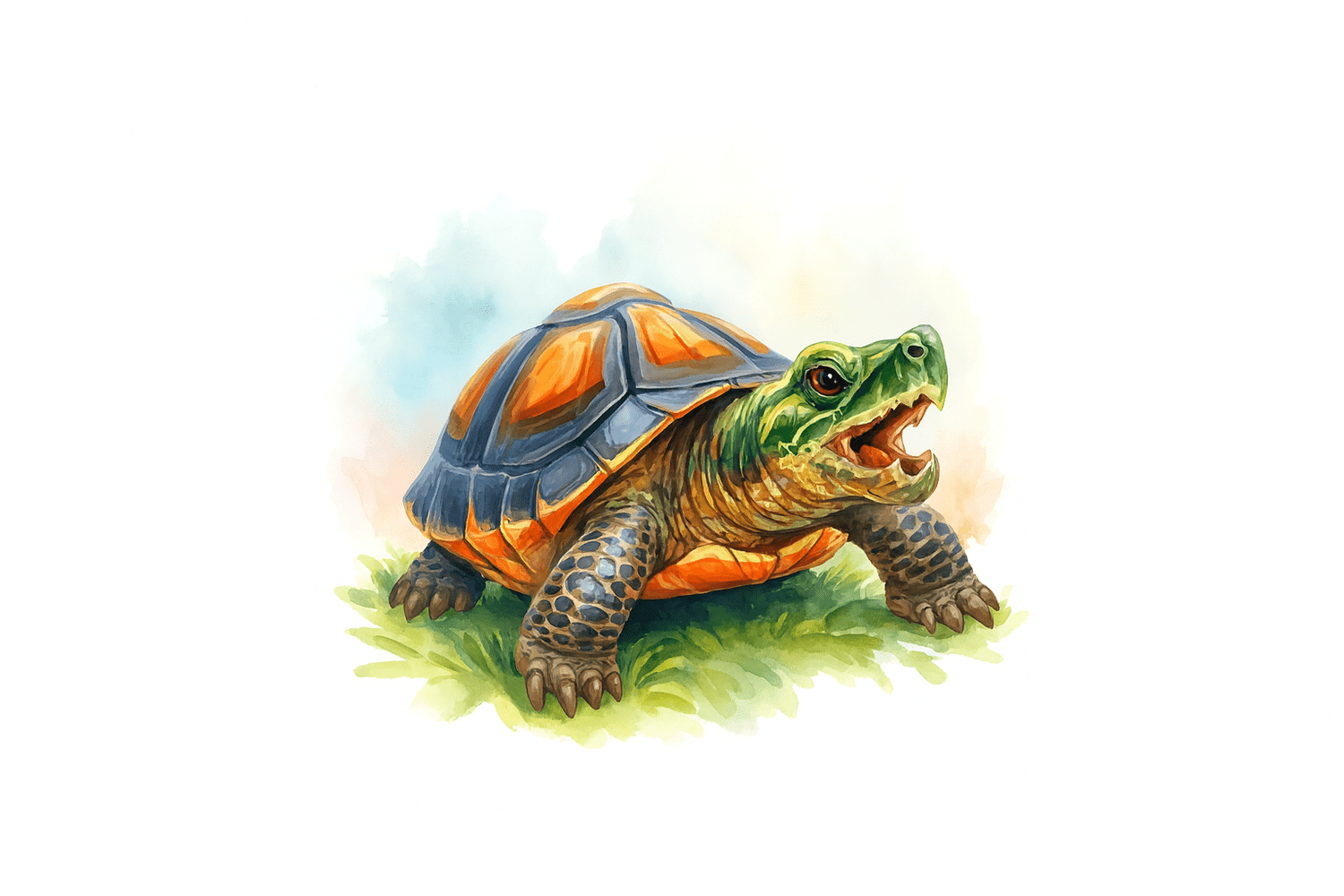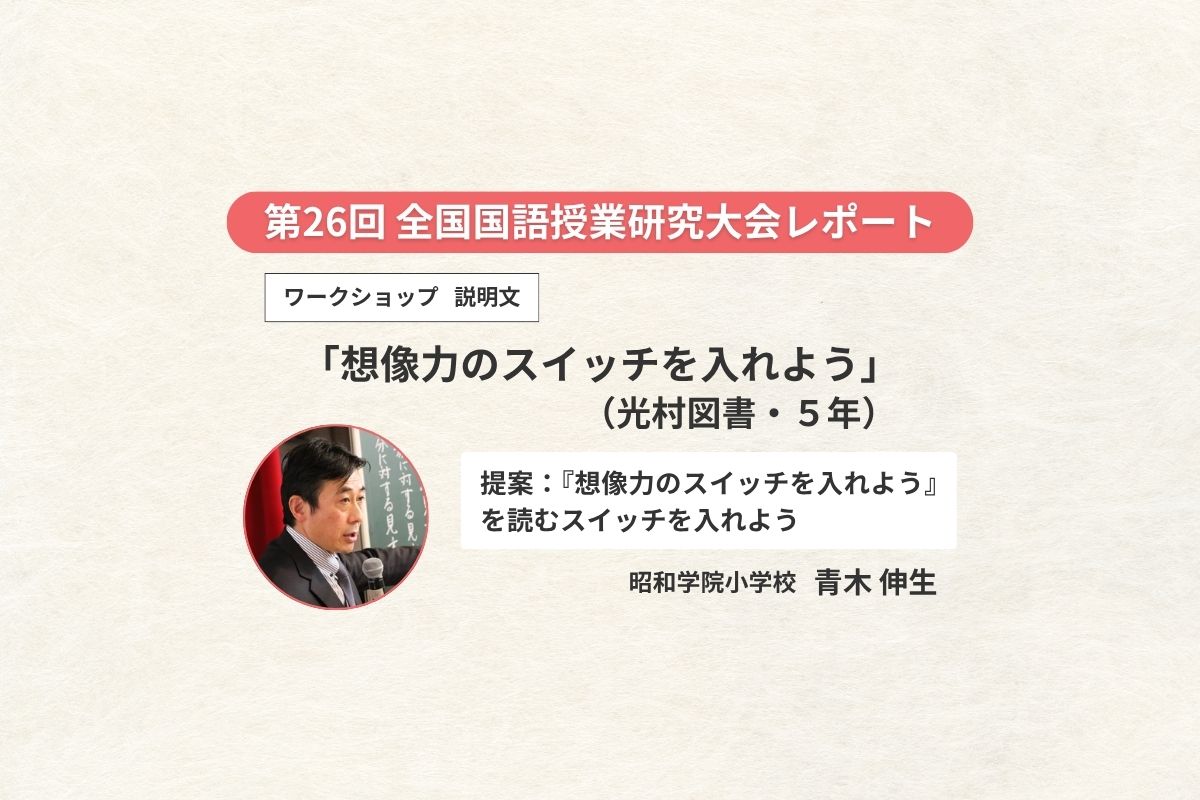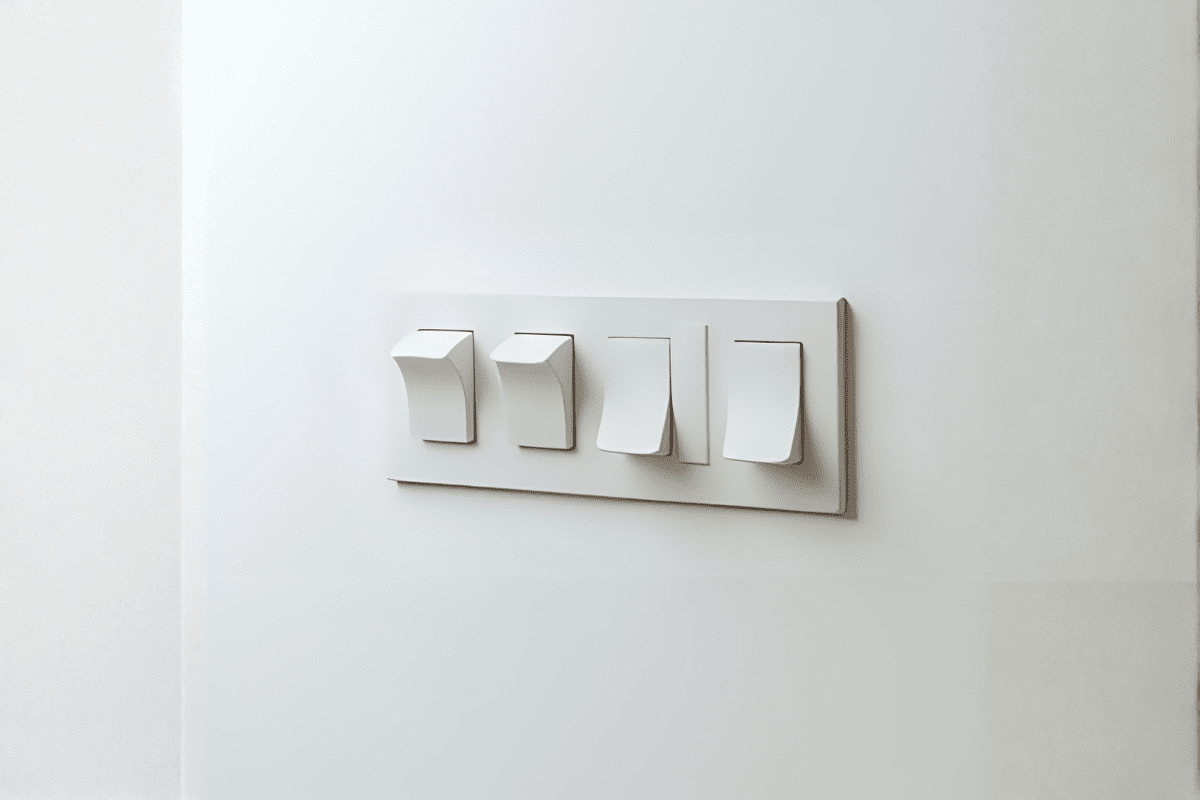子どもと創る「国語の授業」
![]() 有料記事
有料記事
「まんがの方法」
―筆者の提案に素直に乗り、説明文を読むことを楽しむ体験を―
今回は小崎景綱先生(埼玉県・さいたま市立新開小学校)に、教材「まんがの方法」最終段落の筆者の問いかけを起点として、実際に「まんがの方法」を探して紹介する活動を通して、読むことの必然性とおもしろさを実感させる授業づくりをご提案いただきました。 説明文を読む力を自覚し、読むことそのものを楽しむ態度へとつながると考えられます。
![]() 有料記事
有料記事
論説文を読み自分の考えをまとめる授業をおこなうために
-「『弱いロボット』だからできること」-
本教材「『弱いロボット』だからできること」の実践において、今回は田中元康先生(高知大学教職大学院 教授/高知大学教育学部附属小学校 教諭)に、はじめに自分なりのロボットへの考えを確かにし、筆者の主張と根拠を的確に捉えていく中で、自分の考えを形成・更新していく授業づくりをご提案いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
2つのアプローチで「大造じいさんとガン」を攻略する
今回は、青木伸生先生(昭和学院小学校校長)に、子どもたちが本教材「大造じいさんとガン」を読み深め、自分なりの攻略法を見いだす2通りの単元づくりをご提案いただきました。 いずれも作品全体の構造をとらえ、表現技法や人物の心情変化を読み取る力を伸ばし、最後には、主題について自分の言葉で表現する力が身につきます。
![]() 有料記事
有料記事
「筆者の考え」と対話しよう
―「カミツキガメは悪者か」―
本教材の明快な筆者の考えや主張を受け、なぜそう言い切れるのか、その根拠や理由を追究し、筆者と対話してゆく授業づくりについて、安達真理子先生(カリタス小学校)にご提案いただきました。 実体験に基づく筆者の強いメッセージとタイトルの問いかけを生かして、子どもたちの自分事としての主体的な読みを引き出します。
![]() 有料記事
有料記事
想像力スイッチを使って、何を読む
―5年「想像力のスイッチを入れよう」―
今回は仲野和義先生(大阪府・富田林市立向陽台小学校)に、情報を正しく読み取り、批判的に考える力を育てる授業づくりについてご提案いただきました。情報の受け手としての意識を養い、また社会科や情報リテラシーの知識とも関連づけることで、批判的な視点をもてるようにします。