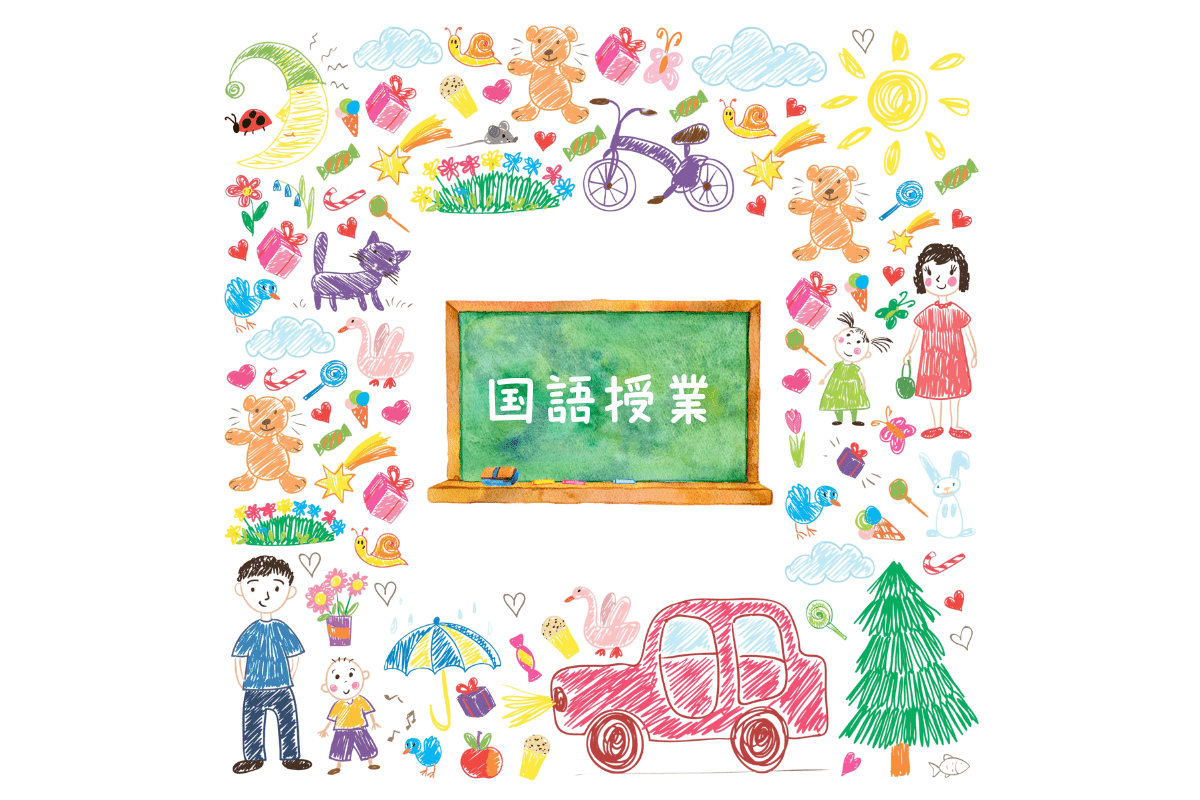
5分でわかる「楽しい!」授業のつくり方 -「子ども主語」の国語授業をつくろう!-
|
執筆者: 小西敦司
|
5月号の「5分でわかるシリーズ」は、小西敦司先生(大阪府・摂津市立三宅柳田小学校)に、子どもたちが「楽しい」「おもしろい!」と思える活動を学習内容に取り上げたり、自分たちで学習を調整できるよう学びの選択肢を広げたりすることで、「子ども主語」となる国語授業のつくり方についてご提案いただきました。
目次
そんな子どもたちの声、聞いてみたくありませんか?
そして、このような声が自然と聞こえる授業は、子どもたちが「主体的」に学習に取り組めている証と言えるでしょう。
「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について(諮問)」(令和6年12月25日 中央教育審議会)でも、顕在化している課題の1つとして「主体的に学びに向かうことができていない子供の存在」が挙げられており、主体的な学びを引き出す授業づくりは、ますます重要なテーマとなっています。
文部科学省の「主体的・対話的で深い学びの実現(『アクティブ・ラーニング』の視点からの授業改善)について(イメージ)」では、子どもが主体的に学習に取り組む姿を、『学ぶことに興味や関心をもち、自己のキャリア形成の方向性と関連づけながら、見通しをもって粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる』と示しています。
ここからは、
という2つの問いについて考察していきます。
私はこれまで、教師が学習材を提示し、単元の学習課題や1時間の「めあて」「課題」などを設定し、子どもたちがそれに取り組むという、「教師が主語」の授業を展開してきました。しかし、そのような授業では、子どもたちが興味をもてずに遊び始めたり、窓の外を眺めていたりする様子が見られました。
子どもたちが「学ぶことに興味や関心をもてる」ようにするためには、様々な方法が考えられます。中でも、私が特に重要だと考えるのは、「子ども」を主語にした授業づくりへの転換です。
以下では、実践例を交えながら、その考えを具体的に述べていきます。
子どもたちが過去にどのような活動を「楽しい!」と感じてきたのか、普段どのような「学習形態」や「遊び」に夢中になっているのか。そうした子どもたちの姿を丁寧に観察し、国語の授業に少しでも取り入れることができれば、子どもたちは学習に興味をもち、主体的に取り組むようになるのではないでしょうか。
写真1は、光村図書6年「やまなし」の授業で行った言語活動の様子です。子どもたちは普段から、登場人物やキャラクターになりきる活動を好んで行っており、休み時間には教室にあるパペットや人形と楽しそうに遊んでいます。そこで、この単元では、ペープサートを通して「やまなし」の世界観を表現する活動を中心に取り入れました。
このように、子どもたちの興味や関心に基づいた言語活動を設定することで、休み時間や放課後まで熱心に取り組む姿が多く見られました。
また、子どもたちのこれまでの学びのつながりを意識するために、学年の初めには、「過去にどのような学習をしてきたのか」「どんな力がついたのか」を振り返り、共有する時間を設けています。そうすることで、単元の初めには【写真3】のように、子どもたちは学習内容に応じて自分たちで活動を選び、主体的に学びを進められるようになります。
スティーブン・R・コヴィーは、著書『7つの習慣』(2013)の中で、主体性を「人間として自分の人生に対して自ら選択し、自ら責任をとるということ」と定義しています。また、文部科学省の「主体的・対話的で深い学びの実現(『アクティブ・ラーニング』の視点からの授業改善)について(イメージ)」(2017)では、「主体的な学び」を、「学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連づけながら、見通しをもって粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる」ことと捉えています。
国語の授業においても、子どもたちが「やりたい!」ことを「自己選択・自己決定」できる機会を増やし、学習計画を立て、見通しを持って学習を進められる環境を整え、学習の場を広げていくことで、「楽しい!」「もっとしたい!」という主体性を引き出すことができるでしょう。
「春風をたどって」(光村図書・3年)の学習では、「登場人物の行動から気持ちを読み取る力をつける」という共通の学習課題を設定しながら、これまでの経験をもとに「音読劇」「行動に線を引き気持ちを想像する」「音読発表会」の3つの活動から表現方法を子どもたちが選べるようにしました。
このように、「自己選択・自己決定」できる場があることで、
といった子どもたちの声が挙がり、主体的に活動に取り組むことができました。
光村図書・6年「聞いて、考えを深めよう」の単元では、「インタビューの中で、自分の思う『学校の良さ』と、先生の思う『学校の良さ』を比べながら聞く」という共通の学習課題を設定しつつ、図1のように、インタビューする先生、発信方法、まとめ方などを子どもたちが選択できるようにしました。また、「自己選択・自己決定」を促し、自分自身で計画を立てられるように、振り返りシートを共有し、学習の進捗状況を振り返りながら、必要に応じて計画を調整できるようにしました(図2)。これらにより、子どもたちは見通しをもち、自分たちから進んで学習に取り組むことができました。
「子どもたちの興味や関心を見取る」こと、そして「子どもたちの学びの場を広げ、自己選択・自己決定」できるようにすることは、「子ども主語」の国語授業を構築する上で非常に重要な要素です。ただし、どのような活動でもよいというわけではありません。各単元で「何を学習するのか」という目標をしっかりと共有し、子どもたちの活動の様子から学びの価値を見いだすことが不可欠です。
私自身も、これからも「子ども主語」の国語授業を、子どもたちと共に創り上げていきたいと考えています。
〔引用・参考文献〕
小西敦司(こにし・あつし)
大阪府・摂津市立三宅柳田小学校
明日の国語授業を語る会 理事
