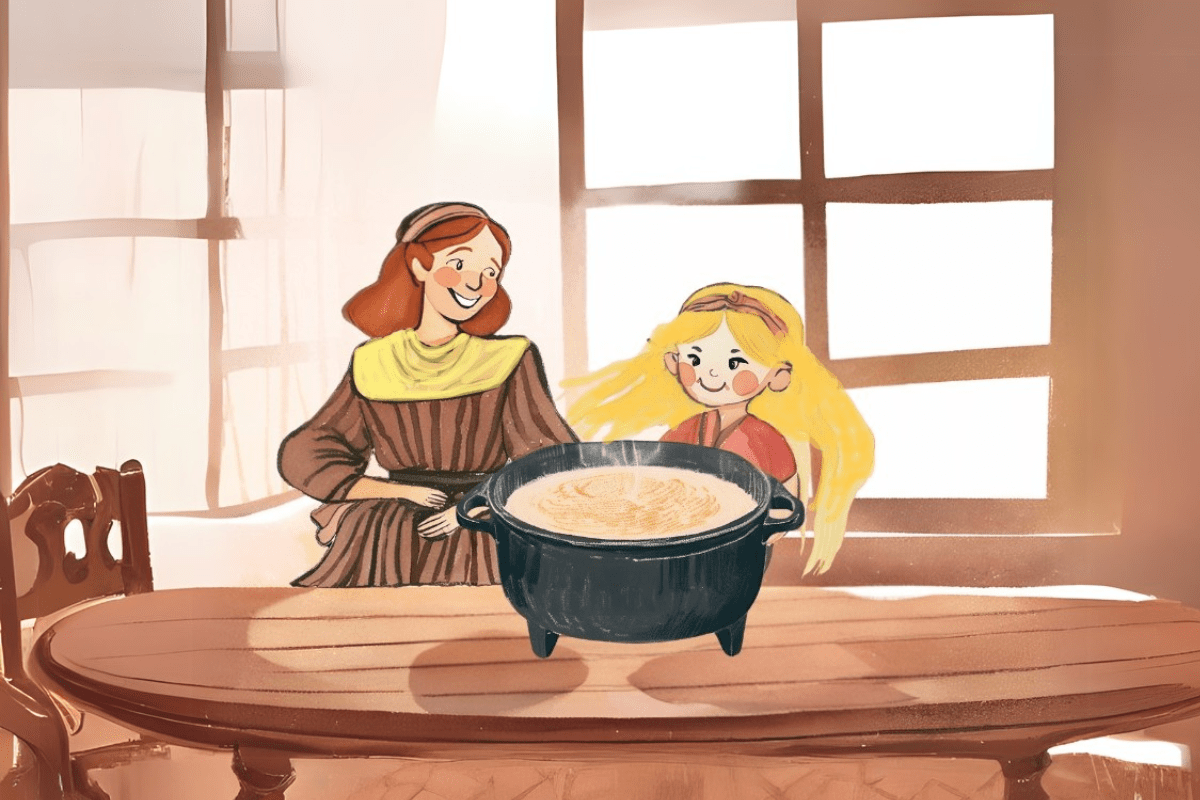
「おかゆのおなべ」 -低学年物語文でも根拠が大切であると実感できる授業-
|
執筆者: 柘植 遼平
|
単元名:かぎ(「」)の役割をマスターしよう
教材:「おかゆのおなべ」(光村図書・1年)
本教材では、「おかゆのおなべ」の呪文を、誰が知っていて、どのように言ったのかということが、この物語の起承転結をつくる鍵となっています。本教材の学習を通して、物語文を読む上で重要な、会話文を押さえることに意識が向くようになるでしょう。
今回は柘植遼平先生(昭和学院小学校)に、かぎ(「」)の役割や知識を深めつつ、かぎ(「」)が誰のセリフなのか本文を根拠にしながら読み進めることで、文学のおもしろさにふれられるような授業づくりの工夫を紹介いただきました。
目次
国語の読みものの学習は説明文と物語文の2つに大別される。説明文は、客観的に読みやすいこともあり、本文を根拠に具体的な言葉に注目しやすく、用語などの指導事項について、系統を意識した読みがわかりやすい。その反面、物語文の学習は登場人物の気持ちを問う活動があることから、どうしても主観的であったり、抽象的な学習になりがちであったりした。もちろん、物語文も言葉にこだわり、本文を根拠にした授業の実践例はいくつもある。しかし、いまだに気持ちのみを問うような実践も見受けられる。それが悪いとは一概にはいえないが、系統を考えていく上では必ずしも適切とはいえない。
そこで、この課題を解決すべく、より系統を意識した授業ができないかと考えた。系統を意識する上では、該当学年で必要な知識や用語の学習をきちんと行っておく必要がある。
光村図書の場合、1年生の物語では、
の学習が必要である。
現状の学習で、①と②については、1年間の物語文で繰り返し学習することで学ぶことができている。その反面、③については、「くじらぐも」「たぬきの糸車」などで行っているが、十分とはいえない。それは、2年生「お手紙」の学習時に実感することができる。2年生を担任するたびに、すっかり忘れている子どもを何人も目にしてきた。この③を今回は、なんとかしたいと考えた。
国語の学習に限らず、子どもたちは日常生活の中でかぎ(「」)を目にしている。それは、本や絵本であったり、何かの宣伝CMやポスターであったりする。本や絵本の場合はかぎ(「」)が会話文(セリフ)であることが多い。しかし、宣伝CMやポスターなどでは会話ではなく「強調」の役割として使われている。大人はそれを理解しているので勝手に、「1年生で学習したし、よく見るものだからわかっているでしょ」と思ってしまっていることがある。「③カギかっこ=会話文」ということを学んだ後に、詳しくふれる機会が少ないのである。
かぎ(「」)については、算数でいう繰り返し出合うことで理解していく習熟に当たる学習が、1年時に足りていないことを表していると感じた。そこで、かぎ(「」)について学習を行うために適した教材で、授業づくりの工夫を考えた。
