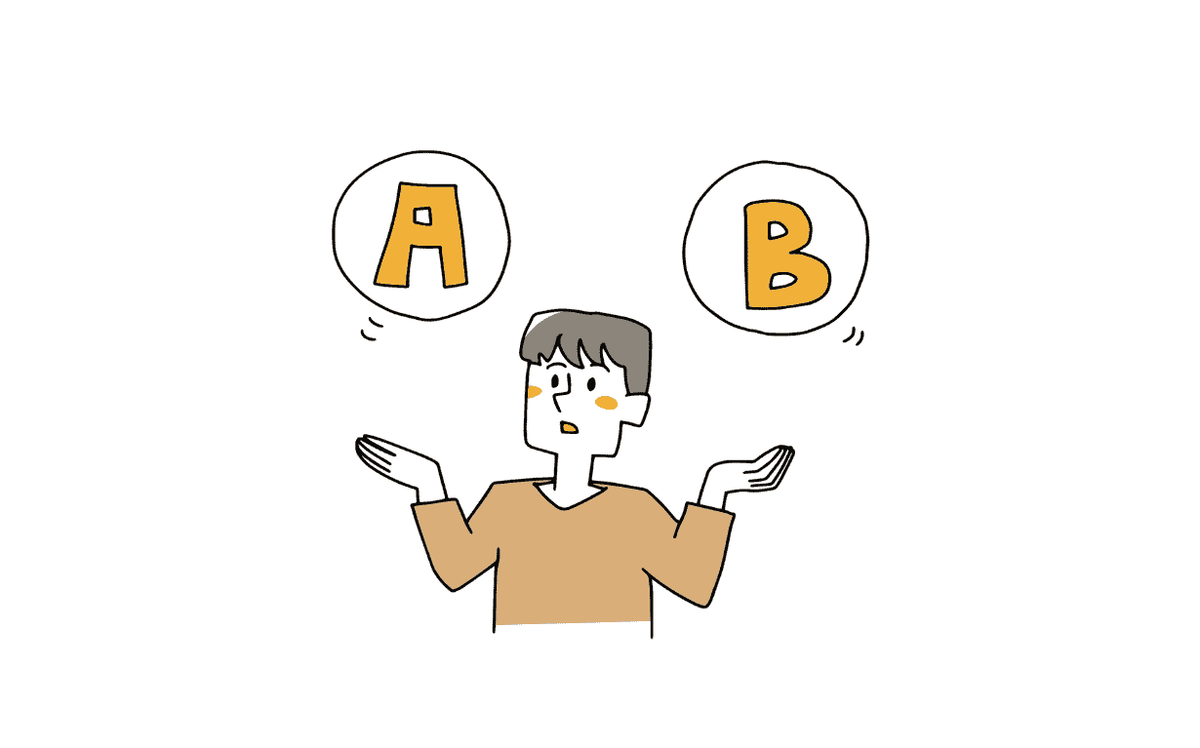
「思いやりのデザイン/アップとルーズで伝える」 -「くらべる説明文作り」で対比的にとらえるよさを実感しよう―
|
執筆者: 山本 真司
|
単元名:くらべて考えよう 教材:「思いやりのデザイン/アップとルーズで伝える」(光村図書・4学年)
今回は、山本真司先生(愛知県・南山大学附属小学校)に、子どもたちが物事を対比的にとらえることに自覚的になり、日々の生活へと結びつく力を育むような授業づくりについてご提案いただきました。文章の内容そのものにとどまらず、事柄の関係性へと目を向けさせることが重要になります。
また、基本三部構成や段落同士の関係を視覚化した段落構成図を、ぜひ板書や資料作成に役立ててみてください。
目次
「ノートに手書きがいい? タブレットにタイピングがいい?」
「海に行く? 山に行く?」
「都会がいい? 田舎がいい?」
「今を楽しむことが大切? 将来のために苦しくても努力することが大切?」
私たちは、日常生活において何かと何かを対比させて考えることがよくある。 また、物事を敢えて対比的にとらえることで、双方のメリットとデメリットを冷静に比較して1つの答えを決断したり、状況に応じて判断したりすることもできる。生きる上で役立つ論理的なものの見方の1つと言える。
4年生の子どもたちは、日々の生活の中で物事を対比的にとらえることもあるのだろうが、そのことを厳密に自覚しているわけではない。
そこで、国語の出番である。
説明的文章を読む学習を通して、生活経験から得ている曖昧な概念が洗練され、自覚的に使える知恵とすることができる。 本教材「思いやりのデザイン/アップとルーズで伝える」は、この物事を対比的にとらえることのよさを学ぶのに適した教材である。
「対比的にとらえる」ことを柱とした単元づくりを通して、学習を「国語」に閉じたものではなく、日常生活に開かれた生きる知恵を学べる学習にしたい。
