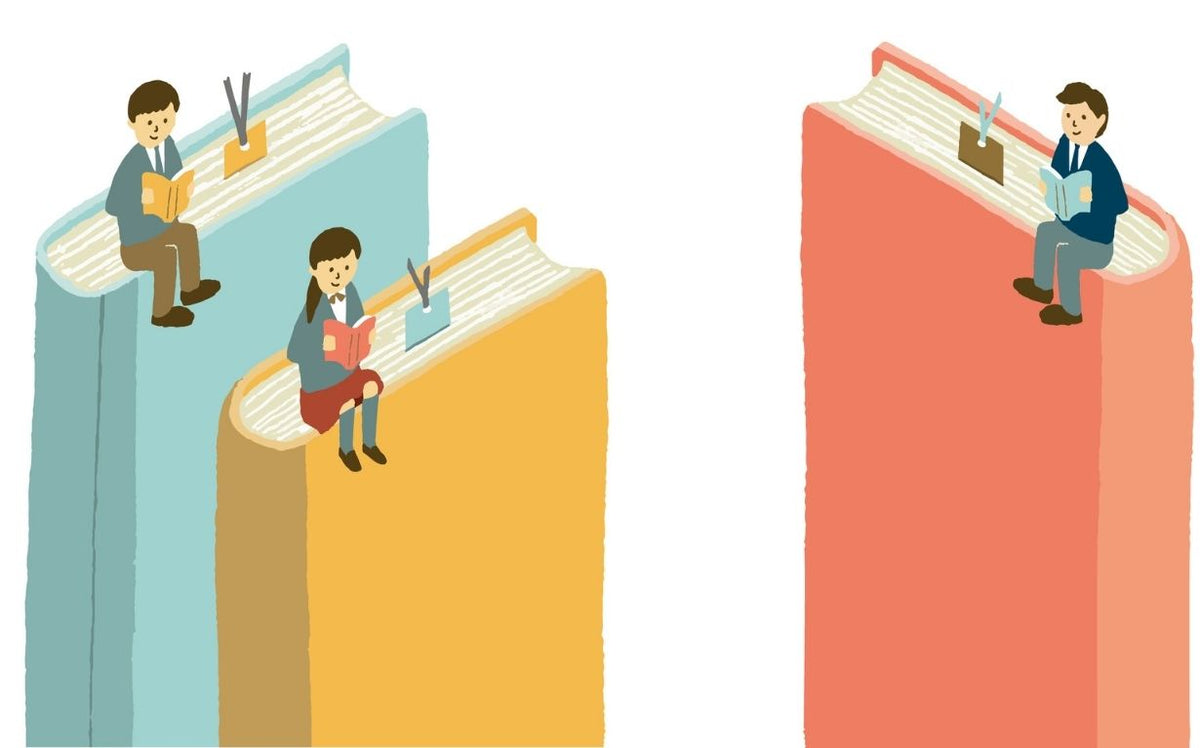
「白いぼうし」 -物語の魅力は「人物相関図」でどのように引き出されるのか?-
|
執筆者: 沼田 拓弥
|
単元名:場面や人物のつながりを読み、考えたことを伝えよう
教材:「白いぼうし」(光村図書/教育出版/学校図書4年)
今回は「白いぼうし」の授業づくりを紹介します。
物語文では、主人公や主人公との関わりが深い人物に注目しがちですが、実はその周りの人物が重要な役割を担っており、「物語をドラマチックにするしかけ」が必ず存在します。
今回は、沼田拓弥先生(東京都・八王子市立第三小学校)に子どもの興味・関心までもが可視化され、さらには思考がどんどん広がる板書をはじめとした授業づくりについてご提案いただきました。
目次
物語教材を扱う授業では、登場人物の関係性をどのように捉えたかによって、読みの深さが大きく変わってくる。
テレビドラマのホームページなどで紹介されている「人物相関図」を見たことがあるだろうか。主人公を中心に、主人公と関わりの深い人物がそばに配置され、登場回数は少ないものの、実は物語の展開に重要な役割を果たす人物がその周りに配置されている。そして、これらの人物をいくつもの線でつなぐことによって、ドラマ内における出来事やお互いの関係性が簡潔に整理される。いわば「物語の縮図」である。これを見れば、視聴者が、物語の大体を捉えられるものになっている。
実は、国語授業で扱われる物語作品もこの「人物相関図」を用いることで、子どもたちに多くの発見をもたらすことができる。これまでの国語授業では、登場人物の関係性を整理する際、物語の中心人物Aと対人物Bの二人の関係性に焦点化することが多かったのではないだろうか。お互いをどのように思っているのか(例えば、「大造じいさんとガン」「ごんと兵十」「がまくんとかえるくん」など)を考え、整理する授業が一般的な授業展開といえる。もちろん、中心人物と対人物の関係を捉えることは、物語を読み味わう上で必須の力である。
しかし、本当に物語のおもしろさを引き出しているのは、一瞬だけ顔をのぞかせる周辺人物ではないだろうか。つまり、「大造じいさんとガン」では、おとりとなった1羽のガン、「ごんぎつね」では、加助や兵十のおっかあ、「お手紙」では、かたつむりくんである。これらの登場人物は、登場回数は少ないものの、実は中心人物の重要な行動のきっかけとなる大切な役割を果たしている。
このように考えると、物語中の人物は、誰一人として無意味なものは存在しない。作者は、必ず「意味」をもたせてその場に登場させているのである。それは、中心人物に直接、影響を与えるものだけではない。作品の雰囲気を醸し出したり、中心人物とその周りにいる人物をつなげたりする役割も担っているのだ。まさに、「物語をドラマチックにするしかけ」ともいえるだろう。
ぜひ、これまで扱ってきた作品の登場人物をもう一度見直してみてほしい。必ず思わぬ発見があるはずである。
このように、各登場人物が果たす役割や関係性を整理する中に、物語の魅力を引き出す新たな「気付き」や「発見」が生み出されるのである。本稿では、この人物関係を整理する方法の1つとして「人物相関図」を活用し、より物語作品の魅力を引き出す学びの在り方に迫りたい。
