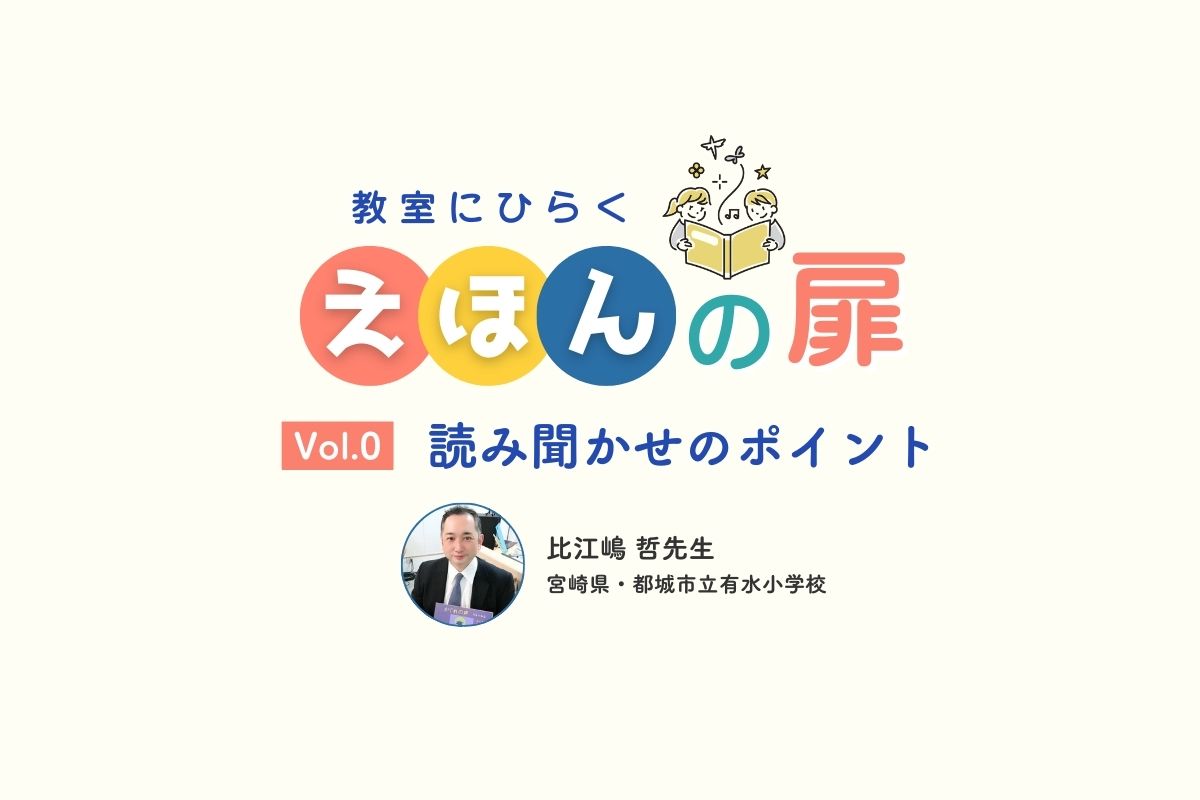
教室での読み聞かせ ー成功の秘訣
|
執筆者: 比江嶋 哲
|
今回は、比江嶋哲先生(宮崎県都城市立有水小学校)に、教室で絵本を読み聞かせをする際に、子どもたちが集中して聞けたり、お話の世界を楽しめたりするためのさまざまなコツをご紹介いただきました。
本の持ち方や、めくり方、読む間合い、ちょっとした工夫で、読み聞かせの時間が、穏やかで心地よいひとときになるのではないでしょうか。
でも何より大切なことは、先生も子どもたちと一緒に、お話の世界に浸って楽しむことです。
ぜひ、ちょっとしたすき間時間や帯単元として、教室に絵本の読み聞かせを取り入れてみてください。
どんな本をいつ読むのか計画を立てておきましょう。変化のある組み合わせ、読む順番を工夫しましょう。
季節感や行事など、時期に合わせた選書も大切です。
同じ学級で過ごす子どもたちでも、読書経験は様々です。どの子どもも楽しめるように意識しましょう。
ある程度の大きさがあって、少し離れた場所に座っていても見えることが大事です。
見開きで一場面、または1ページに一場面が望ましいでしょう。
素朴に読むようにしましょう。
声は明瞭に、ゆっくりと意識しましょう。
地の文を大切に…物語を語っているという意識を大切にしましょう。
本がぐらつかないように、脇を締めて、安定した持ち方で持ちましょう。 自分の体で本がかくれないようにしましょう。
手は絵本の上か下にかけて、腕で紙面を隠さないようにしましょう。
めくる速さや間も、読み味わうための大切な要素です(話の展開にあった、めくる速さの工夫をしましょう)。
子どもたちが絵を見る時間を、十分に保障しましょう。
めくる前には一呼吸おき、めくってからも、すぐに言葉を重ねないようにしましょう。
〔読み始め〕
①表紙を見せ、タイトル、作者名、訳者名を読みましょう。
②前見返し、タイトルページを1ページずつめくって、本文に入るようにしましょう。 見返しに絵がある場合は、その絵もしっかり見る時間を取りましょう。見返しは、本文までの大事な「まえがき」です。
〔読み終わり〕
①読み終わったら、後ろ見返し、裏表紙も見せ、表紙にもどって「(タイトル)でした。おしまい」でしめくくりましょう。
②表紙、裏表紙の絵がつながっている場合は、広げて両方見せてから終わりましょう。
〔大型絵本〕
たてに長い絵本、横に長い絵本、全体的に大きな絵本などがあります。
絵に迫力があるものは、子どもたちにしっかり見えるように意識して読みましょう。
〔エプロンシアター〕
お話に出てくる家や風景、登場人物をエプロンに付け、ストーリーの展開に合わせて動かすことで、臨場感のある読み聞かせをすることができます。
比江嶋 哲(ひえじま・さとし)
宮崎県都城市立有水小学校教頭
全国国語授業研究会理事/全国大学国語教育学会会員/日本国語教育学会会員
