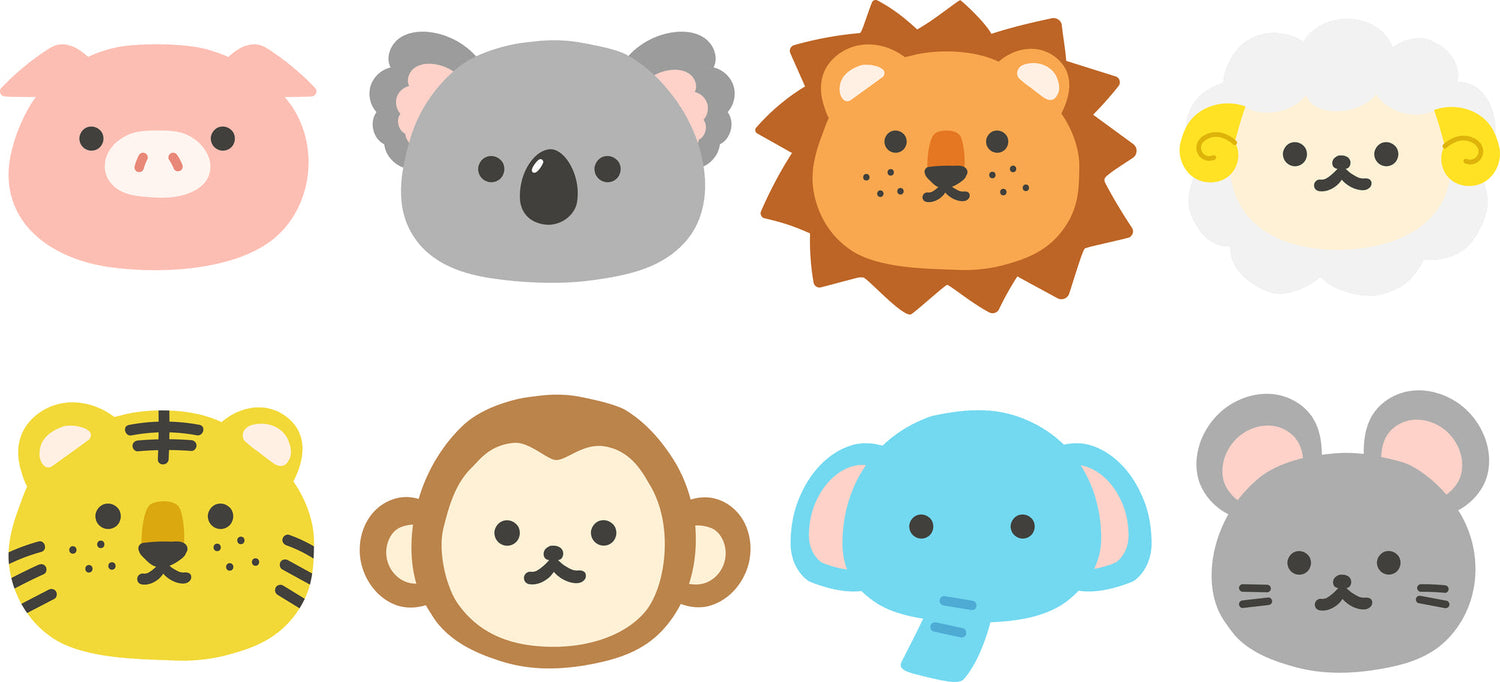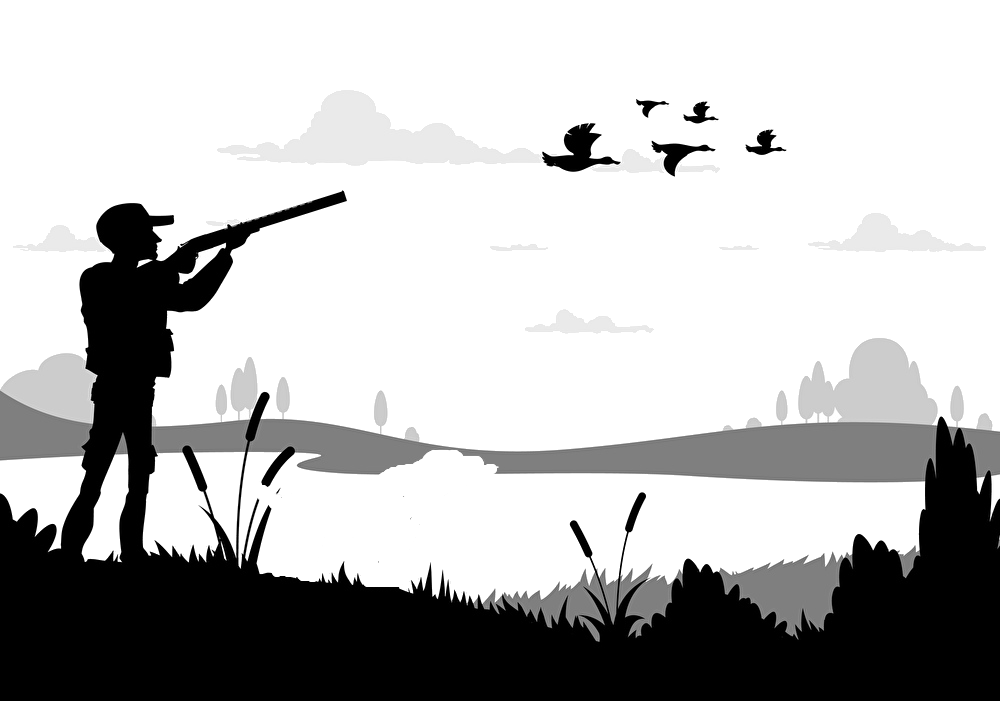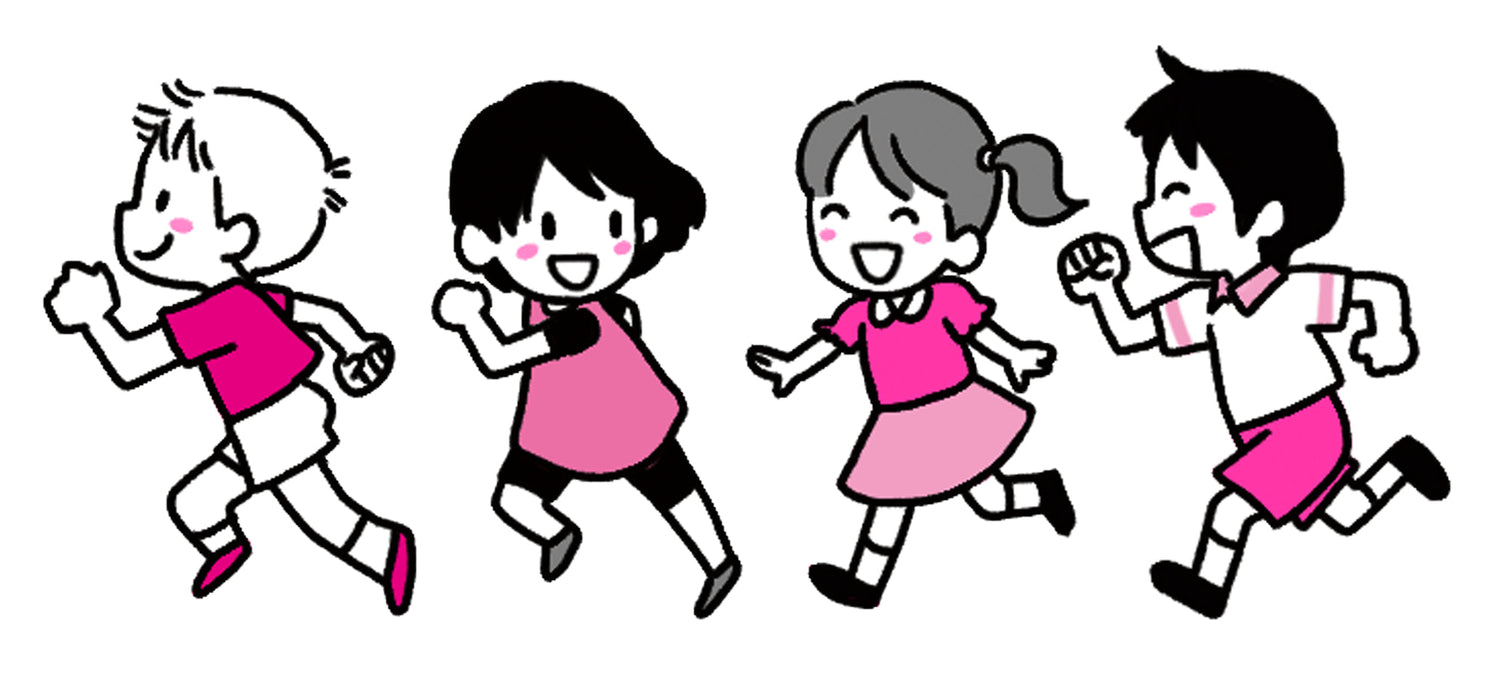子どもと創る「国語の授業」
![]() 有料記事
有料記事
「どうぶつの赤ちゃん」
-学びの選択肢が個と協働の学びを支える-
「どうぶつの赤ちゃん」の授業づくりを紹介します。本教材は、ライオンとしまうまの2つの事例を挙げて、問い対する答えを説明しており、読者が2つの事例を比較しながら読むことを促す仕掛けが工夫された説明文です。今回は、山田秀人先生(宜野湾市立大山小学校)に子どもたち一人ひとりが参加する国語授業を目指すための表現活動の工夫や、子どもが自分で学び方を選択できる手だての具体について、本教材での授業に沿ってご提案いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
「大造じいさんとガン」を私はこう授業する!!
「大造じいさんとガン」の授業づくりを紹介します。本教材は、人物の見方・考え方の変容を捉えることをねらいとし、また、衝撃的な結末は子どもたちの記憶にもずっと残るであろう、昔から教科書に掲載されている定番教材です。今回は藤田伸一先生(神奈川県・川崎市立土橋小学校)に、細やかな教材分析の内容と、人物の心情に新たな観点から迫るポイントを押さえた授業づくりの具体についてご提案いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
「どうぶつ園のじゅうい」で「読む・書く」力をつける授業づくり
「どうぶつ園のじゅうい」は、獣医である筆者が自分の一日の仕事について時系列で説明した文章です。〈はじめ・中・おわり〉の三部構成で、〈中〉の部分に仕事内容が述べられ、筆者がしたこととその理由が説明されています。 説明文ですが、「ひとあんしんです」「ようやく長い一日がおわります」のように、筆者の思いや心情が記されている点が特徴的です。
単元を通して継続したい「問い」の意識
-2年・「お手紙」「どうぶつ園のじゅうい」の実践から-
今回の5分でわかるシリーズは、子どもたちに単元を通して継続して意識することのできる問いの工夫について、佐藤亜耶(白河市立白河第二小学校)先生に提案していただきます。叙述に基づいて、子どもたち自身が問いの根拠を見つけ、考えることは国語の学習において大切なことです。2年生の「お手紙」「どうぶつ園のじゅうい」の教材を例に、授業においての「問い」づくりを一緒に考えていきましょう。
![]() 有料記事
有料記事
「おにごっこ」
-<つながり>から学びを深める低学年の説明文授業-
「おにごっこ」の授業づくりを紹介します。 子どもたちにとって親しみ深い遊びを題材にすることで、積極的な言語活動を促すことができる本教材。おもしろさを通して、文章の構造や事例の並べ方を理解し、中、高学年へとつながる「文章を見る目」の素地を育てます。 今回は、沼田拓弥先生(東京都・八王子市立第三小学校)に子どもが前のめりになる授業づくりについてご提案いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
「海の命」の授業アイディア
-FUNからINTERESTの授業づくり-
「海の命」の授業づくりを紹介します。本教材は、小学校6年間の最後の物語文であり、語り手が太一の視点に沿って語っていること、比喩や色彩語、擬音語などが豊富に使われる情景描写が多いことも特徴であります。 今回は、溝越勇太先生(日野市立日野第七小学校)に、「初発の感想を書けない」子どもへの指導の工夫をはじめ、子どもたち自身が国語の世界の楽しさを味わえる、そんな授業づくりについてご提案いただきました。