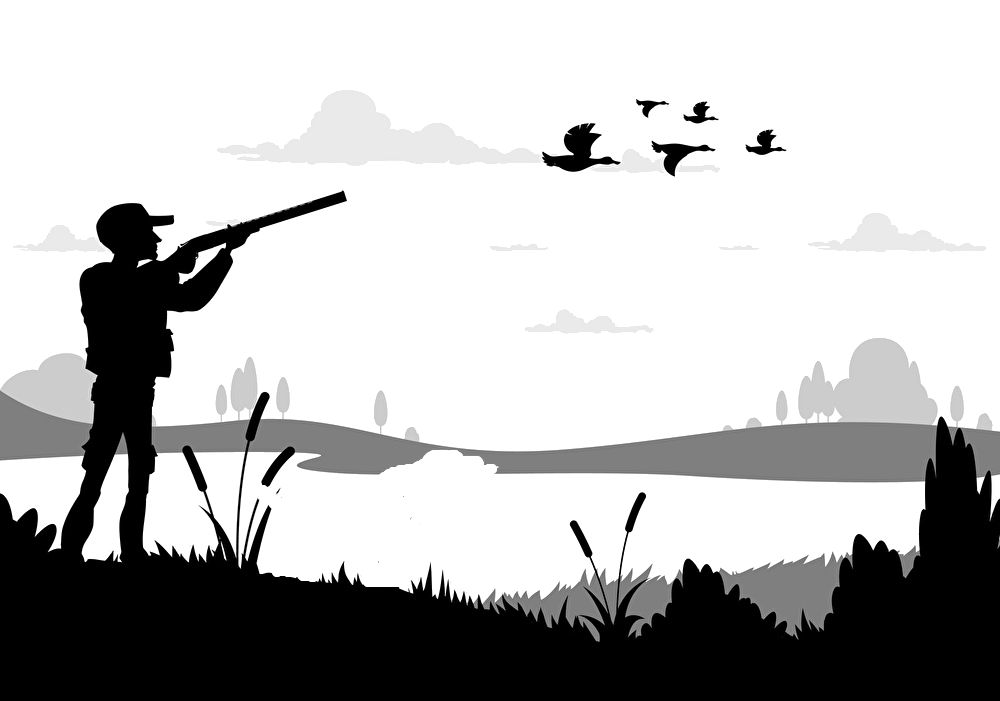
「大造じいさんとガン」を私はこう授業する!!
|
執筆者: 藤田 伸一
|
単元名:人物の見方・考え方の変容を捉えよう
教材:「大造じいさんとガン」(全社/5年)
「大造じいさんとガン」の授業づくりを紹介します。
本教材は、人物の見方・考え方の変容を捉えることをねらいとし、また、衝撃的な結末は子どもたちの記憶にもずっと残るであろう、昔から教科書に掲載されている定番教材です。
今回は藤田伸一先生(神奈川県・川崎市立土橋小学校)に、細やかな教材分析の内容と、人物の心情に新たな観点から迫るポイントを押さえた授業づくりの具体についてご提案いただきました。
目次
戦時中に書かれた作品である「大造じいさんとガン」は、今もなお教科書に掲載され読み継がれている。なぜ、こんなに古い作品が残っているのだろうか。どうして本教材を授業で扱う必要があるのか。その問いに答えていこうと思う。
その理由は、おそらく、教材としての何らかの価値を有しているからにちがいない。それをあぶり出し、子どもたちにとって学びがいのある「言葉の力」を教師がまず自覚する必要があるだろう。
◎人物の見方・考え方の変容を捉えやすい
◯人物の心情に新たな観点から迫ることができる
・情景描写から
・色彩語から
中心人物である「大造じいさん」が、数度にわたる戦いを経て「ガン」とりわけ「残雪」への見方・考え方が変化していく。「たかが鳥」から「英雄」へと大きく見方・考え方を変えている。人物の見方・考え方の変容を捉えることが、本単元の中心となる。この変容を捉える力が、6年で学習する「海の命」に活かされる。太一が生きる「海」への見方を変えていく過程を自力で捉えていくことにつながっていく。
どのように人物の見方・考え方を捉えていくのかを考える前に、「大造じいさん」を変える対象として描かれている「残雪」は、人物なのかどうかに言及していきたい。
結論は「No」である。鳥という動物としてあくまでリアルに描いていると私は捉えている。人間対鳥の戦いなのである。鳥としての本能や習性で「残雪」は作品世界を生きる。その存在を「大造じいさん」のフィルターを通して、まるで人物が行動しているかのように映っていく。
では、どのように人物の見方・考え方に迫ればよいのだろうか。「大造じいさんの残雪に対する見方・考え方がどのように変わっただろう?」このように発問をすれば何人かの子どもは動くことだろう。しかし、これでは課題を解決していこうという意欲が湧かない。それのみならず、どう変化を捉えればよいのかが分からない。作品全体を通してどのように変わってきたのかという変容の全体像も見えない。
そこで必要になってくるのが、具体的な言語活動である。「人物の見方・考え方グラフ」を導入する。下の資料1を見ながら読み進めてほしい。
ノート1ページ分を取る。右側が大造じいさん。左側に残雪を配置する。上段には、一から四場面の番号を振っておく。大造じいさんが、どう残雪を見ているのか、それを場面ごとに点を打つことによって視覚化していく。中心の破線のラインに打った場合は、対等関係を意味する。破線より下に点を打った場合は、自分より下に見ていることになる。破線より上に打った場合は、自分よりも上の存在だと見ているというように表していく。
ここで気を付けていきたいポイントが3つある。
