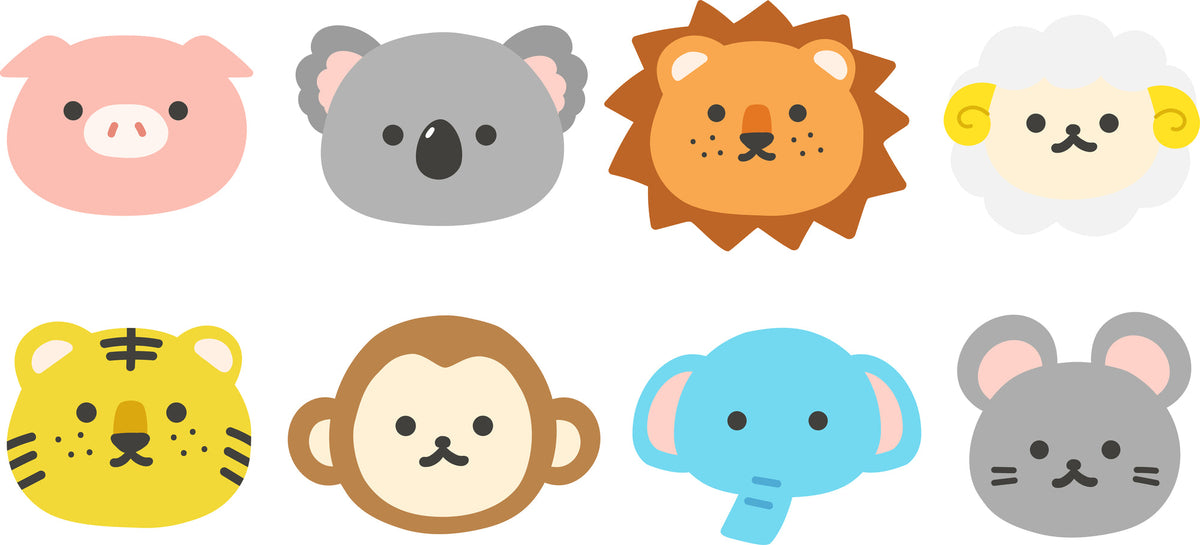
「どうぶつの赤ちゃん」 -学びの選択肢が個と協働の学びを支える-
|
執筆者: 山田 秀人
|
単元名:くらべて よもう 教材:「どうぶつの赤ちゃん」(光村図書/1年)
「どうぶつの赤ちゃん」の授業づくりを紹介します。本教材は、ライオンとしまうまの2つの事例を挙げて、冒頭の問いに対する答えを説明しており、子どもが2つの事例を比較しながら読むことを促す仕掛けが工夫された説明文です。今回は、山田秀人先生(沖縄県・宜野湾市立大山小学校)に子どもたち一人ひとりが参加する国語授業を目指すための表現活動の工夫や、子どもが自分で学び方を選択できる手だての具体について、本教材での授業に沿ってご提案いただきました。
目次
ここで言う「参加」とは、学習の場に居るだけではない。子ども一人ひとりが課題をもって、その解決に向けて自分なりに活動していることだと考えている。 例えば、教師の一方的な発問により、一問一答形式の授業で、いわゆる勘のいい子どもだけが発言していく授業があったとする。勘のいい子の発言のみが板書される黒板をノートに写すだけでは、ほかの子どもたちにとって、そこに一人ひとりの学習が成立しているとは言い難い。
藤井千春によれば、「学習とは、既有の知識を使用して世界と相互作用し、自らの知識体系(概念)を修正・発展的に再構成していく知的活動」であると述べられている。このことを本単元において考えてみる。動物の赤ちゃんについて、子どもが既にもっている知識や説明文についての知識体系を教材と向き合うことで、修正・発展的に再構成していくことだと捉えた。
ここでは、そのような学習のあり方が成立する全員参加の国語授業を支える手だてとして、次の2つを紹介したい。
