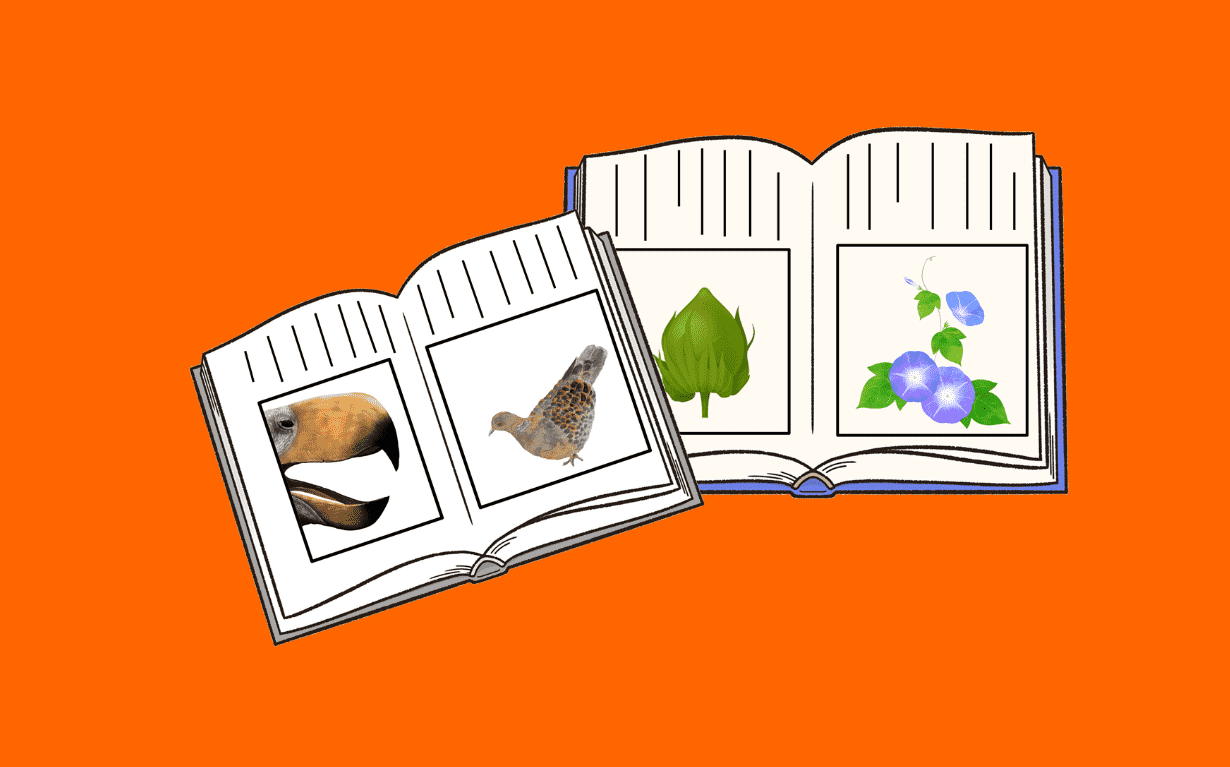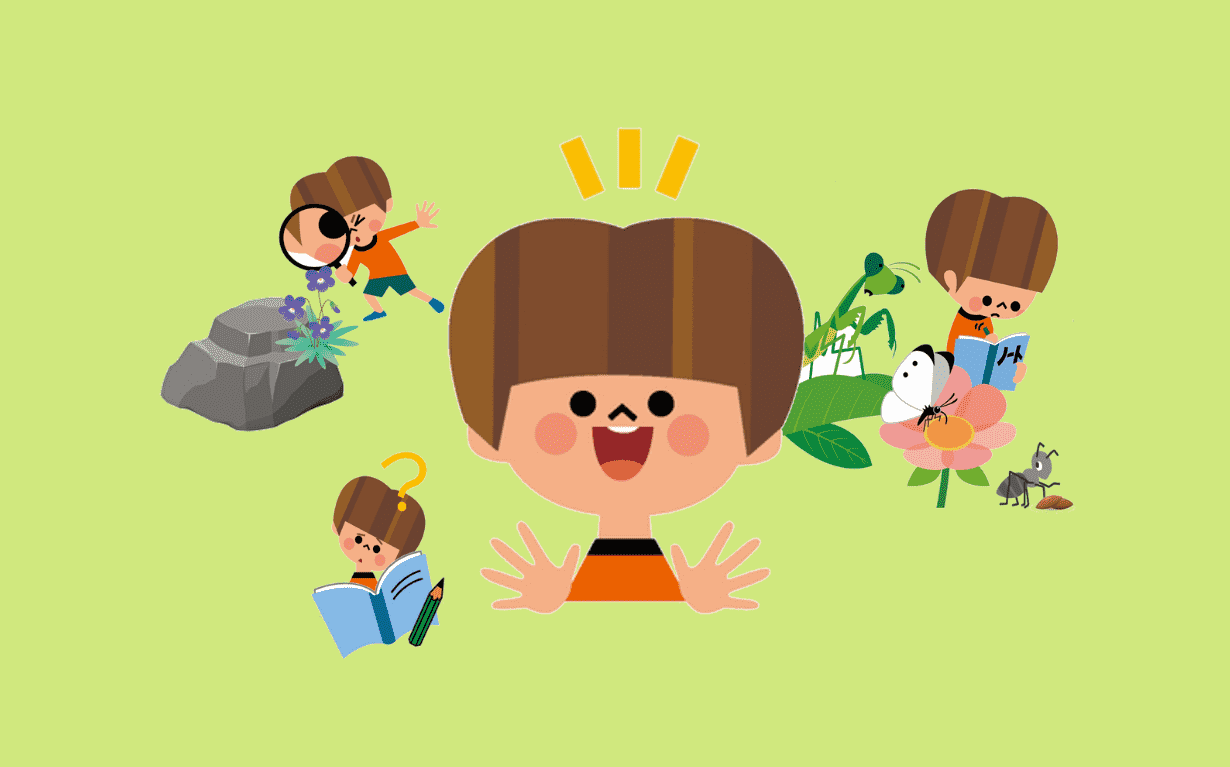子どもと創る「国語の授業」
![]() 有料記事
有料記事
新教材「つぼみ」
-旧教材「くちばし」と見比べて読み、「問い」と「答え」の関係を深めよう!-
1年生はじめての、説明文の学習となる新教材「つぼみ」(光村図書 1年)では、「問い」と「答え」が明確に示されることで、説明文とはある事柄について筋道を立てて説明するものであることを、学習者が押さえることができます。 今回は笠原冬星先生(大阪府・寝屋川市立三井小学校教諭)に、子どもたちが文章を読み比べることを通して、説明文の特徴や構成に意識的になることができる授業づくりを、提案していただきました。
![]() 有料記事
有料記事
つながりで読む国語の授業づくり
―2年・「すみれとあり」―
「伏線」と聞くと、物語文を思い浮かべる方が多いでしょう。 説明文においても伏線を意識することで学びを広げていくことができます。 今回は、2年1学期において、学ぶことを楽しむ姿勢を育てていくための学習の様子を紹介します。 なお、2年生に伏線という用語は難しいので、「つながり」を考えて学習することの大切さとして伝えています。
5分でわかる 学習者の思考を叙述へと誘う挿絵の活用法
今月の5分で分かるシリーズは、木𠩤先生(山口県・長門市立仙崎小学校)に、物語文の学習でよく行われる挿絵を並び替える学習活動をあらためて問い直し、充実した活動になるコツを紹介していただきました。ヴィジュアル・シンキング・ストラテジーズ(VTS)といった教育プログラムを導入することで、子どもたちが挿絵を観て、対話を通して物語を想像し、ワクワクしながら自分なりの解釈と読みをもつことにつながります。
![]() 有料記事
有料記事
「インターネットは冒険だ」
-「要旨をまとめる」とは何か? をおさえて読もう-
今回は、田中元康先生(高知県・高知大学教職大学院教授/高知大学教育学部附属小学校教諭)に、教材「インターネットは冒険だ」(東京書籍・5年)の授業づくりの工夫について、紹介していただきます。説明文の学習で当たり前のように行われる「要旨をまとめる」とはどういうことなのか。あらためてその意味や方法を確認しながら学ぶことで、汎用的な読みの力が育ちます。
![]() 有料記事
有料記事
読後感から始まる国語科授業づくり①
-4年・「白いぼうし」—
文学の授業における、初発の感想を書かせるという活動に替わるものとして、「読後感」を書くという実践を以前掲載した。これを基にした授業づくりについてこれから述べていきたい。 文学作品に出合ったときの新鮮な気持ちを大切にしたいと思う。教師主導で学習課題を設定することもあるだろうが、やはり子どもが自ら読んでいくための問いをもてるようにするためにはどうしたらよいかと考えたとき、読後感から問いをつくっていくということは、その1つの方法であると考える。
![]() 有料記事
有料記事
「まいごのかぎ」
-知識や経験と結び付けて読む力を育む-
本教材「まいごのかぎ」(光村図書・3年)は、登場人物 りいこが次々と遭遇する不思議な出来事が、第三者目線とりいこの視点とを織り交ぜて描写されることで、読み手もまるで巻き込まれていくかのように展開し、ワクワクしながら物語の中に入り込むことができます。 今回は小島美和先生(東京都・杉並区立桃井第五小学校)に、一つひとつの叙述を自身の経験を想起しながら丁寧に押さえ、りいこの気持ちや行動と比較することで、人物像に迫っていく授業づくりを、紹介していただきました。