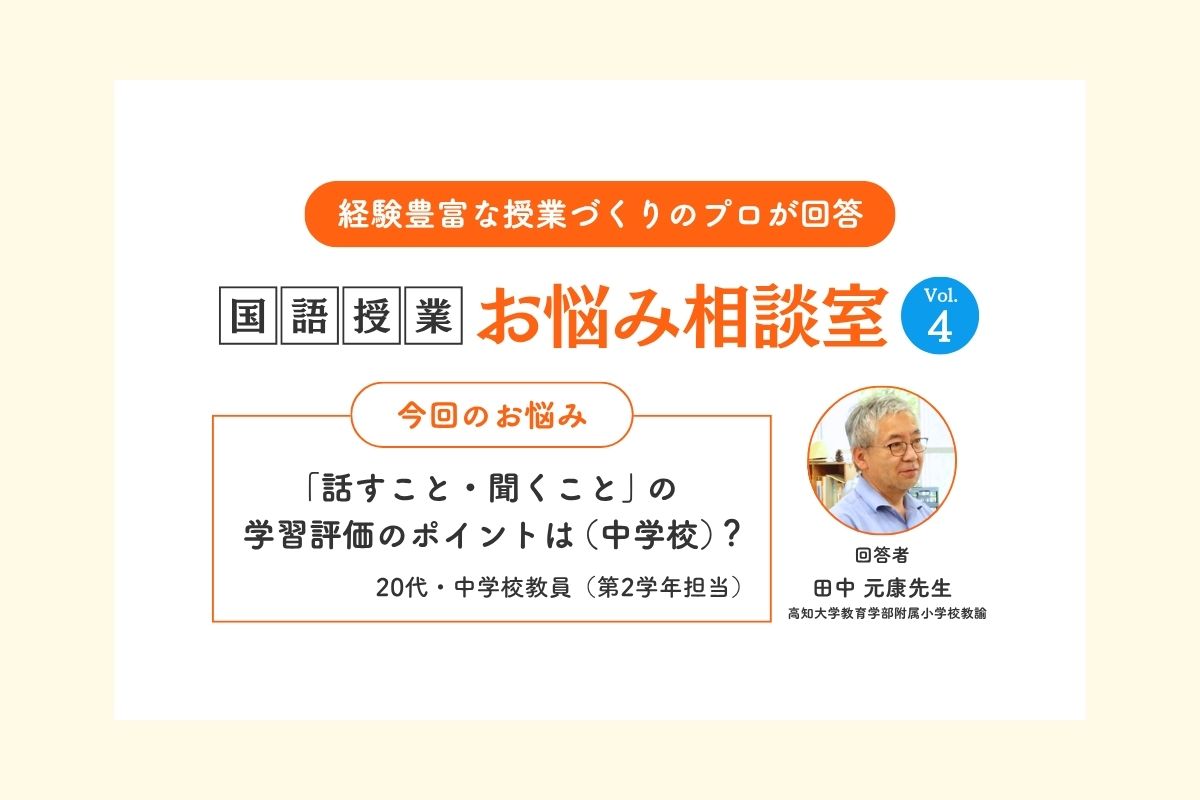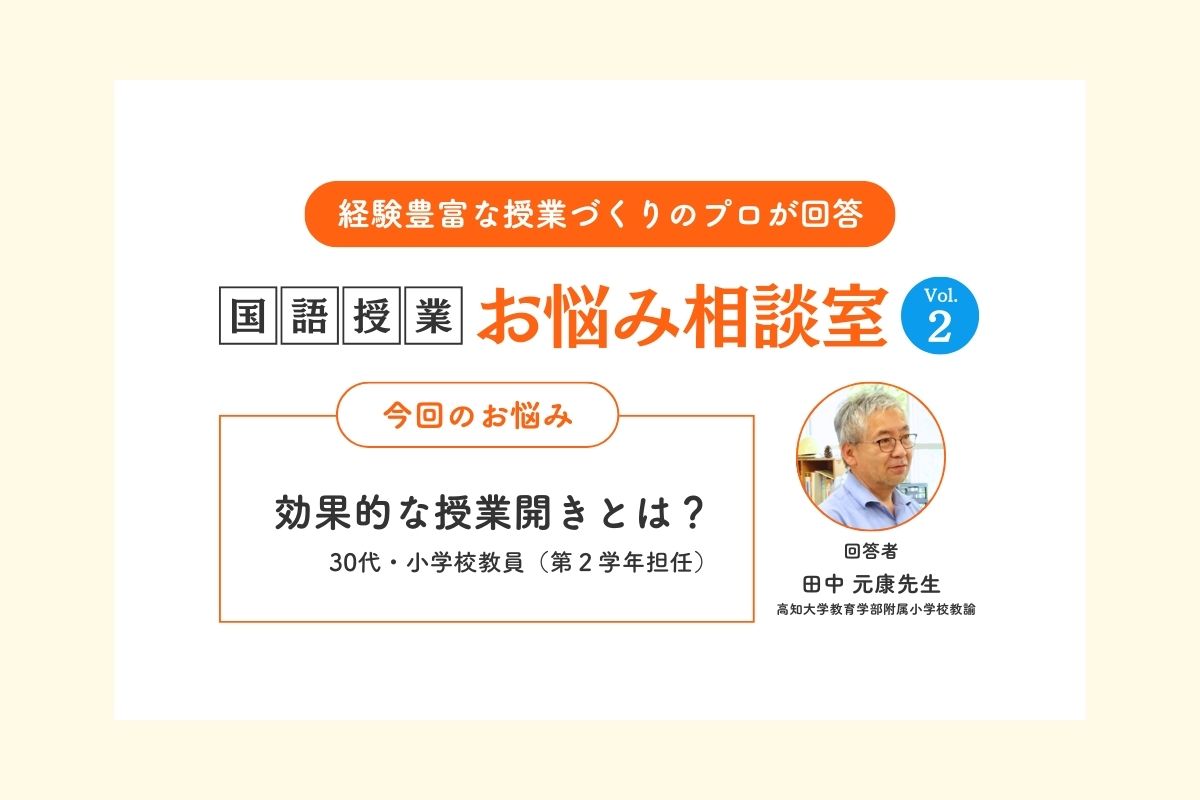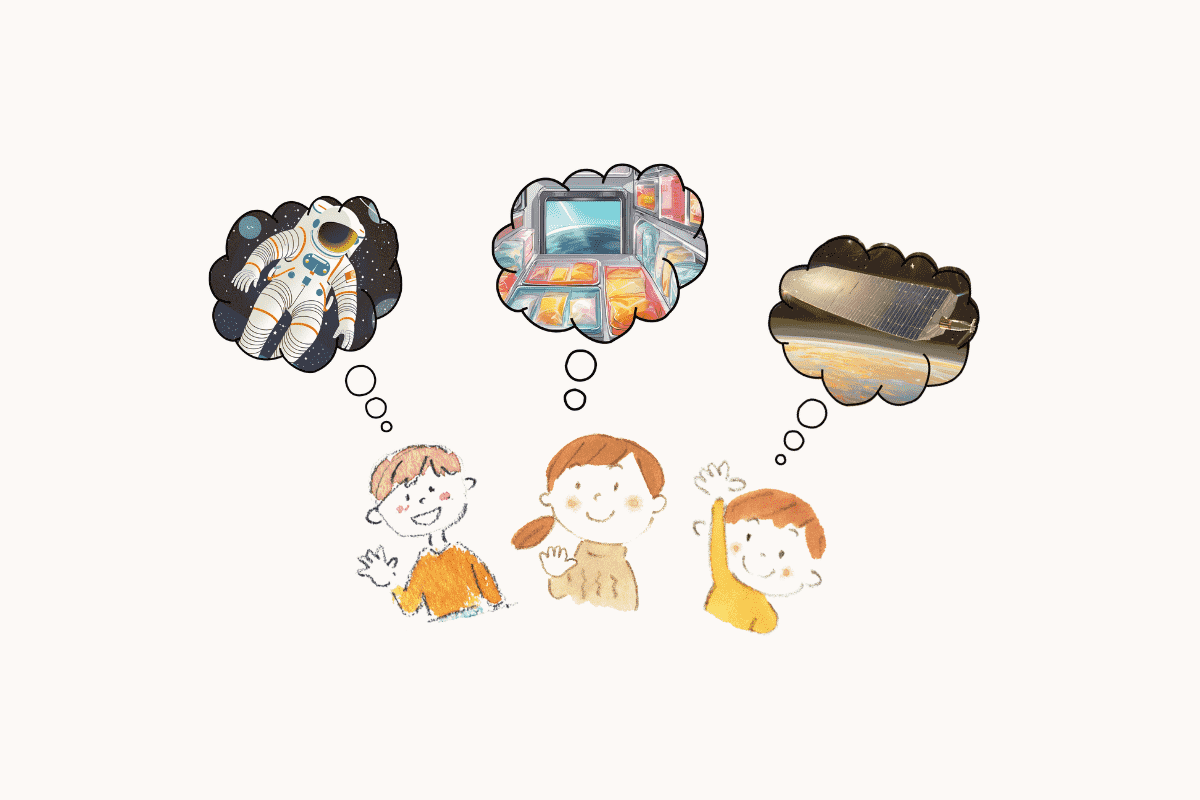子どもと創る「国語の授業」
![]() 有料記事
有料記事
「永遠のごみ」プラスチック
―重ね読みから自分の考えをもつ説明的文章の授業づくり―
今回は本教材の授業づくりにおいて、田中元康先生(高知大学教職大学院 教授/高知大学教育学部附属小学校 教諭)に、本文と資料①②を合わせて読み、それぞれの主張と説明の仕方を子どもたち自身でまとめるという学習活動についてご提案をいただきました。その活動を通して、筆者の考えと相対化された自分なりの考えをもつことができ、発表へ向け、わかりやすい説明の工夫にも意識的になることでしょう。
![]() 有料記事
有料記事
Q 「話すこと・聞くこと」の学習評価のポイントは(中学校)?
作文やノート、ワークシートなどに文字言語として表すもので評価する「書くこと」や「読むこと」とちがって、音声言語を対象とする「話すこと・聞くこと」は評価の方法やタイミングに悩むところです。 今回は、「話すこと・聞くこと」の評価を、教師にとって現実的で、生徒にとってわかりやすいものとするためにはどのように考えたらよいのか、田中元康先生(高知大学教育学部附属小学校)に回答いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
Q 効果的な授業開きとは?
先生方と同様、子どもたちも新たな出会いと始まりに、ドキドキの心持ちでいる4月。 だからこそ授業開きでは、表現すること、できたという思いをもつこと、そして、互いを知るという経験を積むことができるようにしたいものです。 そこで、「表現をして・達成感を味わう、詩の音読・暗唱」「互いを知る話し合い活動」の2つをご紹介します。 「国語の授業ってワクワクする!」そんな声が聞こえる教室を目指しましょう。
![]() 有料記事
有料記事
「宇宙への思い」
—著者の「思い」を読み取り、みんなで考えを共有しよう—
新教材「宇宙への思い」は、本文中、宇宙そのものへの感想や気持ちが表れている箇所が実は少なく、宇宙での経験や研究(事実)を通して、地球や身近なことの未来をどのように考えたのか(願い)が、最後に述べられていることが特徴的です。 本教材について、田中元康先生(高知大学教育学部附属小学校教諭/高知大学教職大学院教授)に、主語と文末に着目して読み、著者の述べている考えと事実を整理していく学習活動について提案していただきました。根拠に基づいて自分なりにまとめるため、より友だちと考えを共有し、読み深めたくなるでしょう。
![]() 有料記事
有料記事
「インターネットは冒険だ」
-「要旨をまとめる」とは何か? をおさえて読もう-
今回は、田中元康先生(高知県・高知大学教職大学院教授/高知大学教育学部附属小学校教諭)に、教材「インターネットは冒険だ」(東京書籍・5年)の授業づくりの工夫について、紹介していただきます。説明文の学習で当たり前のように行われる「要旨をまとめる」とはどういうことなのか。あらためてその意味や方法を確認しながら学ぶことで、汎用的な読みの力が育ちます。
![]() 有料記事
有料記事
「ごんぎつね」
-思いつきの感想の交流からの脱却-
「ごんぎつね」の授業づくりを紹介します。本教材は各社の教科書に掲載されている定番教材です。登場人物である「ごん」と「兵十」の行動から、心情の変化を読み取ることができます。今回は、田中元康先生(高知大学教育学部附属小学校教諭/高知大学教職大学院教授)に、ごんと兵十二人の関係性に着目し、距離を読むことで、子どもたち自身が考えや感想をもって交流し合う授業づくりについてご提案いただきました。