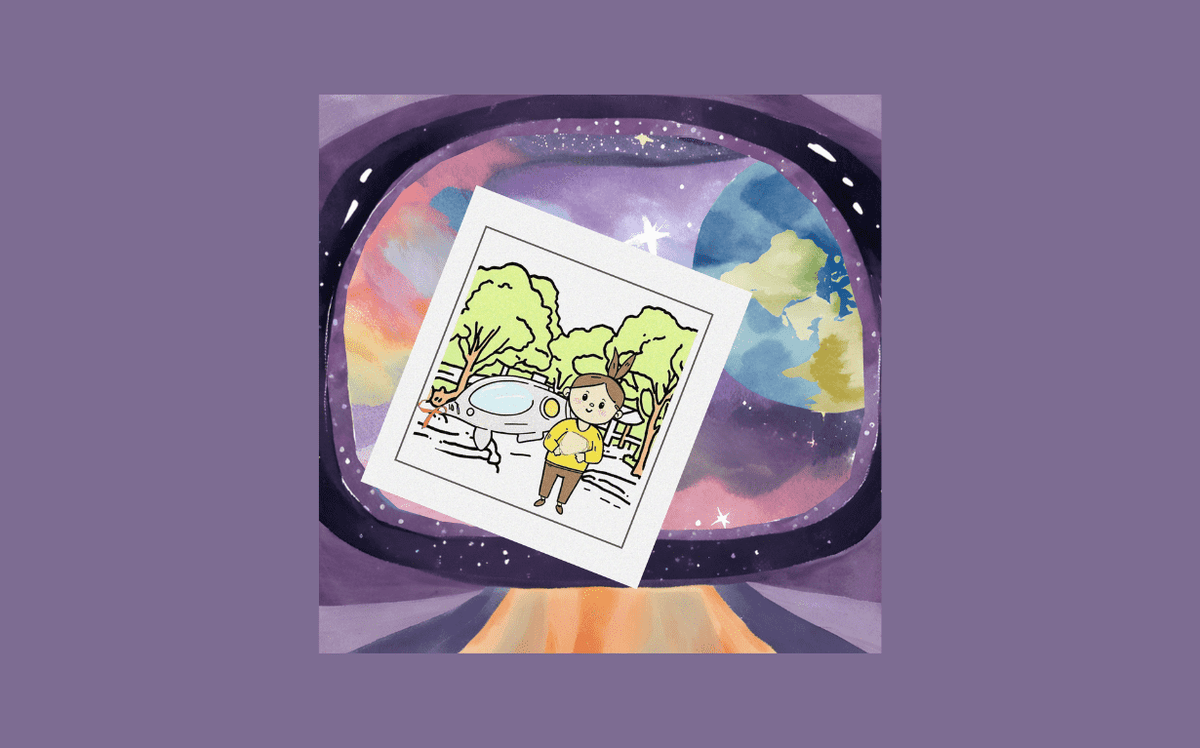
「みきのたからもの」 -低学年で「問いを中心に俯瞰した読みをする」体験をさせよう -
|
執筆者: 比江嶋 哲
|
本年度より登場した「みきのたからもの」(光村図書・2年)は、中心人物みきと宇宙から来たナニヌネノンとの交流を描き、次々と現れる不思議な出来事に、子どもたちがワクワクしながら読み進めることのできる物語文です。
今回は比江島哲先生(宮崎県・都城市立有水小学校)に、初読の感想を想定した上で、物語文の展開や叙述、登場人物の気持ちの変化について、子どもたちの俯瞰的な読みが進むような、問いの整理や発問の工夫をご提案いただきました。
目次
2年生11月下旬で学習する「読むこと」の学習材である。
登場人物は、みきと宇宙から来たと言うナニヌネノン。この2人の不思議な出会いから、お互いの思いを話すことで分かり合い、交流するという内容である。その後の、みきについても書かれており、題名の「たからもの」が何を指しているのか、わかるようになっている。
これまでの物語文教材と違い、自分に近い登場人物が出ていることで、自分と照らし合わせて読むことができる教材でもある。
物語の内容をおおまかに話すこと(あらすじ)については、これまで「スイミー」でお話を紹介して好きなところを伝えるという学習や、「ミリーのすてきなぼうし」で、お気に入りの本を紹介し合うという学習で行っている。
今回は、あらすじと自分が好きなところを紹介するだけでなく、登場人物の様子から行動を具体的に想像させたい。つまり、登場人物の行動が分かる言葉をおさえ、「~という言葉から○○の~という気持ち(行動)が分かります」というような学習を展開していく必要がある。
