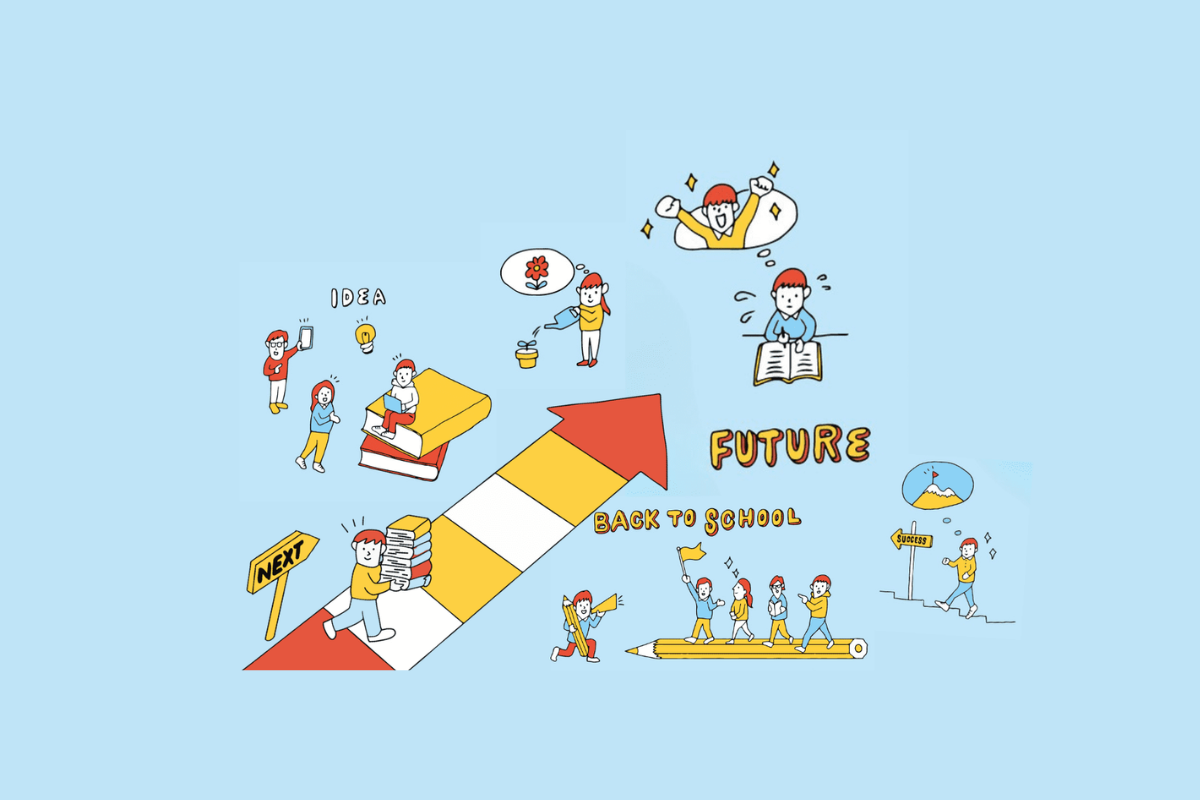
「探究する国語授業」をデザインする —「5つの条件」と「10の裏側」-
|
執筆者: 溝越 勇太
|
目次
「『探究』が大切というのはわかるが、正直何からやってよいのかわからない」
こんな声をよく耳にする。「探究する学び」を実現する難しさはどこにあるのだろうか。
筆者は2つあると考えている。
1つは、「何を(で)指導するか」という指導内容を選ぶ難しさ、もう1つは「どのように指導するか」という指導方法の難しさである。
「何を(で)指導するか」という指導内容に関しては、「5つの条件」(前号「探究する国語授業」をデザインするー『5つの条件』と『10の裏側』ー」.2025年1月23日)で述べた。
本号では、「どのように指導するか」という指導方法に関して「10の裏側」を述べていく。
なお、本稿は第3回目の「筑波探究国語ゼミ」となるが、第1回「サービス・ラーニングの国語授業づくり」、第2回「『探究する国語授業』をデザインする5つの条件」と合わせてお読みいただければ幸いである。
「探究する国語授業」を以下のように定義する。
教室での国語の学びを、地域社会の諸課題を解決するために組織された社会的活動に生かすことを通して、真に生きて働く言葉の力を育てることを目指す国語授業。
これまでの国語授業の問題点は、教科書の中だけ、授業の中だけで、多くの国語の学びが閉じられてしまっていることであると考える。従来の国語授業でも、学習のまとめで本のポップを作ったり、調べたことや興味のあることを図鑑にまとめたりするなどの活動は行われてきた。
しかし、何のためにその活動をしているのかが子どもにとっては不明確なことも多く、活動に対して受動的な子どもがいたり、なかなか活動に参加できない子どもがいたりすることも少なくなかった。
変化の激しい現代の社会、これから子どもたちが生きていく予測困難な時代においては、知識や技能だけでは到底太刀打ちできない。答えのない問題を解決するためには、知識を集め、技能を活用し、学び、想像し、戦略を立て、多面的に物事を見て、批判的に思考し、よりよく判断する、などといった「知性」が必要であろう。
このような知性は、教師が教え込むことができない。言い換えると、授業が教室の中だけで完結してしまっては育たない。教室で学んだ国語の学びを、答えのない問題であふれる実際の地域社会へ出て、誰かのため、社会のために、試行錯誤しながら実際に「使う」。
そんな経験をしてこそ、知性は育まれるのではないかと考える。
「探究する国語授業」をデザインするには、長い期間子どもたちが取り組むことのできる学習の「テーマ」を設定する必要がある。テーマ設定の「5つの条件」については前号で述べているため、概要のみ以下に示す。
