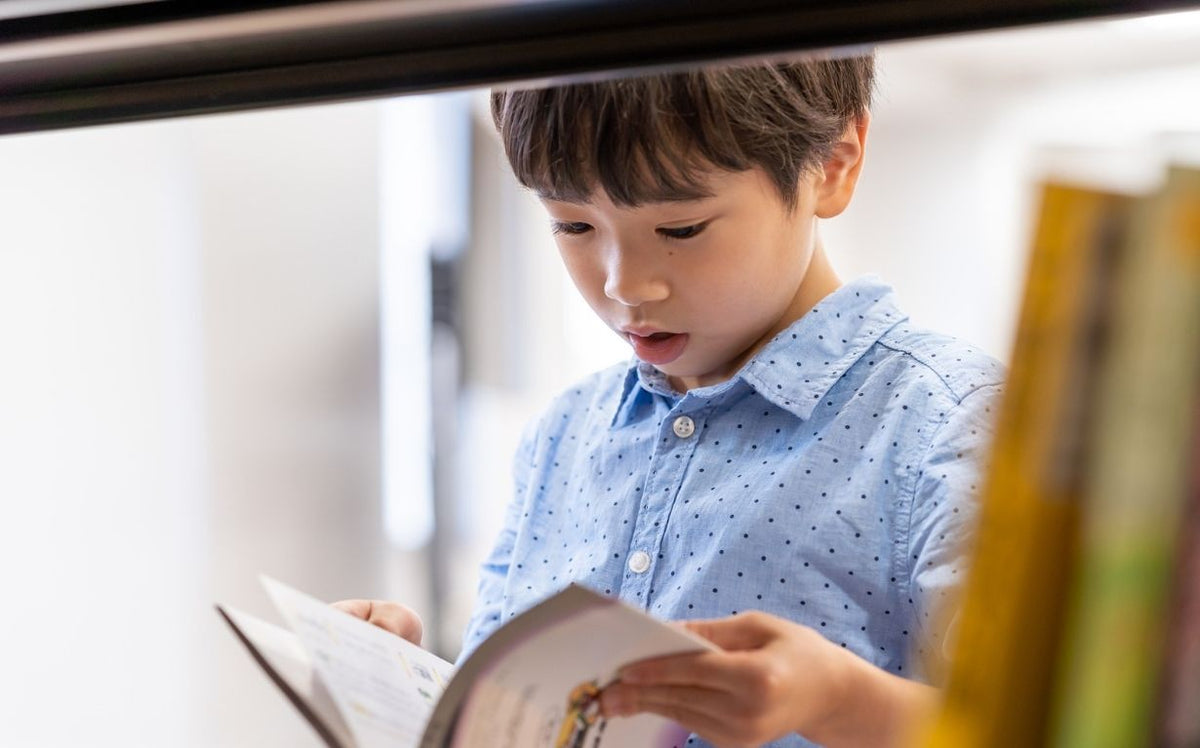
5分でわかる指導技術 子どもの理解を促進する動作化のスキル
|
執筆者: 小崎 景綱
|
今月の5分で分かるシリーズは、子どもの理解を促進する動作化のスキルについて、小崎景綱先生(さいたま市立浦和別所小学校)に提案していただきます。
叙述を動作化することで、場面の様子や情景はもちろん、登場人物の気持ちや心情の変化にも気付きやすくなり、読解に支援が必要な子どもたちにとっての手だてにもなります。
どのような動作化が考えられるのか、定番教材を例に挙げて考えていきましょう。
読み取りが難しい―。音読はできているのに、精査解釈のレベルの読みに進むことができない―。国語授業の中で、子どもも教師もそんな困り感をもっている場面はよく見られます。中学年では、情景や複雑な感情が読解の対象となり、高学年では、中心人物のものの見方や生き方、主題など、より抽象的なものを読む力が要求されます。
子どもの実態と合わない授業展開や言語活動をすれば、国語を熱心に研究している教師が最も避けたい「国語嫌いな小学生」を生みかねません。では、具体的にはどのような手だてがあるのでしょうか。様々な方法がありますが、私からは「動作化」や「劇化」について提案します。
発達段階に合わせて、本文から人物の様子を想像する方法が変わっていきます。小学校学習指導要領(平成29年告示)解説国語編にも、しっかりと記述されています。一部を引用します。
C読むこと (1)構造と内容の把握 イ
第1学年及び第2学年
場面の様子や登場人物の行動など,内容の大体を捉えること。
小学校1・2年生にとって、自分が「したこと」以外の状況を想像することは、往々にして難しいものです。言葉としては、「うれしい」「悲しい」と言えていても、実感を伴った想像にはなっていないことが予想されます。そこで、登場人物の行動、「したこと」を実際に行ってみる、疑似体験することで想像を促します。
「大きなかぶ」(1年)で音読をしたり、動作化や劇化をしたりすることで、内容の把握を促す実践がよく見られるのはこのためです。体を動かして、友達と一緒に引っぱるような動作をする中で、「力を合わせる大切さ」や「抜けた時のうれしさ」を体感し、「うんとこしょ、どっこいしょ」の言い方の変化などに気付くことができます。そこから、「ところが」「それでも」「まだまだ」などのつなぎ言葉の効果にも気付き、国語の読みの世界にも入っていくことができます。
「スイミー」(1または2年)では、スイミーが海のすばらしいものにたくさん会う場面を実際に動いて味わってみたり、岩陰にいた赤い魚の兄弟たちにしたスイミーの提案を、クラスみんなで再現したりすることができます。また、「スイミーはかんがえた。いろいろかんがえた。うんとかんがえた。それから、とつぜん、スイミーはさけんだ。・・・・・・」という場面も、体を動かすことで、何をこんなに考えたのか、という問いをもたせ、読みの世界に引き込むことができると考えます。
低学年で身に付けた、行動を基に大体の内容を把握する力が定着して、初めて以下の段階に進みます。
第3学年及び第4学
登場人物の行動や気持ちなどについて,叙述を基に捉えること。
第5学年及び第6学年
登場人物の相互関係や心情などについて,描写を基に捉えること。
しかし、現場では、全ての子どもが順調にスキルアップしているわけではありません。子どもの発達段階やそれぞれの習熟が、グラデーションになっているのが現実です。叙述を基に登場人物の行動や気持ちを想像できない、そんな3・4年生にどんな支援をすればよいのか。 ここでも、低学年で行った動作化がその方法の1つになると思います。
「ごんぎつね」(4年)の2つの文を例に考えてみます。
雨が上がると、ごんは、ほっとしてあなからはい出ました。空はからっと晴れていて、 もずの声がきんきんひびいていました。
2、3日の雨の間、ごんは穴から出られず一人ぼっちでしゃがんでいた、その後の文です。4年生の子どもたちの多くは、実際にしゃがむ行動を取らずとも、このときのごんの気持ちが想像できます。そのような状況から、「からっと晴れた空」を見たときのごんの気持ちも想像できます。もちろん、叙述を読むだけでは理解が難しいという子どもの実態がある場合には、実際に机の下に、2、3分じっとさせてから、立ち上がって背伸びをしてみるのもよいでしょう。
「空はからっと晴れています」と投げかけ、もずの声をインターネットで検索して聞かせてみましょう。子どもたちは、「やっと出られた」「解放された感じ」「よっしゃー!」などと言い、この時のごんの気持ちを想像できるはずです。同時に、「情景」から心情を読み取るという考え方も習得できます。この開放感が、兵十へのウナギのいたずらにつながります。
次は、兵十と加助がお念仏をすませ、吉兵衛の家から帰る場面です。
ごんは、二人の話を聞こうと思って、ついていきました。兵十のかげぼうしをふみふみ 行きました。
この場面でのごんの気持ちは、その後の「引き合わないなあ」という言葉や、最後にごんの思いが兵十に通じると同時に死を迎えてしまう、それも兵十の手によって、という悲劇的な場面に深くつながっています。
「かげぼうしをふみふみってどういうこと?」という問いを子どもにもたせ、動作化してみると、ごんが兵十と加助の話をかなり近い距離で聞こうとしていることが分かります。
「これは、近いね!」「見つかったらひどい目に遭うはずなのに、どうしてだろう」「そんなに話が聞きたかったのかな」などと、ごんの気持ちにぐっと迫ることができます。
「大造じいさんとガン」(5年)でも、動作化によって、心情を想像するのが難しい子どもを支援できるポイントがたくさんあります。
2年目の小屋の中での場面です。
夜の間に、えさ場より少しはなれた所に小さな小屋を作って―
あかつきの光が、小屋の中にすがすがしく流れ込んできました。
その動きを再現してみると、残雪が引き返した時の、じいさんの何とも言えないがっかり感が想像できるのではないでしょうか。
「海の命」(6年)では、クエに出会った場面で、太一の心情の変化を読み取ることが、単元の肝となります。そこでの読解が難しい場合も、動作化が有効になります。
潜っているところにクエを見つけた太一は、一度息継ぎをし、もう一度潜ります。
太一は永遠にここにいられるような気さえした。しかし息が苦しくなって、またうかんでいく。―背の主は全く動こうとはせずに太一を見ていた。おだやかな目だった。
最後の山場の場面ですが、これも体を動かすことで、太一の興奮と冷静さ、クエの様子を見た太一の心情に迫る支援になります。
細かい教材分析や授業実践については、様々な著書を見れば、たくさん見つけることができますが、低学年での基本的な読解の手だてである動作化を、その後の読みの武器にもしっかりと使うことで、読解が苦手な子どもにも、理解を促し、精査解釈の世界に呼び込める可能性が増します。また、文学的な文章に限らず、説明的な文章でも動作化は有効に働き得ます。
子どもの実態に合わせた授業を行うことは、子どもにとっても教師にとっても余計なストレスを排除し、本当に必要な負荷を得ることにつながります。目の前の子どもたちに力を付け、国語の楽しさを味わえる授業をこれからも模索していきたいものです。
〔引用・参考文献〕
『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説国語編』文部科学省
小崎 景綱(おざき・かげつな)
埼玉県・さいたま市立浦和別所小学校
「子どもの論理」で創る国語授業研究会会員
