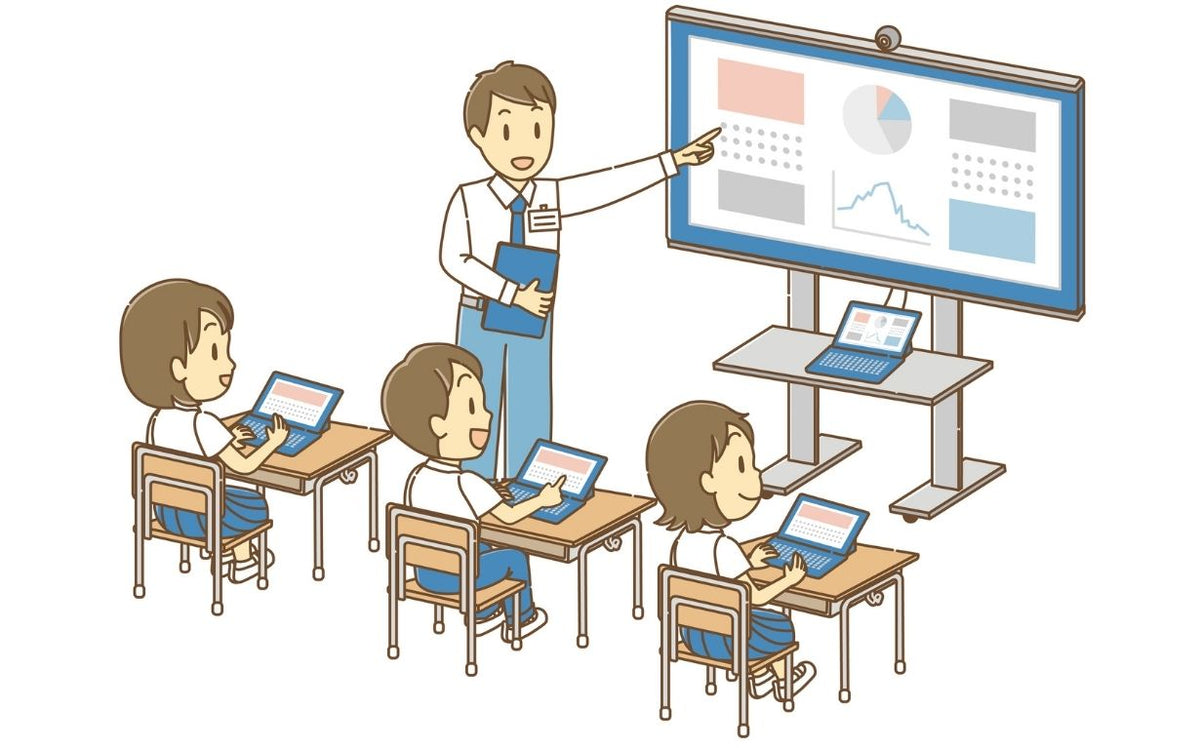
子どもが学びを深める「ICT活用」の指導技術
|
執筆者: 中野 裕己
|
今月の「5分で分かるシリーズ」は指導技術をテーマに、子どもが学びを深める「ICT活用」について、中野裕己先生(新潟大学附属新潟小学校)にご提案いただきました。
「ICTをただ使うだけになってしまっている……」「有効的にICT活用できているか不安……」という先生方も多いのではないのでしょうか。ICTの機能を改めて整理し、具体的な授業アイデアをもとに、本当に「有効なICT活用」について一緒に考えていきましょう。
有効かどうかは置いておいて、まず使わせよう」
一人一台端末導入期に、ある意味スローガンのように聞かれたフレーズである。
教師も子どもも経験がないわけだから、使いながら使い方を考えていこうというのが、導入期の考え方であった。実際にこのような考え方で導入期を過ごした学校は、一定の成果を得たと考える。子どもはICTを使うことに慣れ、教師は学び方を子どもに渡すという指導観をもつことができた。
だからこそ、そろそろ考えていかなければならないことは、ICTが「いつ、どのようなときに有効か」ということである。1年生にノートの書き方を教えるのと同じように、音読の作法を教えるのと同じように、ICTの有効な使い方を教えることは重要である。
誤解のないように述べておくが、「まず使わせよう」というスタンスを否定しているわけではない。このスタンスは、これからも必要である。要するに、「まず使っている」子どもに、「いつ、どのようなときに有効か」を教え導くことが、必要になってくるのである。
「とにかく使わせる」フェーズから、「いつ、どのようなときに有効か」を教え導くフェーズへの移行
ICTが「いつ、どのようなときに有効か」を考えるためには、その機能を明らかにしておく必要がある。機能とは各種学習支援アプリケーションに依存した個別具体的なものではない。学習に関わるICT全般の機能を指す。私は、4つに整理して捉えている。
このような機能を踏まえて、教科内容を習得するために有効に働く学習場面を検討するのである。この学習場面については、「3.授業アイデア」にて授業の具体を通して述べる。
【教材】
「どうぶつ園のじゅうい」(光村2年上)
【学習場面】
「獣医の仕事について知り、感想をまとめる」というめあてを共有し、単元の学習を進めている。子どもは、2〜8段落の各段落に1つずつ、獣医の仕事が書かれていることを捉えている。本時は、「獣医の仕事はいくつの仲間に分けられるか」という学習課題を設定し、各段落に書かれた獣医の仕事を分類する。
【授業の実際】
学習課題を設定した子どもは、段落の内容を確かめて、類似する関係を見いだそうと思考する。そして、「この仕事とこの仕事の仲間は、〇〇という仲間で…」のように、分類していくのである。このような分類する思考操作を行う場面で、ICTの「1) 編集する」機能が有効に働く。
図1の子どもは、端末に配信された段落カードを操作し、分類している。また、分類したカードを囲んで「ちりょう」と、観点を記入している。本教材は、2〜8段落の各段落に1つずつ獣医の仕事が書かれている。したがって、段落カードの分類が、そのまま獣医の仕事の分類となる。
分類する思考操作を可視化することで、子どもは学習の状況を自覚しながら取り組むことができる。これが教科書を見ながら頭の中で行われていた場合、取り組んでいるうちに「何と何を仲間と考えたか」「どのような観点で分類したか」がはっきりしなくなることがある。さらに、ICTにおいては、修正が容易なため試行錯誤しながら分類することが促される。子どもは、試行錯誤することで繰り返し叙述を確かめて、各段落の重要な言葉を見いだすことになる。これは、学習指導要領に書かれた「精査・解釈」の指導事項と合致する。
このように、分類する思考操作を通して国語科の教科内容の習得が図られる学習場面において、ICTの「1) 編集する」機能が有効に働く。また、同様に「比較する」「関連づける」「順序づける」などの思考操作を通して国語科の教科内容の習得が図られる学習場面においても、ICTの「1) 編集する」機能が有効に働くことが多い。
「分類する」「比較する」「関連づける」「順序づける」などの思考操作を通して教科内容の習得が図られる学習場面において、ICTの「1) 編集する」機能が有効に働く。
従来の授業づくりは、教材の特徴を捉え、単元を構成し、授業を構想するという流れで行われることが多かった。これからの授業づくりは、授業を構想した後、「その学習場面でICTの機能が有効に働くか」という検討をすることが重要となる。
〔引用・参考文献〕
中野裕己(2022)『子供が学びを創り出す 対話型国語授業のつくりかた』明治図書出版
中野 裕己(なかの・ゆうき)
新潟大学附属新潟小学校
全国国語授業研究会監事
