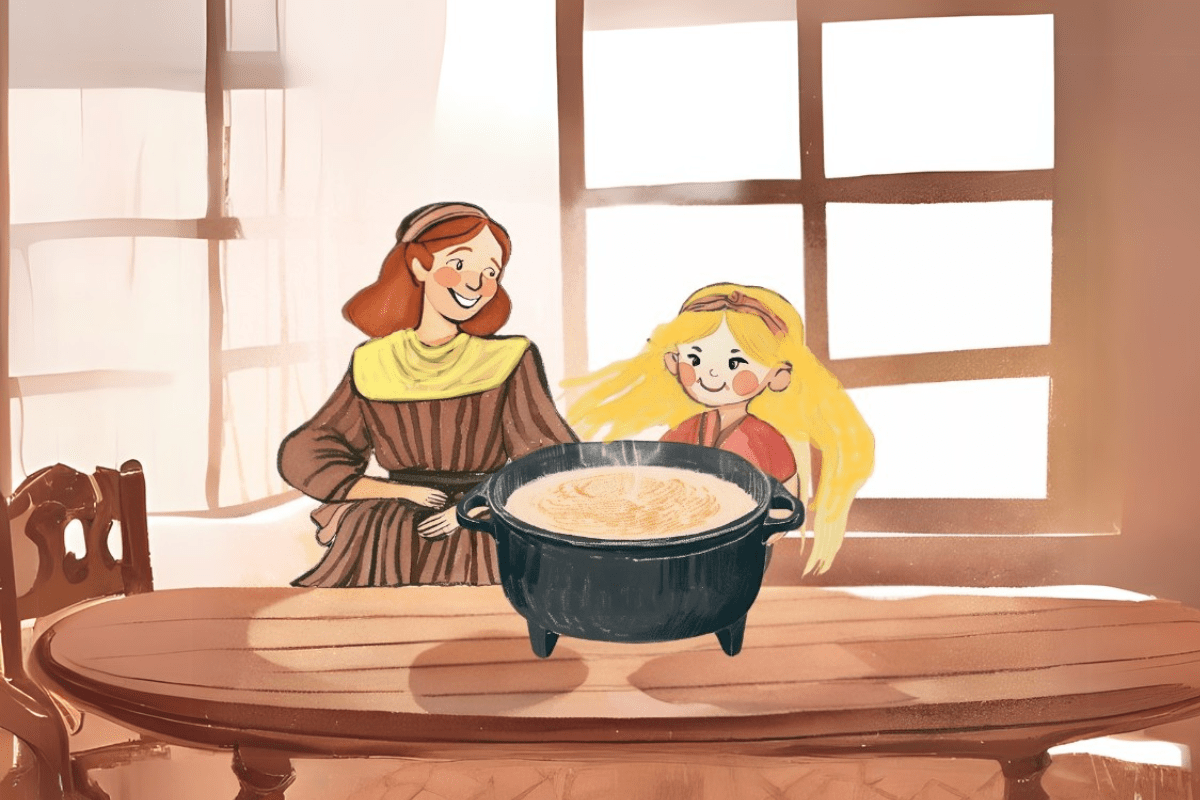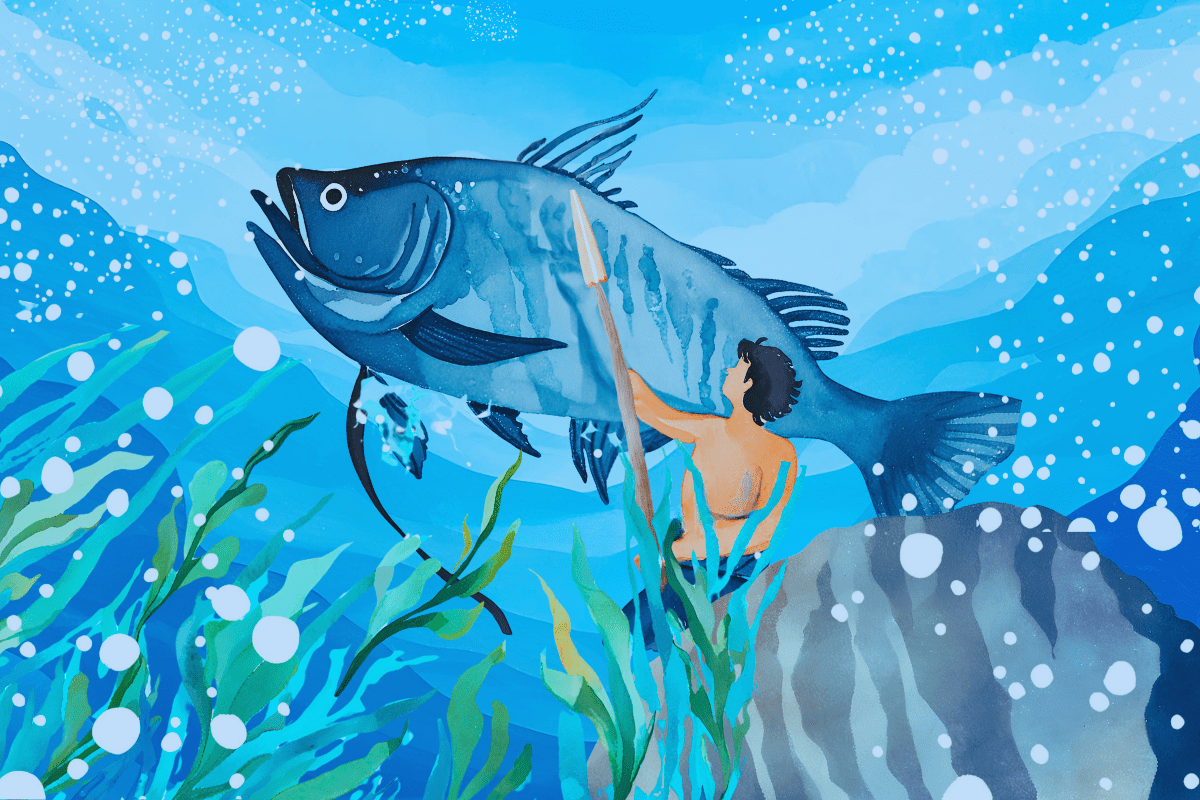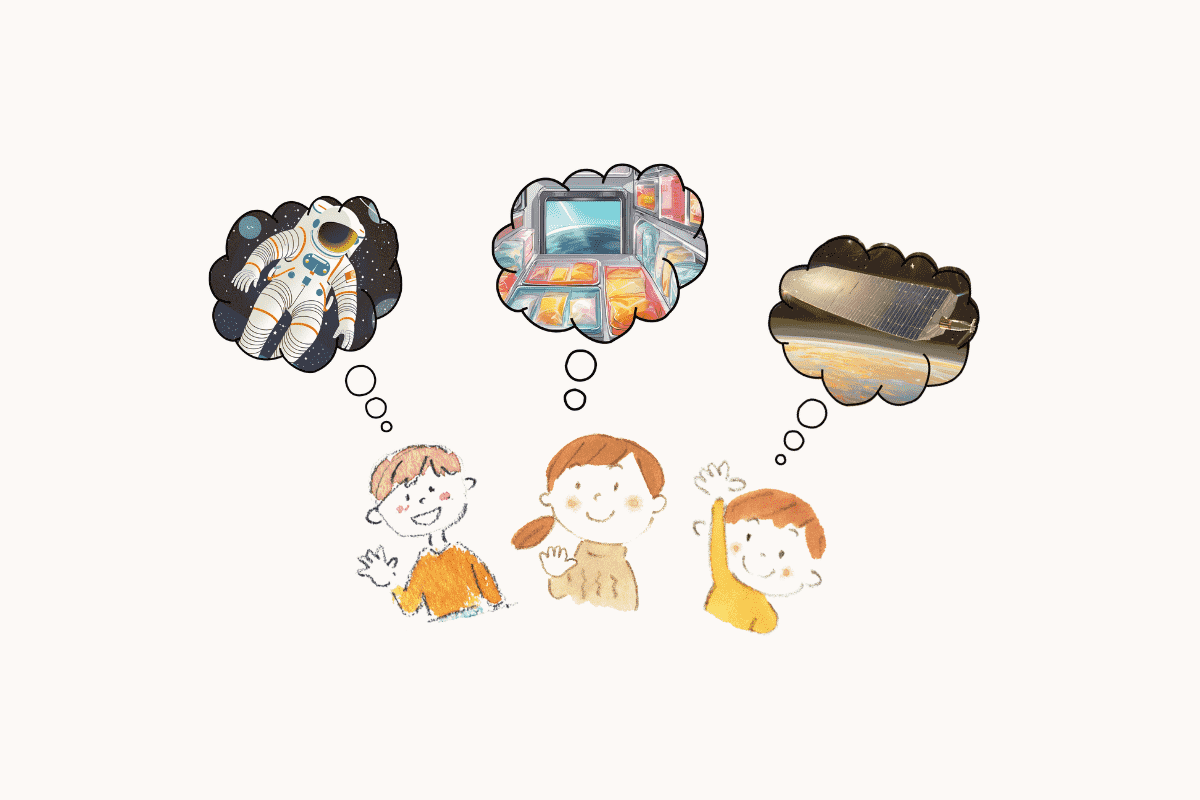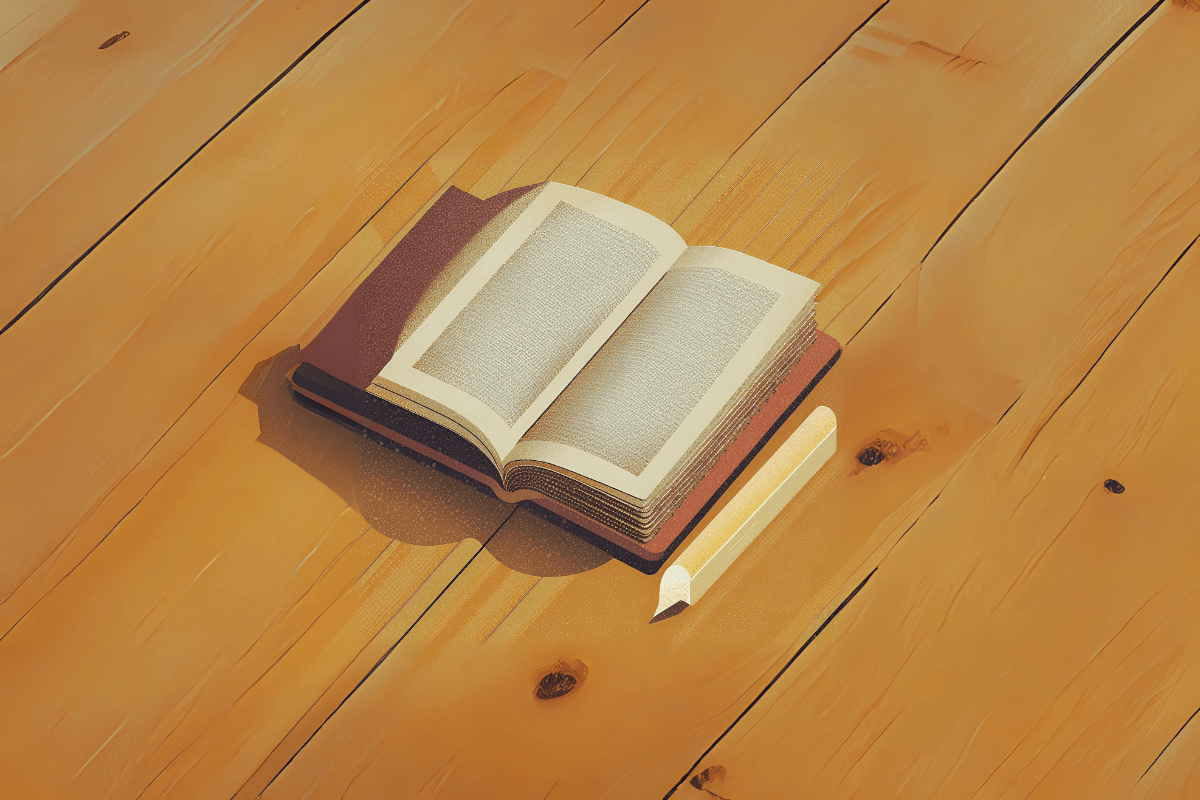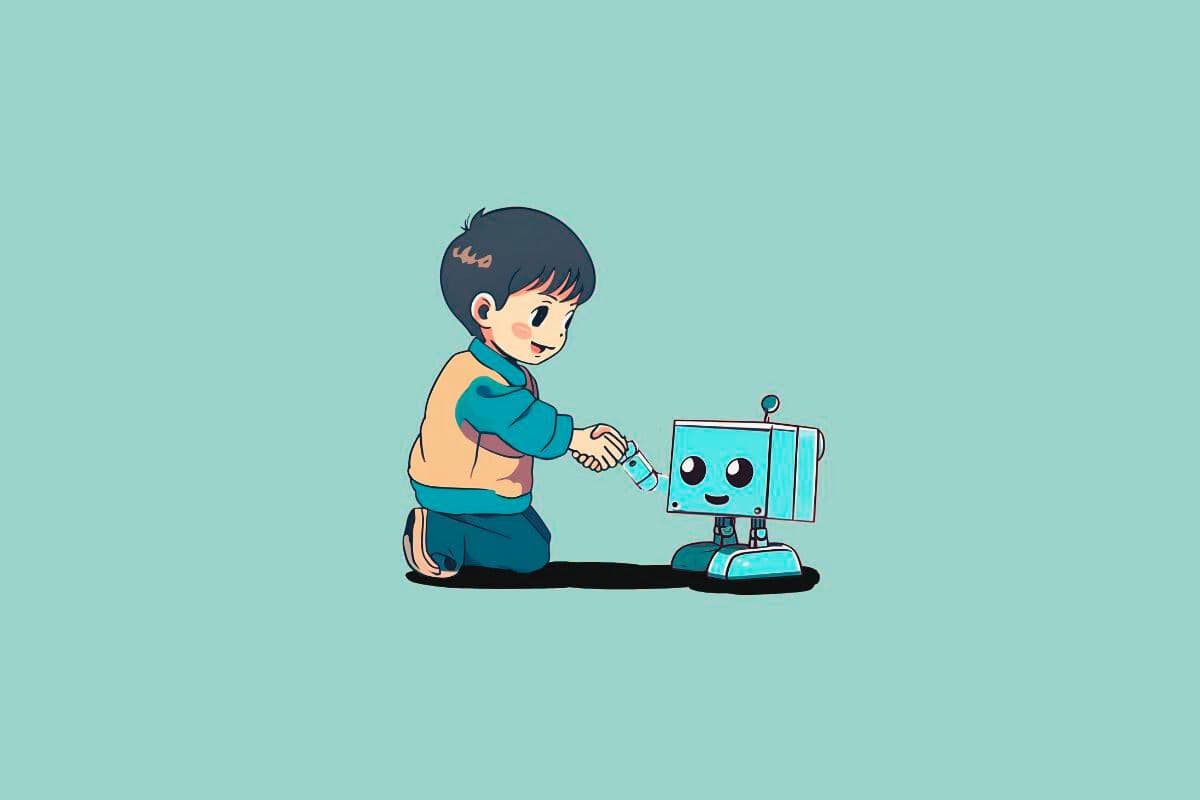子どもと創る「国語の授業」
![]() 有料記事
有料記事
「おかゆのおなべ」
-低学年物語文でも根拠が大切であると実感できる授業-
本教材では、「おかゆのおなべ」の呪文を、誰が知っていて、どのように言ったのかということが、この物語の起承転結をつくる鍵となっています。本教材の学習を通して、物語文を読む上で重要な、会話文を押さえることに意識が向くようになるでしょう。 今回は柘植遼平先生(昭和学院小学校)に、かぎ(「」)の役割や知識を深めつつ、かぎ(「」)が誰のセリフなのか本文を根拠にしながら読み進めることで、文学のおもしろさにふれられるような授業づくりの工夫を紹介いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
子ども主体で「海の命」を読む
-光村図書・6年-
授業で物語を読む楽しさは、その作品のおもしろさや主題について語り合うことにあると考えています。そのような読み手を育むことを目指して、1年生から系統的に読み方を身につけさせています。また、近年は読み方だけではなく、自ら「問い」をもち、それを追究していく学習構想力や自己調整力を培うことも意識しています。 そこで、「海の命」(立松和平 作)を中心教材とした6年生の物語単元では、子どもたちが課題を挙げ、自分の解決したい課題を選択し、互いに交流しながら主題に迫っていくように構想しました。
![]() 有料記事
有料記事
「宇宙への思い」
—著者の「思い」を読み取り、みんなで考えを共有しよう—
新教材「宇宙への思い」は、本文中、宇宙そのものへの感想や気持ちが表れている箇所が実は少なく、宇宙での経験や研究(事実)を通して、地球や身近なことの未来をどのように考えたのか(願い)が、最後に述べられていることが特徴的です。 本教材について、田中元康先生(高知大学教育学部附属小学校教諭/高知大学教職大学院教授)に、主語と文末に着目して読み、著者の述べている考えと事実を整理していく学習活動について提案していただきました。根拠に基づいて自分なりにまとめるため、より友だちと考えを共有し、読み深めたくなるでしょう。
5分でわかる 子ども主体の国語授業のための基礎づくり
今回の5分でわかるシリーズは、佐藤圭先生(東京都・足立区立千寿小学校)に、子どもが主体となる国語の授業をつくるために、押さえておきたい指導技術のアイデアについて、ご紹介いただきました。教師が「待つ」「聴く」「受け止める」から、子どもたちも同じようにふるまえるようになる、ということが大切ですね。
![]() 有料記事
有料記事
「やなせたかし-アンパンマンの勇気」
-先人からのメッセージを捉え、自分自身をアップデートする授業づくり-
2025年春 NHK朝の連続テレビ小説のモデルで話題のやなせたかし氏について、本教材ではその生い立ちからアンパンマンに込めた思いまでを説明しています。筆者である梯久美子氏は、やなせ氏と親交のあったノンフィクション作家であり、その書きぶりは、事実を基にした書き手の視点と、やなせたかしの気持ちの変化を書き分けていることが特徴的です。 今回は安井 望先生(神奈川県・横須賀市立夏島小学校)に、本教材の授業づくりにおいて、自分ならどこが一番重要な場面であると考えるのか、色紙にまとめることをゴールに、目的意識と主体的な読みが育まれるような仕掛けをご提案いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
「『弱いロボット』だからできること」
-当事者意識から読みの必要感へ-
今回は松岡 整先生(高知大学附属小学校)に、本文との出合いを工夫し、新しい事柄と自身との認識のずれを生みだすことで、より主体的で探究的な読みが進むといった、当事者意識から深まる授業づくりの工夫をご紹介いただきました。