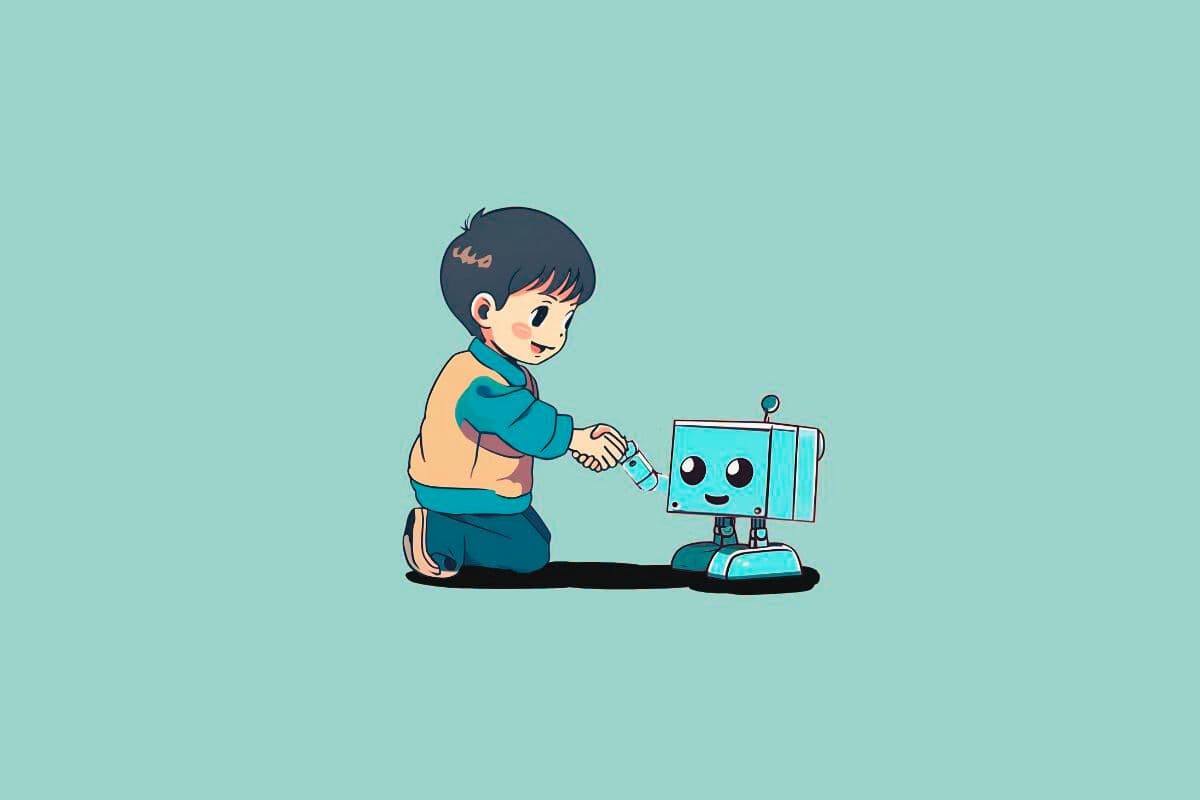
「『弱いロボット』だからできること」 -当事者意識から読みの必要感へ-
|
執筆者: 松岡整
|
単元名:ロボットとの未来を考えよう
教材:「『弱いロボット』だからできること」(東京書籍・5年)
「弱い」と形容するときは生き物についての場合が多く、本教材「『弱いロボット』だからできること」で登場する、「弱いロボット」という事柄はあまり聞き慣れません。そのため、本文の説明を通しての、「便利」「役に立つ」だけでなく、「弱い」ことも「必要である」という考え方との出合いは、新鮮に感じられることでしょう。
今回は松岡 整先生(高知大学附属小学校)に、本文との出合いを工夫し、新しい事柄と自身との認識のずれを生みだすことで、より主体的で探究的な読みが進むといった、当事者意識から深まる授業づくりの工夫をご紹介いただきました。
国語科は、生涯にわたり学び続けるために不可欠な資質・能力、「話す・聞く」「書く」「読む」を育む唯一無二の教科であり、あらゆる教科の土台でもある。
そうであるにもかかわらず、子どもたちは国語科の学びに「思い」や「願い」をもちづらい。なぜなら、母国語であるがゆえ、「自分は国語を使えている」と自覚しているからだ。そのため、学びの必要感をもちづらく、結果として学びの主体性も失われてしまう。
では、どのように必要感をもたせるのか。私は、そのポイントの1つが「当事者意識」であると考える。学びの主語を子どもに据え、単元設計を行うのである。
「読むこと」の領域において、物語文は上記の当事者意識をもたせやすい。なぜなら、子どもたちは教材に共感しやすいからだ。登場人物の心情や行動を自分と重ね合わせることで、内容を徐々に理解することができる。しかし、説明文はそうではない。自分の興味・関心が無いものや普段あまり関わりがないもの、ときには未知の事柄すら学ばなければならない。私自身も、初めは新教材との出合いで張り切って学習に臨むものの、単元の途中から意気消沈していく子どもを何人も見てきた。
本稿では、子ども一人ひとりの学びのエネルギーを持続させるために、当事者意識をもたせ、読みの必要感につなげる単元づくりを提案する。
