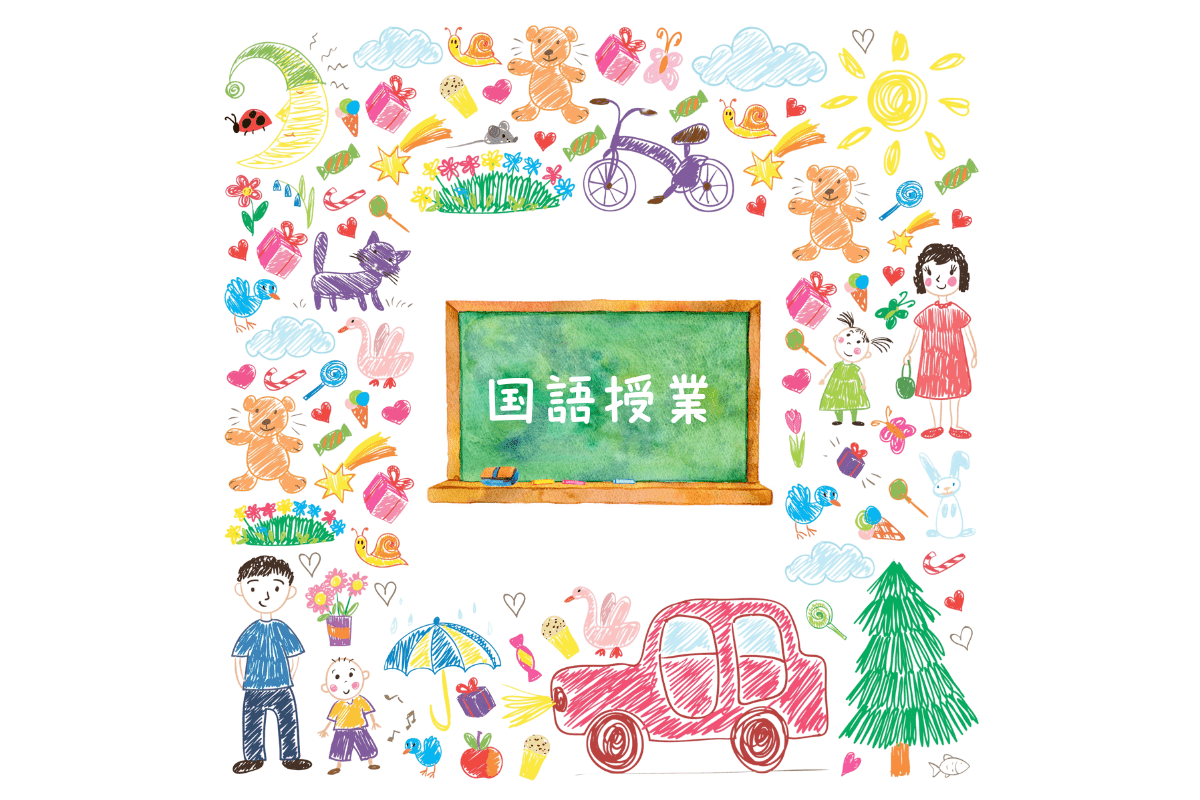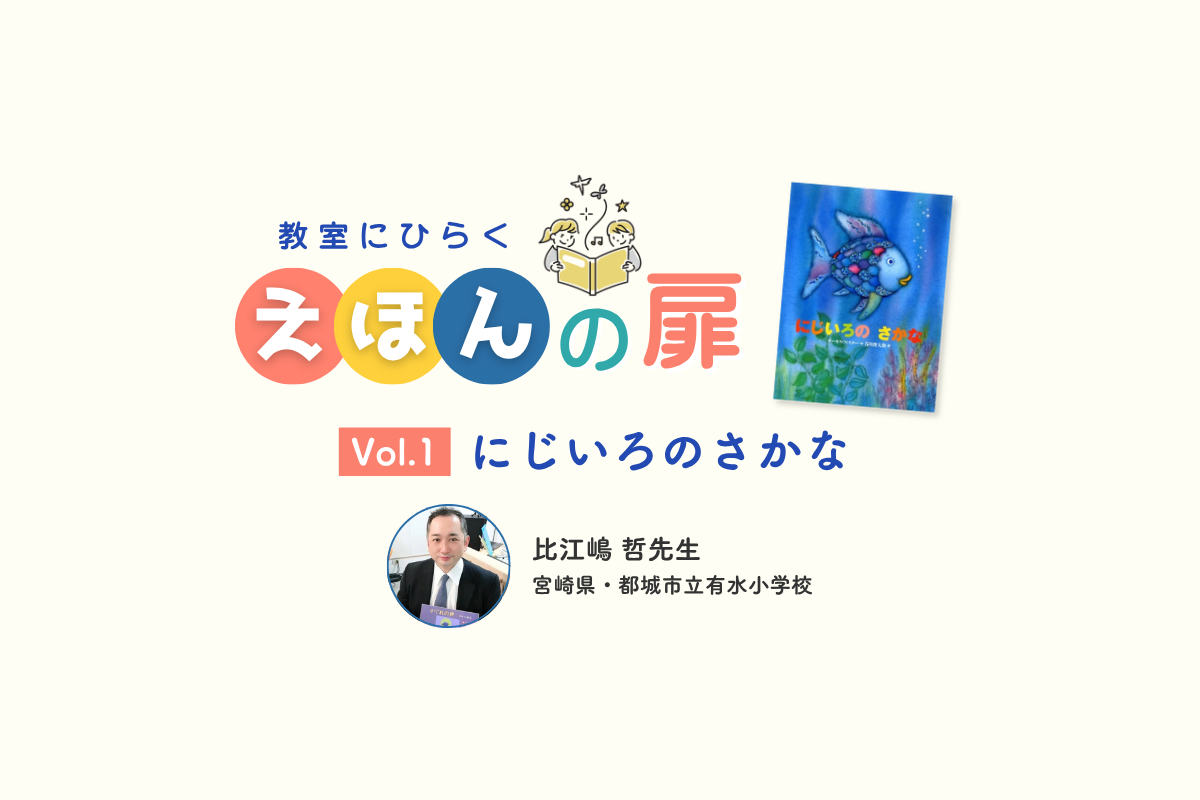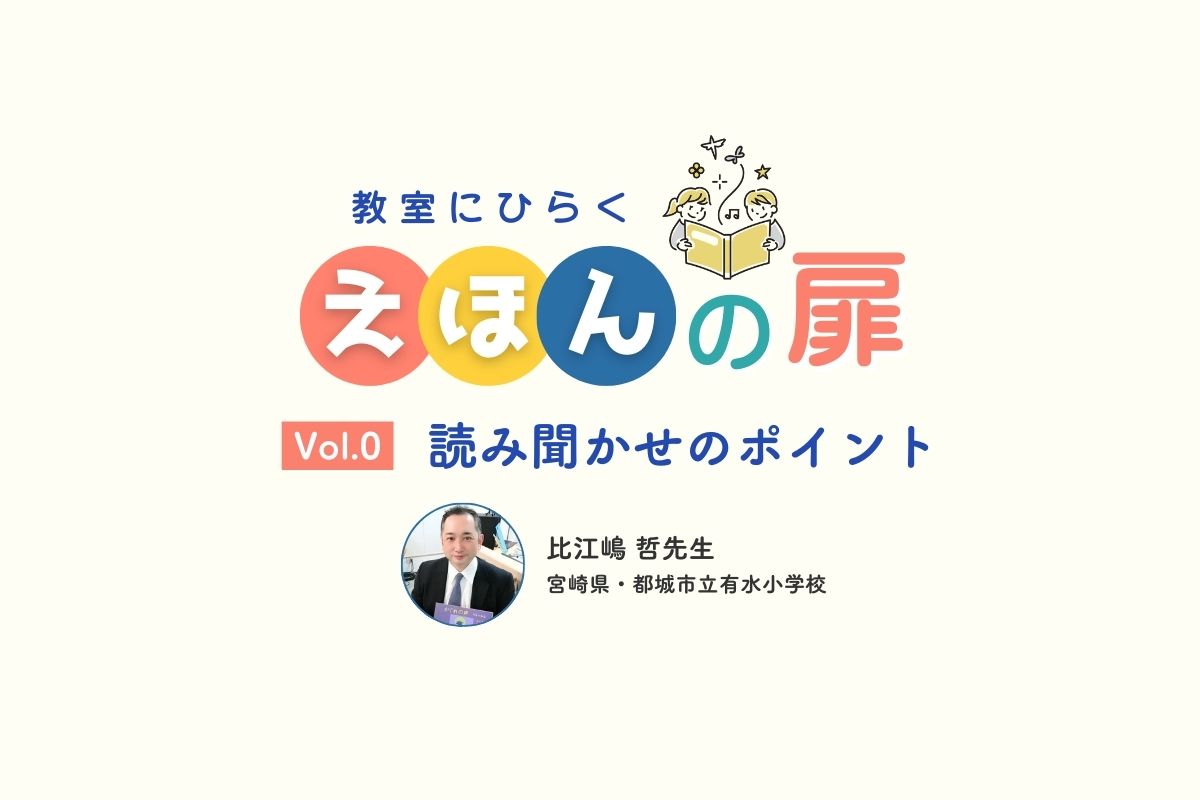子どもと創る「国語の授業」
![]() 有料記事
有料記事
「アイスは暑いほどおいしい?」/「雪は新しいエネルギー」
―図やグラフと文章をつなぐ説明文学習―
今回は本教材について、沼田拓弥先生(東京都・八王子市立第三小学校)に、文章の構造と内容をシンプルに把握することからはじめ、資料と文章のつながりをスモールステップで精査・解釈することで、全員が参加できるような授業づくりをご提案いただきました。
5分でわかる「楽しい!」授業のつくり方
-「子ども主語」の国語授業をつくろう!-
5月号の「5分でわかるシリーズ」は、小西敦司先生(大阪府・摂津市立三宅柳田小学校)に、子どもたちが「楽しい」「おもしろい!」と思える活動を学習内容に取り上げたり、自分たちで学習を調整できるよう学びの選択肢を広げたりすることで、「子ども主語」となる国語授業のつくり方についてご提案いただきました。についてご提案いただきました。
『にじいろのさかな』
ー友達のことを思い、誰にでも優しくしようと思う一冊
海の中のお魚の話といえば「スイミー」がよく知られていますが、今回は、同じ谷川俊太郎さんが訳した「にじいろのさかなシリーズ」の一冊を、比江嶋哲先生(宮崎県都城市立有水小学校)に紹介いただきました。幸せになるために「にじうお」がとった行動、子どもたちはどのように受け止めるのでしょうか。
教室での読み聞かせ
ー成功の秘訣
今回は、比江嶋哲先生(宮崎県都城市立有水小学校)に、教室で絵本を読み聞かせをする際に、子どもたちが集中して聞けたり、お話の世界を楽しめたりするためのさまざまなコツをご紹介いただきました。 本の持ち方や、めくり方、読む間合い、ちょっとした工夫で、読み聞かせの時間が、穏やかで心地よいひとときになるのではないでしょうか。 でも何より大切なことは、先生も子どもたちと一緒に、お話の世界に浸って楽しむことです。 ぜひ、ちょっとしたすき間時間や帯単元として、教室に絵本の読み聞かせを取り入れてみてください。
![]() 有料記事
有料記事
「たんぽぽ」
-国語科の学びと子どもの意欲のバランスを意識した授業づくり-
本教材「たんぽぽ」について、後藤竜也先生(東京都・調布市立八雲台小学校)に、子どもたちが楽しいと思う、たんぽぽについての内容を大切にしながらも、時間や順序に関する書かれ方に気づけるよう、たんぽぽの特徴への関心から考えが広がっていくようにする、授業づくりについてご提案いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
「インターネットは冒険だ」の授業づくり
今回は中野裕己先生(新潟大学附属新潟小学校)に、子どもたちが本教材を読んだとき、どのように感じ、考えるのかを想定した教材研究を行い、自分なりの考えで文章の構造を捉えられるようにするための、ファシリテートの方法についてご提案いただきました。