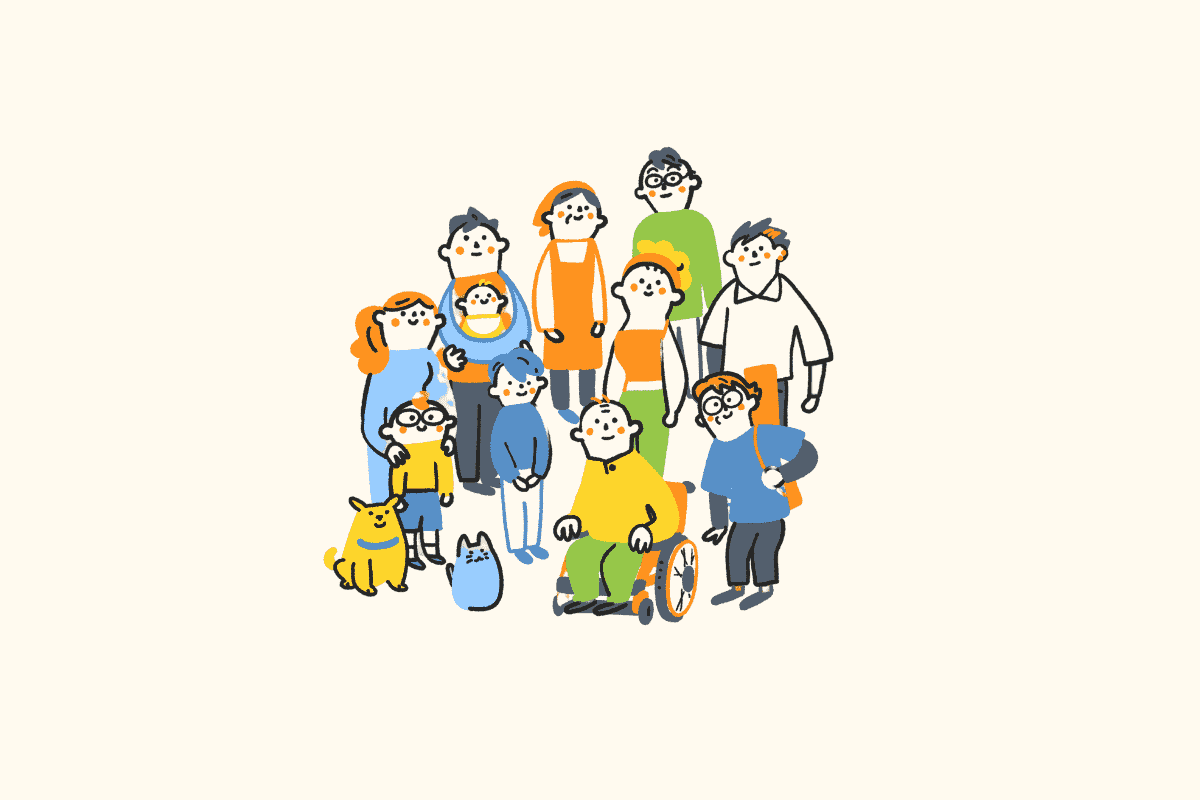
「くらしを便利にするために」 —筆者を感じることで子どもたちが文章に前のめりになる、教科書改訂の時期の説明文授業-
|
執筆者: 小崎 景綱
|
単元名:「便利」とは何か筆者と対話しよう
教材:「くらしを便利にするために」(教育出版・4年)
本教材「くらしを便利にするために」の改訂前の旧題は、「『便利』ということ」でした。改題したことで、はじめから「便利」という言葉に焦点を当てず、本文を読むことを通して、「便利」とは何か、読み手の考えを揺さぶり、見つめ直せるようになったといえます。
小崎景綱先生(埼玉県・さいたま市立新開小学校)に、令和6年度に本教材が改訂されたことを踏まえ、「以前の文章に変更を加えることで、筆者はどのように、何を、読み手により伝えようとしたのか」といった、説明文の工夫における意図や思いに迫ることで、「筆者を読む」力が身に付く授業づくりをご提案いただきました。
目次
学びを子どもに委ねる。子どもが自分の学び方を自己決定できるようにする。
子どもたちが自分の学びを自分でプロデュースできるようになることは、彼らが今後生きていく上で非常に大きな力となる。そのため、子どもの思考に寄り添って授業を展開することは、これからの授業づくりにおいて大きな流れとなっていくことは、間違いないだろう。
また、教師が学びの伴走者と表現されたり、子どもたちとともに教材に向かっていく者として位置づけられたりすることも多く見られる。教育全体に対するこれらの大きなスタンスを大切にしながら、国語科がこれまで突き詰めてきた説明文の読みの力についても、子どもたちが身に付けられるような授業を考えたい。
説明文の読み方の学習で大切なことの1つに、「筆者を読む」がある。多くの実践者・研究者がたくさんの実践をしているが、私も以下の3つの観点から説明文の学習を捉えている。
※二瓶弘行(2015)を参考に表現を一部簡略化したもの
などと、説明文を読むときの前提・基本姿勢を確認する。様々な読みの方略や学習の展開があっても、この前提が大きく揺らぐことはない。
しかし説明文は、物語文に比べて空所に思いを巡らせたり没入したりする類の文章ではなく、子どもたちの中に学び手としての意識をもたせるのが難しい。だからこそ、ただの文字の羅列ではなく、文章の奥に生身の人間がいて、懸命な努力の成果として書かれたものが説明文であるという前提を共有したい。
特に、教科書改訂の時期には、文章内容や書き方が変更されるものも多いため、文章の向こう側の生身の筆者を感じるチャンスである。筆者がどのような思いで変更に踏み切ったのか、思いを馳せることで、文章内容に対する理解が深まると同時に、説明文を読むための力も付いていくことを演出したい。
本教材は、
という意識を子どもたちに芽生えさせるには、ぴったりの教材である。
筆者を読む力の中に、以下の指導事項と関連する細分化された力、読みの方略がある。特に本単元において身に付けたい力について、確認しておきたい。
今月の「教師の必読書」をご紹介いただくのは、赤木詞友先生(福岡県・北九州市立鴨生田小学校)です。子どもの学び方自体が問い直されている今、授業観、教師観自体も大きく変わろうとしています。これからの教育についてリードする著者の、バイブルともいえる1冊を紹介いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
今回は沼田拓弥先生(東京都・八王子市立第三小学校)に、名言カードの作成という表現活動に向けて、岩谷さんにインタビューをするという想定で本文を読み深めることで、おのずと要点をしぼって文をまとめる意識が育まれるという、ユニークな授業づくりのアイデアについてご提案いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
提案:日常生活で発揮できる学びを 南山大学附属小学校 山本真司
2025年全国国語授業研究大会 2年 紙コップ花火の作り方/おもちゃの作り方をせつめいしよう
![]() 有料記事
有料記事
提案:文学的文章を交流しながら俯瞰的に読める単元づくり 宮崎県・都城市立有水小学校 比江嶋 哲
2025年全国国語授業研究大会 3年 ちいちゃんのかげおくり
