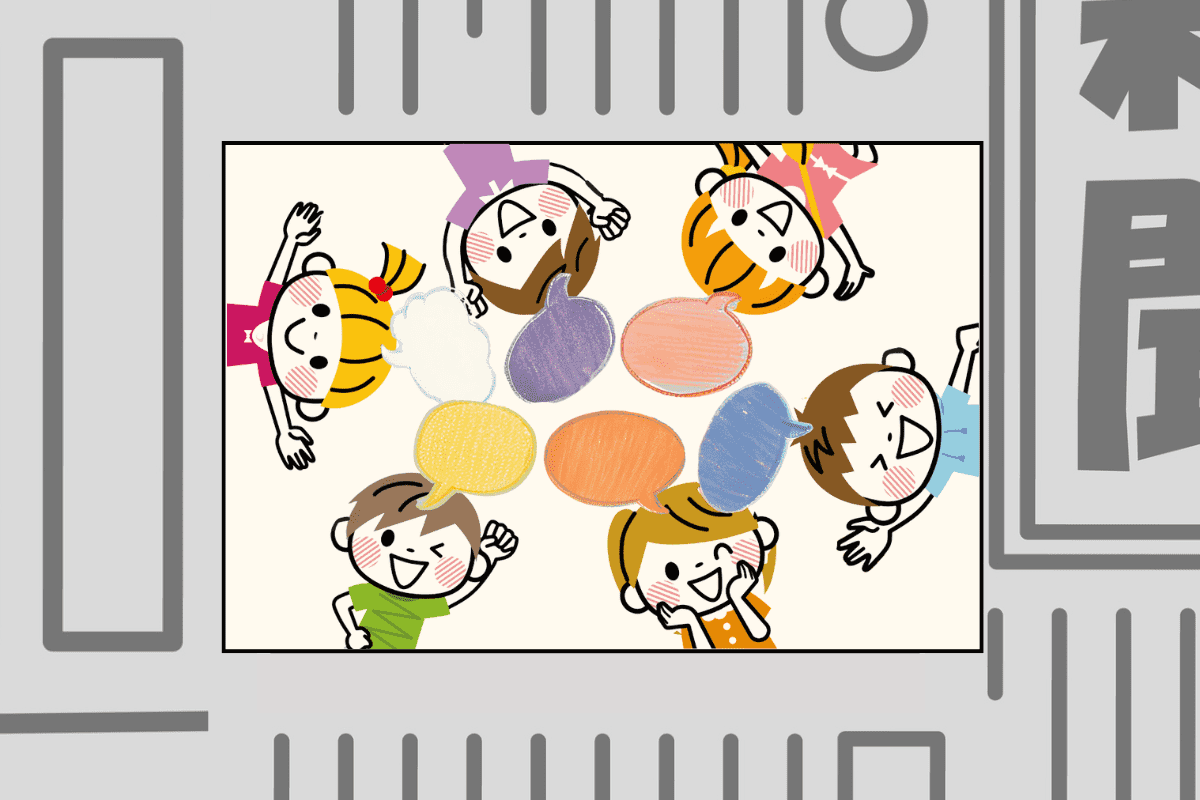
5分でわかる 新聞づくり単元
|
執筆者: 秋山千沙子
|
今月の「5分でわかるシリーズ」は、秋山千沙子先生(東京都・目黒区立上目黒小学校)に、子どもたちが主体的に書く学習に取り組めるための工夫をご提案していただきました。
書くことに苦手意識をもつ子どもにとってハードルが高い「新聞づくり」単元を、「オリジナル話型」を活用した話し合い活動を取り入れることで、相手意識、書く目的を自覚することにつながり、意欲的な取り組みにつながります。
目次
【クラスで主体的に取り組む書く授業】
「新聞を作る」という授業は、様々な学年、教科で行われている。
小学校では切っても切り離せない学習だ。しかし授業前に毎回悩んでしまう。
「テーマは何にするか」
「書くことが苦手な子どもが多い中、書くことを楽しむためにどのように単元学習を充実させるのか」
「『えー、書くのー?』をまた聞くことになるのだろうか……」
そもそも書く単元が得意な子どもも、苦手な子どもも主体的に学習させるには、どのような授業を展開すればいいのだろうか?
この解決法として、子どもたちに「相手意識」や「書く目的」をもたせることが大切なのではないかと考え、今回は「購読者数ナンバー1の新聞を作ろう」というテーマで、新聞を作る単元の学習を進めた。話し合い活動を通して購読者(読み手)を毎時間意識させることで、どのように伝えたら伝わるのか目的や相手意識をもちながら取り組めるようにした。子どもは、購読者(読み手)がどれだけ楽しんで読んでもらえるのかを単元を通して思考し続けた。
2年間担任をしている私の学級では、話し合いの活動に重点を置いており、算数科の学習でも、社会科の知識を深める学習でも、国語科の書く活動でも、作業の合間合間には何度も個人で考えたことを持ち寄り、話し合う活動を取り入れている。話し合い活動では、友だちの新しい視点や違った観点を取り入れていくことで、より内容を充実させることができる。
本単元でも、1人で作成するのではなく読んでもらうことで相手意識をもった記事を書くことができるきっかけとなった。自分よがりの新聞を作っても意味がない。いかに読み手に有益な情報を伝えられるのかに気づかせたい。
自分の世界だけで完結しがちな新聞づくりの単元。購読者(読み手)に寄り添った内容を書けるかどうかを大切に、授業を展開することを意識した。
子どもたちには、単元の導入時に「スクープ」という言葉を使いながら、新聞記者としての意欲を高めさせて学習に入った。実際にはコンテストは開催しなかったが、出来上がった新聞を教室・廊下に掲示したことで互いに見合う時間が自然に生まれた。
また、学校公開時に掲示された新聞を読んだ保護者から、子どもに「すごいね」「新聞を読んで、〇〇のことがよく分かったよ」など、声をかけてくださったことは子どもの達成感につながっていた。
【自分が書きたいことだけを書き続けても意味がない。購読者(読み手)が興味をもたなければならない】
常に相手意識をもたせ、書くことの中心を明確にした。自分で選んだ記事を決め、記事を書き出す前にもグループで内容を推敲した。友だちの意見を聞き、伝えたいことをさらに「すごい!」と思ってもらえるようなアイディアを出し合う時間を何度も設けた。
すると、自然と子どもの伝えたい思いが高まり、購読者(読み手)を意識して記事を書くことができるようになってきた。
【書く単元でも話し合いのスキルが高まる!?】
記事を決める、割り付けを決める、記事を推敲する……。その都度話し合いの活動を入れた。話し合いの際には、教師のモデルトークを行い、要点がずれない手立てを行った。
話し合いの際に子どもがよく使っていたのは、2年間学級で貯め続けている話型である。 授業中に出てきた子どもの発言から「4年1組のオリジナル話型」を作った。私の担当する4年1組では、この話型を使って他教科やその他の時間でも自分の意見をより正確に相手に伝えるために、どの話型を使えばよいか常に思考しながら、話し合い活動を行ってきた。
このような活動を継続してきた結果、子どもは単元や教科を超えて話し合いの力を付けることができている。この最強オリジナル話型が4年1組の子どもたちの学習活動を後押ししている。
上記の言葉は、単元が終わった後に子どもたちから出た言葉である。この単元が始まる前に思っていた、「えー。書くのー?」ではなかった。たくさんの人の意見を聞き、書き上げた自分の文章に自信が付いたのではないだろうか。
書くことを通して、書いて伝える楽しさを味わった子どもは現在、社会科見学で行った浅草の「浅草パンフレット」の作成に意欲的に取り組んでいる。こちらも一人ひとりの視点が生かされていて、興味深いパンフレットになっている。
国語科で試行錯誤しながら取り組んできたことが他教科でも少しずつ成果として表れてきている。子どもだけでなく自分自身も「楽しかった! またやりたい! 次のときは……」と、ワクワクしながら次の教材研究に取り組んでいるところである。
※本授業は、上目黒小学校中学年分科会としての提案授業です
秋山千沙子(あきやま・ちさこ)
東京都・目黒区立上目黒小学校
所属研究会:新算数研究会 目黒支部
