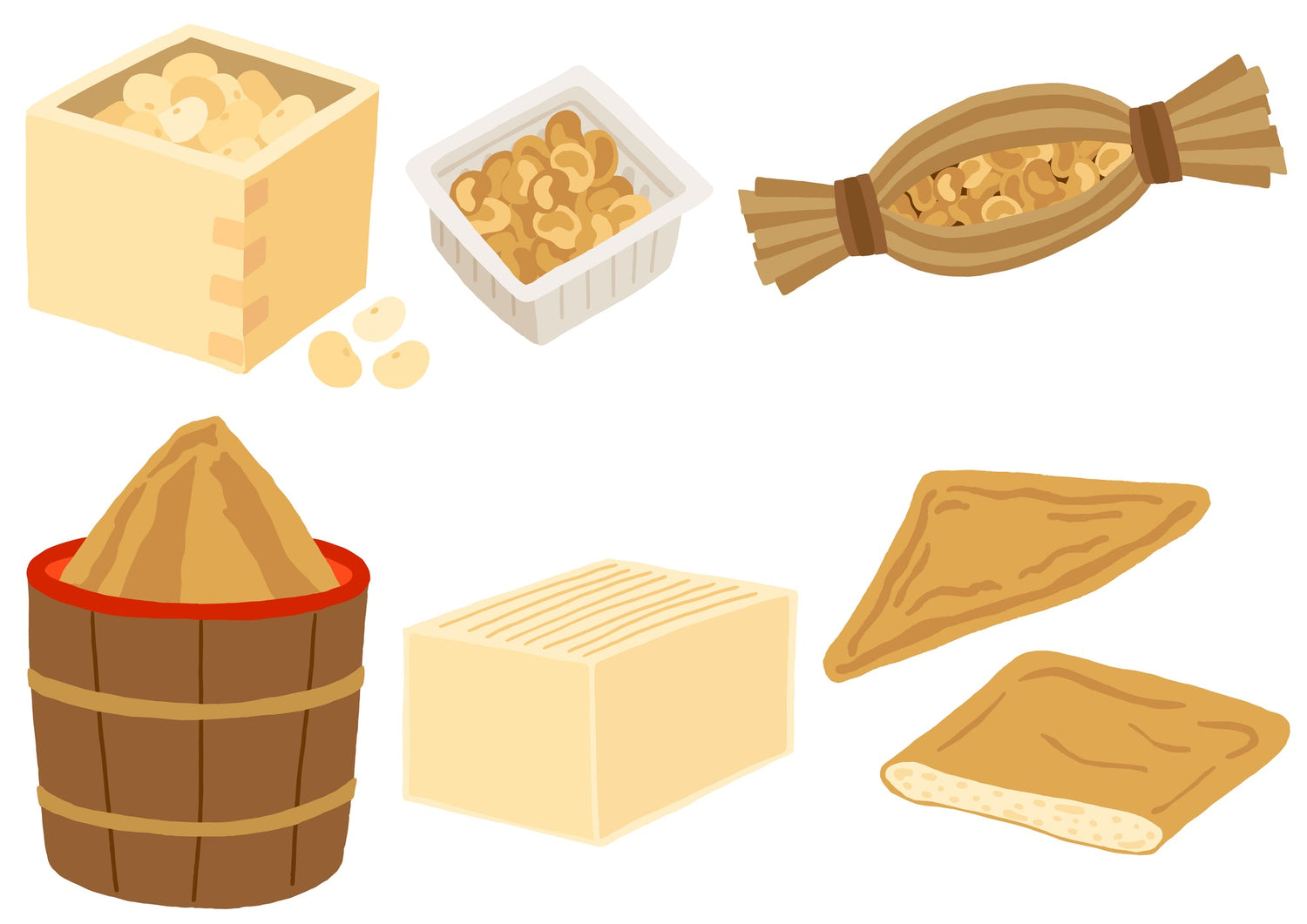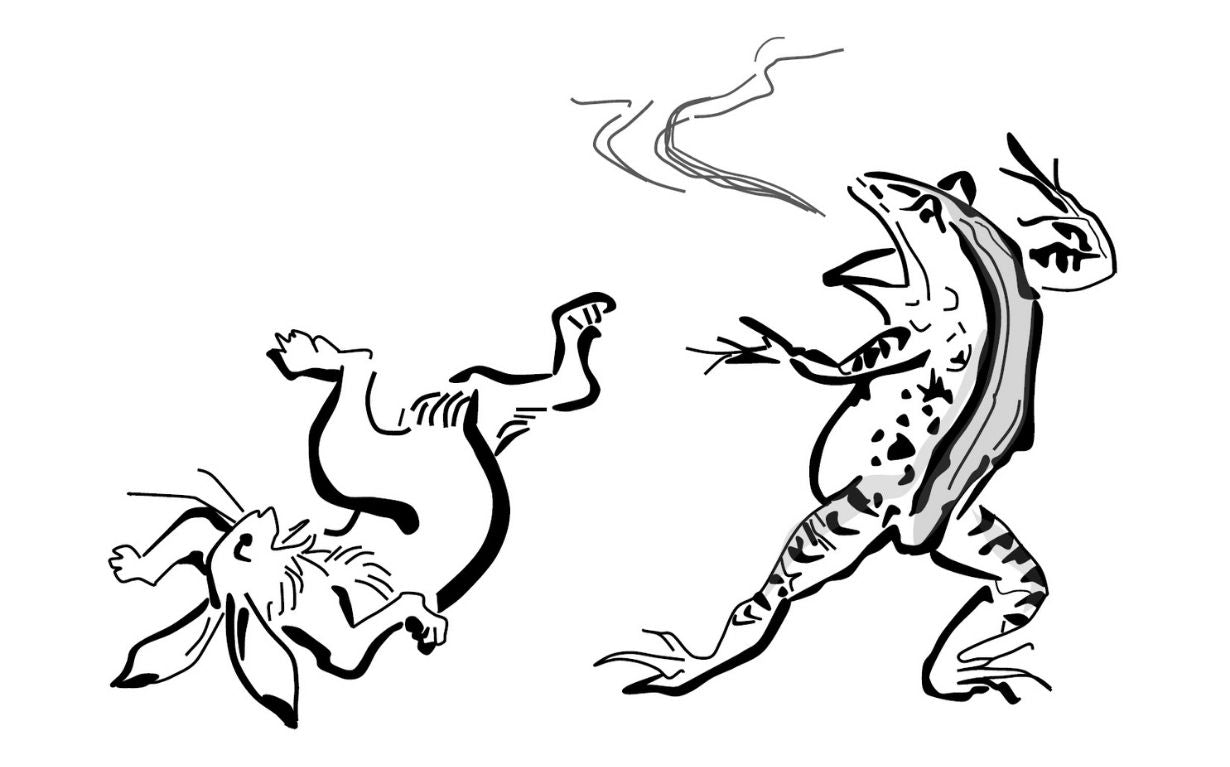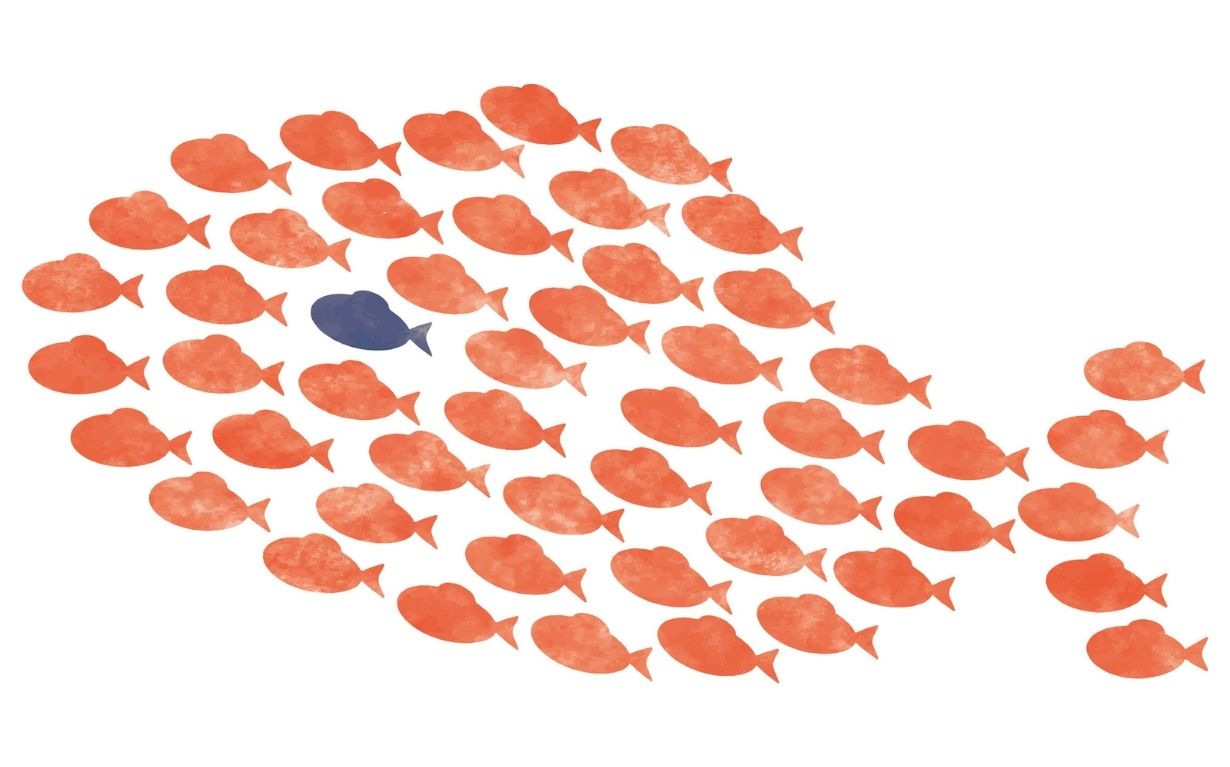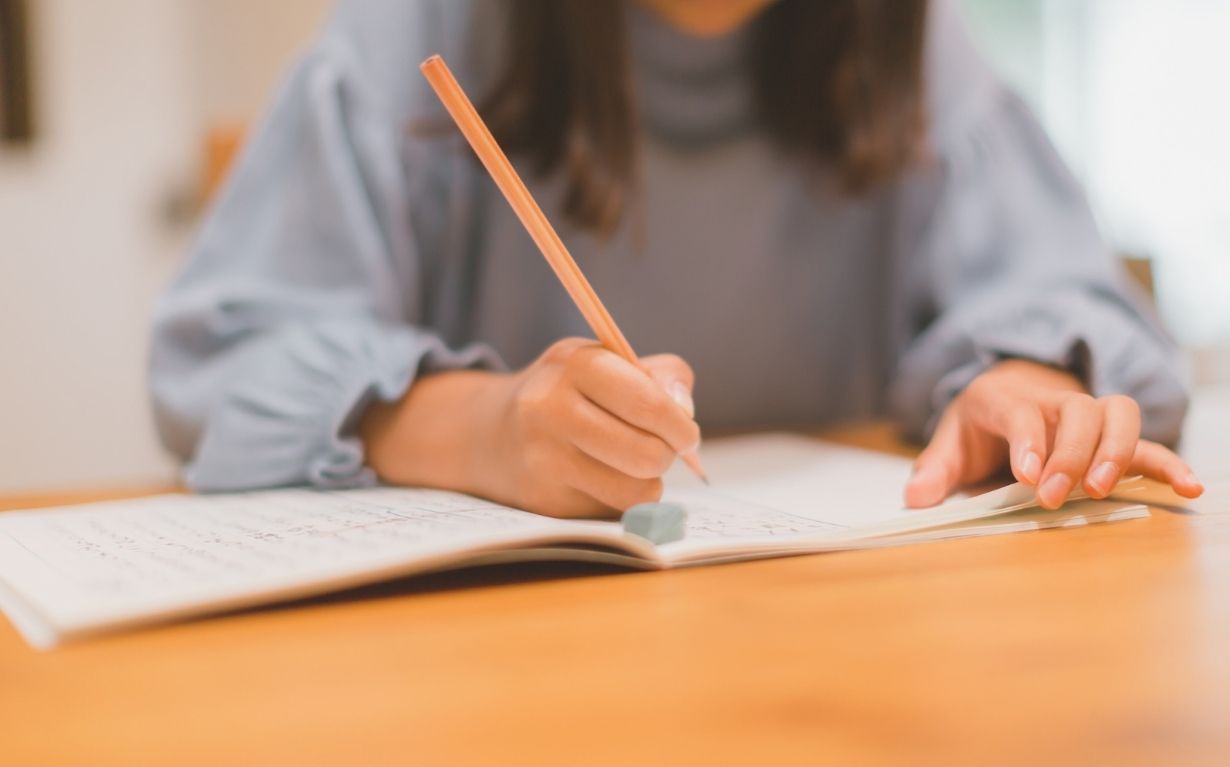子どもと創る「国語の授業」
![]() 有料記事
有料記事
「ごんぎつね」
-思いつきの感想の交流からの脱却-
「ごんぎつね」の授業づくりを紹介します。本教材は各社の教科書に掲載されている定番教材です。登場人物である「ごん」と「兵十」の行動から、心情の変化を読み取ることができます。今回は、田中元康先生(高知大学教育学部附属小学校教諭/高知大学教職大学院教授)に、ごんと兵十二人の関係性に着目し、距離を読むことで、子どもたち自身が考えや感想をもって交流し合う授業づくりについてご提案いただきました。
「すがたをかえるレベル」で「すがたをかえる大豆」を主体的に読む
本教材は事例列挙型の説明的な文章で、例の選び方や分類、順序性を考える手がかりを文章中から見つけることができます。また、学んだ文章の書き方を生かして「食べ物のひみつを教えます」という「書くこと」の学習にも直結しています。
![]() 有料記事
有料記事
学びの必要感をもち、「言葉による見方・考え方」を働かせる授業づくり
「たぬきの糸車」の授業づくりを紹介します。 本教材は、物語の場面の様子から行動を想像しやすいという特性があり、入門期の子どもにとっても楽しく読めるお話です。今回は、長屋樹廣先生(北海道教育大学附属釧路義務教育学校前期課程)に、子どもたちの「大好き」な場面を視点に読むことで、子どもの興味・関心を引き出す授業づくりについて、ご提案いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
「『鳥獣戯画』を読む」を私はこう授業する
「『鳥獣戯画』を読む」の授業づくりを紹介します。本教材は、内容のおもしろさはもちろん、論の展開の仕方、表現の工夫、絵や絵巻物の読み方など、読者を惹きつける筆者の工夫が随所に散りばめられています。今回は、藤田伸一先生(執筆時:川崎市立土橋小学校 現在:神奈川県・川崎市立中原小学校)に筆者の説明に着目し、述べ方の様々な工夫を多角的に見捉えて、子どもたちが自らの表現に生かすことを目指した授業づくりについてご提案いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
「スイミー」
-子どもの追究意識に寄り添った展開を-
「子どもが主体的に読み込んで考えを深めていく姿」を実現させることは多くの先生方の願いである一方で、簡単なことではありません。今回は、山本真司先生(南山大学附属小学校)に「スイミー」を教材に、子どものもった疑問や考えに寄り添い、子どもたちの声をつなぎながら展開していく授業を提案していただきました。子ども同士のやりとりが具体的で、授業づくりの参考になること間違いなしです。
「要約」の指導
-何のために(目的)、どうやって(方法)-
「世界にほこる和紙」の授業づくりを紹介します。本教材は、和紙を作る日本の伝統的な技術について、写真とともに複数の事例をあげながら、分かりやすく説明されています。 今回は、溝越勇太先生(東京都日野市立日野第七小学校)に、本単元のねらいである「要約」の目的と方法を子どもたちが学びを通して自覚し、積極的に取り組める授業づくりについてご提案いただきました。