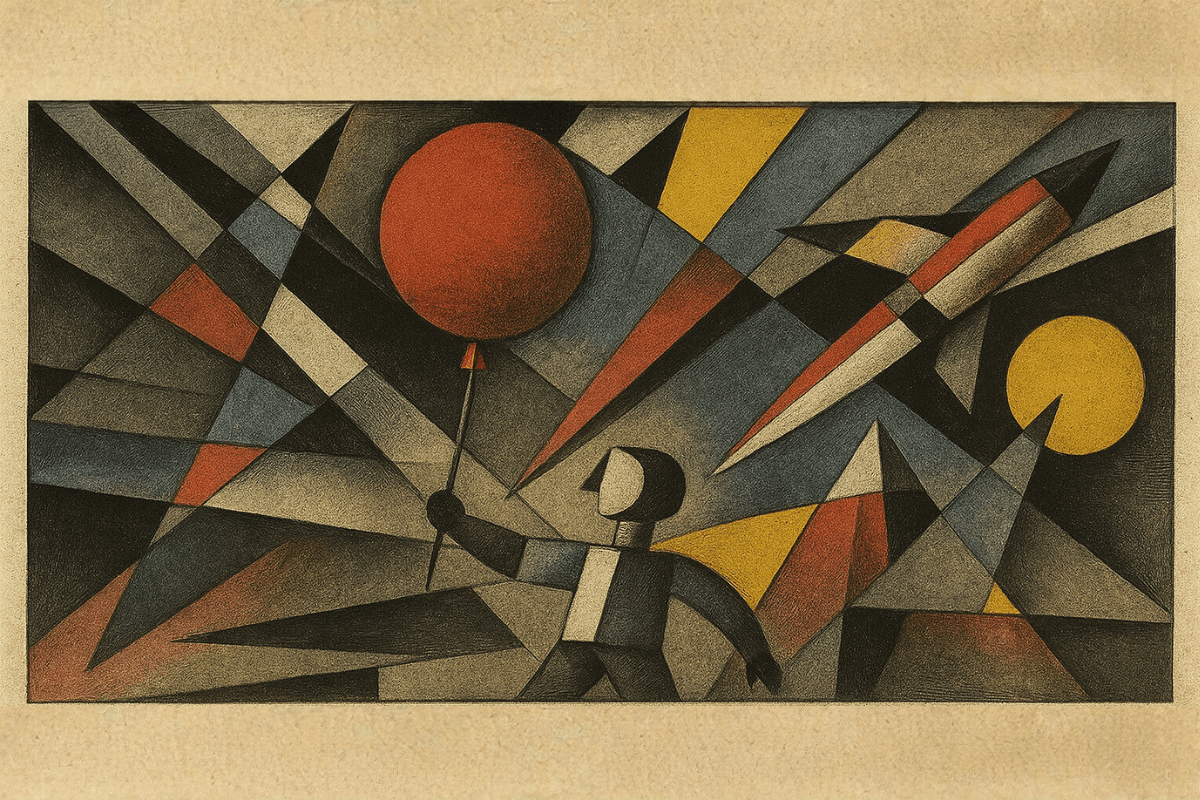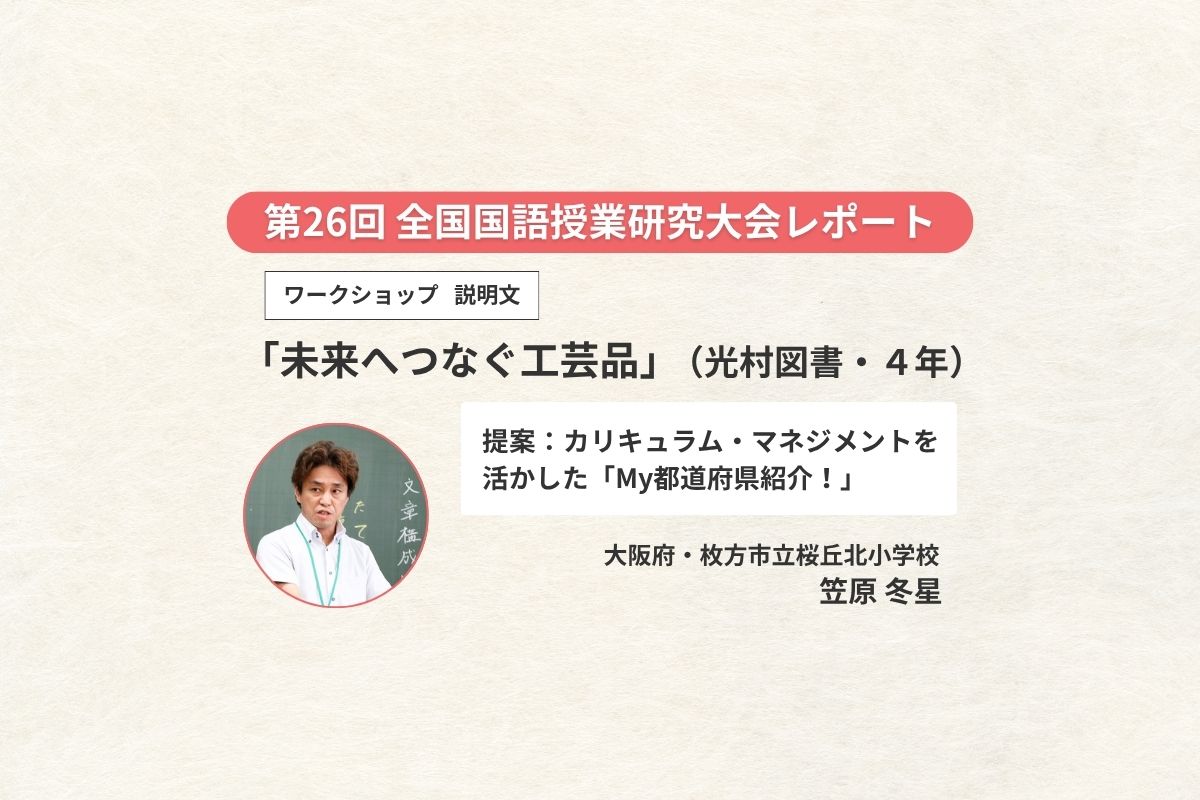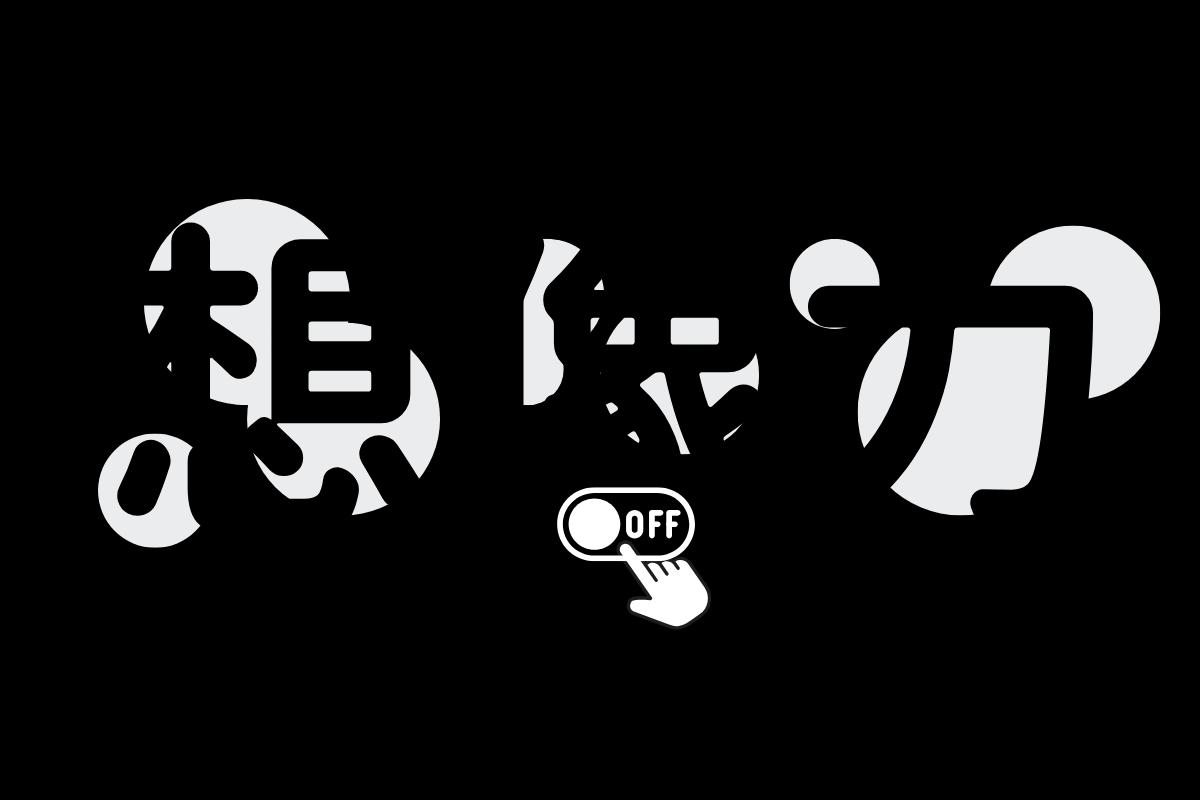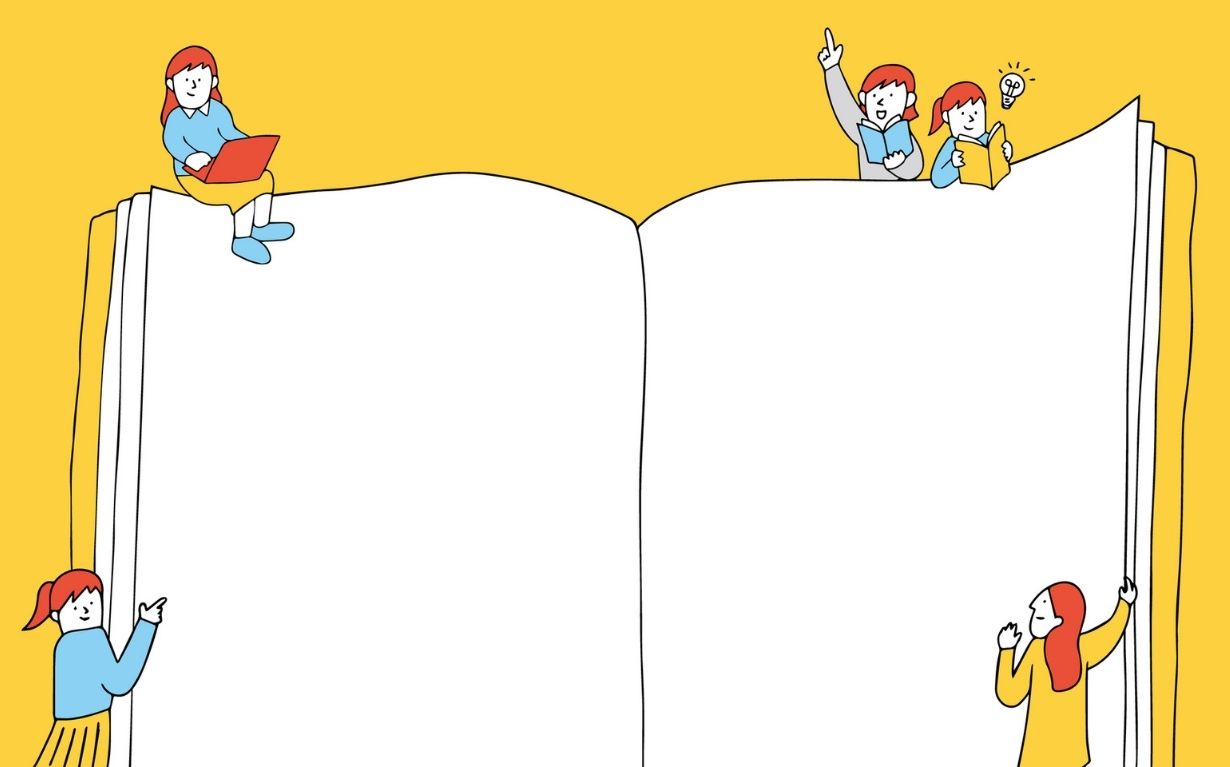子どもと創る「国語の授業」
![]() 有料記事
有料記事
「風船でうちゅうへ」
―筆者の情熱を感じよう!―
今回は笠原冬星先生(大阪府・枚方市立桜丘北小学校)に、本教材の文章を、似た文章構成である「ミラクルミルク」(学校図書 3年)と読み比べることで、順序型の構成であることや意味段落のまとまりに気づきやすくする授業づくりについてご提案いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
「想像力のスイッチを入れよう」
-比較することで、新しい視点を獲得する国語授業-
今回は笠原冬星先生(大阪府・寝屋川市立三井小学校)に、説明文の4つの基本構造をはじめに押さえ、平成27年度版と令和2・6年度版の本教材を読み比べることで、説明文の構造がどのように変化したのか、それぞれにどのようなよさがあるのか、について気づける授業づくりの工夫をご提案いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
「モチモチの木」
-どの子も自分の読みを表現するための手立て-
「モチモチの木」の授業づくりを紹介します。 本教材は、3年生で学習する定番教材です。お話の中では豆太の成長が描かれていますが、最初も最後も「夜、一人でせっちんに行けない」ことで、豆太は本当に成長したのか変容が分かりづらいと感じる子どももいるでしょう。 今回は、笠原冬星先生(大阪府・寝屋川市立三井小学校)に、物語の場面をそれぞれ色分けすることで、その違いを表現しながら読み取っていく授業づくりについて、ご提案いただきました。
カリキュラム・マネジメントを意識した国語授業
「さとうとしお」(東京書籍)の授業づくりを紹介します。本教材は1年生の最初に読む説明文であり、これから6年間で習う説明文を読む構えをもつための重要な教材でもあります。子どもたちにも身近な「さとう」と「しお」を比較しながら、共通点や相違点などを考えることができます。今回は、笠原冬星先生(寝屋川市立三井小学校)に、カリキュラム・マネジメントを意識した授業づくりについてご提案いただきました。