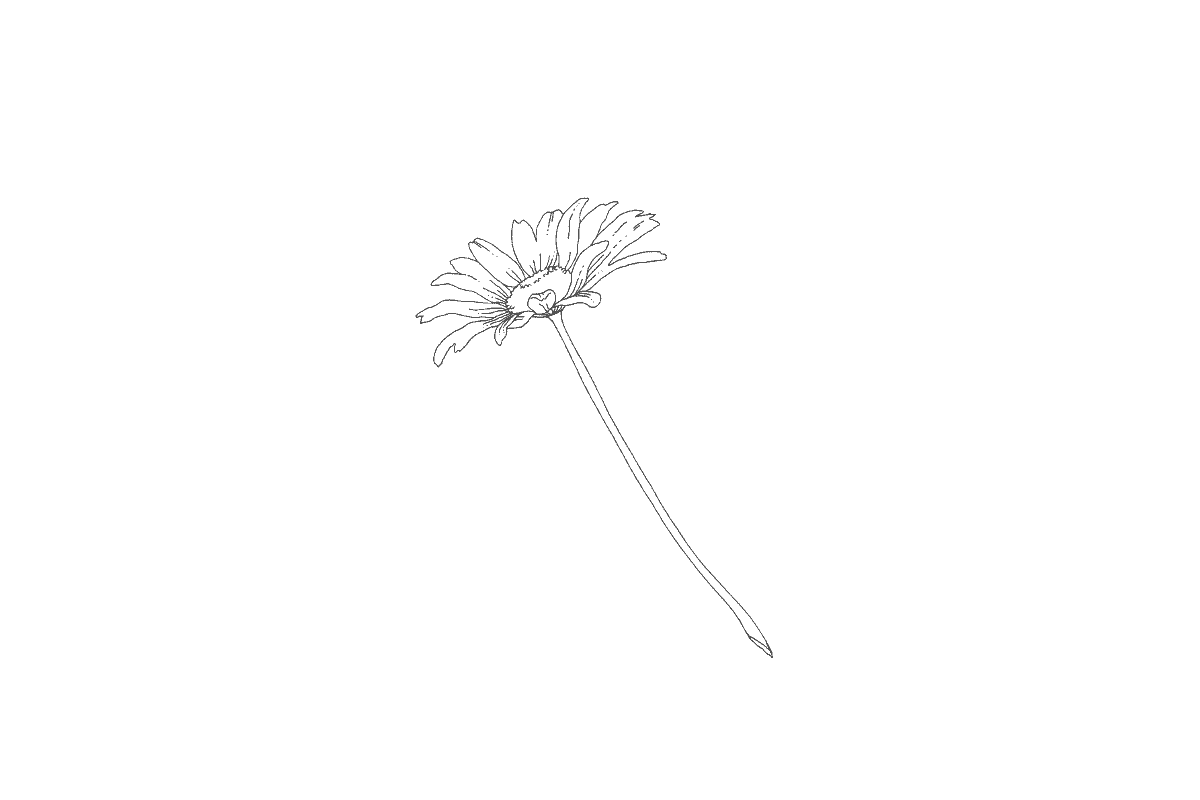
「気付き」から「問い」へ -対比(比較)で読み深める文学の授業-
|
執筆者: 土居 正博
|
単元名:場面の様子を比べて読み、感想を書こう
教材:「一つの花」(光村図書4年上)※掲載は全社
「一つの花」の授業づくりを紹介します。
定番の文学教材のなかでも、指導することが難しいとされる本教材は、叙述と叙述を結び付けたり、描写から登場人物の心情を読みとったりしていく必要があります。
今回は、土居正博先生(川崎市立はるひ野小学校)に、子どもたちが自ら物語の魅力に気付けるような読みを目指す授業づくりについてご提案いただきました。
本教材「一つの花」は、定番文学教材の中でも指導するのが難しい教材の一つとされている。子どもたちがこれまでに学習してきた作品とは違い、同化しやすい登場人物がいなかったり、視点が違っていたりする。
これらのことから、「一つの花は難しい」と言われるのであろう。しかし、裏を返せば、本教材は「特徴的」であるといえる。その特徴を子どもたちが感じ取り、「こういう作品もあるんだな」とよさを捉えられるような指導をしていくべきである。
本教材は、4年生で学習する二番目の文学教材である。これまで子どもたちが読んできた作品は、中心人物に話者の視点が寄り添っている「三人称限定視点」であるのに対し、本教材は、話者の位置がどの人物からも少し距離を置いて客観的に語られる「三人称客観視点」である。高学年に向けて、直接的に心情が描かれていない作品でも、人物の心情の機微を読み取れるようにしていくために配置されている作品と言える。
また、中心人物である「ゆみ子」は読者である4年生の子どもたちよりもずっと幼く、父母はもちろんずっと年上である。子どもたちが同化しやすい人物は出てきていないということになる。だからこそ、叙述と叙述を結び付けたり、描写から読み取ったりする必要性が出てくる。
こうした教材の特性は、本教材を指導することを一見難しくしているが、これらの特性を子どもたちに感じ取らせたり、掴ませたりしていく指導をしていくことができれば、子どもたちが本教材と出合った意味があると言えるだろう。
〔知識及び技能〕
様子や行動、気持ちや性格を表す語句の量を増し、語彙を豊かにすることができる。(1)オ
〔思考力、判断力、表現力等〕
登場人物の気持ちの変化や性格、情景について、場面の移り変わりと結び付けて具体的に想像することができる。Cエ
〔学びに向かう力、人間性等〕
進んで登場人物の気持ちの変化や性格、情景について、場面の移り変わりと結び付けて具体的に想像し、物語の感想を書こうとしている。
| 第一次 | 1) 全文を読み、あらすじを交流する。学習の見通しをもつ。音読練習をする。 |
| 第二次 | 2) 物語の設定を確かめる。問いを出し合う。 3) 一場面を読み、ゆみ子とお母さんについて読み取る。 4) 二場面を読み、お父さんやお母さんのゆみ子への思いを読み取る 5) 三場面を読み、お父さんやお母さんの思いを読み取る 6) 四場面を読み、四場面のある意味を考える。 |
| 第三次 | 7) 読みが変わったところを中心に感想を書き、読みあう。 |
※数字は時数を表す
初読は、あらすじを書かせ交流することから始める(初読であらすじを交流する実践について、詳細は拙著『国語授業の「常識」を疑え!』を参照されたい)。
ここで、ICT端末を使用すると効率的に一人一人のあらすじを交流することができる。ノートに書かせて発表させていた時は、教師が板書で整理していき、読みの共通点や相違点、これから考えていきたいことを見いだしていった。
しかし、写真のように一人一人の書いたあらすじを見ることができれば、子どもたちにはもう一歩先まで学習させることができる。つまり、あらすじを書かせ表現させるだけでなく、「みんなが書いたあらすじを見て気付いたこと」をノートに書かせることまでできるのである。
「一つの花」では、「ゆみ子目線で書いている人とお父さん目線で書いている人がいた」や「四場面について書いている人が少なかった」(初読時には四場面の意義がつかみにくい)など、友達の書いたあらすじを読むことでこの作品の特性に気付いている子がいた。こうした「気付き」はやがて「問い」へとつながっていく。
先述のように、本教材は三人称客観視点なので、人物の心情は直接描かれていない。そのため、叙述や描写から「自分の頭で考え読み取る」ことが大切である。だが、そう伝えただけでは子どもたちは読み取れない。「どのように読み取ればよいか」という考え方や読み方のコツを掴ませていかなくてはいけない。
ここでは、ゆみ子とお母さんを対比させていくとよい。ちょうど説明文「アップとルーズで伝える」(光村4年)で対比について学習した後なので、子どもたちもスムーズに考えることができる。対比することで、読みが深まることを子どもたちに体験させるのである。
ゆみ子とお母さんを対比させていくことで、ゆみ子の幼さやお母さんの子を思う心が際立ち、戦争の悲惨さが強調されていく。子どもたちはこうしたことを体験的に学べば、物語を読む際、意識的に対比を見つけようとするようになる。
場面ごとに読んでいくことを否定する方もいるが、私はこの「一つの花」は子どもにとって少し難しい作品でもあることから、教師と一緒に、一場面ごとに読み取っていくことを選択した。その方が、無理がないと判断したからである。「場面読みはしない」というのは、あくまでも手段であり、目的ではない。
三場面でもお父さんとお母さんの思いを読み取る。授業冒頭で、なぜお父さんとお母さんの思いを読み取るのかを尋ね、確認しておくのも大切なことである。ゆみ子が幼くて、あまり状況等を分かっていないからである。こういうことを押さえておくことも、教師から言われたことをただやるのではなく、主体的な子どもに育てる上で重要である。
ここでは、主に3つの発問を中心に進めた。
「お父さんとお母さん、どちらが悲しいと思うか」
「お父さんはなぜ一つの花を見つめながら行ったのか」
「お父さんが一つの花に込めた思いは?」
この場面はかなり難しいので、はじめの発問は二択にした。そうすることで全員がきちんと参加できるような状況をつくりたかったのである。そのねらいは功を奏し、話し合いは盛り上がりつつお父さんとお母さんの思いへと迫ることができた。
そして二つ目の発問「なぜ一つの花を見つめながら行ったのか」は、これも第二時に子どもたちから出てきたものであった。ここでは、一つの花の状況とお父さんたちの状況を重ねていくと、お父さんが一輪の花に何らかの思いを込めた、ということに迫ることができる。
また、「コスモスは一つだけ咲いていたのか」ということを補助発問すると、「調べたんだけど、コスモスは群生といってたくさん咲くものだそうです。だから、たくさん咲いていたのにあえて一輪だけ持ってきたのではないかな」と気づく子がいる。「一つ」ということに意味を込めたお父さんの思いを考えさせる。コスモスと自分たちを重ね合わせているところに気付かせたい。板書のように、一つの花とお父さんたち(ゆみ子たち)を比べさせるとよいだろう。
三場面はかなり難しいので、はじめの発問は二択にした。そうすることで全員がきちんと参加できるような状況をつくりたかったのである。そのねらいは功を奏し、話し合いは盛り上がりつつお父さんとお母さんの思いへと迫る四場面を扱う際には、第一時であらすじを交流した際、子どもたちも気付いていたように、「四場面をあらすじに入れる子が少ない」ということを想起させ、「なぜ四場面があるのか、その意味は何だろう」と考えさせていくとスムーズだろう。
子どもたちから色々と意見が出されていくと、「戦争が終わって平和になった、そのよさがよく分かる」という意見が出てくる。その意見を皮切りに、「四場面で、戦争が終わってこれまでの場面と大きく違うところを探してみよう」と投げかけると、子どもたちは自然とこれまでの場面と対比し始める。
それらをプラスとマイナスで黒板に整理していくと、子どもたちは「平和な四場面があることで、それまでの場面のマイナスがきわ立つ」と四場面の意義に気付く。その上で、「でも、四場面には一つだけマイナスがあります。お父さんがいないことです。どんなに食べ物とか暮らしはよくなっても、お父さんだけは帰ってきていない」と最後に発言した子がいた。クラスは「たしかに・・・・・・」と静まり返った。
ここでも、対比を用いて読みを深めた。このような読みを重ねていくことで、単元を通して対比(比較)をしながら読みを深めるということに子どもたちが精通していくことができた。
そして二つ目の発問「なぜ一つの花を見つめながら行ったのか」は、これも第二時に子どもたちから出てきたものであった。ここでは、一つの花の状況とお父さんたちの状況を重ねていくと、お父さんが一輪の花に何らかの思いを込めた、ということに迫ることができる。
また、「コスモスは一つだけ咲いていたのか」ということを補助発問すると、「調べたんだけど、コスモスは群生といってたくさん咲くものだそうです。だから、たくさん咲いていたのにあえて一輪だけ持ってきたのではないかな」と気づく子がいる。「一つ」ということに意味を込めたお父さんの思いを考えさせる。コスモスと自分たちを重ね合わせているところに気付かせたい。板書のように、一つの花とお父さんたち(ゆみ子たち)を比べさせるとよいだろう。
学習のまとめは、授業で詳しく読み、友達と話し合って考えが変わったことを中心に書かせる。少し難しい「一つの花」にはピッタリの課題だと思う。ここで、最初に読んだ時よりも自分の成長を感じられていれば、授業は成功と言えるであろう。
本教材の特性をしっかり子どもたちたちが感じ取れ、捉えられるような指導を目指して単元を構成した。概ね、子どもたちは本教材の特性を掴み、叙述や描写から、主に対比(比較)という思考をしながら読みを深めることができたように思う。一方、子どもたちにとって難しい教材とはいえ、やや教師主導になってしまった感は否めない。子どもたちが問いをもち、自分たちで解決していく中で物語の魅力に気付いていけるような工夫を更に追究していきたい。
〔引用・参考文献〕
田中実、須貝千里(2001)『文学の力×教材の力 小学校編4年』教育出版
土居正博(2023)『4年生担任のための国語科指導法』明治図書出版
土居正博(2023)『国語授業の「常識」を疑え!』東洋館出版社
土居正博(どい・まさひろ)
川崎市立はるひ野小学校教諭
全国国語授業研究会監事/国語教育探究の会会員/東京書籍小学校国語教科書編集委員/教育サークル「KYOSO's」代表/教員サークル「深澤道場」所属
