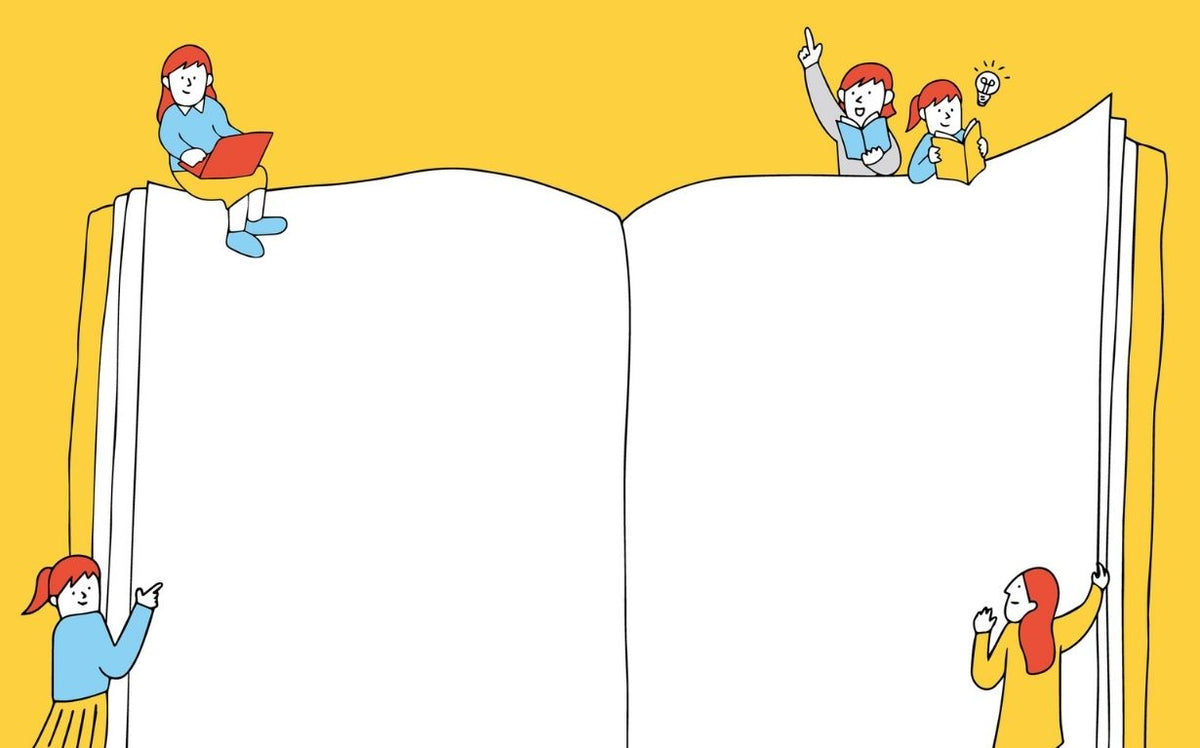
カリキュラム・マネジメントを意識した国語授業
|
執筆者: 笠原 冬星
|
単元名:「さとうとしお」のはかせになろう!
教材:「さとうとしお」(東京書籍1年)
「さとうとしお」(東京書籍)の授業づくりを紹介します。本教材は1年生の最初に読む説明文であり、これから6年間で習う説明文を読む構えをもつための重要な教材でもあります。子どもたちにも身近な「さとう」と「しお」を比較しながら、共通点や相違点などを考えることができます。今回は、笠原冬星先生(寝屋川市立三井小学校)に、カリキュラム・マネジメントを意識した授業づくりについてご提案いただきました。
単元の教材である「さとうとしお」は、砂糖と塩、それぞれの共通点や相違点が簡潔に書かれており、とても分かりやすい文章である。また、本教材は1年生で初めて触れる「説明文」である。言い換えると、小学校6年間で初めて触れる説明文であり、これからの説明文を読む「構え」をもつためにも重要な教材といえる。
説明文は「事実」を正確に伝える文章であり、そのことを意識した授業であることが大切である。そして、砂糖や塩についてより詳しくなるために、調べる活動を行う。このとき、自身で調べるだけでなく、「他者から話をきく(教えてもらう)」活動などを織り交ぜて行うとより主体的に学びに向かうことができる。
文部科学省の資料によると、カリキュラム・マネジメントを行う際には以下のようなことが重要であると示されている。
第1 小学校教育の基本と教育課程の役割
4 各学校においては,児童や学校,地域の実態を適切に把握し,
などを通して,教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと(以下「カリキュラム・マネジメント」)に努めるものとする。
上記1)~3)の3つを満たすことを目指し、今回は「3年生との交流」を取り入れた単元を構成した。
1)に関しては、「国語科」と「理科」を教科横断的な視点で組み立てて行った。
2)に関しては、子どもたちが砂糖と塩についての調べ学習を進めるうち、さらに詳しくなりたいという思いが熟成したタイミングで交流を行った。
3)に関しては、上級生との交流を図るため、3年生を1年生にとって必要な人的体制として単元構成を考えた。
単元の流れは以下の通りである。
また、本教材を1年生の最初に扱う場合、まだひらがなが書けない子どもがいるだろう。その場合は文章に線を引き色分けしたり、まとめは絵(ピクトグラム)でかかせたり、文字以外で視覚化する工夫をするとよい。
本教材は「さとう」と「しお」の共通点と相違点を説明した文章である。教科書では、最初に砂糖と塩の見た目から「どちらもしろいこな」(共通点)であることを述べ、次に、3つの観点(さわったかんじ、なめてみると、なにからできる)から比較し、相違点を挙げている。最後は「どちらもたべものをおいしくする」という共通点でまとめがあり、挿絵とともにイメージしやすく、分かりやすい文章構成になっている。
共通点には「赤」で線を引き、相違点には「青」で線を引くことにより、視覚的に分わかりやすくなる。「赤」→「青」→「赤」の線が見えてくるので、「サンドイッチみたいに挟まれている」など、自分たちの言葉で構造の特徴を言えるとよい。
そして、「さとうとしおの特徴はほかにもあるかな?」と問うことにより、3つの観点以外の特徴についても調べたくなり、「自分たちで調べる学習」につなげることができる。
〔知識及び技能〕
「○○も」や「○○は」など、助詞の違いについて知ることができる。
→文の中における主語と述語との関係に気付くこと。(1)カ
〔思考力、判断力、表現力等〕
同じところ(共通点)や違うところ(相違点)を見つけることができる。
→文章の中の重要な語や文を考えて選び出すこと。Cウ
〔学びに向かう力、人間性等〕
「さとうとしお」について、さらに詳しく調べようとする。
| 第一次 | 「さとうとしお」について読む。(第1時) |
| 「さとうとしお」を読んで気付いたことを書く。 | |
| 第二次 | 「さとう」と「しお」の共通点や相違点を見つけ、調べ学習を行う。(第2・3時) |
| ・共通点や相違点を見つけ、「○○も」や「○○は」など助詞に着目して読む。 ・「さとう」や「しお」についてくわしく調べてみる。 | |
| 第三次 | 3年生より「さとう」と「しお」について話をきく。(第4時) |
| 3年生から同じ重さの「さとう」と「しお」の大きさについて話を聞き、考える。 |
第2時では、本文について詳しく読んでみる。このとき、同じところ(共通点)や違うところ(相違点)を意識して読むようにする。また、先述した通り、本単元を行う時期にはまだ全てのひらがなが書けない子どもがいることが考えられる。その場合は「色鉛筆で線を入れる」など、視覚的に分かりやすい工夫をするとよい。また、まとめは絵(ピクトグラム)などで書くのもよい。
そして、同じところ(共通点)では、「○○も」となっており、違うところ(相違点)では、「○○は」というように助詞の使い分けについても考えることができるとよい。以下に板書とノートの様子を示す。
第4時では、最後に3年生と一緒に授業を行った(ただし、3年生と交流するには、3年生の「ものの重さ」の単元を1学期にずらすか、1年生の単元を3学期にずらすなど検討が必要があり、かつ学年間での調整が必要である)。
3年生の「ものの重さ」の単元では「ものはその種類によって同じ体積でも重さは違う」という学習を行う。その発展として「ものはその種類によって同じ重さでも体積が変わる」という実験を行っておく。具体的には、砂糖50gと塩50gでは同じ重さでも体積は違う、という実験である(写真1)。
のような実験を行うことにより、「砂糖と塩は同じ重さでも体積は違う」ということを知っている3年生が、ゲストティーチャーとして1年生に教えることができる(写真2)。
実際に1年生は、砂糖と塩の新しい「違い」について知ることが可能となる。今回は「同じ重さでも大きさが違う」ことが分かる。
「カリキュラム・マネジメント」を行うことにより、1年生は砂糖と塩を比較し、調べ学習や上級生からの説明を通して新しい発見ができ、知識を深めることができた。3年生とっては自身の勉強したことを「他者に伝える」活動を行うことにより、自身の学習した内容を振り返り、理解を深めることができる。
このように、「他者との交流(人と人とのつながり)」を意識した授業を行うことにより、双方にとってメリットのある授業を行うことができる。
〔引用・参考文献〕
文部科学省 資料「カリキュラム・マネジメントとは」1枚目(https://www.mext.go.jp/content/1421692_5.pdf)
※最終アクセス日:2023年4月17日
笠原 冬星(かさはら・とうせい)
大阪府・寝屋川市立三井小学校
全国国語授業研究会理事/「読皆塾」主宰
