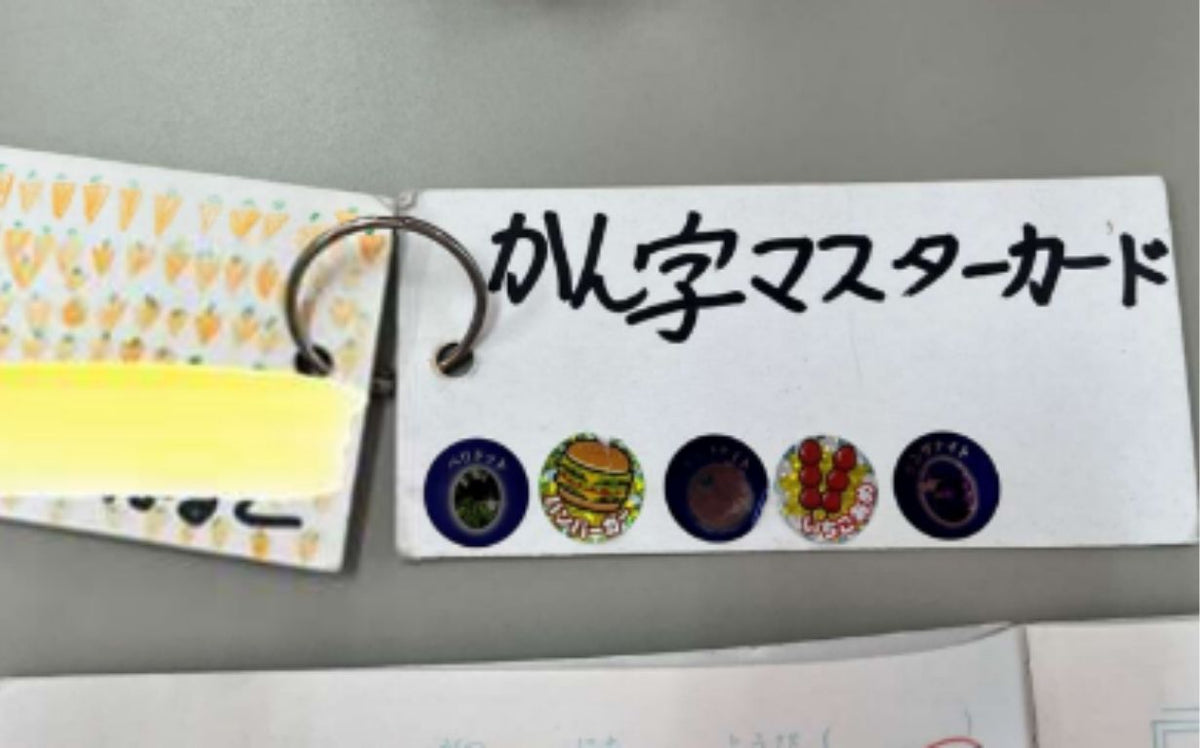
「漢字マスターカード」で目指す、主体的な漢字学習!!
|
執筆者: 古沢 由紀
|
今月の5分で分かるシリーズは、スキマ時間でできる、子どもたちが主体的に漢字を学びたくなるような方法を、古沢由紀先生(大阪府・大阪市立柏里小学校)にご提案していただきました。
ご紹介する「漢字マスターカード」は、子どもたちがすぐに取り組める簡単さと、理解度に合わせて調整ができるため、漢字が苦手な子でも楽しく取り組めることに特徴があります。
ゲーム感覚でアクティビティとしても取り入れやすいため、温かい教室づくりにも役立つでしょう。
クラスには漢字を苦手と感じている子どもが必ず何人かいる。そんな子どもたちに共通していることは、漢字を覚えるまでに時間がかかることである。
しかし、漢字の学習は、読むことや書くことの学習と異なり毎日くり返し行うことで定着する学習である。毎日いやいやでやっている子どもたちは、結果、漢字テストでは何も書けず、さらに漢字ぎらいに拍車をかけることになる。子どもたちは決して不真面目にしているわけではない。きちんと漢字の宿題も提出し、漢字ドリルや漢字ノートも丁寧な字で書いている。それにもかかわらず、漢字テストになると漢字を書くことができないのである。
筆者が初任者のとき、漢字が苦手な子どもに対してひたすら間違えた漢字を書くよう指導したときがあった。夕方までかかってしまい、子どもも私もへとへとになった記憶がある。
決められた授業時数の中で、毎日の漢字学習時間を確保していくこと自体が至難の業であった。どうすればよいものかと頭を悩ませていたとき、ふと「授業で漢字を教えることも大事だが、子どもたちに自ら漢字を学習する方法を身に付けることが先決ではないか」と思い始めた。
森川正樹(2010)は、効果的な時間の活用によって子どもたちの学びを確保することができるとし、「スキマ時間」の重要性を述べる。森川のいうスキマ時間とは、授業中や日常生活中(子どもにも教師にも)に生まれてくる少しの時間、およそ5分から10分くらいの、ともすれば何となく無駄に浪費してしまっているような時間である。例えば、朝の準備が終わった後、発育測定の後、給食の後、掃除が終わった後などのちょっとだけ空いた時間のことを指す。このようなスキマ時間を活用することで、漢字学習の時間を捻出できると考えた。
また、棚橋尚子(2015)は、「国語教育における漢字指導」について「自立して漢字を習得していくことができる学習方略を身につけさせること」が「核心となる」と述べている。つまり、教師は漢字を教えるのではなく、子ども自らが漢字を学習する能力を身に付けさせることが必要である。
さらに、土居正博(2019)は、一般的な漢字指導では「チェック量」が少ないと言及しており、効果的に繰り返して練習しシステム化することを提案している。土居は、書けない漢字だけを練習することで、個々の理解度に合わせて主体的に漢字の習得に取り組むことができると述べる。
漢字の練習にはいろいろな方法があるが、一般に採られている方法は、たくさん書いて覚えるという方法である。たしかにそれは1つの有効な方法であるだろう。しかし、漢字を苦手と思っている子どもほど、たくさん書くことをいやがる傾向にある。
子どもだけでなく教師にとっても効率的で、子どもが主体となって学んだことを自覚化する学習を目指していきたい。
以上のことをふまえ、子ども自らが漢字の学習に取り組めるように考案したのが「漢字マスターカード」である。
まず、5~10問程度の漢字テストを行う。そこで、子どもたちの漢字の力量、習熟度をチェックする。間違えた漢字をカードに書き出す。そして、そのカードを何度も反復する。次に、覚えた漢字がいくつあるか自己チェックを行う。この一連の流れを繰り返すことが、漢字マスターカードによる学習である。
このサイクルを回すことによって、漢字の学び方を身に付けることを想定している。
まず、子ども自身が覚えていない漢字を自分自身で把握するために、15分程度のスキマの時間を用いて「力量チェック」を次のような学習の流れで行う。今回は漢字の「書き」の場合で説明したい。
次は、漢字マスターカードに書き出した漢字を覚えているか確かめるために、「自己チェック」を行う。これも、先ほどの「力量チェック」と同様に、スキマ時間を用いて次のような学習の流れで行った。
1年間を通してこのような漢字学習の一連のサイクルを繰り返した結果、漢字ぎらいだった子どもは、3学期の漢子テストでは最終的に100点をとることができた。徐々に点数が上がっていき、すらすらと漢字を書く姿に変わり、自信に溢れていた。
たくさん漢字マスターカードをちぎることができた子どもには、「本日の漢字マスターは○○さん!」と言ってみんなで褒め称えたり、漢字マスターカードを全部無くすことができたら「漢字マスター賞」としてシールをあげたりして、子どもたちのやる気が継続するように工夫した。ちょっとしたゲーム感覚で楽しみながら取り組んでいくことが大切である。
1人ではなかなか取り組めない子どもも、クラス全員で目標をもって取り組むことで、継続していくことができるだろう。競争ではなく、昨日の自分より今日の自分がどうだったかを常に意識して取り組むように伝えて、温かい教室づくりを目指したい。
学級でスキマ時間ができたときに、漢字マスターカードを開く習慣を身に付けられていれば、いちいち指示を出さなくても知的な時間へと変わり、教室が騒然とすることがなくなるだろう。
大切なことは、指示されなくても、子ども自らが個々の理解度に合わせて、主体的に漢字に取り組む学習方法を習得することである。
〔引用・参考文献〕
森川正樹(2010)『学習密度が濃くなる“スキマ時間”活用レシピ50例―教室が活気づく、目からウロコ効果のヒント教材集』pp.13-16、明治図書出版
棚橋尚子(2015)「学習方略を身につけさせることのできる漢字指導を目指して」『日本語学』34-5、pp.22-32
土居正博(2019)『クラス全員が熱心に取り組む! 漢字指導法 ―学習活動アイデア&指導技術』、pp.16-17、明治図書出版
古沢 由紀(ふるさわ・ゆき)
大阪府・大阪市立柏里小学校
国語教育探究の会/全国大学国語科教育学会/『子どもの論理』で創る国語授業研究会/国語科学習デザイン学会/関西国語授業研究会/国語教育伸の会(代表)
