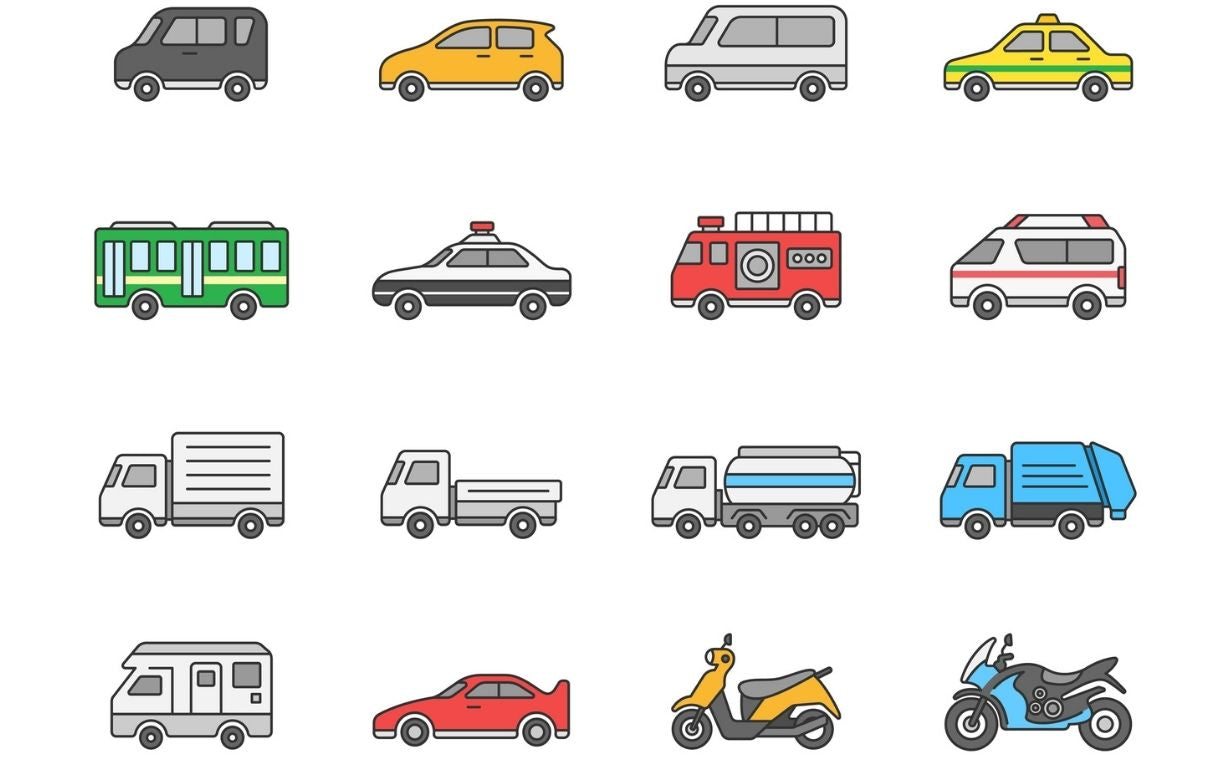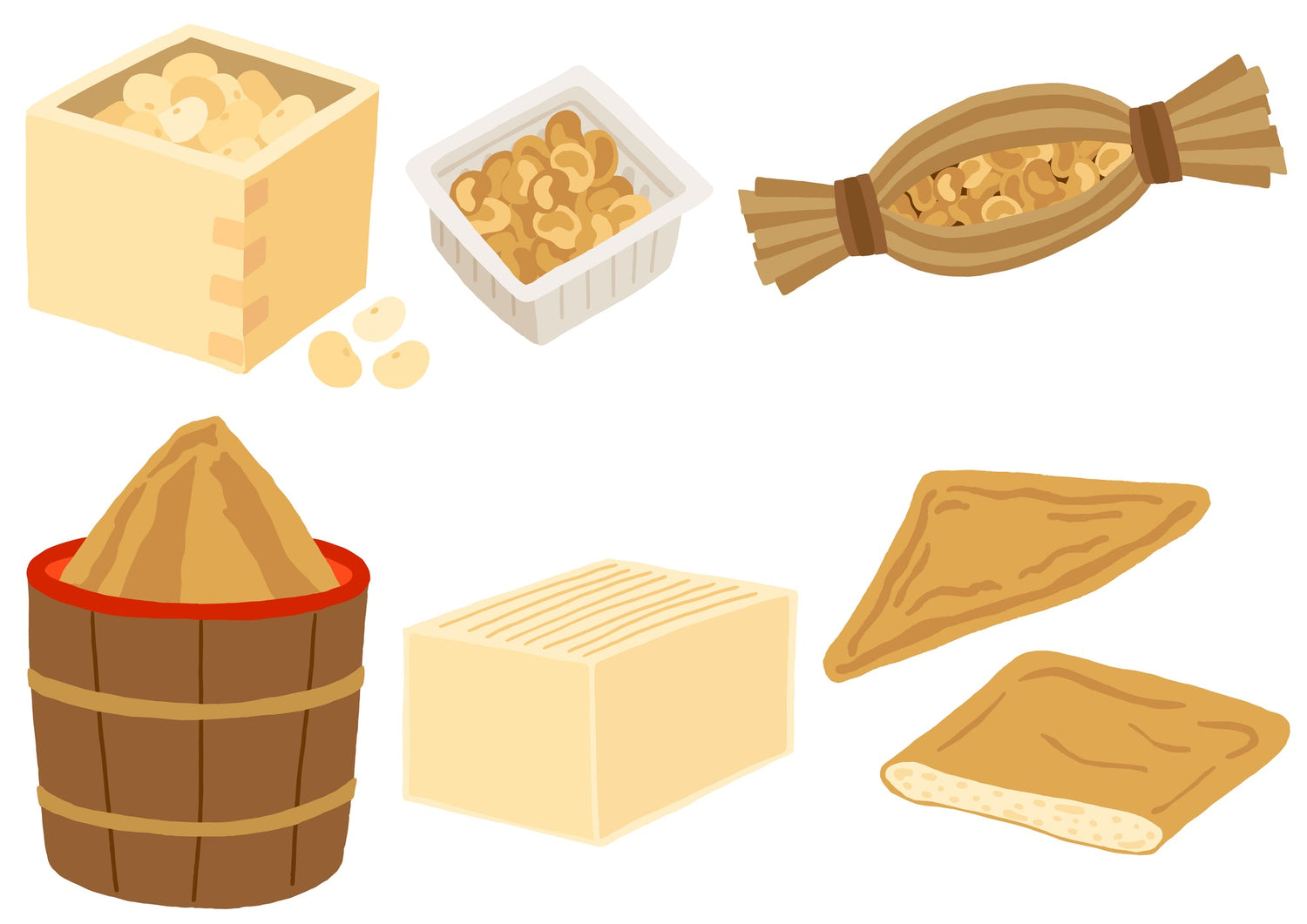子どもと創る「国語の授業」
![]() 有料記事
有料記事
「モチモチの木」
-どの子も自分の読みを表現するための手立て-
「モチモチの木」の授業づくりを紹介します。 本教材は、3年生で学習する定番教材です。お話の中では豆太の成長が描かれていますが、最初も最後も「夜、一人でせっちんに行けない」ことで、豆太は本当に成長したのか変容が分かりづらいと感じる子どももいるでしょう。 今回は、笠原冬星先生(大阪府・寝屋川市立三井小学校)に、物語の場面をそれぞれ色分けすることで、その違いを表現しながら読み取っていく授業づくりについて、ご提案いただきました。
単元の構成を子どもに選択させる授業づくり
本教材はさけの成長が時系列に沿って書かれており、子どもたちも興味をもちやすい説明文です。2年生の子どもたちにも、自ら学びの目的意識をもって学ぶ順番を選択させることで、「個別最適な学び」「協働的な学び」の素地をつくっていきます。
物語の構造をシンプルに捉え、主題へと迫る読みの授業
今回は、石原厚志先生(立川市立新生小学校)による、物語の構造はシンプルに捉えつつ、「心情の変化」を「ものの見方の深化」として読むことで、主題に迫ることができる読みの授業づくりについて、ご提案です。
「じどう車くらべ」
-「書くこと」につなげる読みの授業づくり-
小島美和先生(東京都・杉並区立桃井第五小学校)による「書くこと」につなげる読みの授業づくりのための三つのポイントを教えていただきます。子ども自身が「読むこと」の学習の中で、大事な言葉や文に合ったものを選ぶことができる授業づくりをご提案です。
![]() 有料記事
有料記事
「ごんぎつね」
-思いつきの感想の交流からの脱却-
「ごんぎつね」の授業づくりを紹介します。本教材は各社の教科書に掲載されている定番教材です。登場人物である「ごん」と「兵十」の行動から、心情の変化を読み取ることができます。今回は、田中元康先生(高知大学教育学部附属小学校教諭/高知大学教職大学院教授)に、ごんと兵十二人の関係性に着目し、距離を読むことで、子どもたち自身が考えや感想をもって交流し合う授業づくりについてご提案いただきました。
「すがたをかえるレベル」で「すがたをかえる大豆」を主体的に読む
本教材は事例列挙型の説明的な文章で、例の選び方や分類、順序性を考える手がかりを文章中から見つけることができます。また、学んだ文章の書き方を生かして「食べ物のひみつを教えます」という「書くこと」の学習にも直結しています。