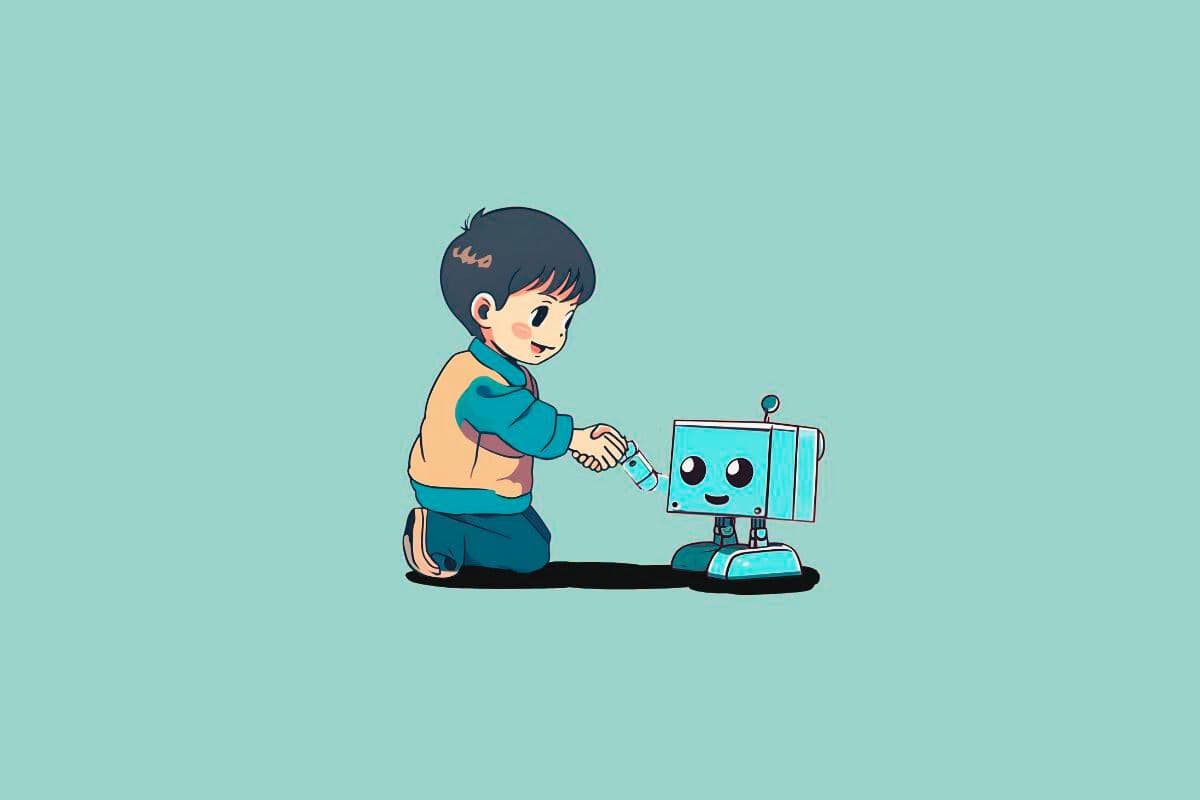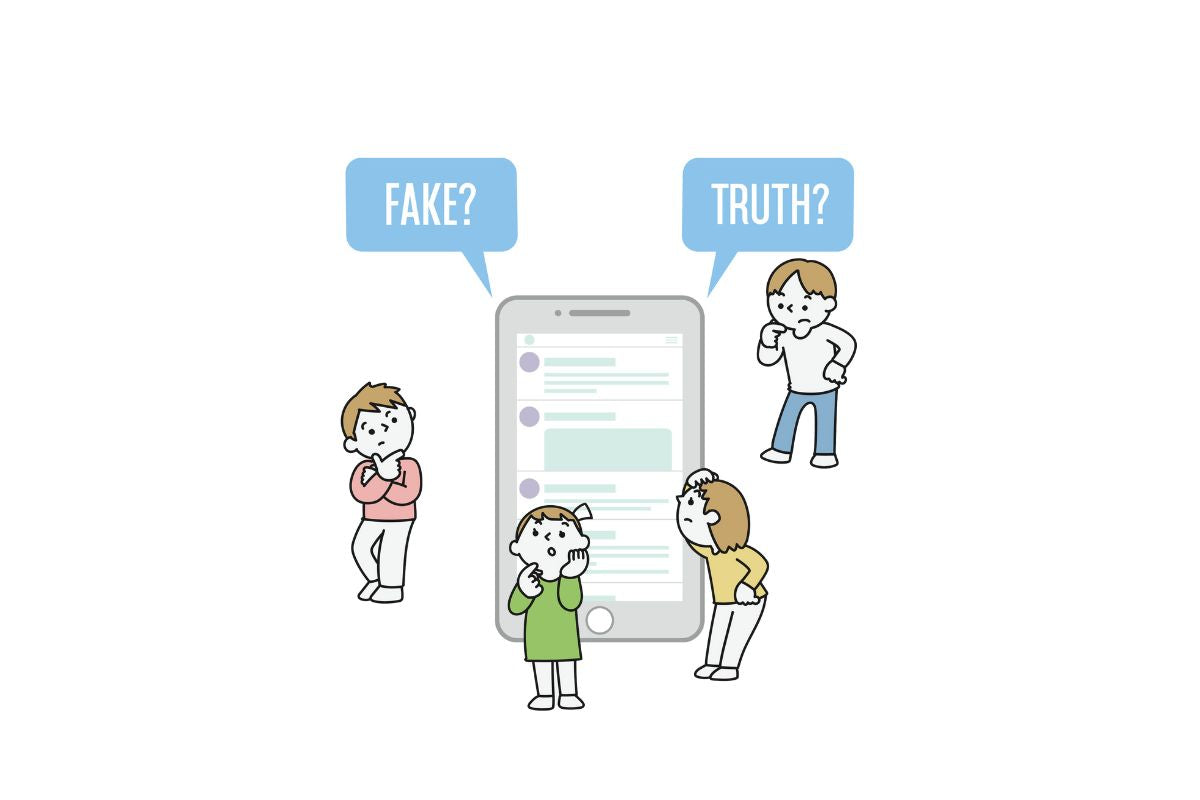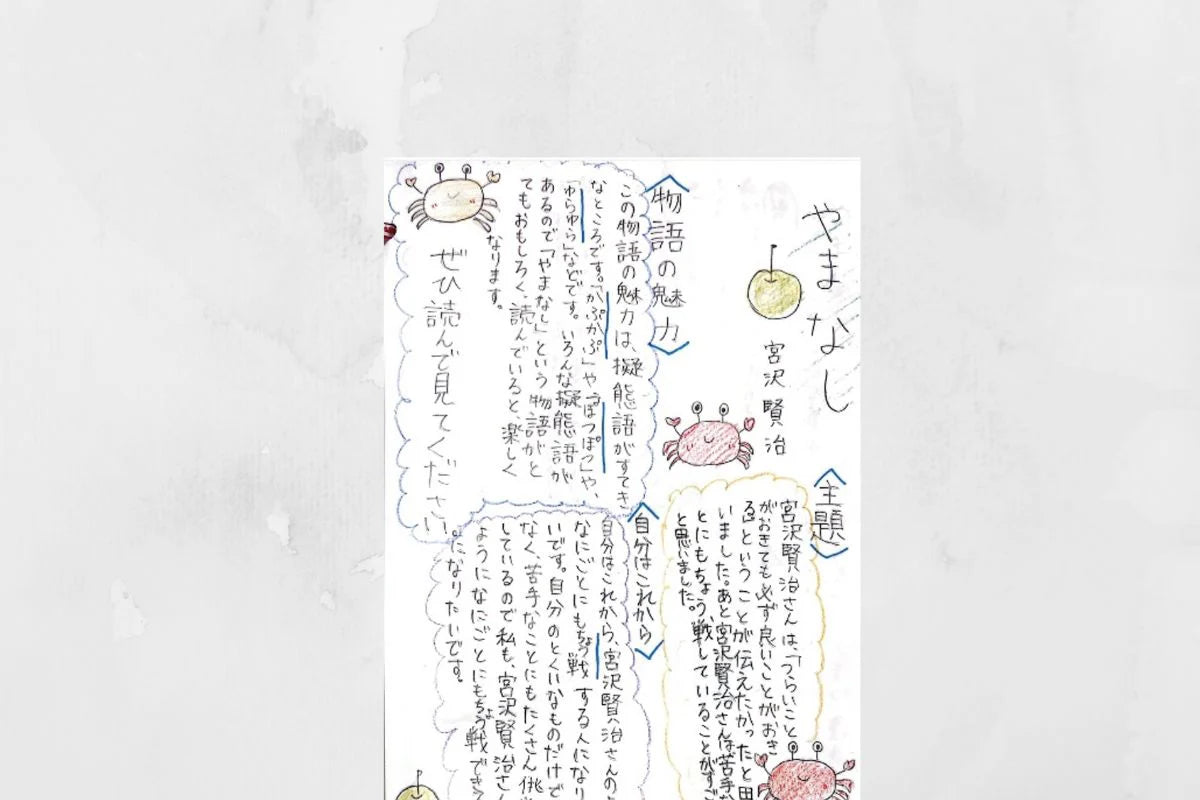子どもと創る「国語の授業」
![]() 有料記事
有料記事
「『弱いロボット』だからできること」
-当事者意識から読みの必要感へ-
今回は松岡 整先生(高知大学附属小学校)に、本文との出合いを工夫し、新しい事柄と自身との認識のずれを生みだすことで、より主体的で探究的な読みが進むといった、当事者意識から深まる授業づくりの工夫をご紹介いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
子どもの「できた!」をつくる「ビーバーの大工事」の授業づくり
-だいじで読むと、わかる!見える!すごい!-
本教材「ビーバーの大工事」は、タイトルからはその大工事の目的がわからず、謎に包まれています。「ガリガリ」「ドシーン」のオノマトペや「近よって みますと、」とあるように、まさに目の前のビーバーの行動を実況しているかのように説明が展開されることで、ワクワクしながら読み進めることができ、最後に判明する、大工事の目的とその壮大さには驚きが待っていることでしょう。 今回は斎藤由佳先生(神奈川県・逗子市立沼間小学校)に、説明文を読み深める上で、「何を明らかにしたいか」「何に気をつけて読みたいか」といった、「だいじの基準」を学級で共有し、更新することで、自分なりの「だいじなことば」の探究が進むようになる授業づくりの工夫をご紹介いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
登場人物への共感から読みを深める「たずねびと」の授業デザイン
今回は三笠啓司先生(大阪教育大学附属池田小学校)に、物語文の学習で、登場人物が出合った出来事を実際に疑似体験することで、登場人物の心情の揺れ動きを実感を伴って理解することができる、「共感読み」を取り入れた授業づくりをご提案いただきました。共感読みから生まれた自分なりの問いを全体で共有することで、子どもたちが「考えたい問い」が立ち上がり、子どもたちと一緒に単元をつくることができます。
![]() 有料記事
有料記事
「想像力のスイッチを入れよう」を私はこう授業する!!
「想像力のスイッチを入れよう」の授業づくりを紹介します。本教材は、SNSが拡大する現代において、情報を適切に吟味したり、違う視点から考慮したりする大切さを伝え、これからの社会を生きる子どもたちにとって重要な情報リテラシーについて考えることができる教材です。 今回は藤田伸一先生(神奈川県・川崎市立中原小学校)に、問いかけやゆさぶり発問の工夫によって、子どもの読みたい意欲を引き出す授業づくりについてご提案いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
「やまなし」
-難解教材こそ全員参加の授業を!-
今回は久住翔子先生(新潟大学附属長岡小学校)に、教材「やまなし」について、「Which型の課題」や「ゆさぶり発問」を用いて、自分の立場を決めたり無理なく考えの視野を広げたりすることで、子どもたち全員が参加できる授業づくりをご紹介いただきました。 考えたいことについて直接問いかけるのではなく、「Which型の発問」と「ゆさぶり発問」を組み合わせることで、子どもたちの「どうしてだろう」「なぜだろう」を引き出し、考えるべきポイントが焦点化されます。
![]() 有料記事
有料記事
「固有種が教えてくれること」
-具体的な子どもの姿で授業づくりをしよう-
今回は中野紗耶香先生(東京都・国分寺市立第三小学校)に、教材「固有種が教えてくれること」の筆者の説明の仕方と資料の効果をとらえる学習を通して、目指したい子どもの姿から単元のねらいを設定し、子どもの思考の文脈にそった必然性のある単元計画を立て、本時を組み立てるなど、 目の前の子どもの姿をもとにした単元構想の方法をご提案いただきました。