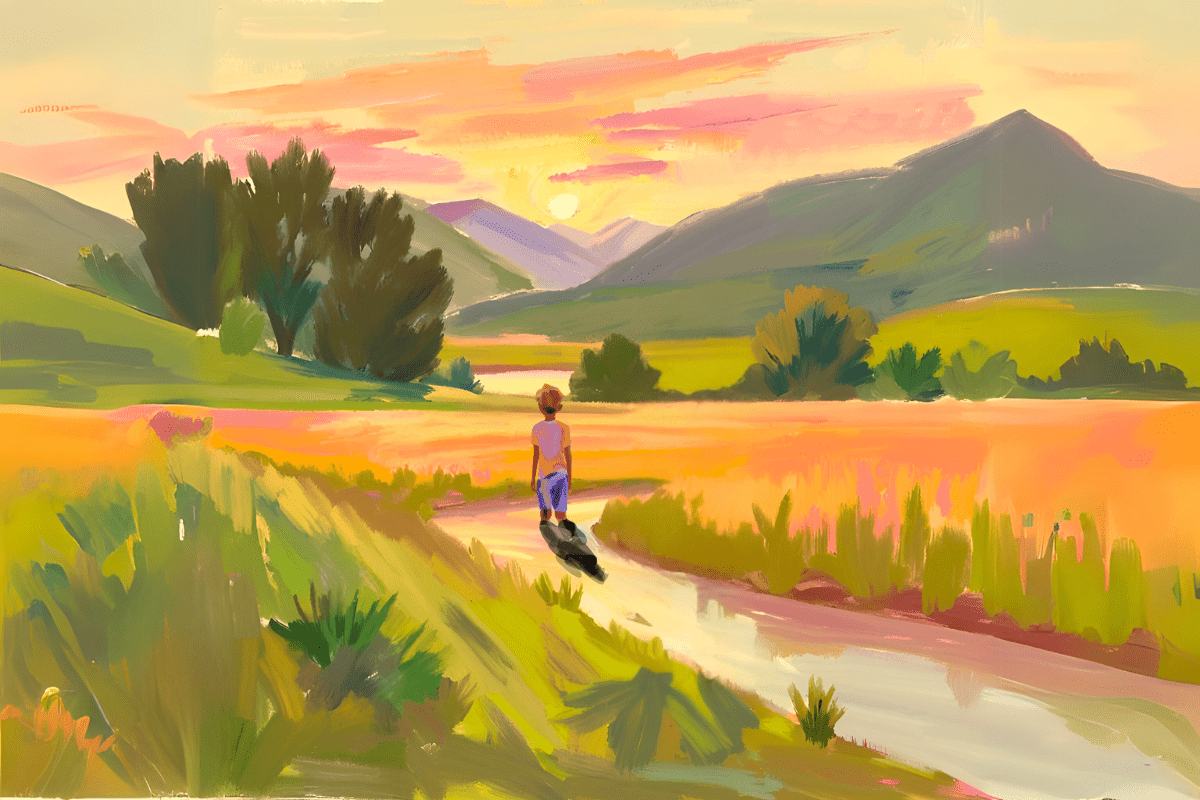子どもと創る「国語の授業」
![]() 有料記事
有料記事
「一つの花」
-自分で学びをつくる 問いへの寄り添い方-
今回は斎藤由佳先生(神奈川県・逗子市立沼間小学校)に、内容の読みをそろえるための「つかみの問い」と、自分の「問い」を見直し物語の核に迫る「深める問い」、この2つの「問い」を段階的に考えていくことで、自身で読みを深める学び方を学ぶことができる、授業づくりのアイデアをご提案いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
「自然のかくし絵」の授業づくり
―「段落」から見えてくる文章構成-
本教材「自然のかくし絵」では、保護色によって昆虫がどのように敵から身を隠しているのか、「はじめ」「中」「おわり」の三部構成で説明されます。「中」で、隠れ方の事例を紹介した後、保護色だけで、はたして完璧に身を隠せられるのかといった、2つ目の「問い」が提示されることが特徴的です。 今回は石原厚志先生(東京都・武蔵野市立第一小学校)に、一つひとつの段落の役割を押さえた後、段落のつながりから筆者の説明の工夫を捉えることで、段落に着目して読むことの大切さに気がつけるような授業づくりについて、ご提案いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
「白いぼうし」
-新学年スタート! なぞを解き明かす楽しみをみんなで味わおう-
本教材「白いぼうし」は、タクシー運転手の松井さんが体験する、乗客の女の子が突然消えるという不思議なお話です。「はたして女の子はちょうちょだったのか」などの謎の答えは最後まで描かれておらず、ミステリーのような不思議なお話でありながら、白いぼうしなどの色彩表現、夏みかんの香りなどの描写から、さわやかな読後感が味わえる物語文です。 今回は中野紗耶香先生(東京都・国分寺市立第三小学校)に、叙述をもとに謎をといていく読みの楽しさを感じられる、授業開き間もない4月にぴったりな物語文の授業づくりについて提案をいただきました。
![]() 有料記事
有料記事
「笑うから楽しい」「時計の時間と心の時間」「主張と事例」の3つの教材を読みとらせる単元デザイン
教材「時計の時間と心の時間」は、「心の時間」はそのときの状況や一人ひとりで感じ方が異なることを、わかりやすい例から実験の事例へと順に挙げて説明し、正確な「時計の時間」と合わせてどのように生活すべきなのか、読者に考えるきっかけを与えてくれます。 今回は比江嶋 哲先生(宮崎県・都城市立有水小学校)に、「〔練習〕笑うから楽しい」「時計の時間と心の時間」「〔情報〕主張と事例」を通して学習することで、「主張と事例の関係をとらえる」力が育めるような授業づくりをご提案をいただきました。
![]() 有料記事
有料記事
「やくそく」
-同化体験を通して、物語世界を豊かに想像する文学の授業-
本教材「やくそく」について、三笠啓司先生(大阪教育大学附属池田小学校)に、登場人物に同化する体験を通して、一人ひとりが想像力を働かせ、豊かに物語世界を楽しむことができる、「同化体験」を取り入れた授業づくりのご提案をいただきました。
![]() 有料記事
有料記事
「川とノリオ」
-子どもの思考をフル回転させる! 発問のつくり方-
本教材「川とノリオ」は、太平洋戦争の時代を背景に、父の出征と戦死、母の広島での原爆死など、幼いノリオの経験する悲劇を描いた物語作品です。川の情景描写、登場人物の行動描写などから豊かに心情を読み取ることができる教材です。 今回は大矢直子先生(千葉県・浦安市立浦安小学校小学校)に、表現技法に着目して、子どもたちが読みを深め、広げるためには、どのような発問をすればよいのか、多くのアイデアをご提案いただきました。