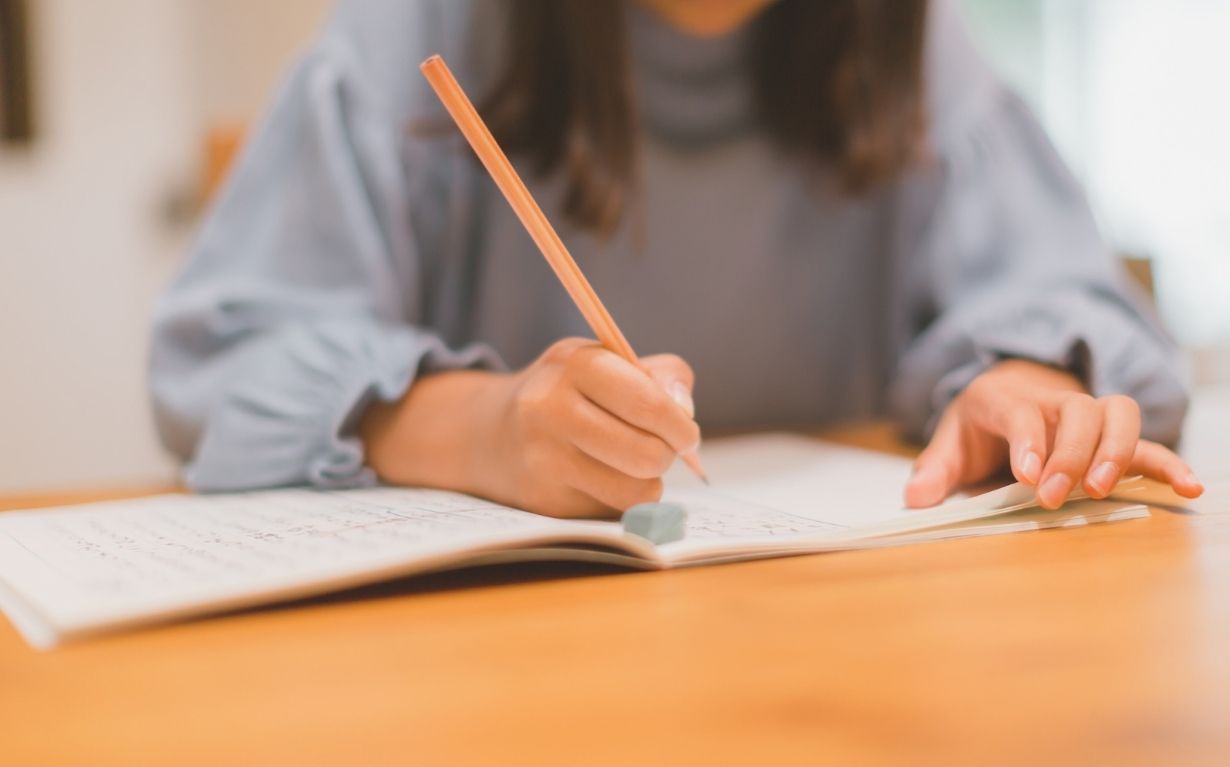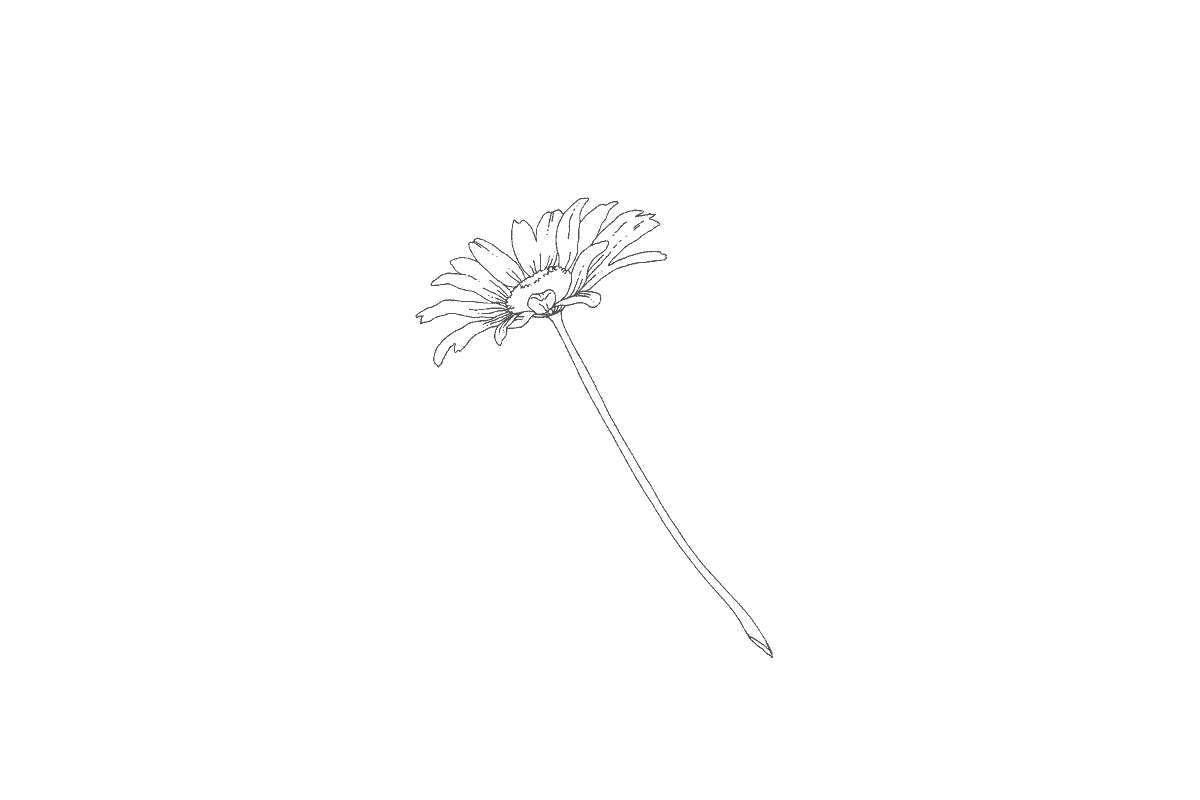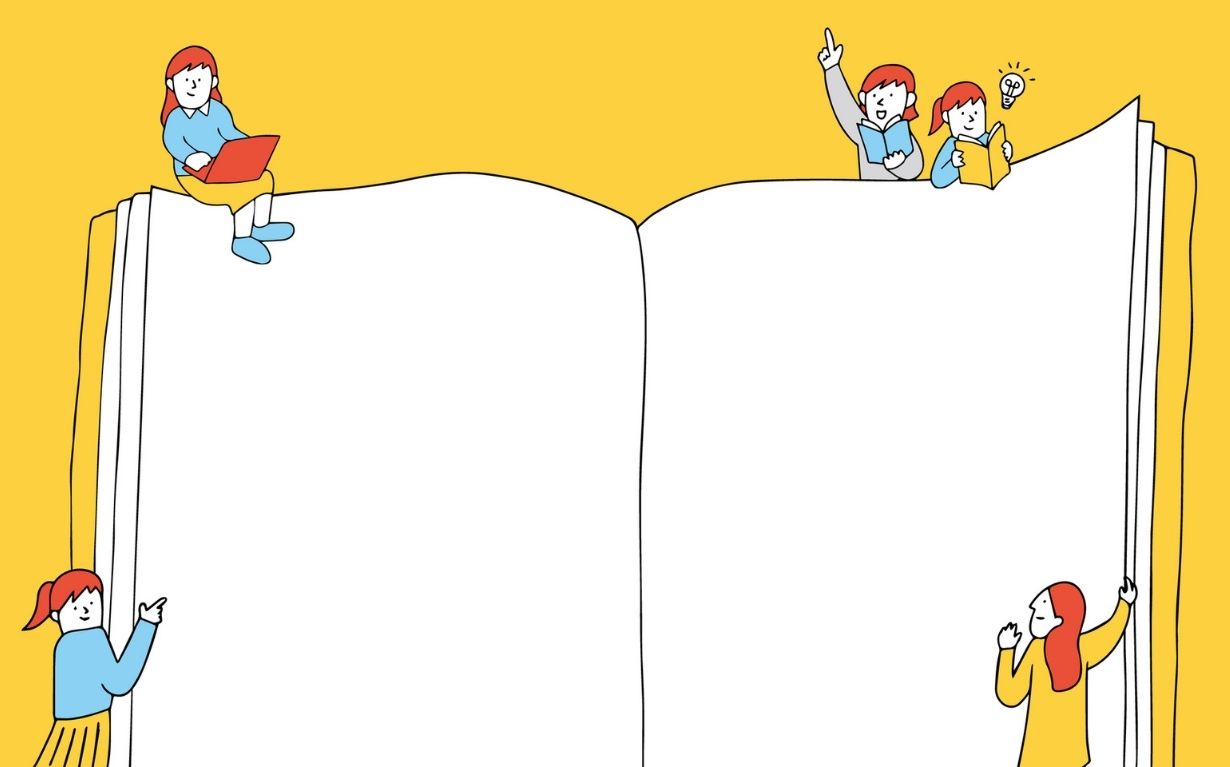子どもと創る「国語の授業」
「要約」の指導
-何のために(目的)、どうやって(方法)-
「世界にほこる和紙」の授業づくりを紹介します。本教材は、和紙を作る日本の伝統的な技術について、写真とともに複数の事例をあげながら、分かりやすく説明されています。 今回は、溝越勇太先生(東京都日野市立日野第七小学校)に、本単元のねらいである「要約」の目的と方法を子どもたちが学びを通して自覚し、積極的に取り組める授業づくりについてご提案いただきました。
「気付き」から「問い」へ
-対比(比較)で読み深める文学の授業-
「一つの花」の授業づくりを紹介します。 定番の文学教材のなかでも、指導することが難しいとされる本教材は、叙述と叙述を結び付けたり、描写から登場人物の心情を読みとったりしていく必要があります。 今回は、土居正博先生(川崎市立はるひ野小学校)に、子どもたちが自ら物語の魅力に気付けるような読みを目指す授業づくりについてご提案いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
どの子も、きれいなひらがなが書ける
-なぞらない「ひらがな書写」指導のコツ-
国語入門期では、「ひらがな書字」は必須の指導内容である。どの子も、ひらがなが書けるように丁寧に指導する必要がある。 しかし、一般的には、きれいなひらがなを書けるように指導することは難しいようである。ひらがなが書けるのは「書字」のレベル。そして、きれいなひらがなが書けるのは「書写」のレベルである。
子どもの声を育てる「音読」のスキル
今月の「5分で分かるシリーズ」では、子どもの声を育てる「音読」のスキルについて学びます。 授業や宿題で取り組む音読も、目的やその効果を意識することが、子ども一人ひとりの声を育てていくうえで大切になります。弥延先生には、マンネリ化を防ぐ音読の様々な形態についてもご紹介いただきます。
カリキュラム・マネジメントを意識した国語授業
「さとうとしお」(東京書籍)の授業づくりを紹介します。本教材は1年生の最初に読む説明文であり、これから6年間で習う説明文を読む構えをもつための重要な教材でもあります。子どもたちにも身近な「さとう」と「しお」を比較しながら、共通点や相違点などを考えることができます。今回は、笠原冬星先生(寝屋川市立三井小学校)に、カリキュラム・マネジメントを意識した授業づくりについてご提案いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
「白いぼうし」
-物語の魅力は「人物相関図」でどのように引き出されるのか?-
「白いぼうし」の授業づくりを紹介します。 物語文では、主人公や主人公との関わりが深い人物に注目しがちですが、実はその周りの人物が重要な役割を担っており、「物語をドラマチックにするしかけ」が必ず存在します。 今回は、沼田拓弥先生(東京都八王子市立第三小学校)に子どもの興味・関心までもが可視化され、さらには思考がどんどん広がる板書をはじめとした授業づくりについてご提案いただきました。