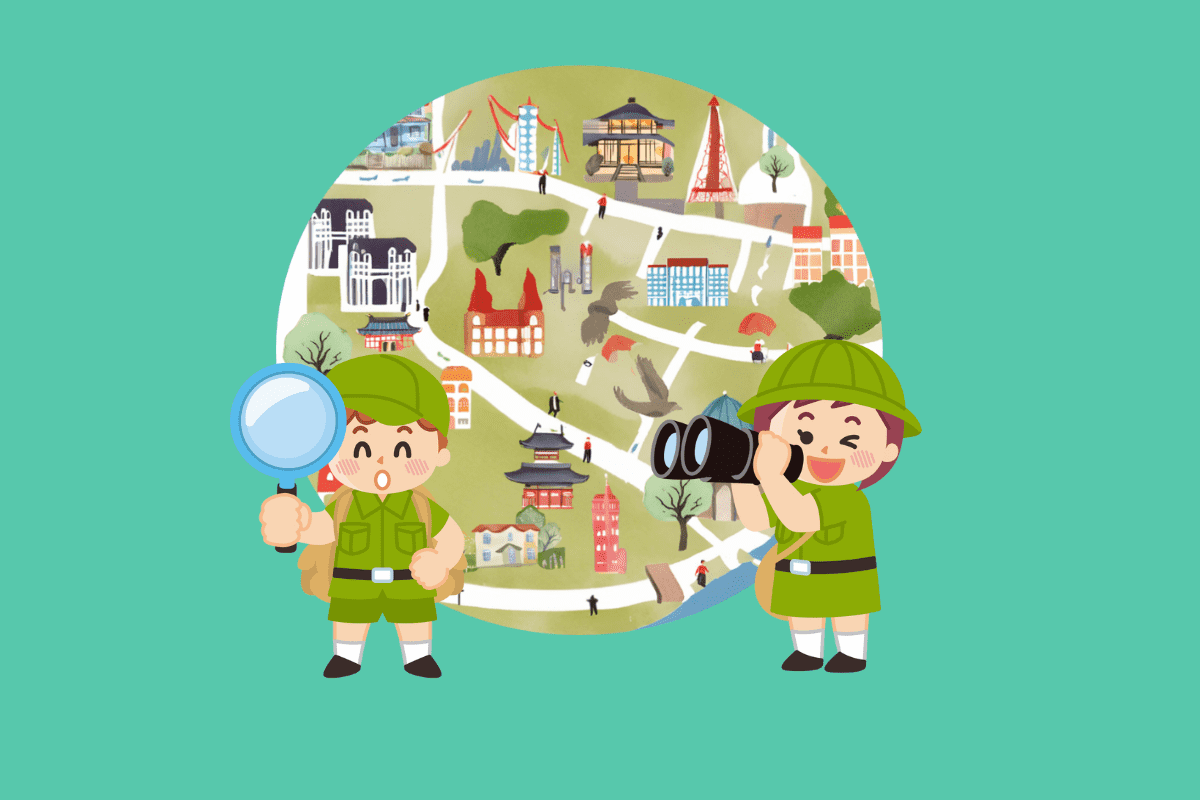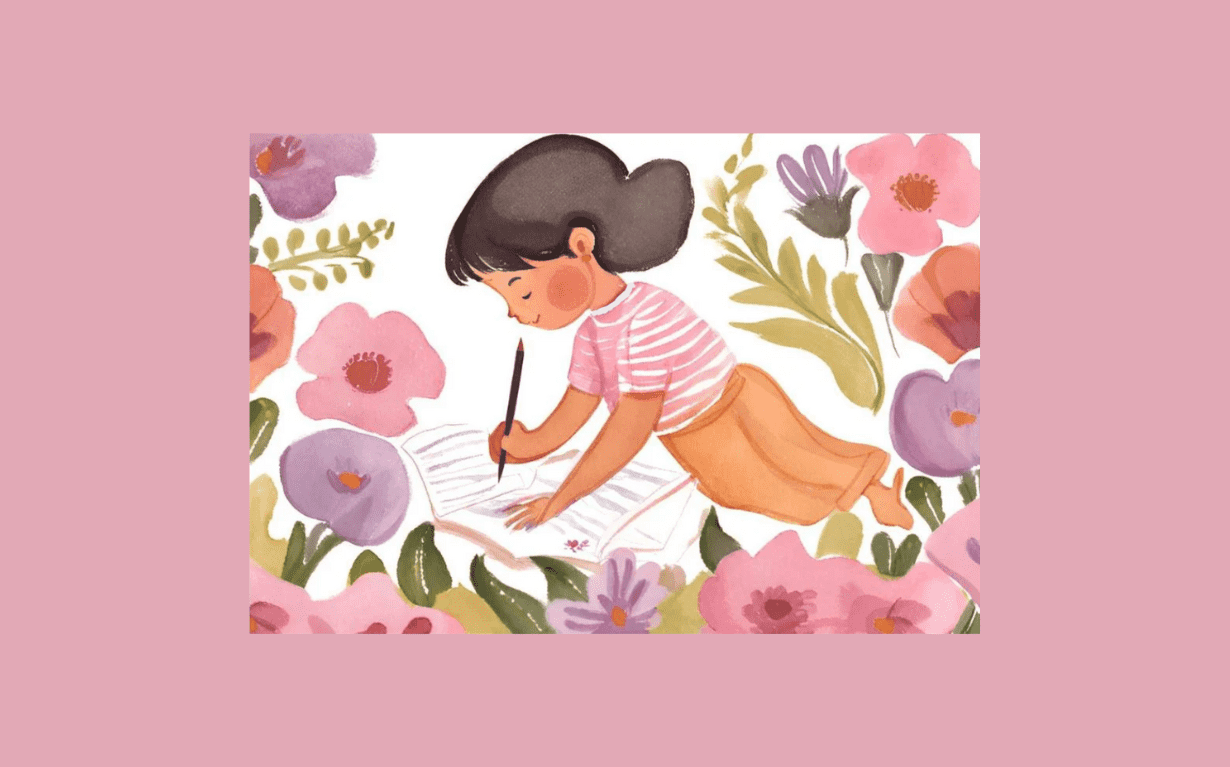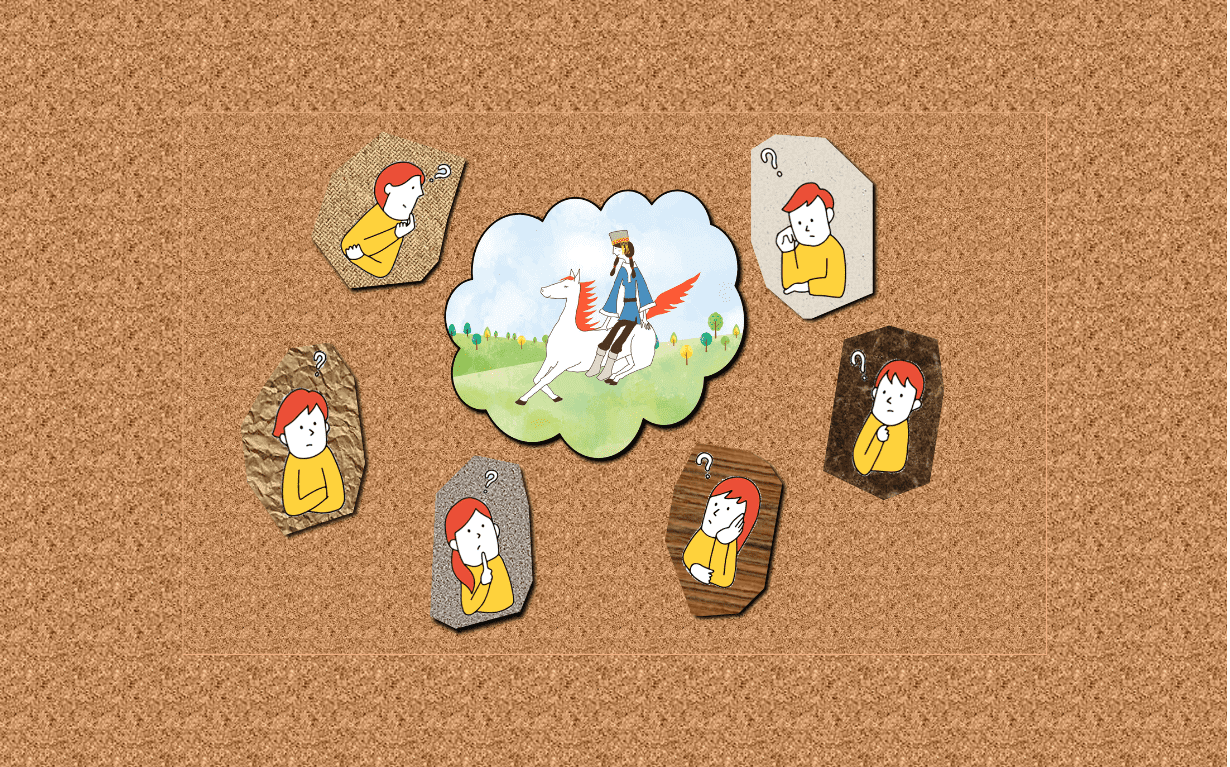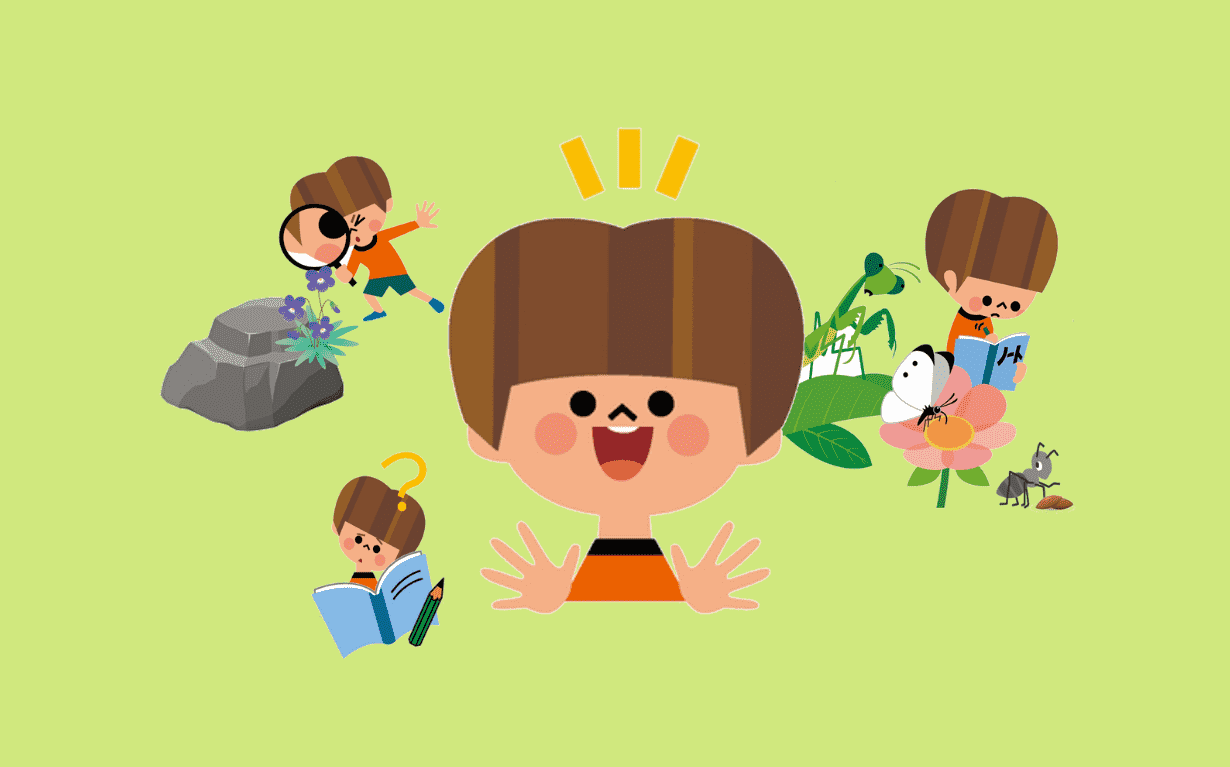子どもと創る「国語の授業」
![]() 有料記事
有料記事
「読み合い」で深めて書く紹介文
―2年・「町の『すてき』をつたえます」―
説明文には、記録文、紹介文、報告文などの種類があり、小学校の6年間で様々な文章を書く経験を積んでいきます。 では、紹介するためには、どのような表現が必要でしょうか。 紹介文を書くためには読者の反応に気づいたり想像したりすることが大切です。 子どもたちがお互いに「読み合う」活動を工夫することで、紹介文の書き方を意識できるような授業づくりを行います。
![]() 有料記事
有料記事
読後感から始まる国語科授業づくり②
-4年「ごんぎつね」-
「読後感をひとことで書く」ということで、全員分の読後感が可視化され、平等に扱われる。初発の感想のように長く書く必要もなく、文章を書くことを苦手と感じている子どもも抵抗なく取り組むことが可能となる。また、同じ教材であっても、読後感はそれぞれの子どもの実態によって変わってくるところもおもしろい。今回は、「ごんぎつね」の授業の実践を例にご紹介する。
![]() 有料記事
有料記事
リフレクション型国語科授業の展開
-問いを評価する、その授業展開-
リフレクション型国語科授業は、教師の「教え方」ではなく、子どもの「学び方」を中心とした授業展開です。「問い」をつくり、「問い」で読み合い、「問い」を評価することを1つのサイクルとして位置づけています。 前回は、物語「ごんぎつね」を例に、立てた問いでの読み合いに焦点を当てて、その授業展開を紹介しました。読み合いの授業の実際を具体的に、また、どのような単元計画となっているかを知っていただけたと思います。 今回は、「問い」を評価することに焦点を当てた授業展開の実際を紹介していきます。
![]() 有料記事
有料記事
サービス・ラーニングの国語授業
-1年説明文「つぼみ」の授業実践-
これまでの国語授業の問題点は、教室の中だけ、授業の中だけで、多くの国語のこれまでの国語授業の問題点は、教室の中だけ、授業の中だけで、多くの国語の学びが終わってしまっていることにあると考える。 これまでも第三次で本のポップを作ったり、調べたことや興味のあることを図鑑にまとめたりするなどの活動は行われてきた。 しかし、何のためにその活動をしているのかが子どもにとっては不明確なことが多く、活動に対して受動的な子がいたり、なかなか活動に参加できない子がいたりすることも少なくなかった。 そこで、地域の人のためになるようなオーセンティックな「目的」を設定し、国語で学習したことを「使う」場面(経験)を設定する、サービス・ラーニングを取り入れた授業づくりを行った。
![]() 有料記事
有料記事
子どもが「問い」をつないで読む
-「スーホの白い馬」(光村図書・2下)-
2年生の物語学習「スーホの白い馬」の実践を例に、低学年が「問い」をもち、追究する学びについて探ります。本単元の提案は、次の3点です。 ・初読後の感想の書かせ方を工夫して考えのズレに気づかせることで、単元を貫く「問い」をもつことができるようにする ・〈確かめ読み〉を終えた段階で、「問い」を再検討する ・単元を貫く「問い」を意識させ続けることで、その他の「問い」を子どもがつなぎながら読み進めることができるようにする
![]() 有料記事
有料記事
つながりで読む国語の授業づくり
―2年・「すみれとあり」―
「伏線」と聞くと、物語文を思い浮かべる方が多いでしょう。 説明文においても伏線を意識することで学びを広げていくことができます。 今回は、2年1学期において、学ぶことを楽しむ姿勢を育てていくための学習の様子を紹介します。 なお、2年生に伏線という用語は難しいので、「つながり」を考えて学習することの大切さとして伝えています。