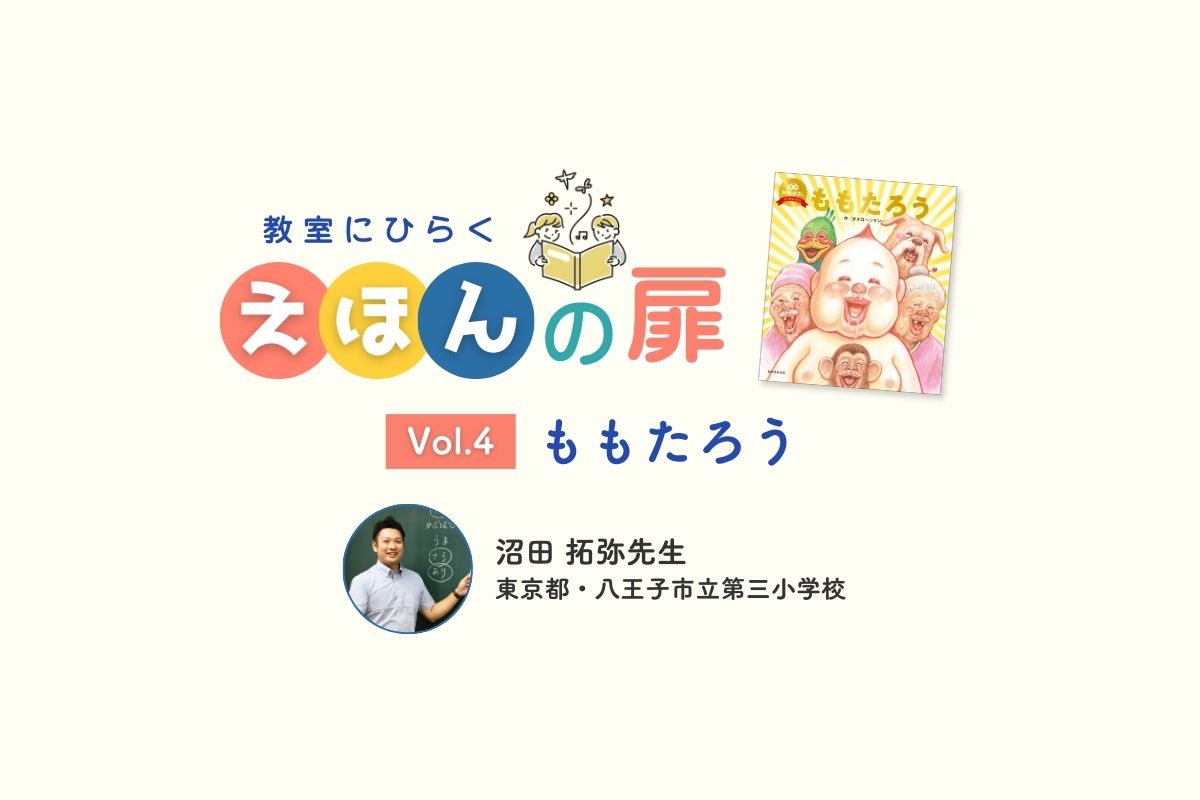
『ももたろう』 ー教室が子どもたちの笑い声で溢れるとびっきりの笑本(えほん)
|
執筆者: 沼田 拓弥
|
書名:ももたろう
作・絵:ガタロー☆マン
出版社:誠文堂新光社
出版年:2020年
ページ数:40
パロディ作品のよさは、知っているお話だからこそ安心して物語の世界に浸ることができること。同時に、知っているからこそ、その変わっている部分の面白さを感じられることでしょう。
今回は、沼田拓弥先生(東京都・八王子市立第三小学校)に疲れているときにちょっと元気をくれるお話を紹介いただきました。
「昔々、あるところに…」という、昔話お決まりのフレーズから始まります。
おじいさんとおばあさんはそれぞれ出かけて行き、おばあさんが川で大きな桃を拾ってきます。桃から生まれた男の子は「桃太郎」と名付けられ、すくすく大きく育ちました。
あるとき、悪さをくり返す鬼を退治してほしいという話があり、桃太郎はその話を引き受けます。そして、おばあさんからもらった吉備団子を腰に下げ勇んで出発します。道中、猿・雉・犬を仲間にした桃太郎は、ついに鬼ヶ島へと辿り着きます。
悪さをくり返す鬼と戦った桃太郎たち。この続きは…。(もうみなさんも知っていますよね!?)
桃から生まれた桃太郎が、猿・雉・犬を仲間にして鬼ヶ島へと鬼退治に行く有名なお話です。
幼いときに誰もが1度は聞いた(読んだ)ことがあるでしょう。
そんな昔話を、漫画家デビュー30周年を記念して漫☆画太郎が「ガタロー☆マン」として描いたパロディ作品です。
実は、本編とはちょっと違った内容で読者を楽しませてくれる部分もあります。子どもたちは読み聞かせを聞きながら「あっ!ちょっと違う!」なんてつぶやきをもらしますよ。
なによりこの絵本は、表紙に「笑本 おかしばなし」と掲げているだけあって、終始、子どもたちの笑いが止まらない作品になっています。基本的な物語の展開を知っているからこそ、聞き手の子どもたちも安心して読み聞かせの世界に入り込むことができます。
そして、何と言っても「子どもたちの笑いポイント」をわかっている作者が描く「絵」も魅力的です。爆笑間違いなしの作品になっています。
「まだ読み聞かせをやったことがなくて不安…」という方も、この作品そのものが自然と子どもたちの心に響いてくれますので安心して取り組むことができます。
また、この本はシリーズ作品として『おおきなかぶ〜』『てぶ〜くろ』も出版されています。どちらの絵本もパロディ作品として、子どもたちの笑いを引き出す「笑本」です。合わせてご覧ください。
なお、小学校中学年以降であれば、この作品をきっかけに「パロディ作品を作ってみよう」という書く活動へとつなげることもできます。
例えば、『桃太郎』であれば、鬼の視点から話を再構成してみてもおもしろいかもしれません。「実は、鬼だってこんなことを考えていた……」なんて新事実を明らかにしたパロディが作れそうです。原作へのリスペクトと作品のよさを生かしたパロディ作品づくりを子どもたちと楽しんでみましょう。
なんと言ってもこの本のおもしろさは、教室に一体感が生まれる「ページめくり」です。
ページをめくる度に、「〜ました!!!」という語尾がくり返し強調される構成になっています。
最初は、読み手である教師がおもいっきり楽しみながら読んでみましょう。
全部で15回の「〜ました!!!」が登場します。子どもたちは2、3回目にもなれば、ノリノリで一緒に声を出し始めます。そして、爆笑しながら、絵本にくぎづけです!
作者の描いた子ども心をくすぐる絵を視覚的に楽しみながら、声を出すことで聴覚的・感覚的にも楽しむことができます。
中学年以降の読み聞かせであれば、途中から子どもたちに読み手をバトンタッチすることもできるかもしれません。
子どもたちは先生の読み方をよく見て、聞いています。先生の読み方を真似しながら……。「読みたい!」「やってみたい!」と立候補する子が続出すること間違いなしです。いつもはちょっとやんちゃなあの子が、ノリノリで活躍する意外な姿が見られるかもしれません。
そして、シリーズ作品として紹介した『おおきなかぶ〜』と『てぶ〜くろ』も、基本的には文の語尾をみんなで声を揃えながら読むことができる構成になっているので、『ももたろう』を読み聞かせすれば、次の1冊へとつなげることができる部分も魅力的です。
係活動で「読み聞かせ係」があれば、係の子どもたちが休み時間に教室に友達を集めて取り組み始めます。読み聞かせの楽しさを実感してもらえる1冊ですね。
沼田 拓弥(ぬまた・たくや)
東京都・八王子市立第三小学校/指導教諭
全国国語授業研究会常任理事/東京・国語教育探究の会事務局長/「立体型板書」研究会主宰/日本授業UD学会会員(授業UD教育士)/新しい国語実践研究会幹事/全国大学国語教育学会会員/
