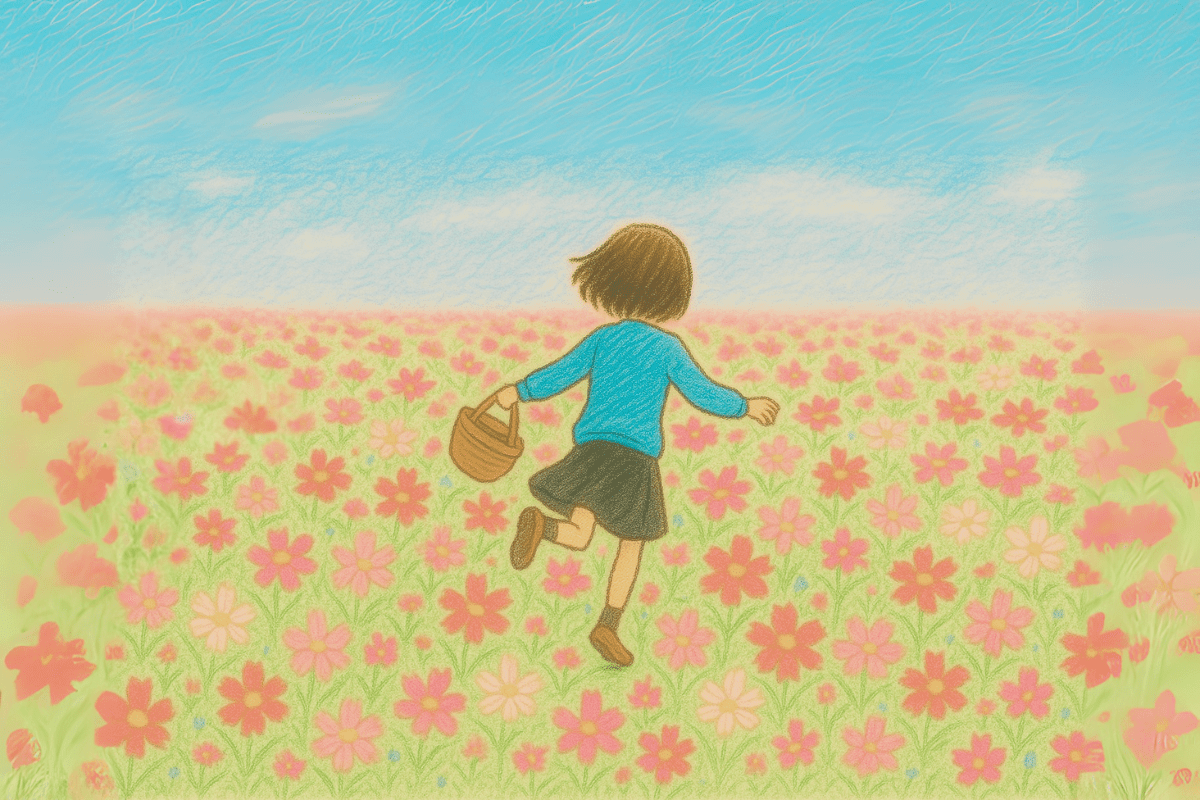
戦争文学の授業を創る -4年「一つの花」-
|
執筆者: 弥延 浩史
|
戦争文学(平和教材)と呼ばれるものがある。小学校の国語科で扱うものだと、「ちいちゃんのかげおくり」「一つの花」「たずねびと」「模型の街」「川とノリオ」などがそれにあたる。戦争文学という括りであっても、「つけたい言葉の力」に目を向けていく必要があるのは言わずもがなである。子どもが戦争文学から何を感じ取るのか、どんなテーマを受け取るのかということは、子どもの側に委ねられるべきであり、平和の大切さを押しつけるような教材にしてはならない。
教科書に掲載されている作品の中で最近見られるのが、物語の設定が戦中ではなく現代であるという作品だ。現代の子どもである綾や亮太の視点から戦争を描いているのが「たずねびと(光村図書・五年)」であり、「模型の街(東京書籍・六年)」である。 また、「ちいちゃんのかげおくり」「一つの花」「川とノリオ」のように、戦中を描いた作品は長く掲載されている。
今回は、この中の「一つの花」を中心に実践を紹介し、その後どのような活動を系統的におこなっていくのかということを述べていく。
まず、教材分析の段階で、(教材)特性として以下の点を考えた。
あえて「戦争の時代の生活について書かれている」としたのは、現代を生きる子どもたちにとって、戦中のことはあまり身近とは言えないからである。子どもたちの祖父母の世代も多くが戦後生まれである。だからこそ、「一つの花」のように直接戦争を描いた作品だと、現代を生きる子どもたちが時代設定などについて理解しにくいケースがあったり、教える側が、この時代の悲劇などを感傷的に取り扱うことに終始してしまったりするケースがある。つまり、戦争文学を扱う難しさは、他ジャンルの文学作品以上にあると考える。
次に、「一つの花」は「三人称客観視点」で書かれている物語であるという点が特性である。文学作品の多くは「三人称限定視点」であることが多く、「特定の視点人物に語り手が寄り添う形」をとってストーリーが展開していく。「視点人物=中心人物」であるため、中心人物の心情が語り手を通して語られる。「三人称全知視点」のように、視点人物がさまざまな登場人物になる作品も中にはあるが、これも限定視点での読み方を知っている子どもたちには、それほど難しくはない。しかし、「三人称客観視点」は、人物の心情をはっきりとは語らない。例えば、「~と思いました」というような、心情を直接表す表現は「一つの花」の作中では見当たらない。
さらに、言葉のくり返しがあることも「一つの花」の教材特性の1つであろう。本作では、「一つだけ」という言葉のくり返しが重要になる。戦中と戦後という大きな時間の経過があるとともに、戦中に数多くくり返されてきた「一つだけ」という言葉が、戦後では出てこない。題名が「一つの花」であるように、「一つ」や「一つだけ」という言葉は作品を読んでいく際に大切にしていき、子どもたちにも着目させていきたいところである。
それでは、実際にどのような授業を展開することができるのかを、ここから述べていくこととする。
