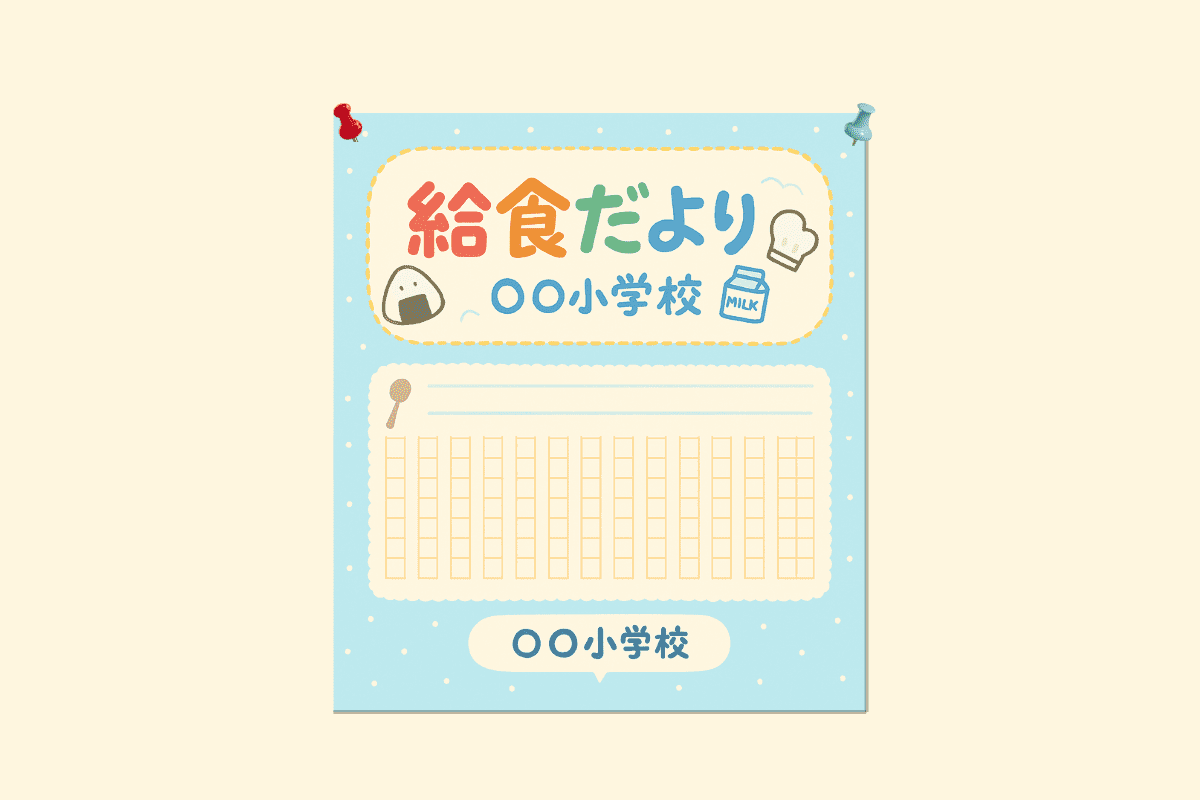
「給食だより」を読みくらべよう ―大森先生へ手紙を書こう―
|
執筆者: 流田 賢一
|
単元名:大森先生へ手紙を書こう
教材:「『給食だより』を読みくらべよう」(東京書籍・3年)
本教材では2つの給食だよりが挙げられ、両方ともに、「しっかりと野菜を食べてほしい」ことを伝えることが目的でありながら、それぞれ異なる理由の内容から記述されています。同じ点と違う点を比較しながら、筆者の工夫や読者への伝わりやすさを考えることで、説明文の目的と構成について理解を深めることができるでしょう。
今回は、流田賢一先生(大阪府・大阪市立堀川小学校)に、給食だよりの作者である大森先生へ、「どちらの給食だよりがよいと思ったのか」について手紙を書くという課題を設けた授業づくりをご提案いただきました。この課題を通して、2つの文章を比較し、よいと思った根拠をしっかりともち、自分の考えを表現する力を育めます。
目次
伝えたいことが同じである2つの給食だよりを読み、同じところと違うところを見つけることにより、筆者の工夫を読み取ることをゴールとする。そのために、言語活動を「どちらの給食だよりがおすすめか」とすることで、おすすめの給食だよりとしてどちらか1つを選択し、その理由を書くこととした。
この給食だよりを読む対象は、学習者である3年生と同じ小学生である。自分たちが、いいなと思った給食だよりはどちらなのかを考えることで、筆者が読者である小学生に伝わるために工夫していることに気づき、理由を記述できることをめざしている。学習の評価としては、どちらの給食だよりを選択していてもいいが、どのようなことを理由として記述しているのかを評価対象とする。
以上のような設問は、毎年のように全国学力・学習状況調査で出題されている。全国的に正答率が低くなっているため、多くの実践例や授業事例が紹介されている。この設問には、「選択をすること」「選択をした理由や自分の考えを書くこと」「2段落構成で書くこと」と複数の力が必要になる。特に、自分の考えを記述することが苦手な子どもが多くいることがわかっている。選択した理由や考えを書けるようにしていきたい。
また、2段落構成で書くことについても、1マス空けて記入するきまりが身についていない場合もあるため、日頃の学習からくり返し取り組んでいきたい。
そのため、この設問と同じように本単元でも、「選択した給食だよりは何か」「その理由は何か」を「2段落構成で書くこと」とした。
