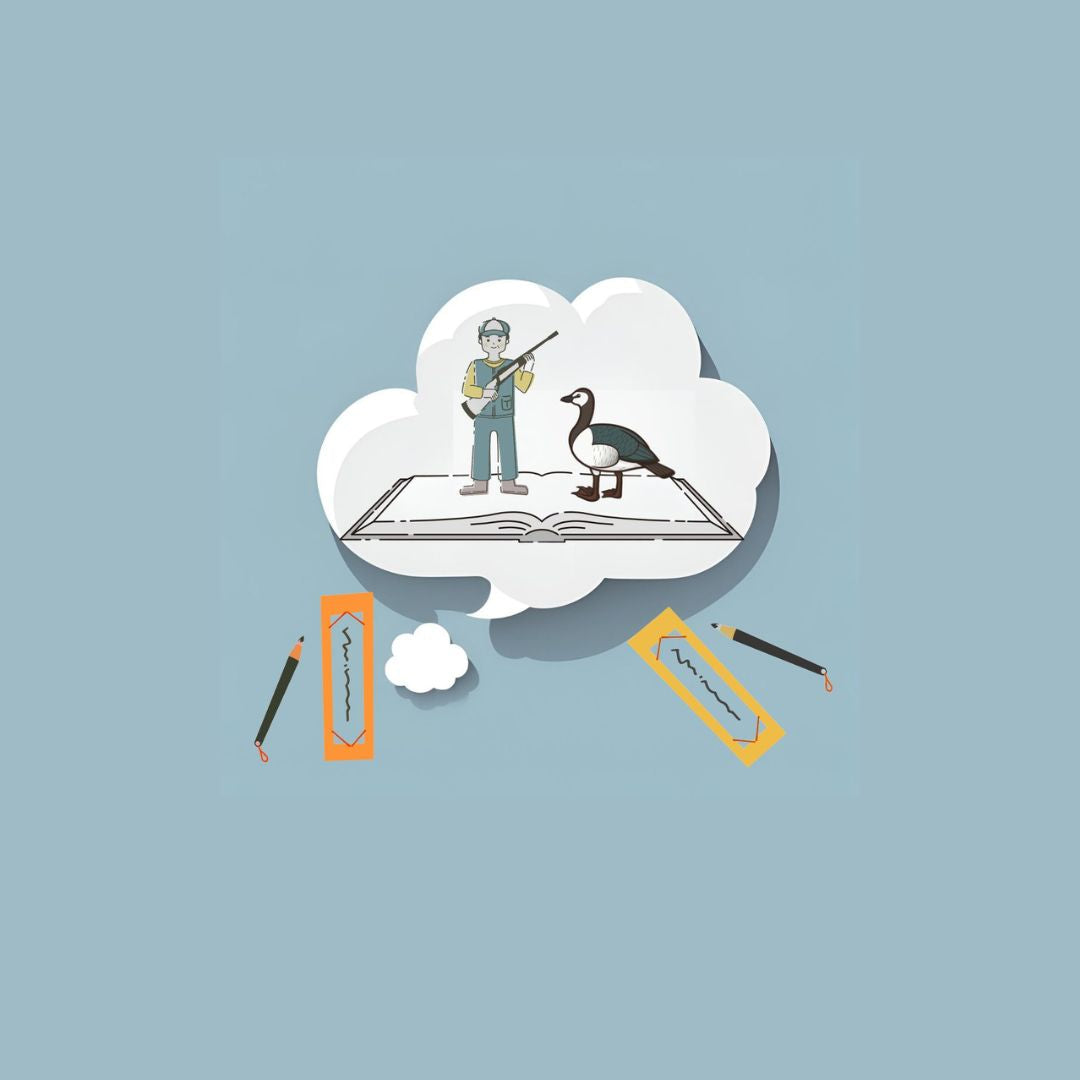
5分でわかる 短歌づくりで主体的な物語文の読みを -「大造じいさんとガン」で中心人物の心情を読む-
|
執筆者: 根本俊彦
|
今回の5分でわかるシリーズは、根本俊彦先生(私立清泉小学校)に、物語文の中心人物になりきり、心情を短歌で表現する言語活動を通して、叙述一つひとつのへの意識が高まり、楽しみながら主体的に読めるようになる工夫をご紹介いただきました。
「子どもたちが教科書の叙述一つひとつに注目し、立ち止まって考え、気付いたらどっぷりと物語の世界に浸かっている」。
これは、物語文の授業をするときの私の願いです。しかし、登場人物の心情の変化を何となく捉えた気になって終わってしまったり、あとになって、子どもが叙述に基づかない解釈をしていたことが分かったりするような経験をすることが何度もありました。
そこで、文章を場面分けし、起こった出来事や心情の変化を子どもとの対話を通して捉えていくといった授業の流れではなく、もっと子どもたちが主体的に物語の世界に入り込み、教科書の叙述一つひとつの言葉に立ち止まって作品を読み進めていくような授業ができないかを考え実践しました。
「大造じいさんとガン」の単元で、大造じいさんの気持ちを短歌で表現する言語活動を通して、「大造じいさんとガン」を読み深めることができた例をご紹介します。
「大造じいさんとガン」は、ガンの頭領である残雪への見方の変化が描かれた物語です。
はじめは、残雪のことを「たかが鳥」としか見ていなかった大造じいさんが、数度の戦いを経て「英雄」、「えらぶつ」として見ることになります。
この大造じいさんの残雪に対する大きな見方の変容を、叙述を根拠にきちんと捉える。その変容を捉えるために、「大造じいさんになりきって自分ごととして考える」というねらいをたてました。
この2つの授業者の願いを達成するために、大造じいさんが歌人だったとして、残雪との戦いが終わる度に、戦った1年を振り返って短歌を作っていたとしたら、どのような短歌を作ったかを大造じいさんになりきって考える活動を行いました。
なぜ、短歌を文学作品の読みに活用したのかというと、この実践を行った学級は、短歌や俳句への関心が高い学級だったからです。俳句や短歌を扱う時間は毎回大きな盛り上がりを見せており、夏休みの思い出や今月の目標などを、よく俳句や短歌で表していました。
また、俳句と異なり短歌は七・七音長く、その長さゆえに情景だけでなく、より具体的に心情も詠むことができます。大造じいさんの心情面での大きな変容が描かれるこの作品において、以上の理由から、短歌づくりの言語活動を通して、より主体的に物語を読み進めていくことができるのではと考えました。
単元計画は以下のとおりです。
大造じいさんと残雪との戦いは、3年間の戦いです。1年ごとに読み深めた後に短歌づくりを行いました。短歌づくりのルールは、大造じいさんがもし歌人だったらと仮定し、
この3つをルールとしました。以下、子どもたちがつくった短歌を抜粋してご紹介します。
大造さんの残雪への感嘆する気持ちなど、まだ大造じいさんの残雪を甘く見ている余裕が感じられるような短歌ができあがりました。作った短歌は、友達同士で見せ合い、どの短歌がよいと思ったのか投票も行いました。そして、どんな所がよいのかを共有しながら、この場面での外せない言葉などを確認していきました。
子どもたちが短歌づくりをするときの様子を見ていると、各場面の最も象徴的なシーンの言葉を使って、短歌を作ろうとしていることが分かりました。
そこで、物語の2年目の短歌から、子どもが叙述に基づいて使ったキーワードごとに、短歌を種類分けしてみました(下記表参照)。
物語の2年目の場面では、「タニシ」「ううんとうなる」という言葉を用いて、短歌を作る子どもが多いことが分かりました。
このことから、この2年目の場面では、「タニシ」を用いた作戦を行ったが失敗に終わってしまった、というところに注目して場面を捉えて読んでいるという、短歌づくりをとおした子どもの読みの実態も見えてきました。
ここでも物語の2年目の短歌と同様に、使われたキーワードごとに、短歌の種類分けを行いました。
言葉の種類ごとに分けると、上記の図のようになりました。短歌に使われた言葉を見てみると、残雪が仲間を守るために戦う場面で短歌を作った子どもが、31人の学級のうち14人でした。
ハヤブサとの戦いを終えて、瀕死状態の残雪の場面で短歌を作った子どもが10人いました。この3年目の場面では、子どもたちは、残雪が仲間を守るためにハヤブサと戦う所を山場と捉えて読んでいることが分かりました(下記図参照)。
物語の1年目~3年目までの短歌を並べました。1年目の短歌では、大造じいさんの残雪への余裕が感じられますが、2年目の短歌ではその余裕が無くなってきて、3年目ではそんな残雪に心打たれる大造じいさんの心情の変化を、短歌を通して表現することができました。
今回の単元では、各年の戦いを読み深める → 短歌づくり → 友達の作品を見て投票 → 感想を共有という流れで行いました。 成果として、
①場面から心情を表現する短歌の変化
短歌づくりにおいて、はじめはただ場面を表す短歌を作る子どもが多かったのですが、友達の短歌を見合ったり、どんな短歌がよいと思ったのか話し合ったりする活動の中で、うまく大造じいさんの気持ちを短歌で表現することができるようになりました。
②五七五七七に言葉を入れることでの本文の言葉を探す意識の高まり
冒頭にも記述したように、31文字の中で気持ちを表現するため、より言葉に敏感になります。どの言葉を用いて、短歌を作るのか、どの言葉がその場面の大造じいさんの気持ちを表現するのに相応しいかを考える中で、子どもたちの本文の言葉に注目する意識が高まりました。
③各場面の情景描写で表される心情についての理解の深まり
「大造じいさんとガン」の作品では、情景描写がふんだんに使われています。情景描写が大造じいさんのどのような気持ちを表しているのか、より深く捉えようとする子どもが増え、短歌の中にも積極的に用いようと努めていました。
④友達の作品を読むことで、各場面のキーワードの認識
作った短歌を友達と見合う活動のなかで、各場面の大事なキーワードを確認することができました。友達同士で大事だと思うキーワードにずれがあると、そこから自分の考えを伝え合う話し合いにも発展していきました。
特に3年目の場面では、残雪がハヤブサから仲間を守ろうと奮闘する場面と、瀕死状態の残雪に心打たれる場面とで、どちらがこの3年目の場面の山場と捉えるのか、短歌づくりをきっかけに話し合いが白熱しました。
⑤子どもたちの読みの実態の把握
作った短歌を見ることで、その場面のどこに注目しているのか、どのように読んでいるのかという、子どもの読みの実態を把握することができ、その後の授業の展開で生かすことができました。今回の実践により、短歌づくりを通して叙述に立ち返る意識の高まりや、本文の表現一つひとつを大切にしようとする子どもたちの姿を見ることができました。
根本俊彦(ねもと・としひこ)
私立清泉小学校
所属研究会:創造国語
