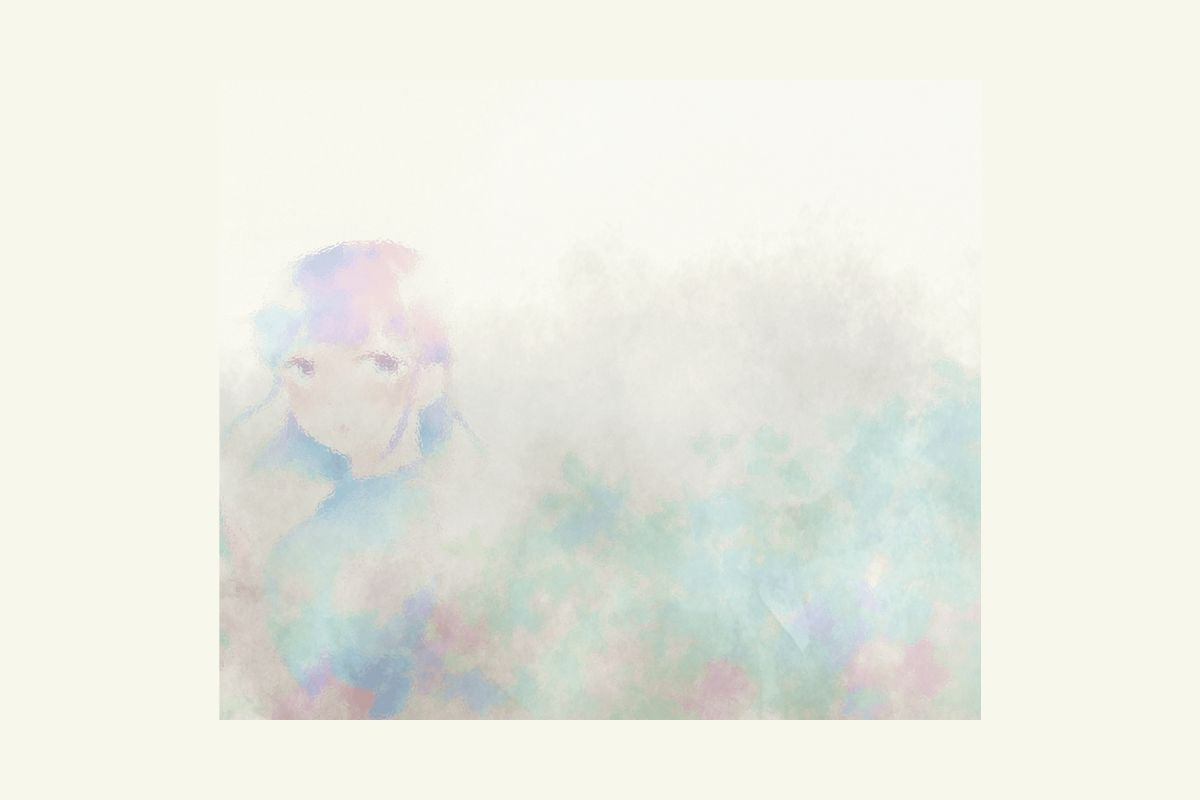
「自分事の学び」を創る文学の授業 -子どもが「問い」をつくり、「問い」で読み合い、「問い」を評価する-
|
執筆者: 小泉 芳男
|
単元名:作品のメッセージを探ろう
教材:「たずねびと」(光村図書・5年)
教材「たずねびと」(光村図書・5年)は、「原爆供養塔納骨名簿」に自分と同姓同名の名前を見つけたことから、「楠木アヤ」について気になった主人公の綾が、彼女について尋ねるうちに、普通に暮らす多くの人が亡くなった原爆の悲惨さや、それを忘れないでいることの大切さに気付いていく物語文です。
今回は小泉芳男先生(広島県・広島市立袋町小学校)に、「問いをつくり、決定し、問いで読み合い、問いを評価することで、あらためて問いを考える」といった、一連の探究のサイクルを繰り返すことで、「自分事の学び」を創ることのできる授業について提案していただきました。
目次
子どもが「自分事」として学ぶ姿は、授業者の理想である。
しかし、その実現は簡単ではない。
図1は、稿者が学びの場での「自分事の学び」の範囲を図化したものである。
教室内では図1のように、様々な立ち位置の子どもたちが存在する(それぞれの具体は表1を参照)。これらの子どもたちの「
そのカギとなるのは、「問い」である。「問い」があるから、学びが駆動する。
本稿では、可能な限り具体的な授業場面を示し、子ども自身が「問い」をつくり、「問い」で読み合い、「問い」を評価するという「国語学習サイクル」(香月2023)による授業展開を提案する。
