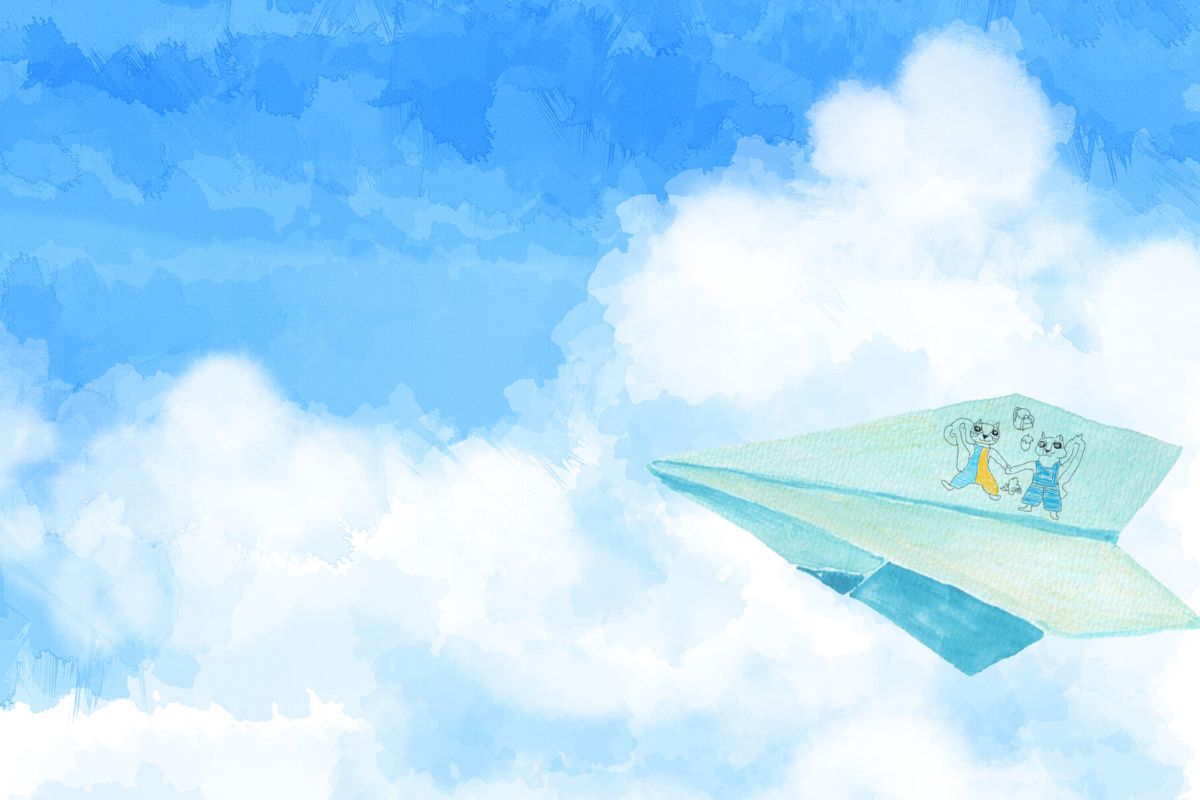
「紙ひこうき、きみへ」 -「人物像」を捉えて表現しよう!-
|
執筆者: 沼田 拓弥
|
本年度より登場した「紙ひこうき、きみへ」(教育出版 3年)は、しまりすキリリの、風のようにふわりと現れ、居なくなってしまったみけりすミークとの友情と揺れ動く気持ちが描かれ、読み手もどこか遠くにいる友人に思いを馳せたくなる物語文教材です。
今回は沼田拓弥先生(東京都・八王子市立第三小学校主任教諭)に、プロフィールカードをまとめる言語活動を通して、物語文学習において重要となる人物像を読み取る力が、子どもたちにしっかりと身に付く、単元づくりをご提案いただきました。
目次
この物語は、中心人物であるしまりすのキリリと、旅をすることが好きなみけりすのミークの出会いを通した心温まる話である。
2人の出会いのきっかけは、ミークが飛ばした青い紙ひこうき。
物語冒頭に登場するこの紙ひこうきは2人の心をつなぐ重要なアイテムとして、物語終盤にも再び登場する。
物語中盤は、心配性なキリリに対して、さっぱりとした性格であるミークが対照的に描かれ、2人の会話を中心に展開される。キリリの不安な気持ちがどのように変化していくのか、読者としても気になりながら、読み進めることのできる作品だ。
物語終盤には、旅行かばんの中から色とりどりの蝶が飛び出す様子が描かれており、読者の頭の中には爽やかな景色が広がることだろう。ミークが残したキリリへの「また会おう、きっとだよ。」という締めくくりのメッセージによって、教科書には描かれていない今後の2人の関係性が気になる物語でもある。
教科書の「学習の手引き」には、登場人物の人物像や中心人物・キリリの心情の変化を扱う授業展開が提示されている。子どもたちと作品の出合いの際、もしくは単元終盤には、絵本の読み聞かせを行ってもよいだろう。多くの挿絵によって、言葉だけでなく、より細かな様子まで具体的にイメージをすることができる。
実は、絵本の中には、教科書には掲載されていない表現や続きの話があり、キリリとミークのその後を知ることができる。授業に入る前には、ぜひ、一度絵本を手に取ってご覧いただきたい。
登場人物の人物像は、「会話文」や「特徴的な行動」「見た目」「物事の考え方」「好きな〇〇」等から読み取ることができる。この物語は、キリリとミークを比較しながら2人の特徴の描かれ方を読み取ることで、今後の物語作品を読むときに活用できる「人物像を捉える読みの視点」を獲得することができる。
今月の「教師の必読書」をご紹介いただくのは、赤木詞友先生(福岡県・北九州市立鴨生田小学校)です。子どもの学び方自体が問い直されている今、授業観、教師観自体も大きく変わろうとしています。これからの教育についてリードする著者の、バイブルともいえる1冊を紹介いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
今回は沼田拓弥先生(東京都・八王子市立第三小学校)に、名言カードの作成という表現活動に向けて、岩谷さんにインタビューをするという想定で本文を読み深めることで、おのずと要点をしぼって文をまとめる意識が育まれるという、ユニークな授業づくりのアイデアについてご提案いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
提案:日常生活で発揮できる学びを 南山大学附属小学校 山本真司
2025年全国国語授業研究大会 2年 紙コップ花火の作り方/おもちゃの作り方をせつめいしよう
![]() 有料記事
有料記事
提案:文学的文章を交流しながら俯瞰的に読める単元づくり 宮崎県・都城市立有水小学校 比江嶋 哲
2025年全国国語授業研究大会 3年 ちいちゃんのかげおくり
