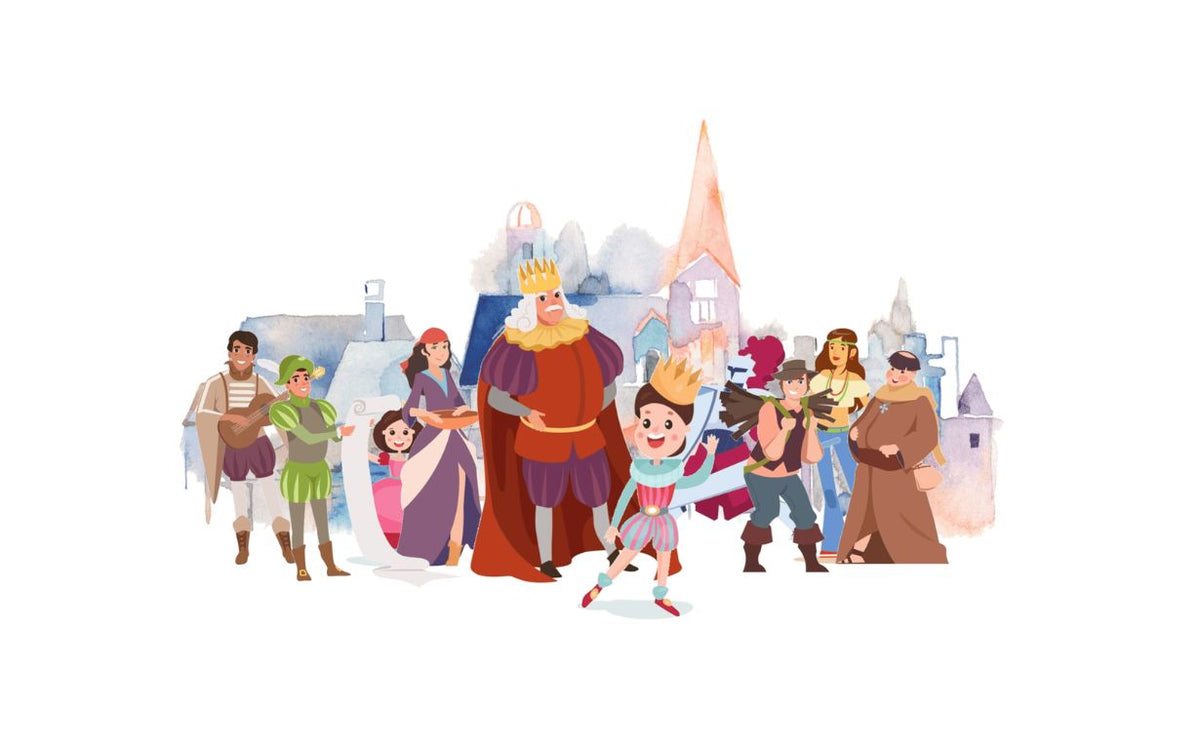
「世界でいちばんやかましい音」 -物語文を読む、本来のおもしろさを活かそう-
|
執筆者: 井上 幸信
|
単元名:物語の組み立てについて考えよう
教材:「世界でいちばんやかましい音」(東京書籍 5年)
今回は井上幸信先生(新潟県・五泉市立橋田小学校教諭)に、「世界でいちばんやかましい音」(東京書籍 5年)について、物語文を読むということの、本来のおもしろさをそのままに活かす授業づくりの工夫を提案していただきました。
物語の「おもしろさ」を感じる理由=物語の組み立て、場面のつながりが巧みであるということを示し、子どもたちが、物語の組み立てに意識が向くようにする単元冒頭のしかけや、それぞれの場面の必要性を確かめられるようにする授業展開にご注目ください。
目次
今回とり上げる、物語文「世界でいちばんやかましい音」と出合ったときのことを、私ははっきり覚えている。
世界中に広がっていく「世界中の人が、一人残らず、同時にどなる」計画。
物語の展開に合わせて、読み手である私の心中でも「興奮は、どんどん高まって」いった。
そして、ある日小さな町で1人のおくさんが言い出した「世界でいちばんやかましい音というのを、ちょっと聞いてみたい気がする」という素朴な願い。その言葉に共感しつつも、「一体どうなってしまうのだろう?」というドキドキ、ハラハラとした気持ちになった。
もちろん、山場を越えたあとの納得感や、すっきりとした読後感も印象に残っている。基本的な物語の組み立てを巧みに活用して創作された、素晴らしい児童文学だと思った。
「世界でいちばんやかましい音」に限らず、児童向けの物語作品は、本来子どもたちが「読むことを楽しむ」ことを目的に書かれたものである。それを学習材として授業で扱うのは、あくまでも大人の都合でしかない。
前述の通り、この作品は物語の基本構造を巧みに活かして書かれており、特に「山場」に至るまでの展開や、「山場」を越えたあとの変化は、物語の読み方を学習する素材としては最適である。優れた作品であるが故に授業者の学習デザインにも力が入るが、優れた作品であるからこそいたずらに学習過程を複雑にすることなく、シンプルに作品のもつおもしろさを読み、考える単元を目指したい。
そのためには、まず授業者が作品を読むことを楽しみ、読む中で感じ取ったおもしろさや巧みさを明確化することが必要と考える。例えば、私ならば以下の点をピックアップしたいと思う。
ここで挙げた要素は、授業で物語文を読む際にはきちんと押さえておきたい、「時・場・人」などの設定や、基本的な物語の構造にそったものである。「世界でいちばんやかましい音」の作品としてのおもしろさは、これらの組み合わせが織りなすシンプルな仕組みから生まれている。
本稿では、この「おもしろさ」が生まれる理由を読み解く活動を通して、物語の組み立てについて学ぶ学習デザインを提案する。
「世界でいちばんやかましい音」の物語文としての特性は上述の通りである。そして、この特性はそのまま学習材としての価値でもある。
教科書では「物語の組み立てについて考えよう」という単元名で、ここで育みたい言葉の力は「物語の全体像をとらえる」ことと設定されている。物語全体における各場面の役割、物語の始まりと終わりでの変化と、人物の心情や関係、状況の変化などを関係付けてとらえることを通して、物語文の全体像を読む力を子どもたちに培うことを目指す単元となっている。
「世界でいちばんやかましい音」はこれらの要素が非常に分かりやすく描かれた作品である。
◎物語の全体像を捉え、物語の中で大きく変化したことについて、考えたことを話し合うことができる。
〔知識及び技能〕
〔思考力、判断力、表現力等〕
〔学び向かう力、人間性等〕
| 第一次 | 作品と出合い、作品の冒頭と終末との変化を読む(第1時) |
| |
| 第二次 | 展開と山場の組み立ての効果を読む(第2・3・4時) |
| |
| 第三次 | 作品全体の場面の組み立てが生み出すおもしろさを読む(第5時) |
|
単元の導入で、しっかりと組み立てに目を向けることができるよう促したい。
そこで、作品の冒頭に登場する、町の入り口の立て札の文言「これよりガヤガヤの都 世界でいちばんやかましい町」と、作品終末に登場する立て札の文言「ようこそ、ガヤガヤの都へ 世界でいちばん静かな町」とを提示し、「ガヤガヤの都はどのように変わったのだろう?」「どんなことが起これば、このような大きな変化が起きるのだろう?」と問う。
子どもたちは【世界でいちばんやかましい → 世界でいちばん静か】という明かな変化を捉えた上で、
「立て札に『ようこそ』と、歓迎する言葉が付いた。都の人々が優しくなったのではないか」
「静かにすることがいいことだと感じるような出来事が起こるだろう」
「やかましいことが大きなトラブルになるのではないだろうか。トラブルを避けるために静かになるのかもしれない」
など、立て札の記述内容からさまざまな予想をするであろう。
このような予想をした上で作品全体と出合うことで、変化が生まれる理由に着目しながら初読に取り組むことができる。
物語の展開部分の出来事と、その出来事を読んだときの感想を押さえていく。
感想は第1時で作品を通読する際にメモしておくとよい。初読を教師による読み聞かせとし、子どもたちにその時々の感想をつぶやくなどの、表現しながら聴くように促すことで、学級のおおまかな感想を引き出しておく方法も有効である。
ここでは、概ね、各場面に対して子どもたちから、次のような感想が出てくると予想される。
ここでは、学習者の素朴な感想を大事にしたい。
上記の感想の例は5年生のものとしてはやや幼く見えるかもしれないが、これはあくまでも感想であり、批評ではない。その感想が、どの出来事や言葉から生まれたのかを確認しながら、読者としての心の動きをみんなと共有する。
前時までにまとめた各場面の感想を確認したあと、「もしこの場面がなかったら、この作品のおもしろさやよさはどう変化するか」を考える。
もちろん、「世界でいちばんやか ましい音」はそれぞれの場面、それぞれの出来事が巧みに組み合わされた作品なので、どの場面がなかったとしてもそのよさやおもしろさは損なわれてしまう。当たり前のことではあるが、そのことを再確認することこそが、実感を伴って「物語の組み立て」「場面の役割」を理解することにつながる。
「この場面のハラハラがあるから、山場での『よかった〜!』という気持ちが生まれる」
「最初に世界でいちばんやかましい音の計画が大規模に世界中に伝えられる様子が書いてあるから、『ちょっと聞いてみたい』がこっそり、少しずつ広まっていく様子にドキドキする」
など、「この場面、この出来事があるから『世界でいちばんやかましい音』という物語のおもしろさが生まれている」ということに気づくことができるように単元を締め括りたい。
「物語を読む」とは、そもそもどういう営みなのだろうか?
そんな自分の中の問いと向き合う中で生まれたのが本単元である。
授業の中で物語を読むこという行為は、生活の中で読書することとは異なる価値をもつ。
「物語の組み立て」や「場面の役割」を考えることは、思考の材料としてのストーリー(論理)構成について知り、思考する経験を積むことができるという点で、大きな価値がある。しかし、学習価値のみを追求し、物語を読むという営みが本来もっているおもしろさから離れるような授業になってしまうのも、何か違うような気がしてならない。
本稿では、物語がもつおもしろさや素晴らしさを存分に活用した単元・授業を考えることの提案を試みた。
これをお読みいただいたみなさんにも、「(授業で)物語を読む」ことの意味を再考していただければ幸いである。
井上幸信(いのうえ・ゆきのぶ)
新潟県・五泉市立橋田小学校教諭
全国国語授業研究会理事/明日の国語授業を語る会事務局/新潟音読研究会幹事/新潟デジタル・シティズンシップ教育研究会代表
