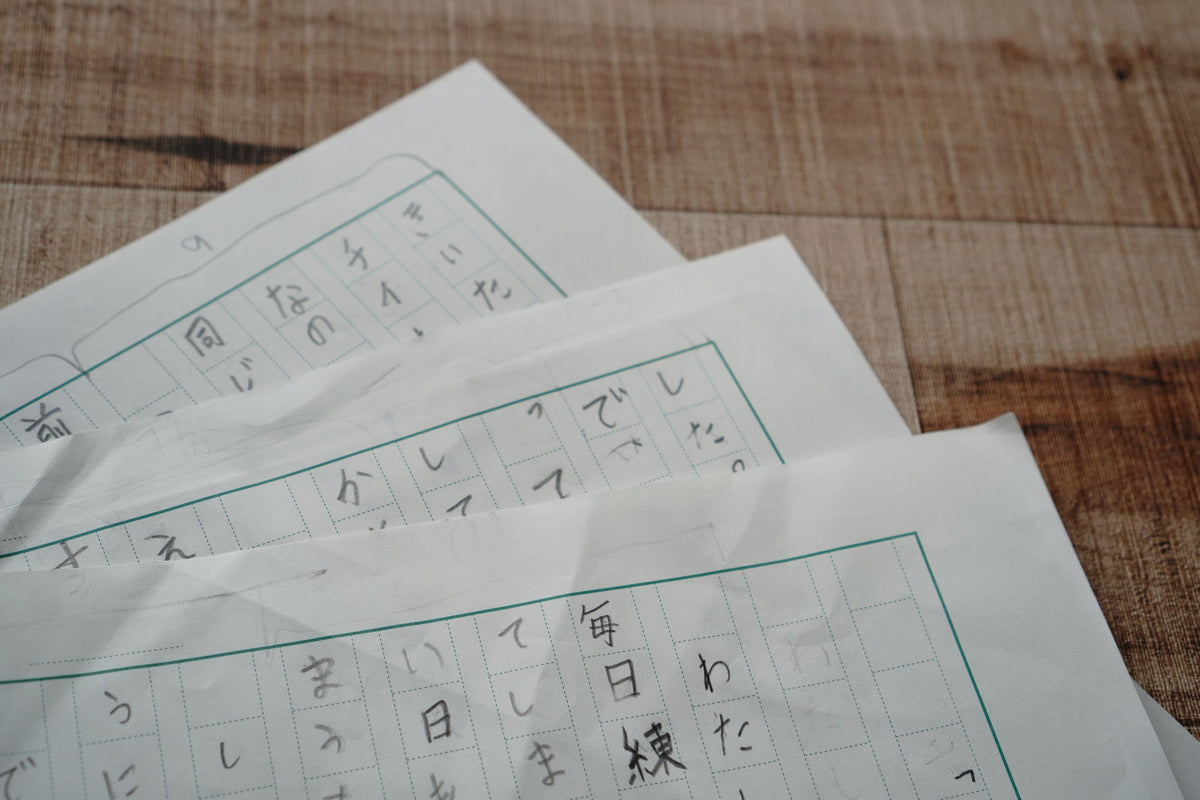
新教材「文様」の教材研究と授業づくり
|
執筆者: 髙橋 達哉
|
今回は髙橋達哉先生(東京都・東京学芸大学附属世田谷小学校)に、新教材「文様」(光村図書・3年上)について、続く教材「こまを楽しむ」を踏まえた上で分析し、授業づくりのポイントとその具体例を紹介していただきました。
3年生はじめ、説明文に親しむための【れんしゅう】として、本教材にはどのような特性があるのでしょうか。
また、どのようにすれば主体的に読みを深められるのか、「ゆさぶり発問」のアイデアにもご注目ください。
目次
本教材は、「こまを楽しむ」の練習教材という位置付けである。そのため、題材が異なるだけで、基本的な文章の構造や説明の仕方は、「こまを楽しむ」と共通している。どちらも、複数の事例が紹介される事例列挙型と呼ばれる説明文である。
「こまを楽しむ」の学習に活かすことを考慮し、さらには2学期教材である「すがたをかえる大豆」へとつながることを見据えて、特にポイントとなる本教材の特性や、その特性から見出せる指導内容(教科内容)を以下に挙げたい。
第2学年までの学習においても、形式段落番号を振るなどして学習している用語であるが、ここで改めて段落の意味や役割、段落の分け方を確認するようにしたい。
具体的には、教科書P.64「たいせつ」にも示されているように、「一つ一つの段落には、それぞれ、ひとまとまりのないようが書かれている」ということ、説明する内容が少し変わる場合には、段落を分けて説明することで、読み手にとって分かりやすい文章となることについて理解を促したい。
