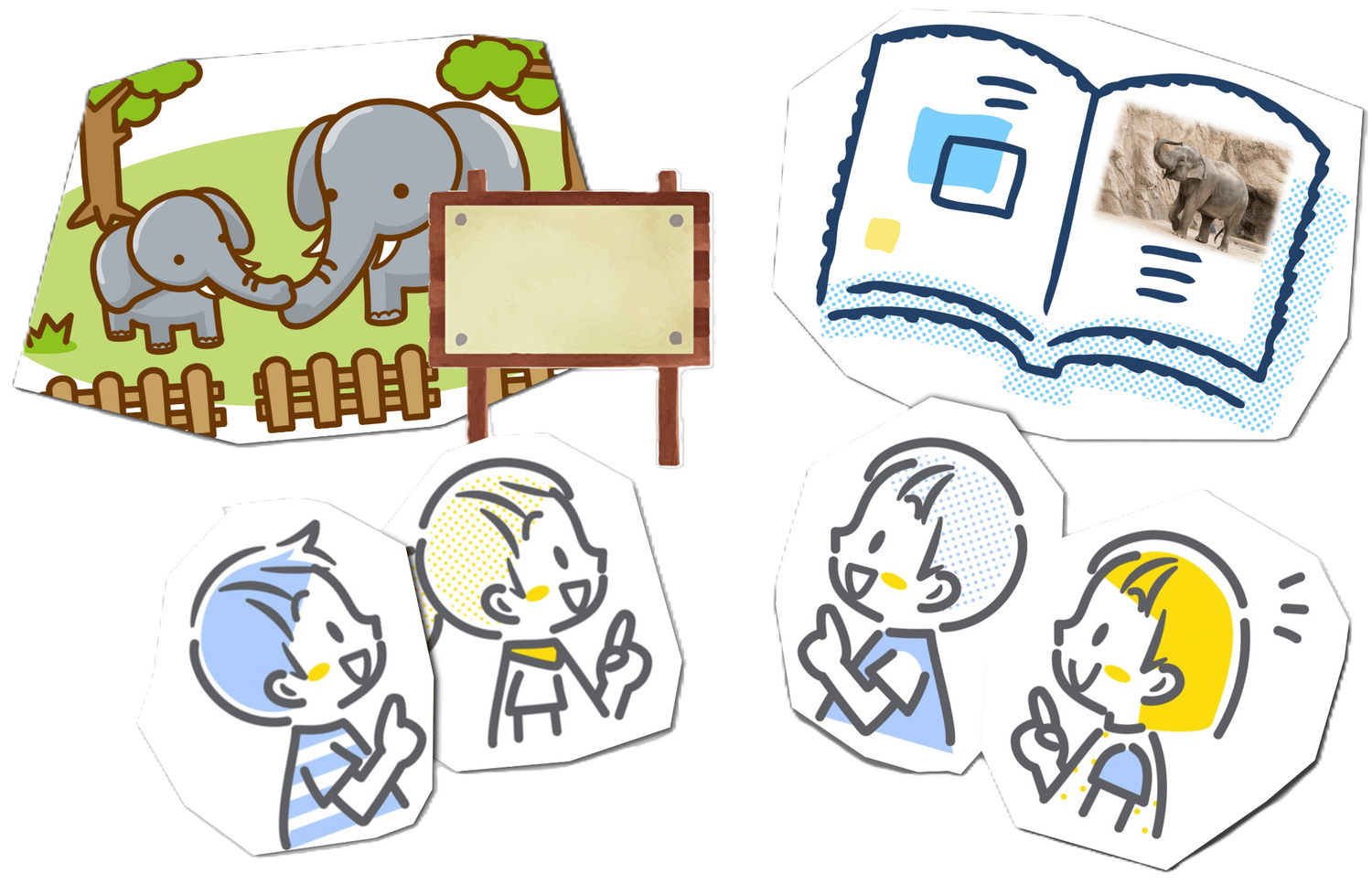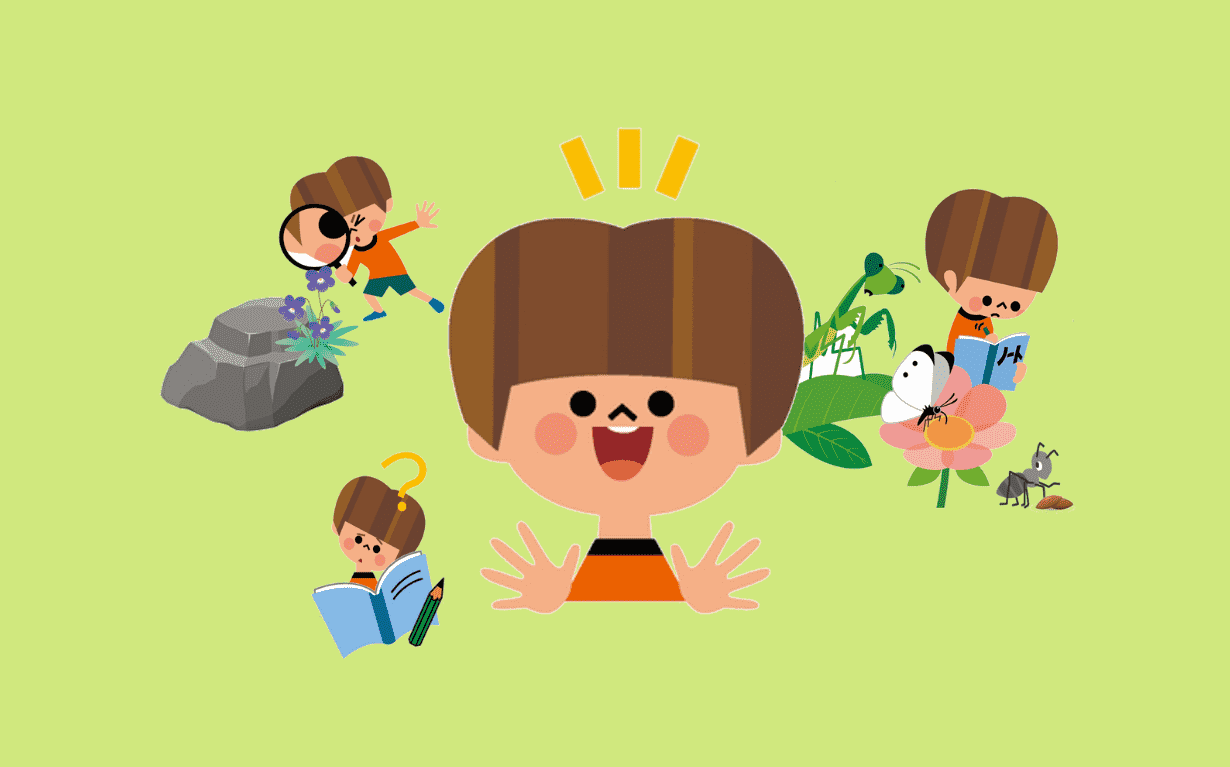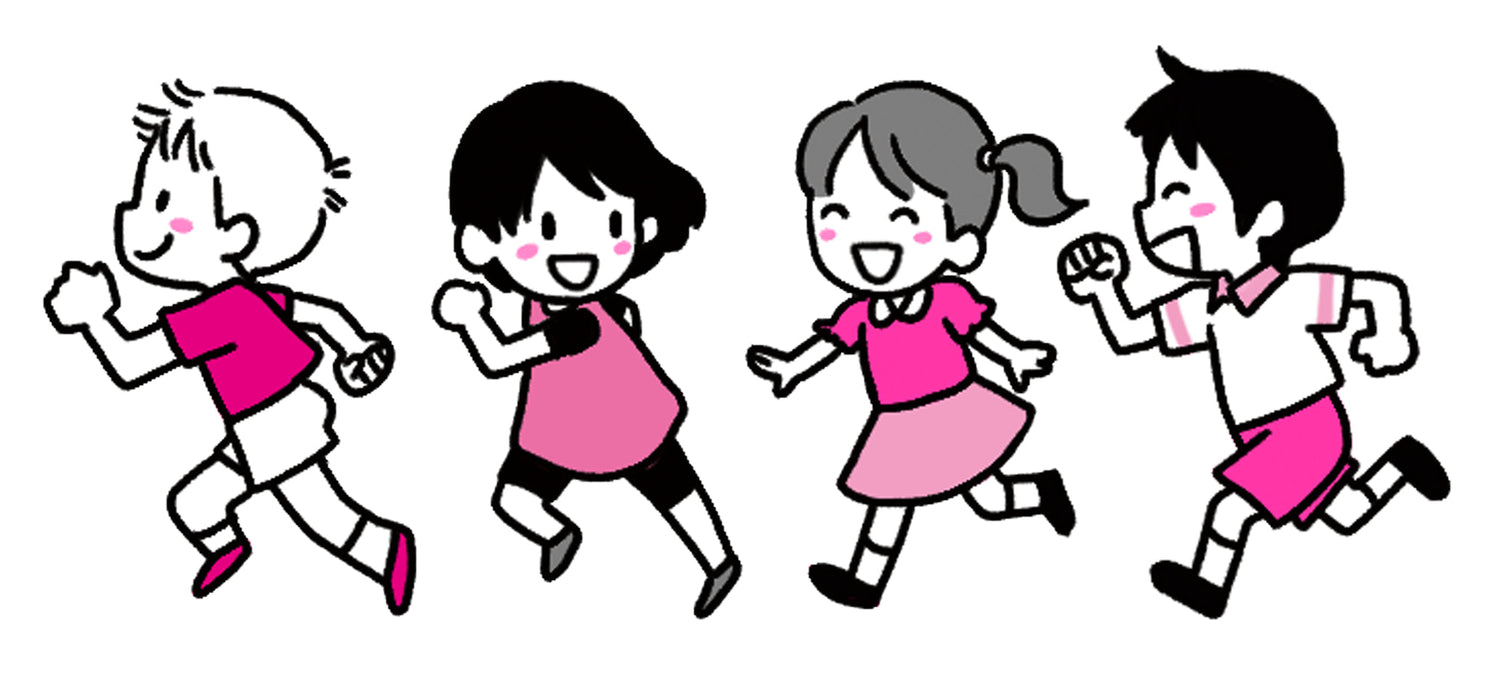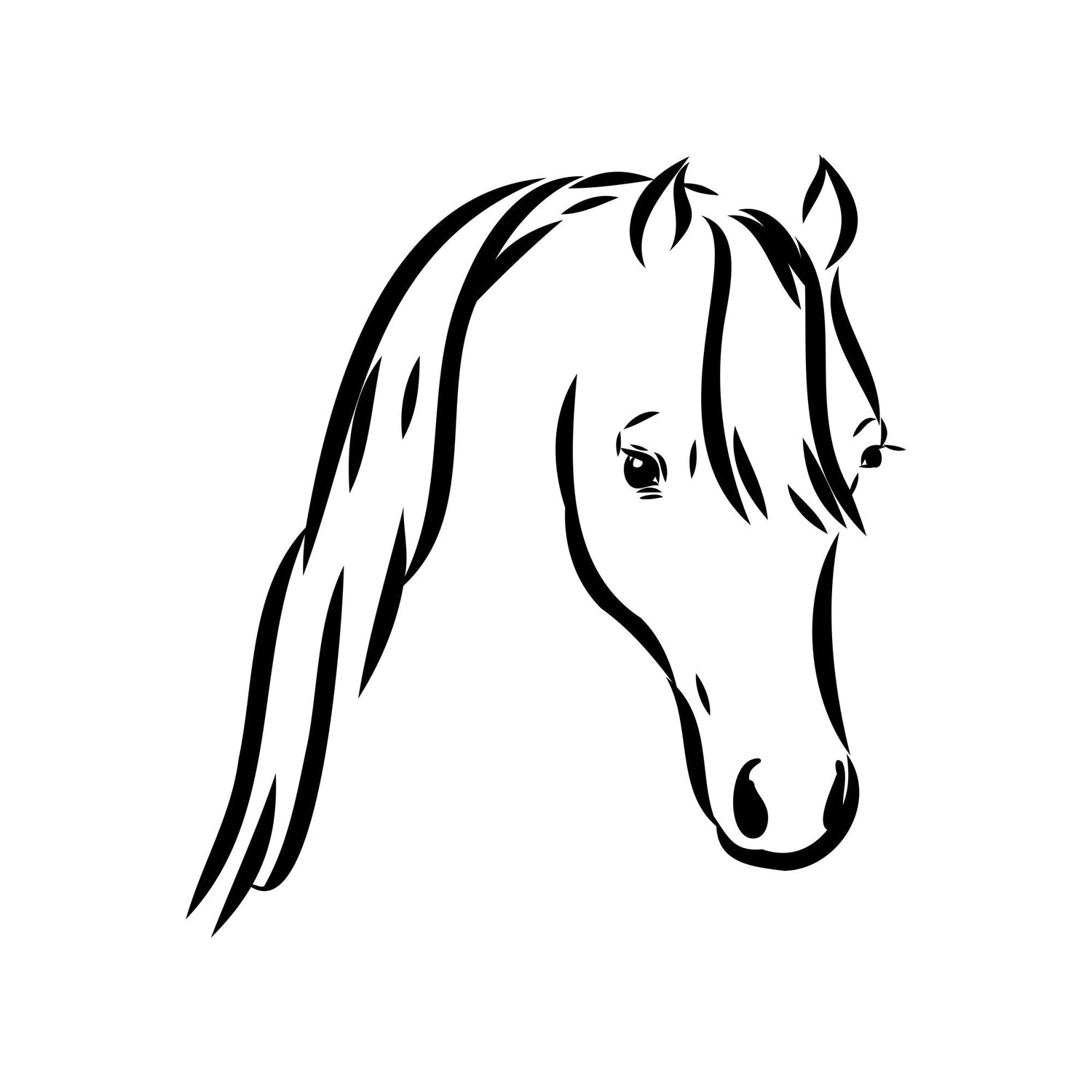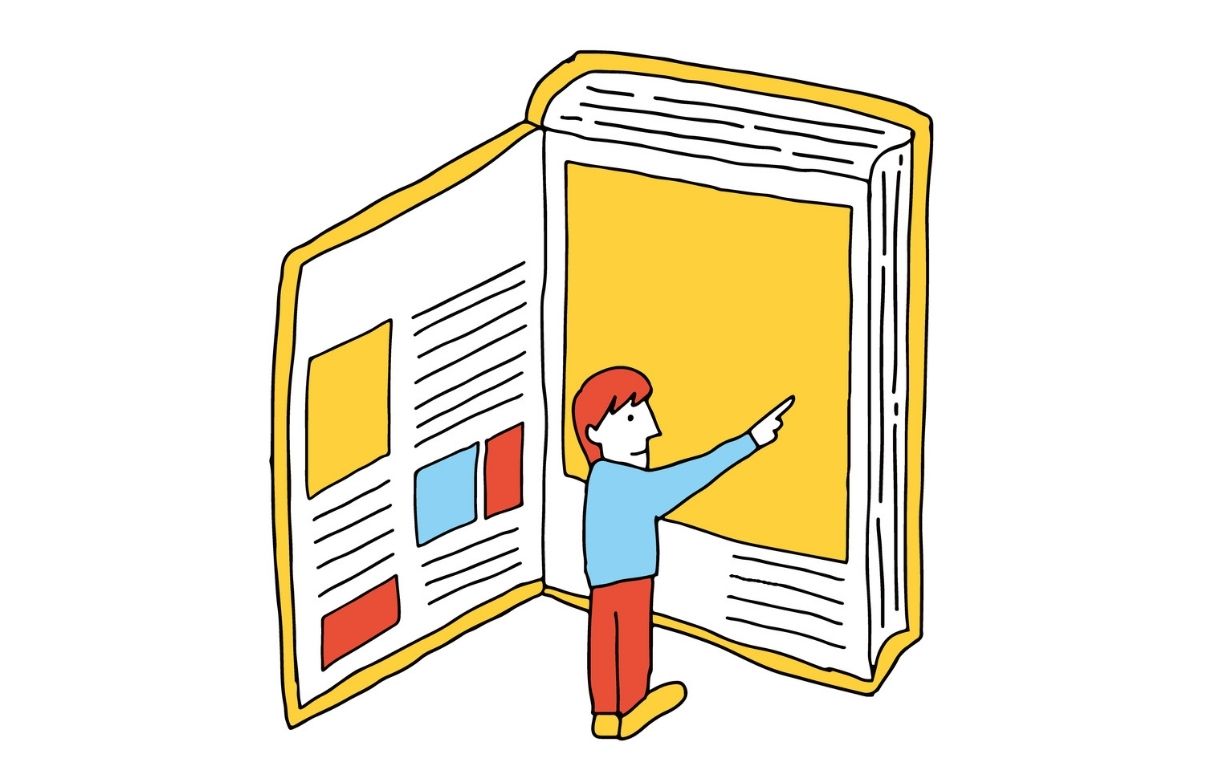子どもと創る「国語の授業」
![]() 有料記事
有料記事
「どうぶつ園のかんばんとガイドブック」の授業づくり
新教材「どうぶつ園のかんばんとガイドブック」(東京書籍 2年)では、かんばんとガイドブックの書かれ方や内容を比較し、違いを発見することを通して、読み手にとってわかりやすい説明とは何か、説明の仕方と目的について学習することができます。 今回は中野裕己先生(新潟大学附属新潟小学校・指導教諭)に、子どもたちがかんばんとガイドブックを比較する上で、どのようにすればその精度を上げられるのか、導入と内容の整理の方法についてご紹介いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
つながりで読む国語の授業づくり
―2年・「すみれとあり」―
「伏線」と聞くと、物語文を思い浮かべる方が多いでしょう。 説明文においても伏線を意識することで学びを広げていくことができます。 今回は、2年1学期において、学ぶことを楽しむ姿勢を育てていくための学習の様子を紹介します。 なお、2年生に伏線という用語は難しいので、「つながり」を考えて学習することの大切さとして伝えています。
単元を通して継続したい「問い」の意識
-2年・「お手紙」「どうぶつ園のじゅうい」の実践から-
今回の5分でわかるシリーズは、子どもたちに単元を通して継続して意識することのできる問いの工夫について、佐藤亜耶(白河市立白河第二小学校)先生に提案していただきます。叙述に基づいて、子どもたち自身が問いの根拠を見つけ、考えることは国語の学習において大切なことです。2年生の「お手紙」「どうぶつ園のじゅうい」の教材を例に、授業においての「問い」づくりを一緒に考えていきましょう。
![]() 有料記事
有料記事
「おにごっこ」
-<つながり>から学びを深める低学年の説明文授業-
「おにごっこ」の授業づくりを紹介します。 子どもたちにとって親しみ深い遊びを題材にすることで、積極的な言語活動を促すことができる本教材。おもしろさを通して、文章の構造や事例の並べ方を理解し、中、高学年へとつながる「文章を見る目」の素地を育てます。 今回は、沼田拓弥先生(東京都・八王子市立第三小学校)に子どもが前のめりになる授業づくりについてご提案いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
「スーホの白い馬」
-教師が教えたいことを、子どもが学びたいことへ-
「スーホの白い馬」の授業づくりを紹介します。本教材は、既習のハッピーエンド型のお話とは違う結末や、中心人物の心情が表れる複合語・繰り返し・比喩などの表現の工夫があるという特徴がある。今回は、髙橋達哉先生(東京学芸大学附属世田谷小学校)に、子どもの「学びたい」「考えてみたい」「話し合ってみたい」という思いを引き出す、効果的な発問を取り入れた授業
「やってみたい」と思わせるしかけをして、考える部分を焦点化しよう
今回は、比江嶋哲先生(宮崎県・都城市立西小学校)による、本単元のねらいである説明の工夫について読みとることができる授業づくりについてご提案です。