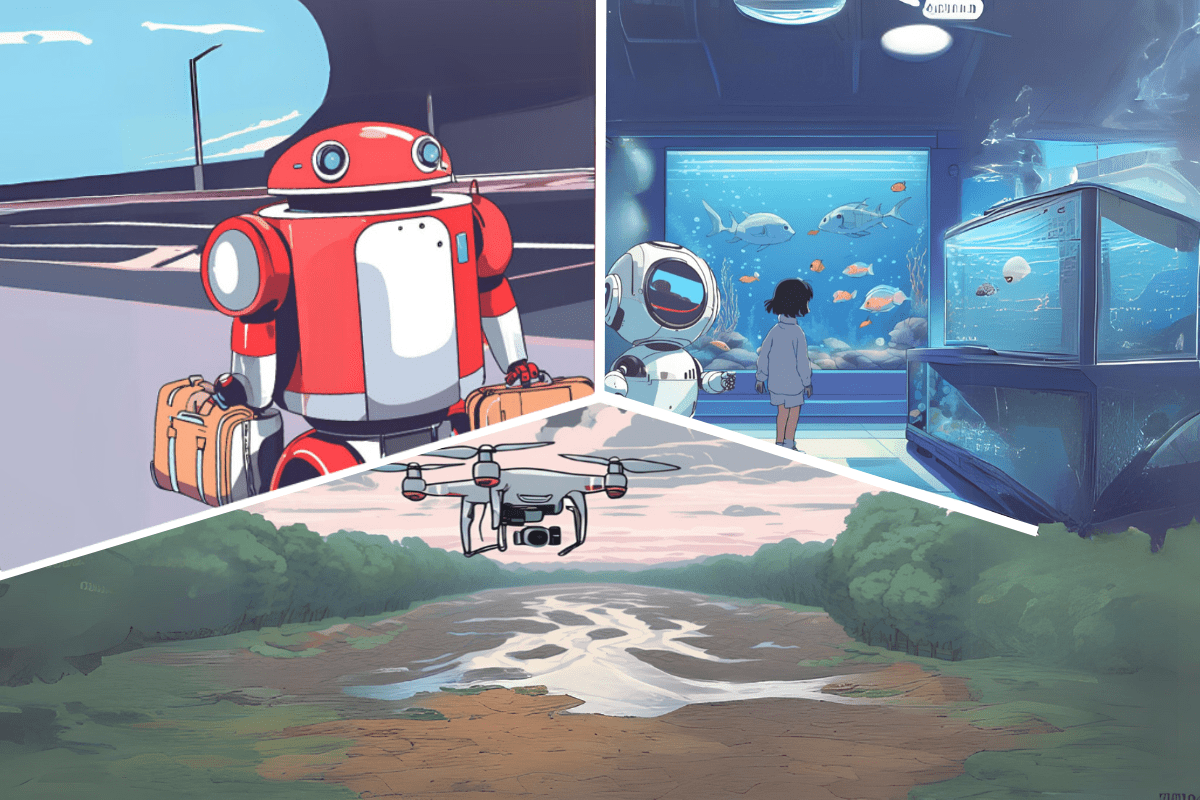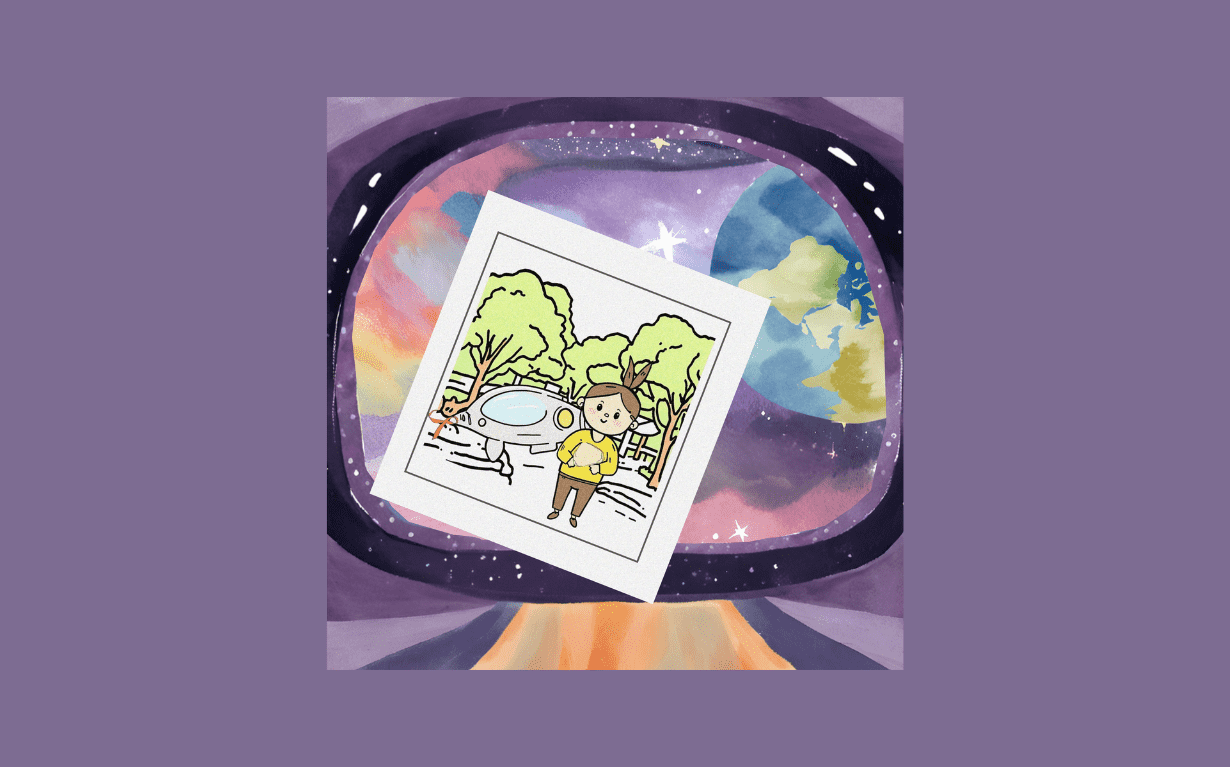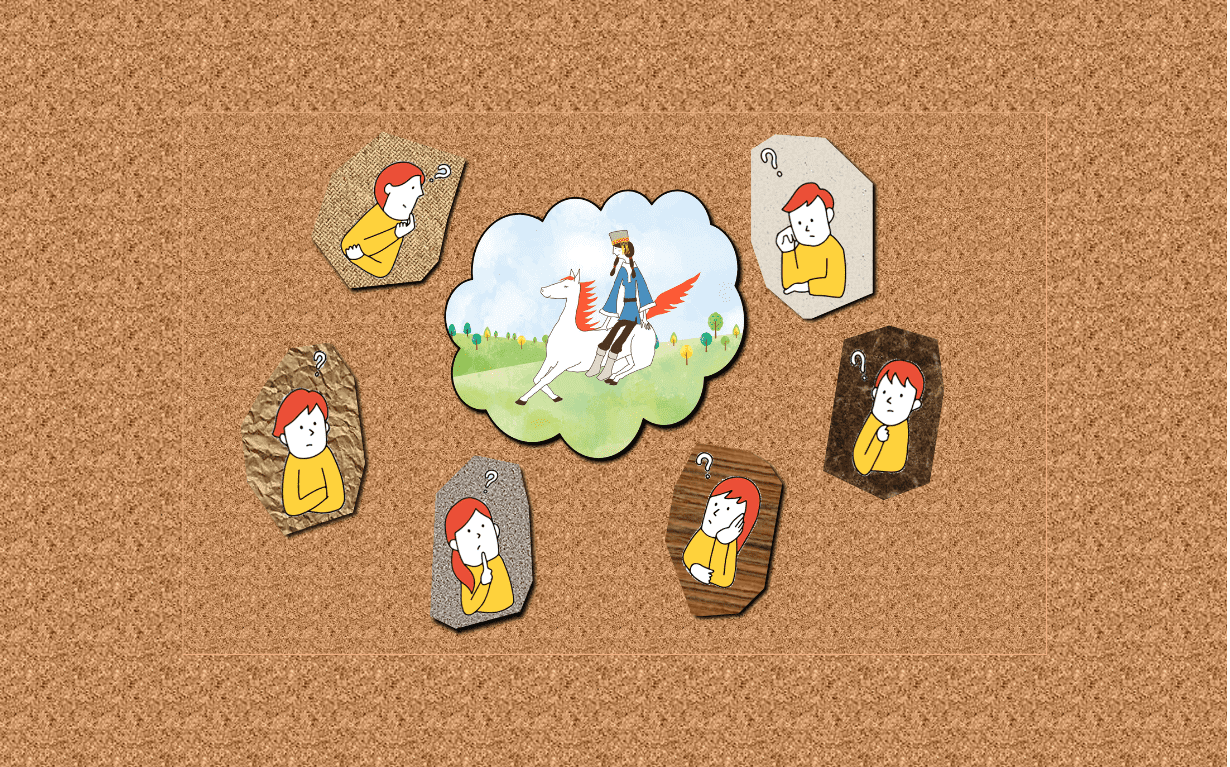子どもと創る「国語の授業」
![]() 有料記事
有料記事
「はるねこ」
—登場人物のしたことや気持ちに気をつけて読もう-
新教材「はるねこ」は、「あや」のもとに手紙が届く場面から物語は始まり、「はるねこ」との不思議な出来事の回想場面をはさんで、現在の場面に戻ってくる額縁構造となっています。小学校で二度目の春を迎える2年生にとって、春の訪れについて、想像が膨らみワクワクするようなファンタジー作品です。 今回は柘植遼平先生(昭和学院小学校)に、会話文から登場人物の気持ちや様子を想像する力を育むために、リーダー「…」の部分に着目したり、登場人物の気持ちをふまえて音読の仕方を考えたりする学習活動をご提案いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
子どもに委ねる国語の授業
-2年「アレクサンダとぜんまいねずみ」レオ=レオニ作品を読む-
4月の学級開きは、子どもたちが育つ学級の姿をイメージすることから始めます。 昨年はどのような1年間でしたか。 私自身を振り返ると、「子どもに委ねる」をテーマに考えることが増えました。これまでは、あるべき姿を求め過ぎて、教師が出過ぎていたようにも思います。 子どもが自ら考えるための力を奪っていたのではないかと考えると、「どこまで子どもに委ねていいのか。教師の出方はどうなのか」といった新たな課題が見えてきます。 今回は、指導計画の大枠を教師がデザインし、読みを深める過程を子どもに委ねる授業を目指していきます。
![]() 有料記事
有料記事
子どもの「できた!」をつくる「ビーバーの大工事」の授業づくり
-だいじで読むと、わかる!見える!すごい!-
本教材「ビーバーの大工事」は、タイトルからはその大工事の目的がわからず、謎に包まれています。「ガリガリ」「ドシーン」のオノマトペや「近よって みますと、」とあるように、まさに目の前のビーバーの行動を実況しているかのように説明が展開されることで、ワクワクしながら読み進めることができ、最後に判明する、大工事の目的とその壮大さには驚きが待っていることでしょう。 今回は斎藤由佳先生(神奈川県・逗子市立沼間小学校)に、説明文を読み深める上で、「何を明らかにしたいか」「何に気をつけて読みたいか」といった、「だいじの基準」を学級で共有し、更新することで、自分なりの「だいじなことば」の探究が進むようになる授業づくりの工夫をご紹介いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
「ロボット」で「読む」力をつける授業づくり
新教材「ロボット」は、「問い」と「答え」、「まとめ」がわかりやすく段落で分けられており、説明文の基本的な3部構成を確かめることのできる教材です。今回は小島美和先生(東京都・杉並区立桃井第五小学校)に、この説明文の3部構成をしっかりと押さえつつ、「問い」の「答え」となる事例の紹介のされ方や順序に意識が向くようになる、問いかけの工夫についてご紹介いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
「みきのたからもの」
-低学年で「問いを中心に俯瞰した読みをする」体験をさせよう -
本年度より登場した「みきのたからもの」(光村図書・2年)は、中心人物みきと宇宙から来たナニヌネノンとの友情を描き、次々と現れる不思議なことに、子どもたちがワクワクしながら読み進めることのできる物語文教材です。 今回は比江島哲先生(宮崎県・都城市立有水小学校)に、子どもの初読の感想を想定した上で、物語文の展開や叙述、登場人物の気持ちの変化について、俯瞰的な視点をもてるよう問いをつくる授業づくりの工夫を、ご提案いただきました。
![]() 有料記事
有料記事
子どもが「問い」をつないで読む
-「スーホの白い馬」(光村図書・2下)-
2年生の物語学習「スーホの白い馬」の実践を例に、低学年が「問い」をもち、追究する学びについて探ります。本単元の提案は、次の3点です。 ・初読後の感想の書かせ方を工夫して考えのズレに気づかせることで、単元を貫く「問い」をもつことができるようにする ・〈確かめ読み〉を終えた段階で、「問い」を再検討する ・単元を貫く「問い」を意識させ続けることで、その他の「問い」を子どもがつなぎながら読み進めることができるようにする