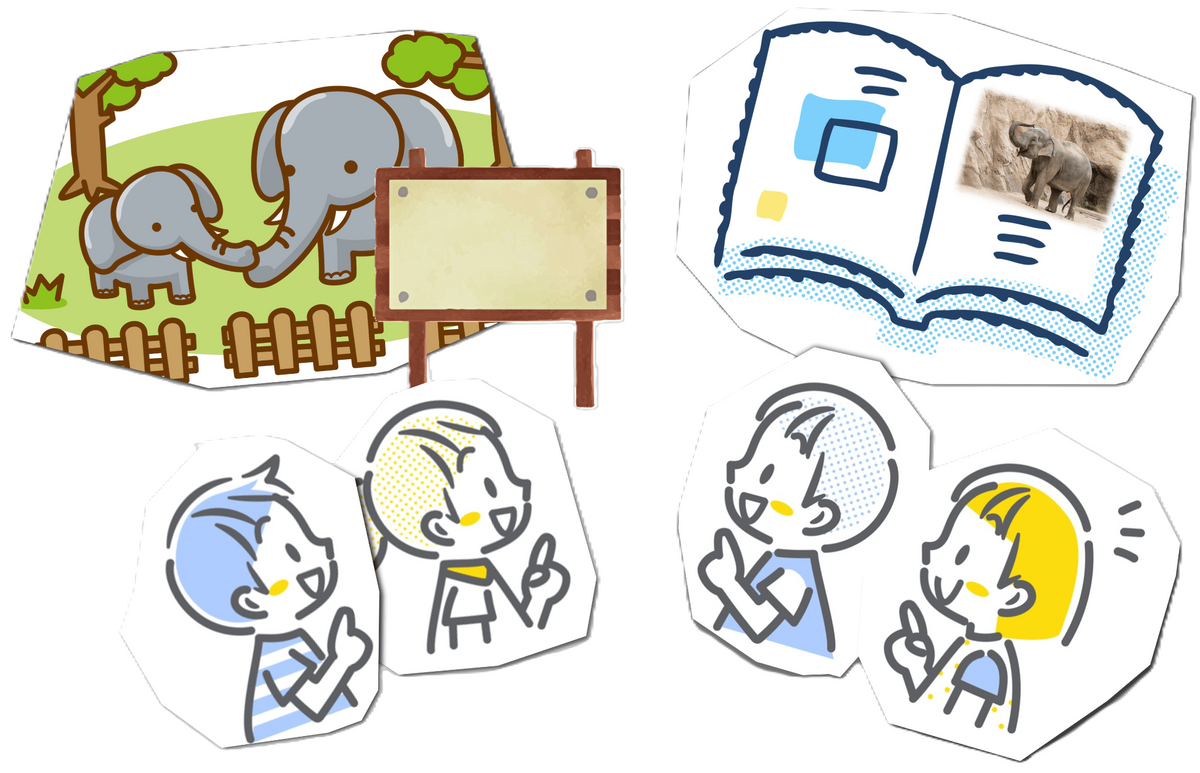
「どうぶつ園のかんばんとガイドブック」の授業づくり
|
執筆者: 中野 裕己
|
新教材「どうぶつ園のかんばんとガイドブック」(東京書籍・2年)では、かんばんとガイドブックの書かれ方や内容を比較し、違いを発見することを通して、読み手にとってわかりやすい説明とは何か、説明の仕方と目的について学習することができます。
今回は中野裕己先生(新潟大学附属新潟小学校・指導教諭)に、子どもたちがかんばんとガイドブックを比較する上で、どのようにすればその精度を上げられるのか、導入と内容の整理の方法についてご紹介いただきました。
目次
どんなときに誰が読むか
対象について端的に書かれているものが、かんばんである。
本教材では、アフリカゾウについて、「すんでいる場しょ」「体の大きさ」「たべもの」「体のとくちょう」が挙げられている。そして、「すんでいる場しょ」が「アフリカ」と単語で書かれているなど、情報が短く表現されている。
このようなかんばんの特徴は、読む人の置かれた状況に合わせたものである。かんばんは、基本的に実物の近くに設置されている。読む人は実物を見ながら、それに関わる情報としてかんばんを読むことになる。当然実物に興味をもっているわけなので、かんばんの情報は端的に書かれていることがふさわしいのである。
