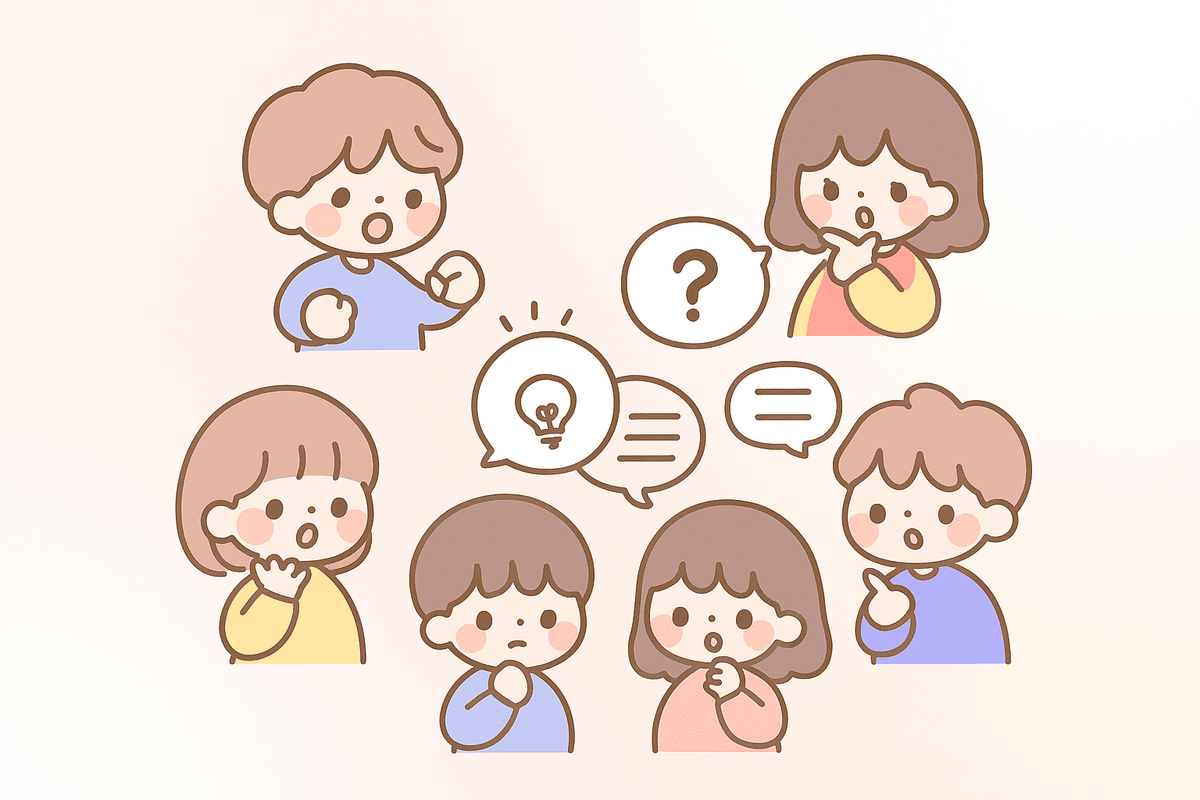
5分でわかる 話し合いができる子どもを育てる指導アイデア
|
執筆者: 佐久目 百合子
|
9月号の「5分でわかるシリーズ」は、佐久目 百合子先生(東京都・練馬区立小竹小学校)に、意欲を引き出す発問や「リレーことば」「問い返し」などの仕掛けを通して、低学年から「聴く」「伝える」スキルを積み重ねる指導アイデアについてご提案いただきました。
毎時間の授業で行われる話し合い活動
「隣の人と話し合って見ましょう」「グループの人に意見を伝えてみましょう」と時間をとった後、話し合いが進んでいない子どもやグループにとっては、不毛な時間だけが過ぎて行ってしまう。教師も話し合っている「風」に満足し、本質を見逃してしまっていることはないだろうか。
また、全体での話し合いでは一部の子どもの意見で話が進み、授業に参加できていない子どもを生み出してしまうことはないだろうか。なぜペアやグループ、全体で話し合うのかを、子どもにとっても必然性を感じられるものにすることが重要であり、また、その目的と意義を踏まえて教師側が意識して、使い分けておかなければならない。
高学年になるにつれて、手を挙げて自分の意見を発する子どもとそうでない子どもが大体決まってくるな、と感じることは教師であれば誰しもが経験したことがあるだろう。成長過程における時期的なものも、もちろんあるが、多くの子どもが抵抗なく自分の意見を述べるためには、経験とスキルが必要になってくる。
経験とスキルとは、どういうことであろうか
他者に意見を伝え、意見を交換し合うには、『①低学年のうちから話し合うことに慣れておくこと』『②自分の意見をみんなに伝えたい、みんなはどう考えているのかを聞きたい、みんなとの話し合いに参加したいと思いながら学習を積み上げていく』ことが、大切になると私は考えている。「話し合い」は急にできるようにはならない。字を綺麗に書くためにはゆっくり書くことやポイントをつかむ必要があり、音読が上手になるためにははっきり読む練習をすることや抑揚をつけて読んでみることを積み重ねてできるようになっていく。
「話し合うこと」も同様、スキルを身につけ、身につけたスキルを使って、ステップアップしていくのである。また、それには慣れ(経験)も必要になる。
ここからは低学年で話し合うスキルを高める方法について、実践を踏まえながら紹介していく。
「答えたい!」「話したい!」と、子どもが感じる発問を教師が提示する必要がある。 1年生「おおきなかぶ」で例えると、「おじいさんはこのときどんな気持ちだったと思う?」と問うより「なぜ、まごより先におばあさんを呼んできたんだろう」と問いかける方が話し合いが活発になった。発問の質を上げ、「伝えたい」思いをもっている子どもの意欲を損ねないよう今後につなげていくこと、発言が苦手な子どもに対しては「これなら答えられるかも」と自信につながるようにしていくことが大切である。
低学年は、自分の思いや考えを「伝える」ことは大好きでも、友だちの話になると手いじりや文房具をいじりはじめてしまい、話を聞いていないことが多くある。学級経営を行う上でも教師が口酸っぱく「話を聞きなさい」と注意する場面も多くなるのではないだろうか。
「聴く」ことができないと、話し合いは成り立たない。低学年で「聴く」練習をすることはとても重要である。そこで「リレーことば」を授業に取り入れてみた。
「リレーことば」とは、前に発言した人の内容に対し自分はどう感じて、どう思っているかを伝える構文である。低学年では話型や構文を示すことは非常に効果がある。「知らない」ものを「知って活用する」ための道具は効果的に使うとよいだろう。
②で述べた「聴く力」を育てるためにも、「問い返し」は有効であり、「問い返し」により授業がぐっと深まっていく。実際に授業で活用しているものとして、次の問い返しがある。
この問い返しにより、子どもはAさんの発言を思い出そうとする作業を始める。
初めの頃、この問い返しをしたところで、実際にAさんの発言をしっかり聴いていた子ども、わかっていた子どもは1/3もいなかった。これはつまり、2/3以上の、聴いていない子どもを含めわかっていない子どもを取り残したまま次に進んでしまっていた可能性があるということである。この問い返しをどの授業でも活用することで『先生はまた尋ねてくるだろう』という予測が子どもの中に生まれる。続けていくことで意識的に「聴く」ことを心掛けるようになる。
これをきっかけに「聴く」習慣が常習化していくと、だんだん「尋ねられるから聴く」から「Aさんの考えは私と似ていた」「Aさんの考えは自分にはなく、とてもおもしろい」といった気づくうれしさ = 聴くことの楽しさに変わっていく。
この問い返しは、子どもの思考を深める上で非常に有効である。「わかる」ことと「わかったことを言語化する」ことには段階が生じる。Aさんが言っていたことを、言語化できるくらい自分の中に落とし込むには、よほど集中して「聴く」といことをしなければならない。相手が言っていたことを自分の中に落とし込み、その上で自分の考えをもち、相手に伝える。このサイクルが深まっていけば、授業は子どもたちのことばで深まっていく。
教師ではなく子どもたち自身が声を上げ、子どもたちの声で授業が創られていくことができるようにする。そうすることで、「受ける授業」から「創り上げていく授業」に子どもの認識も変わっていくのではないだろうか。
本実践は低学年のものであるが、伝え合うことのよさや必要感を実感することで話し合いが活発になる学級づくりは、他学年でも実施可能である。つまり「話し合い」は全学年において必要であり、大切なのである。目の前の子どもたちの実態を踏まえてどのような支援が必要か、どのように伸ばしていけそうかを教師が見取り、ことばを大切にしながら話し合える子どもたちを育てていきたい。
【参考文献】
佐久目百合子(さくめ・ゆりこ)
東京都・練馬区立小竹小学校
