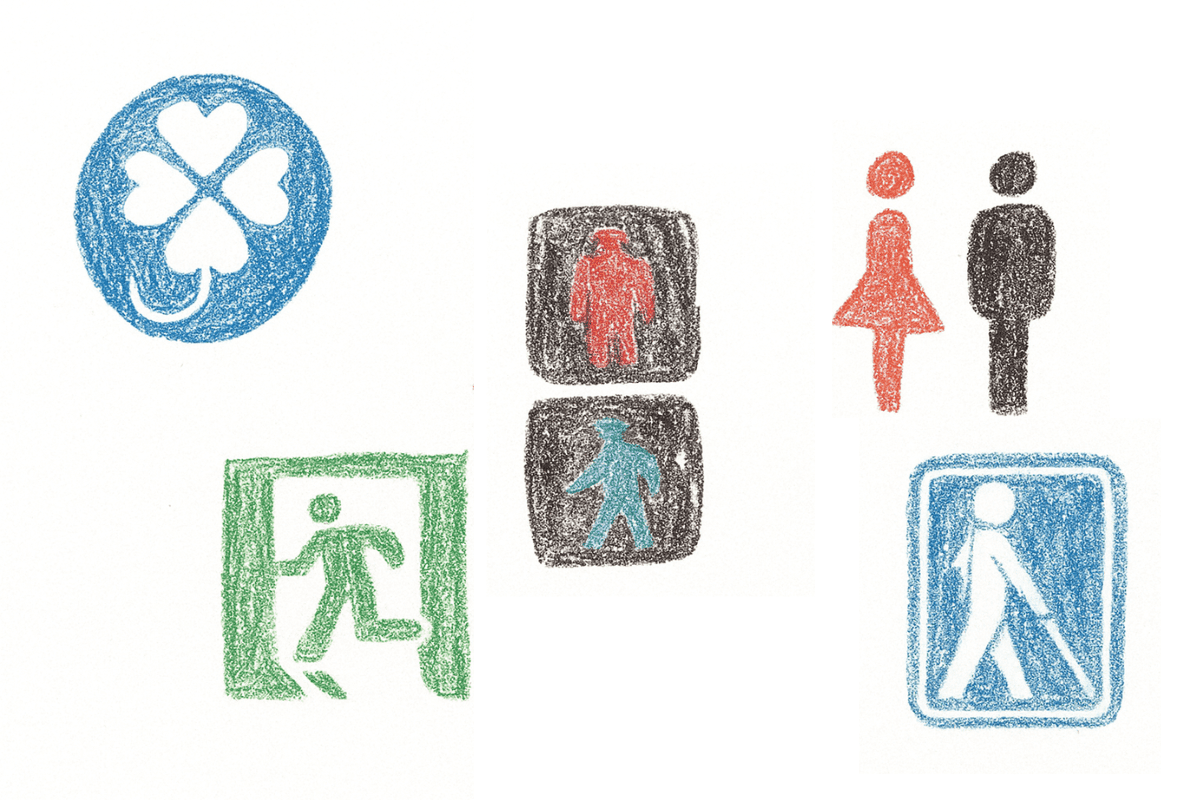
既習を活かしながら本文の構造を1時間で掴む:「くらしと絵文字」 -主体的に学ぶための素地づくり-
|
執筆者: 柘植 遼平
|
単元名:既習を活かしながら本文の構造をつかもう
教材:「くらしと絵文字」(教育出版・3年)
2025年5月、絵文字を生みだし世界に”Emoji”文化を広げたNTTドコモが、「ドコモ絵文字」の提供終了を発表し、話題となりました。iPhoneなどでも使える標準絵文字として、世界的に浸透しきったためです。東京オリンピック2020を境にピクトグラムが再び注目されるなど、ユニバーサルデザインとしての絵文字の発展は、我々の関心を惹き続けています。
今回は柘植遼平先生(昭和学院小学校)に、既習で得た知識を「読みの物差し」として用い、本教材で、生きた資質・能力として応用、新たな知識の発見につなげることで、主体的に学ぶ姿を育む授業の提案をいただきました。
国語の学習は繰り返しの学習である。1年生のときから、説明文も物語文も、繰り返し学習をしてきている。算数などと同様、いかに既習を活用できるかが大事となる教科であることは間違いない。しかし国語の場合、説明文の学習をした後、次の説明文まで数か月の間が空いてしまうことや、教材ごとで本文が全く異なることから、既習を活かしにくいことも事実である。それでも低学年のうちから「問い」「答え」や「はじめ・中・終わり」といったことについては繰り返し学んできた。中学年以降ではそれらを、さらに抽象化(一般化)していくことが大事となる。
つまり、単元で学んだ具体的な「読みの物差し」を抽象化していくことで、次の機会に「使える物差し」にしておきたい。「使える物差し」になることで、自ら学んでいく方法がわかるので、主体的な学び手を育てていくことにつながっていくのである。
そもそも「主体的な学び手」とは、どのような学び手を指すのだろうか。国語の授業では本文があるため、どうしても最初の一手は教師から出すことが多くなってしまう。ここを変えていくには、数年単位での研究が必要になってきてしまう。担任が変わることがある現状では、現実的ではない。そこで、教師から出された本文や発問について、考えていくうちに新たな問いが生まれたり、問いが解けていくうちに読むことが楽しくなったりする姿、自分の中での変化を楽しめる、楽しいと感じられる姿を「主体的な学び手」と捉えていき、そのような姿が見られるようにしたい。
それぞれの学年で「主体的な学び手」を目指して取り組んでいくことはもちろんのこと、6年生になったときに既習となった多くの「使える物差し」を駆使して、読み進めることができるような姿を目指したい。教師が意識して学習を行っていくことが、「主体的な学び手」を育てていくことにつながっていくと考えられる。
