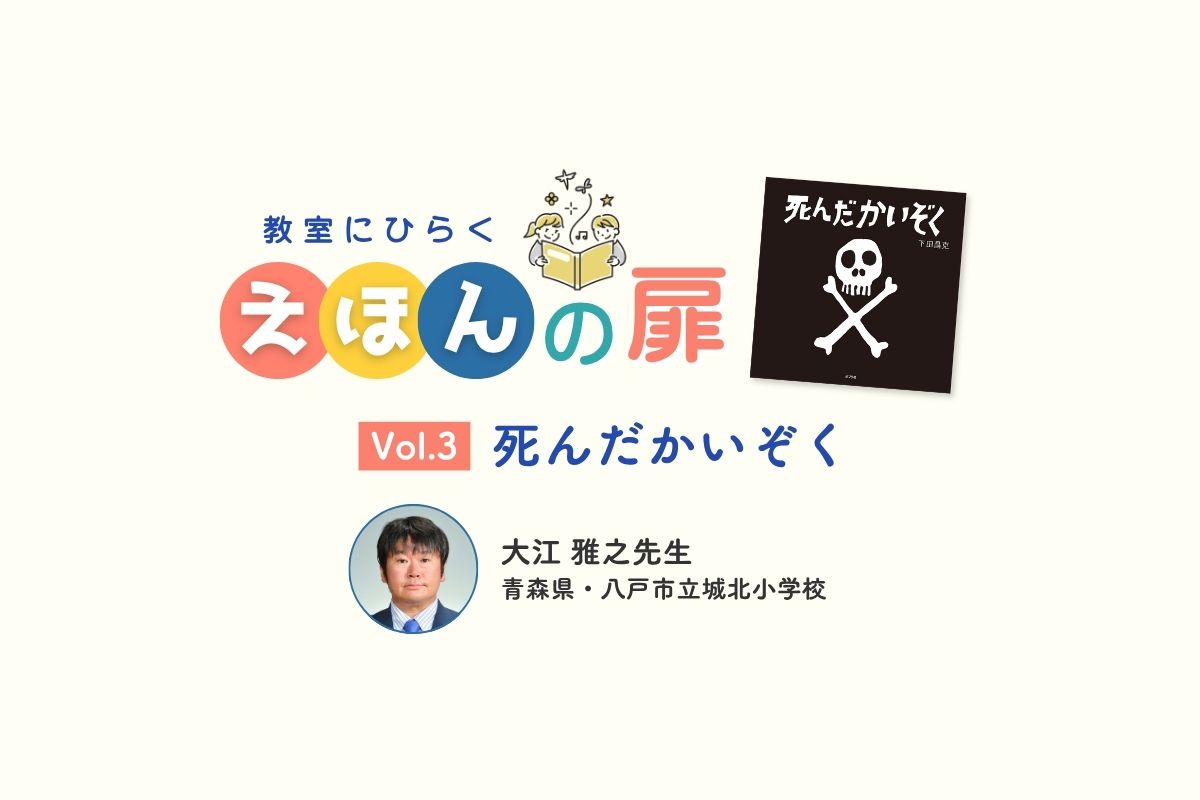
『死んだかいぞく』 ー「死」に向き合い「生」を得る一冊
|
執筆者: 大江 雅之
|
書名:死んだかいぞく
作:下田昌克
絵:下田昌克
出版社:ポプラ社
出版年:2020年
ページ数:38
死にゆく海賊の命尽きるまでを描いた、インパクトの強い一冊です。子ども向けの絵本としては重いテーマを扱っていますが、読み聞かせだからこそ取り上げられる、メッセージ性のある一冊としてご紹介いただきました。
好き放題に生き、欲しいものをすべて手に入れてきた海賊。
いつも酔っ払っていた海賊は腹を刺され、海に投げ込まれる。海賊はどんどん沈んでいく。人くいザメが海賊の帽子を持っていく。しわしわの年取った魚は海賊の金歯をとっていく。青い魚は海賊の爪をうろこに貼り付ける。アンコウは目ん玉をランプにする。タコは海賊の髪の毛をもっていく。
最後に小さな魚たちが寄ってきて「みんなおなかがすいてるんだよ。おまえをたべてしまっていいかい?」と聞く。
海賊はこれまでの自分をふりかえり、小さな魚たちの要求を受け入れる。
海賊はとうとう海の底にたどり着く。真っ暗で、冷たくて、独りぼっちで、たいくつで、さみしい海の底。そんな海の底に光が届いた時、自分の死を受け入れた海賊を待ち受けていた運命とは・・・。
この作品のオススメのポイントは3つあります。
ポイント1「始まり」
いつも酔っ払っていた一人の海賊が、船の上で刺されて海に放り投げられるところから物語が始まります。
絵本らしからぬオープニングのあくの強さは、同時に読み手をいやが上にも引きつけることになります。
「死」から始まるということは、読者は主人公のそれまでの人生について、その後の死んでいく様子から想像するしかありません。海賊が身体に身に付けていた物を分け与え、徐々に死んでいく様子から、何となく主人公のこれまでの人生を窺い知ることができます。
しかし、「死」から始まるという演出は、それまでの人生の意味の無さやチープさを表しているようにも感じます。主人公が歩んできた人生について、書く価値がない、書こうとする気がないというような作者のメッセージを受け取ることができます。
言い換えると、一人の海賊は「死」を迎えることによって初めて価値のある「生」を得ることができたというメッセージにも感じられます。
ポイント 2「失っていく物」
海に沈んでいく海賊は、出会う様々な海の生き物たちに自分の身に付けていた物を分け与えます。
海賊は、「りっぱなぼうし」「りっぱな金歯」「つめ」「目ん玉」「長い髪の毛」「自分自身の身体」の順番に自らを失っていきます。海賊の立派な帽子は「力の象徴」を、立派な金歯は「富の象徴」を感じさせます。これらの物から失っていくことにも、作者の意図がありそうに思えます。より元素的な物へと順番が進んでいくようなイメージでしょうか。
海賊の発言にも変化が見られます。「りっぱなぼうし」が失われる時は、人くいザメに「おれさまの この ぼうしは ぜったいに やらんぞ」と言っていたのが、「自分自身の身体」が失われるときは、たくさんの小さな魚たちに「いいよ。おれさまは うまれてから いままで かぞえきれないほど おまえらを くってきたんだからな」と言っています。
この変化からは、自分の死を受け入れ、達観の域に入ったことを感じさせます。たくさんの小さな魚たちに、「自分自身の身体」を捧げる前に、「おれさまの ぼうし、サメは なかなか にあってたな」というように、それまで物を分け与えてきた生き物たちを思い返す場面も印象的です。海賊は生前、出会った一人一人を思い返すことがあったのでしょうか。物欲や暴力にまみれ、命を取り合う人生。そのような人生に、出会った一人一人を微笑ましく思い返す機会なんて一切無かったことでしょう。
しかし、死にゆく直前に自分の「いのち」を分け合ったことによって、微笑ましく思い返す経験を得ることができました。
まさに、「死」に向き合い「生」を得ることができたと言えるのではないでしょうか。
ポイント3 「色彩」
この作品は、色彩や装丁も個性的であり印象的です。まず、表紙と裏表紙は真っ黒です。表紙の中央にはどくろとクロスした二本の骨が描かれています。本のタイトルと相まってインパクト十分であり、内容への悲壮感を感じさせますが、この表紙以外にはこの作品を表せないような気もします。色彩の美しさは言わずもがなですが、海賊が海底に沈んでいくに従って、暗く濃くなっていく海の色彩の変化は圧巻です。そして、ここでは詳しくは記しませんが、最後の海賊の色彩も筆舌に尽くせないものがあります。
「生」を得ることや感じることの「美しさ」を思わずにはいられません。
読み聞かせの際には、絵本を180度に開いて読み聞かせることを意識します。
その理由は、180度に開くと表紙・裏表紙の端の部分が絵の両脇に表れるからです。
この端の部分は漆黒であり、額縁のように中身の絵を引き立たせる効果があります。海賊のセリフについては、声色を変える必要はありません。ただ、海賊が死を達観していくに従って「読む速さを遅くしていく」ことをおすすめします。
最後のページの前には、間を空けて一呼吸を置いてから、ラストに移行するとよいでしょう。
大江 雅之(おおえ・まさゆき)
青森県八戸市立城北小学校 教頭
全国国語授業研究会顧問
