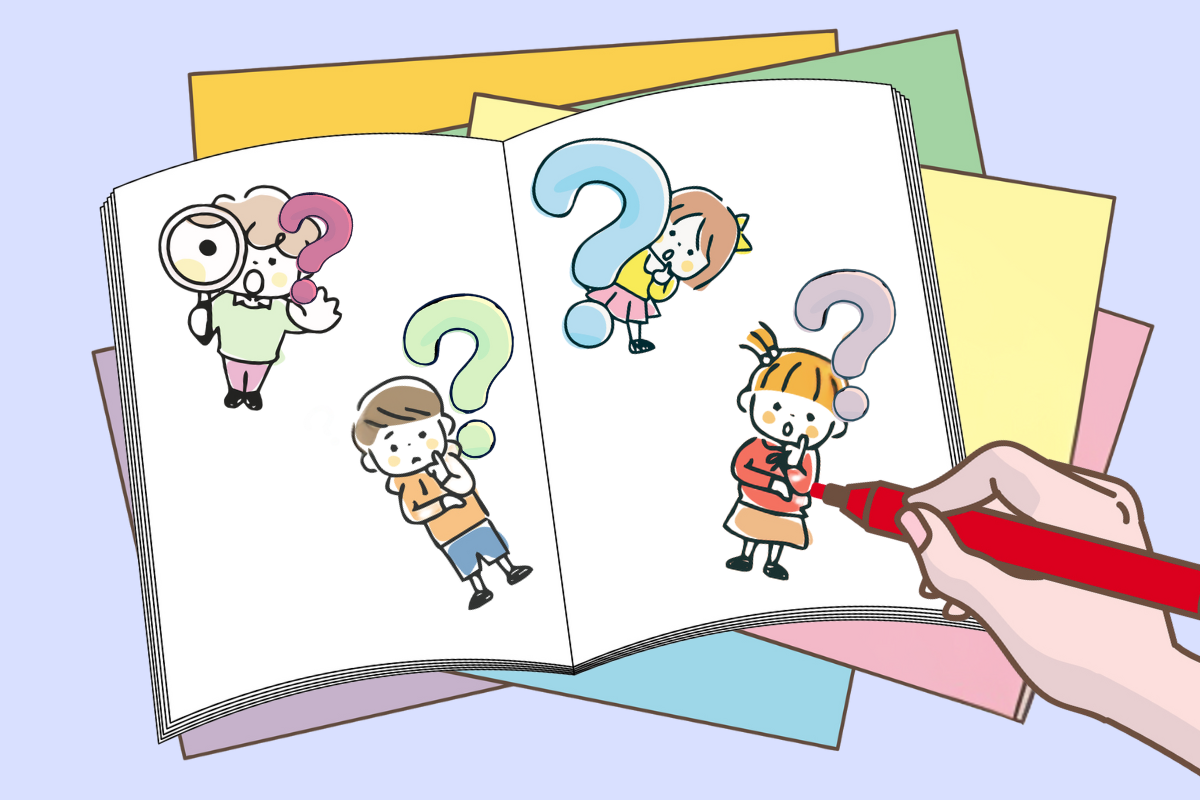
読後感から問いづくりへ -4年「世界一美しいぼくの村」-
|
執筆者: 弥延 浩史
|
学習指導要領において、文学的文章を読むことの学習過程は、「構造と内容の把握」「精査・解釈」「考えの形成」「共有」と示されている。これは、大きく分けると「読み取ること(読解)」と「表現すること」の2つになると考える。
自分が読み取ったことをもとに、その思いや考えについて対話を通して共有し、新たな読みの視点を得たり想像をさらに拡げたりすることが「読解」の部分である。そして、自分が感じたり考えたりしたことを他者に向けて発信するのが、「表現」の部分である。だからこそ、ここで展開される言語活動においては、文章と読み手、読み手どうしが関わり合うことが最も重要であると考える。読解と表現が適切につながっていくような授業展開にすることは言わずもがなである。
文学的文章の授業を展開するに当たって、授業者として大切にしていることは、学習者が「読み取ったことをもとに自身の考えを表現できるようにする」ということである。そこには、何のために表現するのかという「学びの目的意識」が必要である。そして、学習を通してどのような力が身に付いたのかということをとらえ、他の学びにも転用していけるような「学びの自覚化」につなげていくことが必要である。
したがって、単元の導入部分では、いかに子どもが学ぶことに対する「必要感」をもち、「目的意識」をもって学習を進められるようにできるのかを重視する。 そのために、次のように単元の導入部分を整理して授業を進める。
