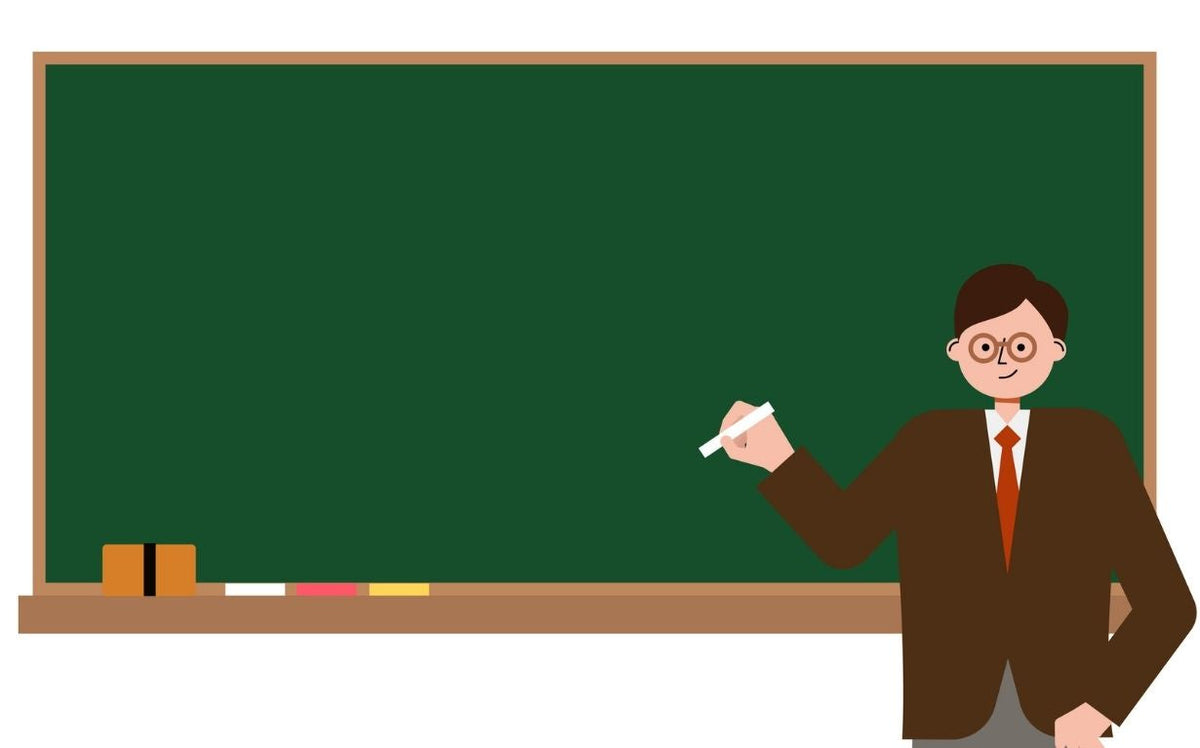
5分でわかる 縦書き板書のコツ
|
執筆者: 井上 幸信
|
今月の5分でわかるシリーズは、井上幸信先生(新潟県・五泉市立橋田小学校)に「縦書き板書」に対する悩みを解決する方法についてご提案いただきました。「黒板に文字を書いていると、だんだん斜めに曲がってしまう……」「縦書きだと特にまっすぐ書けない……」と悩む先生方必見!
一緒に、板書時の体の使い方を学びましょう。
公開授業や書籍・SNSを通して、国語の授業の板書を先生方に見ていただくことがある。そんな時にいただく感想や質問からは、多くの先生方が縦書き板書に悩みを抱えていることが伝わってくる。特に多く寄せられるのは、
「縦書きだと、真っ直ぐ書いているつもりなのに曲がっちゃうんです。」
という声である。国語の板書の多くは縦書きである。「縦に書く」というだけで、横書きの板書とは違った難しさが生まれてくる。だが、逆に考えれば、「縦に書く」ことで生じる難しさを一つ一つ解決していけば、国語の板書は改善できるということでもある。
本稿では、縦書き板書を難しいと感じる先生が多い理由を考えるとともに、その打開策を考えていく。
※論者が右利きであることから、本稿では右利きでの板書について論じていく。左利きの場合は本稿での説明とは異なる縦書き板書の難しさが生じるが、その理由は概ね本稿で述べる人体の構造的な問題と同根である。
前述した通り、「まっすぐに書くことができない。どうすれば真っ直ぐ書けるのか?」という相談は非常に多い。
曰く、「書き進めていくと、行が曲がっていく」「黒板の下の方に書き進むに従って、行が曲がっていく」というのである。
そのような悩みをもつ先生に、国語の板書を書く様子を動画で撮影してもらい、そこから原因を探ってみたことがあった。それら複数の動画から見えてきた、縦書き板書が曲がる原因。それは、板書時の先生方の「体勢」であった。
黒板の下方に書き進むに従い、写真①や写真②のように、体を曲げて板書をしていたのである。この、体の曲がりこそが、縦書き板書が難しいと感じられる最大の理由なのである。
人間の関節の可動域は限定的である。写真3の黄色ラインのように、右腕を楽に動かすことができる範囲は体の中央から右側に向かって弧を描くような軌跡となる。体の軸が垂直であれば、概ね真っ直ぐに縦に文字を書くことができる。
しかし、ここで写真1,2のように体の軸が曲がっていくと、関節の可動範囲も写真4,5のように変わっていく。
このように体の軸が傾くと、縦に書いてきた行は体の向きに影響され、左右に曲がりがちになる。また、関節の可動範囲を考えると、写真4の方向に体の軸が傾けば文字の横画は右下がりになり、写真5のように傾けば、もちろん横画は極端な右上がりになる。
この、体の軸や関節の可動域から生じる傾きこそが、縦書き板書が真っ直ぐに書けない、曲がってしまう根本的な原因なのである。
ここまでで述べてきた通り、縦書き板書が曲がりがちなのは、関節の可動域と体の軸の向きとに理由がある。この2点を考えて板書の仕方、板書時の体の使い方を考えれば、真っ直ぐに縦書き板書を書くための要点も見えてくる。
要は、写真6のように体の軸が左右に傾かないように、概ね背すじを垂直に維持できるように板書することを心がければいいのである。
体の軸を真っ直ぐに保って上から下に板書を書き進めることは、決して難しいスキルを必要としない。写真4,5のような体の軸を曲げた体の下げ方をせず、背筋が真っ直ぐ上方から下方へと下がっていくように体を動かせばいいのである。
写真7は、直立して黒板上方に文字を書く姿勢である。黒板下方に書き進める際は、写真8のように膝を曲げて文字を書く位置を下げるように心がける。そうすることで、体の軸を垂直に保ち、関節の可動域も左右にずれることがないまま、板書を書き進めることができる。
この方法で縦書き板書に取り組むと、1行板書するごとに屈伸運動をするような負荷がかかる。黒板下方に集中して文字を書く場合は、蹲踞の姿勢(あるいは膝立ちのような姿勢)を維持しながら文字を書き続けることになる。写真④⑤のように体を傾けて板書するよりも身体的な負担は大きくなるが、縦書き板書の行を真っ直ぐに保つ上では、効果的な体の使い方である。
縦書き板書が苦手だという先生方の板書を見ていると、行が曲がることに加えて、1行の中で文字の大きさを均等に維持しにくいという難しさも見えてくる。黒板下方に書き進めるに従って文字が大きくなったり、小さくなったりするのである。この、文字サイズのアンバランスが行の曲がりや歪みに見えることがある。
このような板書になりがちな先生は、ここまでに紹介したような体の動かし方(左右に体を傾ける、膝を曲げて体を下げる)などの体の位置の移動をせずに、直立のまま腕だけを下げて板書をしていることが多い。
下に行くほど文字が小さくなる原因は、本稿で繰り返し扱っている関節の可動域にある。直立のまま黒板の下方に文字を書こうとすると、手を動かす位置は腹部から下腹部となる。そのような低い位置では、肘や手首の関節を大きく動かすことはできない。そのため、小さくしか点画を書くことができず、結果として行の下に行くほど文字が小さくなってしまうのである。
下に行くほど文字が大きくなる理由は「錯視」という現象にある。「錯視」とは、文字を見る向きによって遠近法が生じることで、文字の大きさやバランスが偏って見えることである。
写真⑨は、黒板縦方向に並行な二直線をかき、上方から見下ろす角度で撮影したものである。2本の直線は平行なので、本来は上方の赤い円と下方の黄色い円とは同サイズのはずである。しかし、写真の通り二つの丸のサイズは異なって見える。
下にある黄色い円は、上方の赤い円よりも明らかに小さい。これが、視点が上方の赤い円に近い位置にあり、黄色い円は視点から離れた位置にあることから生じる「錯視」である。
このような見え方のまま縦書き板書を書き進めると、行内の文字の大きさが概ね同じであっても下方(黄色い円側)の文字は小さく見えてしまう。そのため、書き手の視覚に従ってバランスを取ろうとすると、下側に書く文字ほど大き目になる。書き手はバランスよく板書しているつもりでも、客観的に見ると下側の文字が大き目に書かれた状態になってしまう。これが、行の曲がりや歪みに見えてしまうのである。
下方にいくと文字サイズが変わってしまうことも、これまでに述べた体の軸を真っ直ぐに保って上から下に板書を書き進めることで改善を図ることができる。体の上下移動によって、関節の可動域を有効に活用したり、錯視を避けたりすることができるからである。
国語の板書は、文字数が多くなりがちである。「読むこと」単元であれば、ある程度は本文を書き写すことも必要になるし、子どもの言葉を記録するにしても語る言葉は多くなる。それらを適宜黒板に書いていく作業は、授業者にとって負荷の大きい営みである。可能なら、何かしらの方法でその負荷を減らしたいと考えるのは、至って自然なことだ。しかし、子どもの思考が、学びが丁寧に見やすく記録された板書を目指すのであれば、これらの負荷を受け入れることが肝要である。
本稿で述べたとおり、縦書き板書が曲がったり歪んだりして見える状態に陥る原因は、身体の機能を適切に活用できていないことにあることが多い。整った縦書き板書を目指すならば、身体の使い方を意識し、全身を使って板書することを心がけるべきである。
〔引用・参考文献〕
・押木秀樹、近藤聖子、橋本愛著 「望ましい筆記具の持ち方とその合理性および検証方法について」 全国大学書写書道教育学会『書写書道教育研究17』(2023年8月17日確認)
井上 幸信(いのうえ・ゆきのぶ)
新潟県・五泉市立橋田小学校
全国国語授業研究会理事/新潟デジタル・シティズンシップ教育研究会代表
